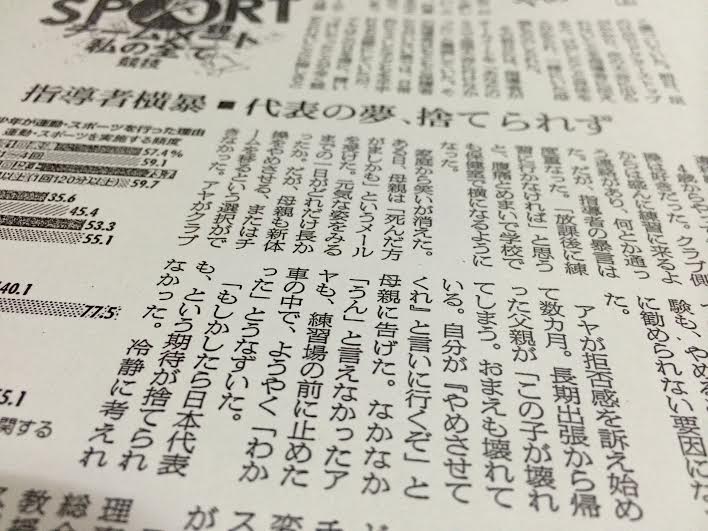教員の「多忙化解消」を目指す検討委員会にオブザーバーとして出席しました。昨年、県で教員の勤務実態調査と意識調査を実施、その結果を踏まえての「多忙化解消」に向けた方策について検討するための会議です。
調査結果を見ると、教員の超過勤務(法では認められていない、いわゆる「サービス残業」)は膨大だし、挙句に「持ち帰り仕事」も多い。土日も部活の指導でつぶれてしまう。会議や打合せは長いし、提出しなければなら . . . 本文を読む
たまたま見たEテレのハートネットTVは、長野県上田市でフリースクール「侍学園」を運営する長岡秀貴さんを紹介していました。様々な事情を抱えながらこの学校に通う生徒たち。テレビカメラの前に出てきた子たちはみんなしっかり自分のことを話せています。これなら社会に出ても大丈夫じゃないかと思いましたが、そうでない子もテレビの向こう側にいるんだろうなと思い直しました。
それでも、「この学校に来て、自分が好きに . . . 本文を読む
ついに来ましたね。「コミュニティ・スクール」の全小・中学校への導入。教育再生実行会議が、このたび、安倍首相に、全国全ての公立小・中学校をコミュニティ・スクールとするとの提言を提出しました。これから文部科学省は、全校指定を目指し、法改正に向けて動き始めることでしょう。
「コミュニティ・スクール」は、新聞などでは「地域運営学校」とも書かれていますが、各学校に、保護者や地域住民で構成される「学校運営協 . . . 本文を読む
特別支援教育は、一人一人に寄り添う“優しい教育”。だから、特別支援教育の考え方やシステムや実践は、障害のない子どもにも有効である。(筑波大学教授 柘植雅義氏、「内外教育」2015年1月30日号「特別支援教育の“範囲”」)。これを読んでハッとしました。
「教育する側」って、子どもがうまく学ぶことができなかったり行動できなかった時に、ついつい「子どもの . . . 本文を読む
社会活動家・湯浅誠さんが、「課題解決は体で学ぶ」という記事(平成27年2月4日付け毎日新聞)の中で、小さい頃、障害を持つ兄と野球をやった時に「みんながルールを調整した」という体験が、今思えばまさに「課題解決型の主体的学習」つまり「アクティブ・ラーニング」の実践だったということを書いています。
次期学習指導要領にもその充実が盛り込まれることになっているアクティブ・ラーニング。要は、ある . . . 本文を読む
八戸市で進めている、小中連携の「ジョイントスクール事業」。今日は、とある小学校で、6年生の算数の授業を中学校の先生方が参観する様子をのぞかせていただきました。
小学校の授業って、本当に「丁寧」という一言に尽きますね。「分からない子がいない」ようにと、丁寧に丁寧にステップが進められていくことに、なんか小学校の先生ってすごいなあと改めて感心しました。一生懸命それについていく子どもたちもかわいい。
. . . 本文を読む
文科省が、公立小中学校の統廃合に関する手引案を公表しました。
市町村立の学校については、基本的にそれぞれの市町村が設置者として統廃合をするかどうかを検討するべきですが、今回の手引は、検討のための一つの判断基準を参考として示したものです。もちろん拘束力はありません。国がこんな手引を示す背景には、少子化がますます進行する中、学校規模に「課題がある」と認識しながら、統廃合などについて検討している市町村 . . . 本文を読む
NPOブックスタートによる「子ども・社会を考える」講演会シリーズに、「赤ちゃん・絵本・ことば」というタイトルの本があって、詩人の谷川俊太郎さんの対談(聞き手:草野満代さん)が紹介されています。
「にゅるぺろりん」、「ぽぱーぺ ぽぴぱっぷ」、「すーびょーるーみゅー」なんていう、一見「無意味な言葉」が次々と飛び出してくる谷川俊太郎さんの絵本。谷川さんは、大人は意味に縛られている、とおっしゃる。
. . . 本文を読む
「アイデアが世界を救う。荒野を転がる地雷撤去ボール」
http://whats.be/105172
実際、地雷除去にどれだけの効果があるのかはわからない。でも、このアイデアに、彼、ハッサニさんの「思い」が込められているのは確かですね。1億個の地雷を、一つでも二つでも取り除きたいという思い。
こういうアイデアを生み出す人にはもうなれないけれど、こういうアイデアを生み出すことがどんなに素敵なこと . . . 本文を読む
テレビで、「ディスレクシア」(読み書き困難=知的に問題はないものの読み書きの能力に著しい困難を持つ症状)のことを取り上げていました。会話でのコミュニケーションや通常の社会生活には問題はないのに、文字を読んだり書いたりすることが不得意という症状で、学習障害の一種と捉えられています。ディスレクシアを抱える人は、目から入る情報を正確にすばやく処理できない。人によっては、文字がかすんで見えたり、重なって見 . . . 本文を読む
全米オープンで準優勝した錦織圭選手。小さい頃の映像なんかをみると、やっぱりもともと才能はあったんだなあと思う。そして、彼自身の努力はもちろんのこと、指導者に恵まれたことも彼を世界一流の選手に育て上げた大きな要因なのでしょう。
あるテレビでは、小学校の頃からバドミントンの有力選手として期待されていた少女が、中学2年の時にスカウトされたことをきっかけに、モデルの世界に入ったという逸話を紹 . . . 本文を読む
数年前にNHKスペシャルで放映された「4年1組命の授業 金森学級の35人」の金森先生、今は大学の先生をされているのですね。
先日、中央教育審議会の道徳教育専門部会が、「道徳」の教科化に向けた方向性を示したことを受けての金森先生の寄稿が先日の新聞に掲載されていました(2014年8月19日付け東奥日報)。佐世保の事件も引き合いにしながら、金森先生は、小学校の先生として自ら実践してきた「命の教育」 . . . 本文を読む
小学校で「お昼寝タイム」だって。こりゃびっくりですね。宮城県のある小学校での試みです。「児童の情緒安定と集中力アップが狙い」で、「子どもたちには『気分がすっきりする』と好評」なんだとか。
15分間「うつぶせ寝」するだけで、頭スッキリするのは確かにわかるけど、それって小学生に必要なもんでしょうか…。子どもは、昼は目一杯活動して、夜ぐっすり眠るものなんじゃないのかなあ。早起きして、朝ウ . . . 本文を読む
今日は午後から夜にかけて、楽しい一日でした。なぜなら、3つのタイプの違う学びの場に、しかもそれぞれに別の立場で居合わせることができたからです。
一つ目は、県立学校長研究協議会。オブザーバーとして参加。後半、グループに分かれての協議もあって、脇から見ていただけですが、今の学校経営の難しさが垣間見えるような気がしました。それにしても、「そこにいる全員が校長」という景色はなかなか見られるものではなく、 . . . 本文を読む
朝日新聞地方版で、青森県ゆかりの様々な識者が教育を語る「教育2014私の「論」」が連載されています。まあ、このシリーズを読んでいると、ほんと、日本人ってみんなが「教育評論家」だよなあと改めて感じます。誰もが教育(学校教育)について一家言持っていて、いつでも語ることができる。
さて、本日(2014年6月14日)付けには、八戸市出身の作家・室井佑月さんが登場。 . . . 本文を読む