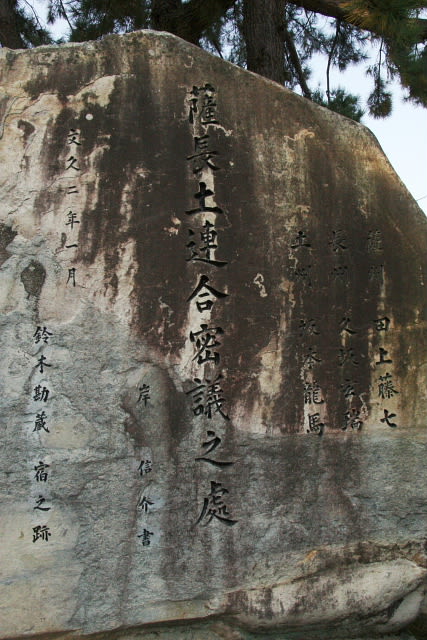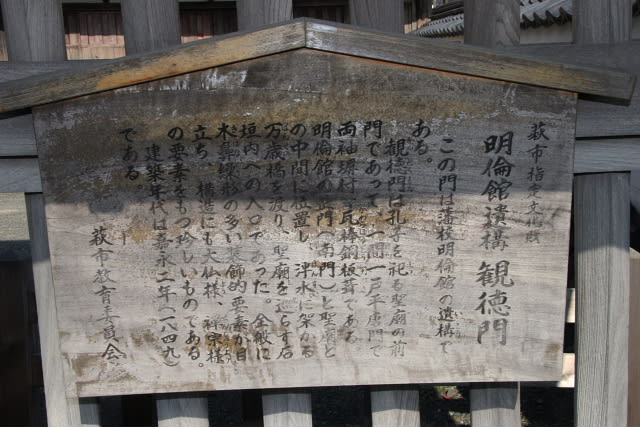保存地区にひと際目立つ建物が菊屋住宅ですが、屋内に入ると見事な庭園を見ることができます。

菊屋家は、毛利藩御用達の豪商ですが、裁判やお役所仕事などの藩の御用に使われたようです。
徳川幕府からの要人を迎えたりするので、立派な庭園が造られたのでしょう。

写真は撮り忘れましたが、この部屋には雪舟の本物の掛け軸が展示してあリます。

皇室をも招いたという菊屋ですので、萩城城下町の有名家屋としての贅を凝らしています。

母屋には商家なので、立派な帳場もあります。

こちらは土間なのですが、空間も広く取ってあり、採光も工夫されていて現在でも使用できそうです。
コンクリートのない当時は、海水から塩を作る際にできるにがりを混ぜ土をこね固めたようです。

母屋から付属屋への通路も、雨に塗れないように十分な屋根と移動スペースがとられています。

菊屋家住宅では、毎年10月20日から11月23日まで、期間限定で秋のお庭を見ることができます。

期間限定という言葉に喜んで、お庭のほうに入らせていただきました。

庭園の様子は次回に紹介いたします。
続く...........................................................。

菊屋家は、毛利藩御用達の豪商ですが、裁判やお役所仕事などの藩の御用に使われたようです。
徳川幕府からの要人を迎えたりするので、立派な庭園が造られたのでしょう。

写真は撮り忘れましたが、この部屋には雪舟の本物の掛け軸が展示してあリます。

皇室をも招いたという菊屋ですので、萩城城下町の有名家屋としての贅を凝らしています。

母屋には商家なので、立派な帳場もあります。

こちらは土間なのですが、空間も広く取ってあり、採光も工夫されていて現在でも使用できそうです。
コンクリートのない当時は、海水から塩を作る際にできるにがりを混ぜ土をこね固めたようです。

母屋から付属屋への通路も、雨に塗れないように十分な屋根と移動スペースがとられています。

菊屋家住宅では、毎年10月20日から11月23日まで、期間限定で秋のお庭を見ることができます。

期間限定という言葉に喜んで、お庭のほうに入らせていただきました。

庭園の様子は次回に紹介いたします。
続く...........................................................。




























 』
』