西門、『延平門(エンペイモン)』です。
JR石川町駅が最寄り駅になります。

平和と平安のやすらぎが末永く続くことを願った門だそうで、守護神は白虎神で色は白です。

柱のてっぺんや見上げた部分に、勇ましい白虎の彫刻を見ることができます。

北門、『玄武門(ゲンブモン)』です。
子孫の繁栄をもたらす、守護神は玄武神です。

『玄武門』、北門の前の道路を渡ると、横浜公園・横浜スタジアムです。関内方面に向いた門です。

黒門の玄武は他の聖獣と比べ聞き慣れない感じがあひますが、蛇のように長い首をもつ亀のことから、子孫の繁栄をもたらす門なのだそうです。
東西南北の門を回るだけでも、結構いい距離で、いい運動になりました。

それでは、西門『延平門』に戻り、西門通りを進むと、中華街大通りの入り口に『善隣門』があります。
『善隣門』は中華街でいちばん最初にできた門です。
横浜中華街のシンボル的存在で、高さ約12m、幅約8mです。
銘板に、隣国や隣家と仲良くするという「親仁善隣」という言葉を掲げ、名称が「善隣門」になりました。

終戦後に当時の平沼亮三市長や内山岩太郎県知事がサンフランシスコのチャイナタウンを視察し、横浜中華街も同様に観光地として発展させられるのではないかと考え、初代の善隣門は1955年に完成しています。

現在の善隣門は二代目で、1989年の横浜開港130周年を記念した横浜博覧会にあわせて建て替えられました。

「親仁善隣」を掲げた『善隣門』より、『朝陽門』を結ぶ通りがメイン通りになる中華街大通りです。

続く........................................................。
JR石川町駅が最寄り駅になります。

平和と平安のやすらぎが末永く続くことを願った門だそうで、守護神は白虎神で色は白です。

柱のてっぺんや見上げた部分に、勇ましい白虎の彫刻を見ることができます。

北門、『玄武門(ゲンブモン)』です。
子孫の繁栄をもたらす、守護神は玄武神です。

『玄武門』、北門の前の道路を渡ると、横浜公園・横浜スタジアムです。関内方面に向いた門です。

黒門の玄武は他の聖獣と比べ聞き慣れない感じがあひますが、蛇のように長い首をもつ亀のことから、子孫の繁栄をもたらす門なのだそうです。
東西南北の門を回るだけでも、結構いい距離で、いい運動になりました。

それでは、西門『延平門』に戻り、西門通りを進むと、中華街大通りの入り口に『善隣門』があります。
『善隣門』は中華街でいちばん最初にできた門です。
横浜中華街のシンボル的存在で、高さ約12m、幅約8mです。
銘板に、隣国や隣家と仲良くするという「親仁善隣」という言葉を掲げ、名称が「善隣門」になりました。

終戦後に当時の平沼亮三市長や内山岩太郎県知事がサンフランシスコのチャイナタウンを視察し、横浜中華街も同様に観光地として発展させられるのではないかと考え、初代の善隣門は1955年に完成しています。

現在の善隣門は二代目で、1989年の横浜開港130周年を記念した横浜博覧会にあわせて建て替えられました。

「親仁善隣」を掲げた『善隣門』より、『朝陽門』を結ぶ通りがメイン通りになる中華街大通りです。

続く........................................................。

























































































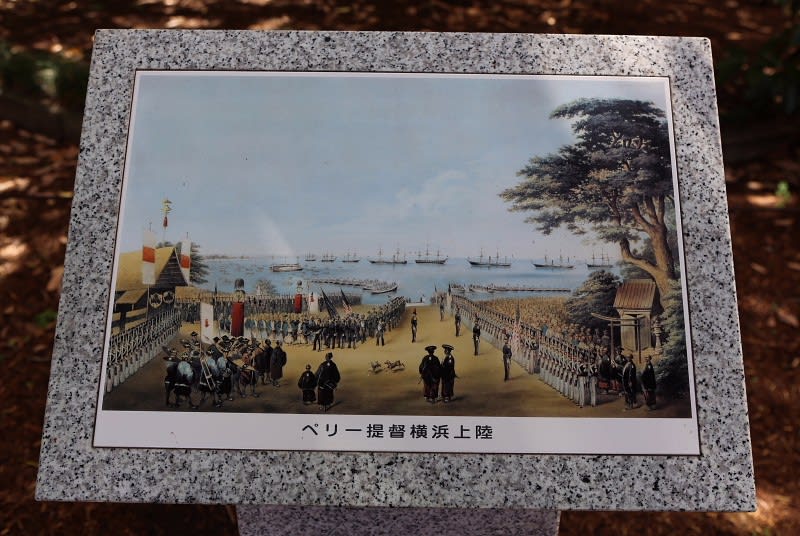
















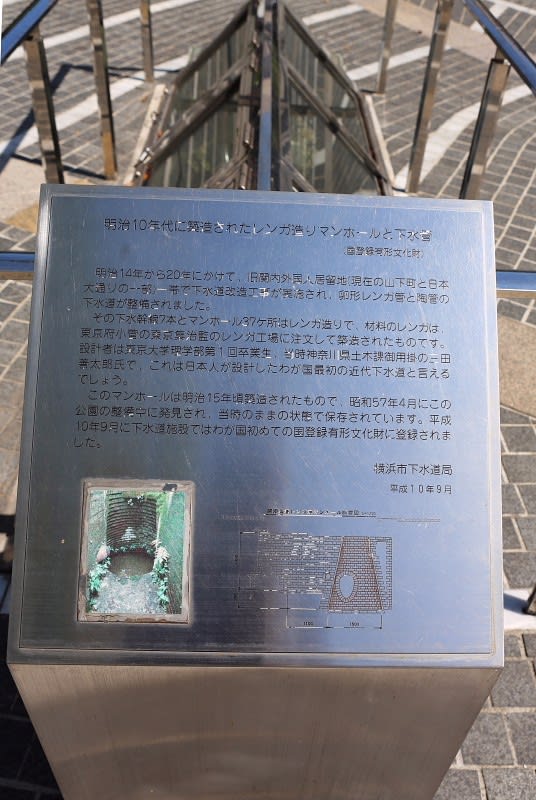




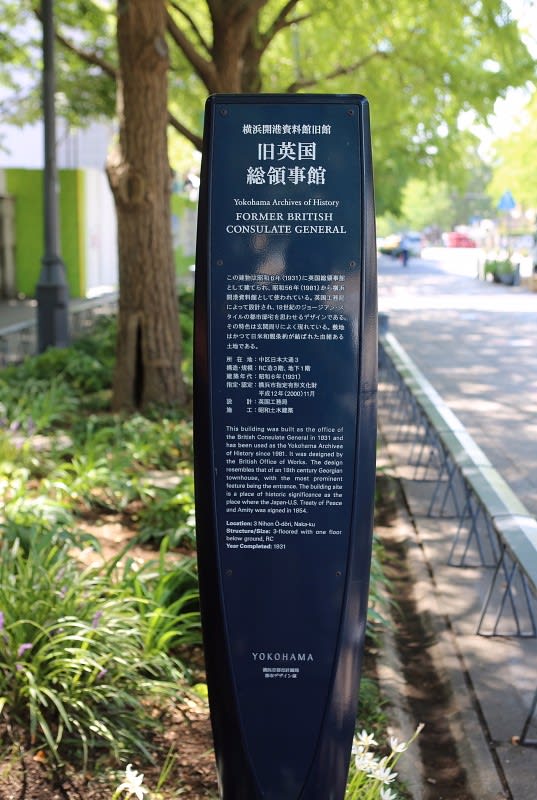













 わが日の本は島国よ
わが日の本は島国よ













