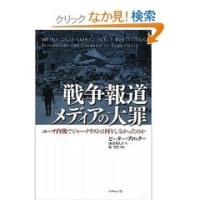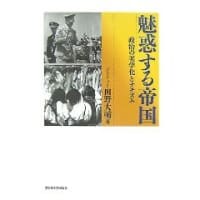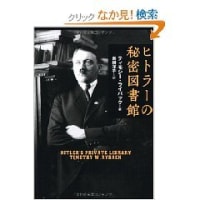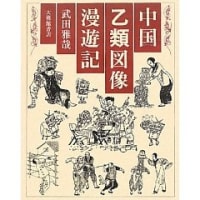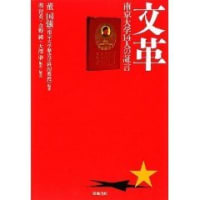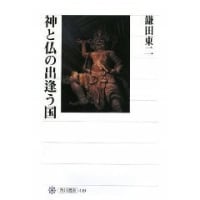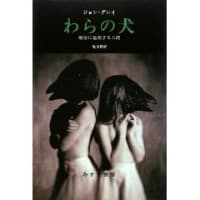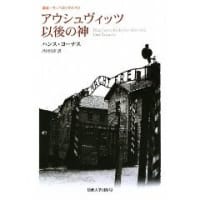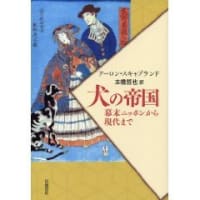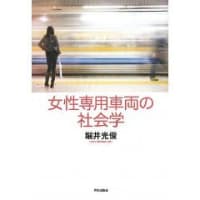今 クラッシツク評論で活躍している人と言えば、片山杜秀氏を思い浮かべるが、本書の許光俊氏は片山氏に比べると相当辛口という感じがする。許氏は本場でのコンサート体験が豊富と紹介があるが、実際何度も海外公演に行かれているようだ。趣味とはいえ相当のお金をつぎ込んでいると言ってよい。本書はハイドン、モーツアルト、ベートーベンの交響曲から始まって、ロマン派からフランスの交響曲、ブラームスから国民楽派、ブルッルクナー、マーラー、ショスタコービッチまで網羅している。意外だったのはベートーベンの交響曲についての評価が低い事だった。
有名な第九について曰く、実はオーケストラにも歌手にも高い力量が求められ、指揮者も並大抵の人では凡庸な演奏に終始してしまうので難しい作品です。最終楽章で、「歓喜の歌」、つまり喜びこそが人々を結び付けてくれると歌われます。うん、まあ、言いたいことは分かりますが。作曲者の善意や理想主義を批判するつもりはないのですが、どうもナイーブすぎて、正直なところ私は苦手ですと。演奏会ではシラーの詩をドイツ語で歌うので、聴衆のほとんどは詩の内容を理解して聞いているわけではない。日本語に訳したものをを聞いたらまた印象は変わるのではないか。確かに訳詞をを読むと気恥ずかしくなる側面はある。万博の開会式で雨の中を市民の合唱隊プラス佐渡裕の指揮で最終楽章が演奏されていたが、これには度肝を抜かれた。なんで第九なのか。意味が分からなかった。許氏はこれを見てどう思われたのか、聞いてみたい。というのも氏はこうも言っているからだ。すなわち、「21世紀の今になって『第九』を完全に受け入れられるのか、疑問に思います。アウシュビッツの後で、いやそれに限らず、世界的な蛮行がいろいろ伝えられる中で、『第九』に感動するのは、野蛮なのではないか」と。その気恥ずかしさを無視して、嬉々として演奏することの傲慢さを嫌った発言と思う。
私が印象深く思ったのは、社会主義国家における作曲家と指揮者についての記述だった。まず東ドイツ出身のクルト・マズアとヘルベルト・ブロムシュテットについて、音楽自体に特別のアピールも、個の表出も、内面性もないと一刀両断。それはもしかしたら強い個性の表現はブルジョワ的で望ましくないからだろうか。指揮者といえども平凡な労働者の一人だったのだろうかと推察して見せる。社会主義が音楽に影響を及ぼす一側面かも知れない。ブロムシュテットについては最近NHKのクラシック音楽館でマーラーの第八番を指揮していたの見たが、御歳97でよくやるなあと感心して見ていたが、許氏は巨匠でも何でもない。何のオリジナリティーもないし、つまらない指揮者だと手厳しい。
同じ社会主義国家の作曲家のショスタコービッチについては、彼を「ソヴィエト」最大の作曲家だと評価したうえで、彼の作品を分析している。有名な第七番「レニングラード」について、第一楽章に現れる主題を軽妙・軽薄・冗談のようだという。独ソ戦という破壊や暴力を暗示したいのに滑稽に登場する。それが最後は異様かつ不気味に盛り上がる。この主題の象徴性についていろんな可能性を示唆するが、何であるかは断言できない。それがショスタコービッチの技量だともいえる。とにかく当局からダメ出しされなかったのだから。最近またNHKの同番組でトウガン・ソヒエフ(ロシア人)の指揮するN響の「レニングラード」を聴いたが、この批評を読んでよくわかった。最後の盛り上がりは多分ソ連の民衆の勝利のの声なのだろう。
またショスタコービッチの交響曲の音質についてラジオで中継するというのがポイントで、高い音域も低い音域も削られていて、中音域で大音量を出すように作られている。要するに電話で音楽を聴いているようなものだからああいう曲になるのだという指摘はまことに面白い。これぞ社会主義の音楽という感じだ。したがって鑑賞者は作曲者が言葉の変わりに音楽に託したものを感じ取ることが必要と述べる。大事な視点だ。これを機にショスタコービッチの交響曲を聞き直してみようと思う。
有名な第九について曰く、実はオーケストラにも歌手にも高い力量が求められ、指揮者も並大抵の人では凡庸な演奏に終始してしまうので難しい作品です。最終楽章で、「歓喜の歌」、つまり喜びこそが人々を結び付けてくれると歌われます。うん、まあ、言いたいことは分かりますが。作曲者の善意や理想主義を批判するつもりはないのですが、どうもナイーブすぎて、正直なところ私は苦手ですと。演奏会ではシラーの詩をドイツ語で歌うので、聴衆のほとんどは詩の内容を理解して聞いているわけではない。日本語に訳したものをを聞いたらまた印象は変わるのではないか。確かに訳詞をを読むと気恥ずかしくなる側面はある。万博の開会式で雨の中を市民の合唱隊プラス佐渡裕の指揮で最終楽章が演奏されていたが、これには度肝を抜かれた。なんで第九なのか。意味が分からなかった。許氏はこれを見てどう思われたのか、聞いてみたい。というのも氏はこうも言っているからだ。すなわち、「21世紀の今になって『第九』を完全に受け入れられるのか、疑問に思います。アウシュビッツの後で、いやそれに限らず、世界的な蛮行がいろいろ伝えられる中で、『第九』に感動するのは、野蛮なのではないか」と。その気恥ずかしさを無視して、嬉々として演奏することの傲慢さを嫌った発言と思う。
私が印象深く思ったのは、社会主義国家における作曲家と指揮者についての記述だった。まず東ドイツ出身のクルト・マズアとヘルベルト・ブロムシュテットについて、音楽自体に特別のアピールも、個の表出も、内面性もないと一刀両断。それはもしかしたら強い個性の表現はブルジョワ的で望ましくないからだろうか。指揮者といえども平凡な労働者の一人だったのだろうかと推察して見せる。社会主義が音楽に影響を及ぼす一側面かも知れない。ブロムシュテットについては最近NHKのクラシック音楽館でマーラーの第八番を指揮していたの見たが、御歳97でよくやるなあと感心して見ていたが、許氏は巨匠でも何でもない。何のオリジナリティーもないし、つまらない指揮者だと手厳しい。
同じ社会主義国家の作曲家のショスタコービッチについては、彼を「ソヴィエト」最大の作曲家だと評価したうえで、彼の作品を分析している。有名な第七番「レニングラード」について、第一楽章に現れる主題を軽妙・軽薄・冗談のようだという。独ソ戦という破壊や暴力を暗示したいのに滑稽に登場する。それが最後は異様かつ不気味に盛り上がる。この主題の象徴性についていろんな可能性を示唆するが、何であるかは断言できない。それがショスタコービッチの技量だともいえる。とにかく当局からダメ出しされなかったのだから。最近またNHKの同番組でトウガン・ソヒエフ(ロシア人)の指揮するN響の「レニングラード」を聴いたが、この批評を読んでよくわかった。最後の盛り上がりは多分ソ連の民衆の勝利のの声なのだろう。
またショスタコービッチの交響曲の音質についてラジオで中継するというのがポイントで、高い音域も低い音域も削られていて、中音域で大音量を出すように作られている。要するに電話で音楽を聴いているようなものだからああいう曲になるのだという指摘はまことに面白い。これぞ社会主義の音楽という感じだ。したがって鑑賞者は作曲者が言葉の変わりに音楽に託したものを感じ取ることが必要と述べる。大事な視点だ。これを機にショスタコービッチの交響曲を聞き直してみようと思う。