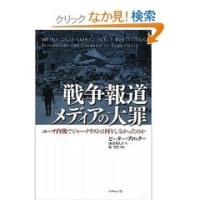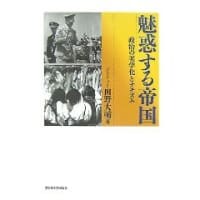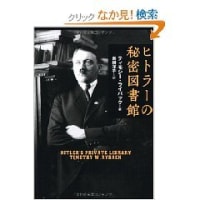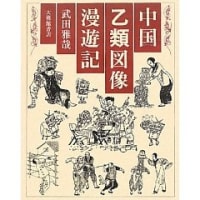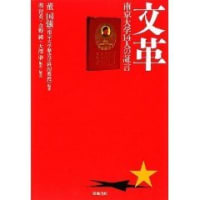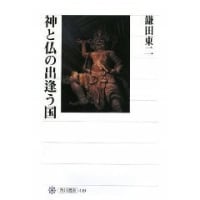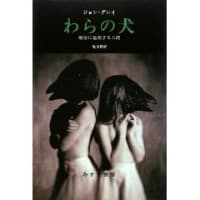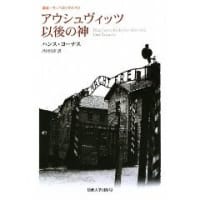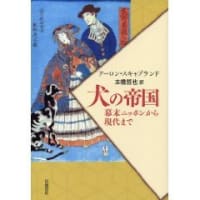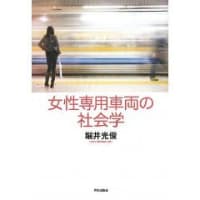この作家の存在は今まで知らなかったが、御年77歳の有名作家・詩人らしい。読書家を自称していた自分の底の浅さを自覚した次第。本書の主人公は夏実という専業主婦で40歳前後。会社員の夫と二人の男の子がおり、小田急沿線の築7年の中古マンションに住んでいる。時代は1990年代の東京、実家は目白で大卒らしい。この設定からすると多分私と同世代という感じがする。1980年頃結婚して家庭に入り、専業主婦になったと思われる。すると夫の給料だけでやりくりするわけだが、東京でマンションを買って生活するわけだから、夫は相当高い給料を取っていることがわかる。夫婦共働きが最近のトレンドだが、まだ結婚が永久就職と言われた時代なのだろう。バブル景気に沸いていた時代でもある。
この専業主婦の夏実の日常を描いているのだが、特にドラマティックな事件が起ころわけではない。平凡な子育ての主婦のルーティーンが繰り返される。まるで主婦のおしゃべりのような内容である。例えば寝室のベッドのシーツを換えるというシーンでは次のような記述がある。「1週間に1度のシーツの交換日であれば、、、、、1週間に1度というわけなどではもちろんなかったが、いつの頃からかシーツの交換日の前の夜に性交をする習慣になっていたのだけれど、新婚の頃は、換えたてのピンと糊のきいた木綿の布地のなめらかでひんやりした感触が官能を刺激したりしてシーツの交換日にも性交をしたものだったが、、、、、」と。この後、夫婦と子供のシーツを洗ってからお風呂に入るのだが、「まだバスタブのお湯は充分な量になっていなったけれど、クリーム色の氷砂糖の粒のようなカミツレの入浴剤を入れ、お湯を出しっぱなししながら浸り、ゆっくりシャンプーをして身体を洗った」と続く。読んでいて恥ずかしくなる描写である。あほなプチブル女の一断面を切り取って絶好調だが、わざとこのような冷笑的表現にしたのだろう。世相に対する批判なのかなと思ってしまう。
またバレンタインデー等の行事にはプレゼントを買うのだが、自分の物もいろいろ欲しいというという場面でこう続く、「ブルガリのリングだのミッソーニのカシミア・コートだのフエラガモの靴と言った類の、古風に言えばブルジュワ趣味、少し前の言い方だとブランド志向で、今ではコマダム系というらしい品物が欲しいというのではなく、(云々)」といろいろブランド物が欲しいが、今はそう簡単に変える状況ではないという反省が吐露される。まさにお気楽な日常だ。私はこれを読んで、田中康夫の『なんとなくクリスタル』『ブリリアントな午後』『たまらなくアーベイン』などのカタログ小説を思い出した。1990年代はこういうのが流行ったのだ。夏実もその流れにはまっている。
最後は夕食のおかずを求めていろいろ思案するが、そうこうしているうちに「少し吐き気がして、電車の振動とは別の軽いめまいのように目の前が微かに揺れる」で終わる。この「めまい」こそ夏実の存在の不安が顕在化したものと言えよう。仕事の苦しみから逃れられた主婦業を謳歌している人間の根源的な不安が現れたのだろう。そうでなければ、ただの主婦の与太話で終わってしまう。
この専業主婦の夏実の日常を描いているのだが、特にドラマティックな事件が起ころわけではない。平凡な子育ての主婦のルーティーンが繰り返される。まるで主婦のおしゃべりのような内容である。例えば寝室のベッドのシーツを換えるというシーンでは次のような記述がある。「1週間に1度のシーツの交換日であれば、、、、、1週間に1度というわけなどではもちろんなかったが、いつの頃からかシーツの交換日の前の夜に性交をする習慣になっていたのだけれど、新婚の頃は、換えたてのピンと糊のきいた木綿の布地のなめらかでひんやりした感触が官能を刺激したりしてシーツの交換日にも性交をしたものだったが、、、、、」と。この後、夫婦と子供のシーツを洗ってからお風呂に入るのだが、「まだバスタブのお湯は充分な量になっていなったけれど、クリーム色の氷砂糖の粒のようなカミツレの入浴剤を入れ、お湯を出しっぱなししながら浸り、ゆっくりシャンプーをして身体を洗った」と続く。読んでいて恥ずかしくなる描写である。あほなプチブル女の一断面を切り取って絶好調だが、わざとこのような冷笑的表現にしたのだろう。世相に対する批判なのかなと思ってしまう。
またバレンタインデー等の行事にはプレゼントを買うのだが、自分の物もいろいろ欲しいというという場面でこう続く、「ブルガリのリングだのミッソーニのカシミア・コートだのフエラガモの靴と言った類の、古風に言えばブルジュワ趣味、少し前の言い方だとブランド志向で、今ではコマダム系というらしい品物が欲しいというのではなく、(云々)」といろいろブランド物が欲しいが、今はそう簡単に変える状況ではないという反省が吐露される。まさにお気楽な日常だ。私はこれを読んで、田中康夫の『なんとなくクリスタル』『ブリリアントな午後』『たまらなくアーベイン』などのカタログ小説を思い出した。1990年代はこういうのが流行ったのだ。夏実もその流れにはまっている。
最後は夕食のおかずを求めていろいろ思案するが、そうこうしているうちに「少し吐き気がして、電車の振動とは別の軽いめまいのように目の前が微かに揺れる」で終わる。この「めまい」こそ夏実の存在の不安が顕在化したものと言えよう。仕事の苦しみから逃れられた主婦業を謳歌している人間の根源的な不安が現れたのだろう。そうでなければ、ただの主婦の与太話で終わってしまう。