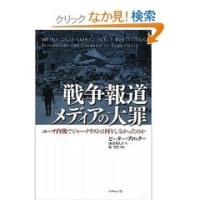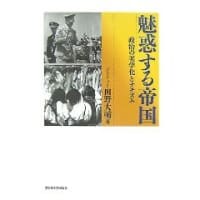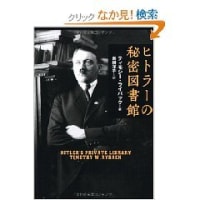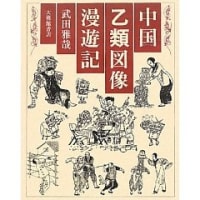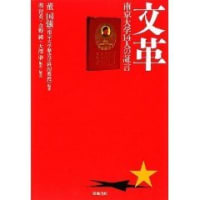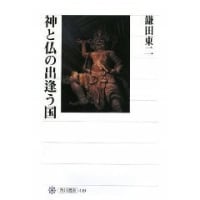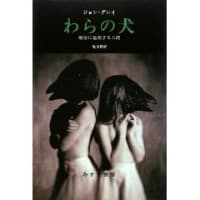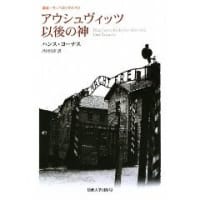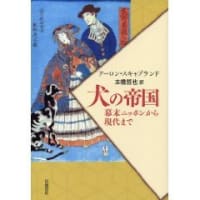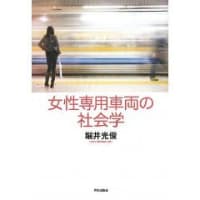日ソ戦争とは、本書の表紙の解説にはこうある。「1945年8月8日から9月上旬まで満洲・朝鮮半島・南樺太・千島列島で行われた第二次世界大戦最後の全面戦争である。短期間ながら両軍の参加兵力は200万人を超え、玉音放送後に戦闘が始まる地域もあり、戦後を見据えた戦争だった。これまでソ連の中立条約破棄・非人道的な戦闘など断片的には知られてきたが、本書では新資料を駆使し、米国のソ連への参戦要請から各地での戦闘の実態、終戦までの全貌を描く」と。一読してこの戦争の悲劇を再認識することができた。
アメリカは戦争終結のためにスターリンに対日本戦参戦を要請していたが、スターリンとしては対独戦に集中するために対日戦を引き延ばしてきた。一方アメリカは原爆の投下を終戦の切り札として準備していた。結局原爆投下とソ連参戦という二つの厄災に襲われて日本は無条件降伏となった。これまで満洲の開拓民やその家族といった非戦闘員を保護しなかった関東軍の責任が問われることが多かったが、著者は無差別攻撃を行ったソ連軍の責任であると断言している。そして次のように言う、「満洲におけるソ連軍の加害を追及すると、満州国時代の日本人から現地民への加害を持ち出して相対化を図ろうとする議論が見受けられる。しかし、それはソ連軍の蛮行を不問に付す理由にはならないだろう」と。正しい見解だと思う。
日本人狩りの例として満洲最大の都市ハルビンの例が挙げられている。ハルビンの1944年の人口は約68万人で、このうち50万人がスターリンの命令でソ連に移送された。軍人だけでは人数が足りず民間人が「員数合わせ」として標的にされた。そのノルマ(ロシア語)を達成しなければソ連軍が処罰されたという。そして彼らは鉄道の改築に従事させられた。またソ連兵の蛮行について指導者がこれを黙認していたことが書かれている。スターリンはソ連兵の評判が悪いと示唆する相手にこう擁護した「兵士たちは疲れ、長く困難な戦いで消耗している。『上品な知識人』の観点から見るなど間違いだ」と。スターリンは無断での退却や、捕虜になることには厳罰で臨んだが、勇敢に戦い勝利に貢献すれば他を大目に見ていた。実際ソ連軍では強姦や略奪に厳しい処罰を下されることはなかったので、蛮行を助長した。これは対独戦争でも見られ、大戦末期ソ連軍によるドイツ人女性に対する性加害も尋常ではなかったといわれている。
これを助長した要因として、日本軍や警察は武装解除されており、日本人男性の多くも軍に召集されていて、ソ連軍の蛮行を留める者がいなかった。それでソ連軍の軍紀も緩んでいたことがある。さらにソ連特有の男尊女卑の社会構造にあるという説を挙げている。そしてソ連における嗜好品や日用品の不足が日本人から貴金属や腕時計、万年筆まで強奪したことも要因だ言っている。そもそも1930年代の大粛清や強制労働など、ソ連は自国の市民の人権すら尊重する国ではなかった。そうした国家が占領地の住民や捕虜を丁重に扱うことはないという著者の言葉は正鵠を得ている。スターリン政権下のウクライナの大飢餓事件を見れば明らかだ。ソ連は共産党が崩壊して今ロシアとなったが、この伝統はプーチンの権力化でどうなっているのか興味が湧く。対ウクライナ戦争でロシア軍の蛮行がないのかしっかりチェックする必要がある。本書は「ソ連軍の満洲侵攻図」(p78~79)「極東ソ連軍主要部隊の編制」(p80)「ソ連軍の指揮系統(日ソ戦争当時)」(P81)など貴重な資料が掲載されている。労作であることは確かだ。
アメリカは戦争終結のためにスターリンに対日本戦参戦を要請していたが、スターリンとしては対独戦に集中するために対日戦を引き延ばしてきた。一方アメリカは原爆の投下を終戦の切り札として準備していた。結局原爆投下とソ連参戦という二つの厄災に襲われて日本は無条件降伏となった。これまで満洲の開拓民やその家族といった非戦闘員を保護しなかった関東軍の責任が問われることが多かったが、著者は無差別攻撃を行ったソ連軍の責任であると断言している。そして次のように言う、「満洲におけるソ連軍の加害を追及すると、満州国時代の日本人から現地民への加害を持ち出して相対化を図ろうとする議論が見受けられる。しかし、それはソ連軍の蛮行を不問に付す理由にはならないだろう」と。正しい見解だと思う。
日本人狩りの例として満洲最大の都市ハルビンの例が挙げられている。ハルビンの1944年の人口は約68万人で、このうち50万人がスターリンの命令でソ連に移送された。軍人だけでは人数が足りず民間人が「員数合わせ」として標的にされた。そのノルマ(ロシア語)を達成しなければソ連軍が処罰されたという。そして彼らは鉄道の改築に従事させられた。またソ連兵の蛮行について指導者がこれを黙認していたことが書かれている。スターリンはソ連兵の評判が悪いと示唆する相手にこう擁護した「兵士たちは疲れ、長く困難な戦いで消耗している。『上品な知識人』の観点から見るなど間違いだ」と。スターリンは無断での退却や、捕虜になることには厳罰で臨んだが、勇敢に戦い勝利に貢献すれば他を大目に見ていた。実際ソ連軍では強姦や略奪に厳しい処罰を下されることはなかったので、蛮行を助長した。これは対独戦争でも見られ、大戦末期ソ連軍によるドイツ人女性に対する性加害も尋常ではなかったといわれている。
これを助長した要因として、日本軍や警察は武装解除されており、日本人男性の多くも軍に召集されていて、ソ連軍の蛮行を留める者がいなかった。それでソ連軍の軍紀も緩んでいたことがある。さらにソ連特有の男尊女卑の社会構造にあるという説を挙げている。そしてソ連における嗜好品や日用品の不足が日本人から貴金属や腕時計、万年筆まで強奪したことも要因だ言っている。そもそも1930年代の大粛清や強制労働など、ソ連は自国の市民の人権すら尊重する国ではなかった。そうした国家が占領地の住民や捕虜を丁重に扱うことはないという著者の言葉は正鵠を得ている。スターリン政権下のウクライナの大飢餓事件を見れば明らかだ。ソ連は共産党が崩壊して今ロシアとなったが、この伝統はプーチンの権力化でどうなっているのか興味が湧く。対ウクライナ戦争でロシア軍の蛮行がないのかしっかりチェックする必要がある。本書は「ソ連軍の満洲侵攻図」(p78~79)「極東ソ連軍主要部隊の編制」(p80)「ソ連軍の指揮系統(日ソ戦争当時)」(P81)など貴重な資料が掲載されている。労作であることは確かだ。