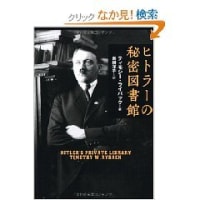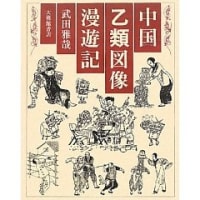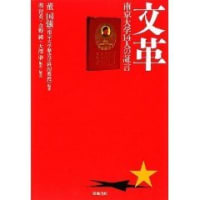副題は「スターリン時代の家族の歴史」で上下二巻、1000ページを超える力作だ。第一章「革命の時代」(1917~1928)から第九章「記憶」(1956~2006)まで共産主義に翻弄された家族の苦難を具体的に記す。NHKの番組に「フアミリーヒストリー」というのがあるが、このロシア版は反革命の烙印を押されて収容所に送られるか処刑されるかという恐怖に日常的に晒されていることに大きな特徴がある。しかもそうなったらなったでそれを甘受せざるを得ないという諦念が支配していることに大きな驚きを覚えた。逆にいうとスターリンの絶対性・無謬性が国民の意識に浸透していたことを物語るものだ。それを支えていたのが秘密警察と軍隊で、国民はこの暴力装置に怯えながら日々の生活を送らざるを得なかった。これが長年に渡ると、人々の心は自己卑下に向かい、反権力の志向が生まれにくくなる。全体主義の恐ろしさである。
ロシア革命を樹立したボルシェビキ(ロシア社会民主党左派)は革命党のエリートとして自己改造に務めようとする中で、その独裁政治を支える社会的基盤は「プロレタリアート」であるとボルシェビキ自身は空想していたが、都市に大量に流入してくる逃亡農民や「プチブル分子」(「クラーク」、商人、聖職者その他)によって「プロレタリアート」が「薄められる」ことに対する恐れが指導部を震え上がらせた。このまま行けば、党は社会的出自を隠しおおせた不純な「利己主義者」や冒険主義者で溢れるのではないかと。そこで著者は言う、この不純分子への恐怖心は、共産党指導部が抱えていた深刻な問題、即ち自信欠如の表れで、この幹部の自信欠如が粛清を繰り返す党風を作り出した。また密告を奨励する乱暴な論理の基礎となったのは「隠れた敵」の正体を暴き出さねばならないという強迫観念だった。1930年代を通じて党指導部が人々の間に広めた思考形式のひとつは、同僚、隣人、友人、親族の中に正体を隠した敵が潜んでいるかも知れないという猜疑心だった。この猜疑心が人間関係を破壊する毒となり、1937~1938年の大テロルの火を煽りたてる油となる。「人民の敵はどんな仮面をかぶって潜んでいるかわからない。時には父親装うことさえある」というようなデマがまことしやかに語られるのだ。そして農業集団化の場合のように、「階級の敵」などの「異端分子」に対する大規模な社会的粛清が同時進行的に展開された。反対派や不服従派になり得る勢力をあらかじめ全面的に排除するのが目的だったと。これは1960年代の中国の文化大革命と同じ構造だ。
人民を相互監視体制に組み込む方法として有効だったのが、集団住宅コムナルカだった。この住宅は壁も薄く、盗み聞き、覗き見、密告が行なわれていた。共産主義の理念は個人よりも全体というのを実践したものだが、このようなプライバシー無視が、結局個人の無力化・諦念に結びつく。日本でも1960~1970年代に多くの団地が都市郊外に建てられたが、団地によっては共産党のオルグが入り、さながらコンミューンの様相を呈していたこともあった。団地の自治会はオルグに好都合な面があるだ。
スターリンはソ連共産党の司祭として人民の死命を制したが、その死後も人民はこの呪縛からなかなか抜け出せなかった。フルシチョフがスターリン批判をした後もなかなか自由にものを言う流れにならなかったと書いてある。ソ連崩壊で、共産主義の呪縛から解放されたと思いきや、今またプーチンという独裁者がロシアを牛耳って、地球規模での制圧を窺っている。中国では習近平という独裁者がポスト毛沢東を狙って存在感を増している。二人ともスターリン的独裁者であるがゆえ、氣が合うのだろう。
それはさておき、ここに登場する家族は密告によって、親が処刑されたり、子どもが収容所に送られたりしながらも、生き残った者は懸命に生きようとしている。親子の別れ、又奇跡的な再会の過程で、紡ぎだされる家族愛は一篇の小説を読むようで、深い感動を覚える。血のつながりはイズムを超えるのだ。
ロシア革命を樹立したボルシェビキ(ロシア社会民主党左派)は革命党のエリートとして自己改造に務めようとする中で、その独裁政治を支える社会的基盤は「プロレタリアート」であるとボルシェビキ自身は空想していたが、都市に大量に流入してくる逃亡農民や「プチブル分子」(「クラーク」、商人、聖職者その他)によって「プロレタリアート」が「薄められる」ことに対する恐れが指導部を震え上がらせた。このまま行けば、党は社会的出自を隠しおおせた不純な「利己主義者」や冒険主義者で溢れるのではないかと。そこで著者は言う、この不純分子への恐怖心は、共産党指導部が抱えていた深刻な問題、即ち自信欠如の表れで、この幹部の自信欠如が粛清を繰り返す党風を作り出した。また密告を奨励する乱暴な論理の基礎となったのは「隠れた敵」の正体を暴き出さねばならないという強迫観念だった。1930年代を通じて党指導部が人々の間に広めた思考形式のひとつは、同僚、隣人、友人、親族の中に正体を隠した敵が潜んでいるかも知れないという猜疑心だった。この猜疑心が人間関係を破壊する毒となり、1937~1938年の大テロルの火を煽りたてる油となる。「人民の敵はどんな仮面をかぶって潜んでいるかわからない。時には父親装うことさえある」というようなデマがまことしやかに語られるのだ。そして農業集団化の場合のように、「階級の敵」などの「異端分子」に対する大規模な社会的粛清が同時進行的に展開された。反対派や不服従派になり得る勢力をあらかじめ全面的に排除するのが目的だったと。これは1960年代の中国の文化大革命と同じ構造だ。
人民を相互監視体制に組み込む方法として有効だったのが、集団住宅コムナルカだった。この住宅は壁も薄く、盗み聞き、覗き見、密告が行なわれていた。共産主義の理念は個人よりも全体というのを実践したものだが、このようなプライバシー無視が、結局個人の無力化・諦念に結びつく。日本でも1960~1970年代に多くの団地が都市郊外に建てられたが、団地によっては共産党のオルグが入り、さながらコンミューンの様相を呈していたこともあった。団地の自治会はオルグに好都合な面があるだ。
スターリンはソ連共産党の司祭として人民の死命を制したが、その死後も人民はこの呪縛からなかなか抜け出せなかった。フルシチョフがスターリン批判をした後もなかなか自由にものを言う流れにならなかったと書いてある。ソ連崩壊で、共産主義の呪縛から解放されたと思いきや、今またプーチンという独裁者がロシアを牛耳って、地球規模での制圧を窺っている。中国では習近平という独裁者がポスト毛沢東を狙って存在感を増している。二人ともスターリン的独裁者であるがゆえ、氣が合うのだろう。
それはさておき、ここに登場する家族は密告によって、親が処刑されたり、子どもが収容所に送られたりしながらも、生き残った者は懸命に生きようとしている。親子の別れ、又奇跡的な再会の過程で、紡ぎだされる家族愛は一篇の小説を読むようで、深い感動を覚える。血のつながりはイズムを超えるのだ。