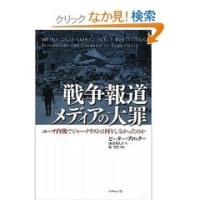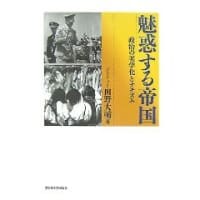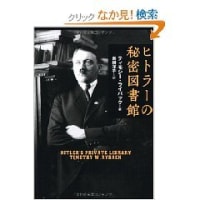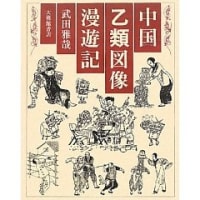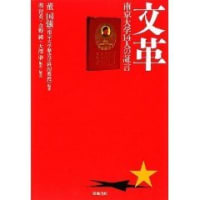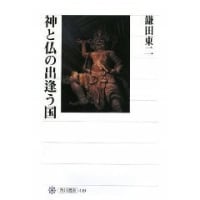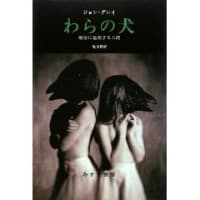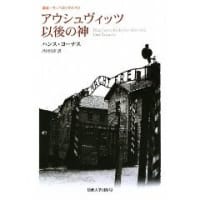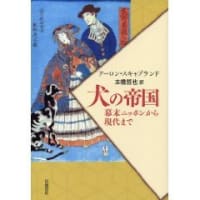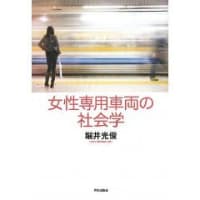本書は2018年刊行の『日本軍兵士』(中公新書)の続編で、副題は「帝国陸海軍の現実」。先の大戦では、約230万人の日本軍兵士が死亡したが、その多くは戦闘による死ではなく、その多くは病気や飢餓による死(戦病死)、大量の海歿死(船舶の沈没による死)、特攻死(特別攻撃による死)であったという前著の指摘には多くの反響があった。今から思えば圧倒的に国力の違うアメリカに戦争を仕掛けたことが不思議だが、その当時の日本軍の幹部に蔓延していた精神論によって押し切られた形になったのは返す返すも残念なことである。真珠湾の奇襲攻撃でアメリカの連合艦隊に打撃を与え、その後有利な形で講和条約を結ぶというのが連合艦隊司令長官・山本五十六の考えだったという。彼は半年間くらいならアメリカと戦えると言っていた。しかし国力の差はいかんともしがたく、最後は広島・長崎による原爆投下で、一般市民に多大の犠牲者が出たことは痛恨のきわみである。
国力の差は兵士の給養の違いに顕著に現れる。1941年から米軍が導入した個人戦闘糧食(Cレーション)は後方から十分な食事を提供できない場合に一人ひとりの兵士に支給される非常食であるが、その中身がすごい。肉と豆の煮込みなどの主食の他、チーズ、クラッカー、デザート、インスタントコーヒー、たばこなどがセットになっていた。個人戦闘糧食としては乾パンくらいしか携行していない日本軍から見ればあまりにも贅沢な糧食だった。このことはアメリカ兵と比較して圧倒的な体格差として現れた。本書では兵士の健康に関してケアーが足りなかった例として、兵士の歯の治療に当たる歯科軍医の育成の軽視、栄養失調や精神的な病に対するケアー、ヘルメット導入の遅れ、防蚊装備(マラリヤ防止)の不備、劣悪な装備と過重負担(革靴を履いたことがない兵士が多かった)、日本海軍の駆逐艦や潜水艦の居住性の悪さ等々、まともに戦えない現実が報告されている。
いわば兵士の人命軽視が日本軍の底流にあったと言わざるを得ない。例えば零式戦闘機(ゼロ戦)は小回りが利いて空中戦で活躍したが、軽量化のために操縦席周りの鉄板が薄く、敵の機銃の攻撃でパイロットが死ぬ場合が多かった。これに対してライバル機のグラマンヘルキャットは重厚な鉄板で操縦席を囲み、パイロットを守ろうとする設計になっていた。戦闘の中でもいかに生き残るかを考えたアメリカ軍に対していかに死ぬかを指導した日本軍の違いが出ている。「一億玉砕」という言葉はそのメンタリティーの表れといえる。
本書で興味深い指摘がもう一つあった。それは「犠牲の不平等」という言葉で、下っ端の兵士ほど死亡率が高いのかという問題である。本書では断定はしていないが、高学歴者は低学歴者より死亡率が低いことは否めないと言っている。しかし、日本軍の場合、人命を軽視した突撃第一主義を特質にしているため、第一線で戦う将校の損耗は一層高くなったとの指摘もある。戦争末期になると軍隊生活未経験者が招集され、兵士としてはほとんど「素人」の集団になった。これを指揮する将校はこれら素人の指揮中に命を落とすこともあっただろう。
この「犠牲の不平等」で思い起こすことがある。戦争末期に海軍兵学校が入学定員を大幅に増やして入学させたということである。これは敗戦後の日本を指導するエリートを少しでも残すための方策と言われている。兵学校に囲って終戦を待つという作戦である。若い頃私が勤めていた学校には海兵上がりの教員が結構いた。海軍の思惑は成功したと言えるかもしれない。学歴は高い方が得をするのかもしれない。
国力の差は兵士の給養の違いに顕著に現れる。1941年から米軍が導入した個人戦闘糧食(Cレーション)は後方から十分な食事を提供できない場合に一人ひとりの兵士に支給される非常食であるが、その中身がすごい。肉と豆の煮込みなどの主食の他、チーズ、クラッカー、デザート、インスタントコーヒー、たばこなどがセットになっていた。個人戦闘糧食としては乾パンくらいしか携行していない日本軍から見ればあまりにも贅沢な糧食だった。このことはアメリカ兵と比較して圧倒的な体格差として現れた。本書では兵士の健康に関してケアーが足りなかった例として、兵士の歯の治療に当たる歯科軍医の育成の軽視、栄養失調や精神的な病に対するケアー、ヘルメット導入の遅れ、防蚊装備(マラリヤ防止)の不備、劣悪な装備と過重負担(革靴を履いたことがない兵士が多かった)、日本海軍の駆逐艦や潜水艦の居住性の悪さ等々、まともに戦えない現実が報告されている。
いわば兵士の人命軽視が日本軍の底流にあったと言わざるを得ない。例えば零式戦闘機(ゼロ戦)は小回りが利いて空中戦で活躍したが、軽量化のために操縦席周りの鉄板が薄く、敵の機銃の攻撃でパイロットが死ぬ場合が多かった。これに対してライバル機のグラマンヘルキャットは重厚な鉄板で操縦席を囲み、パイロットを守ろうとする設計になっていた。戦闘の中でもいかに生き残るかを考えたアメリカ軍に対していかに死ぬかを指導した日本軍の違いが出ている。「一億玉砕」という言葉はそのメンタリティーの表れといえる。
本書で興味深い指摘がもう一つあった。それは「犠牲の不平等」という言葉で、下っ端の兵士ほど死亡率が高いのかという問題である。本書では断定はしていないが、高学歴者は低学歴者より死亡率が低いことは否めないと言っている。しかし、日本軍の場合、人命を軽視した突撃第一主義を特質にしているため、第一線で戦う将校の損耗は一層高くなったとの指摘もある。戦争末期になると軍隊生活未経験者が招集され、兵士としてはほとんど「素人」の集団になった。これを指揮する将校はこれら素人の指揮中に命を落とすこともあっただろう。
この「犠牲の不平等」で思い起こすことがある。戦争末期に海軍兵学校が入学定員を大幅に増やして入学させたということである。これは敗戦後の日本を指導するエリートを少しでも残すための方策と言われている。兵学校に囲って終戦を待つという作戦である。若い頃私が勤めていた学校には海兵上がりの教員が結構いた。海軍の思惑は成功したと言えるかもしれない。学歴は高い方が得をするのかもしれない。