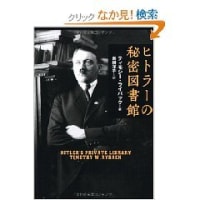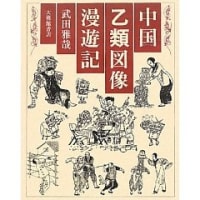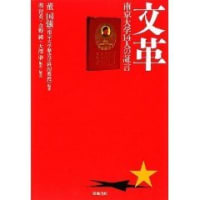本書は将棋の駒にまつわる一大ロマン小説で、毎日新聞に連載されたもの。最近将棋界は藤井聡太八段の活躍で世間の注目を浴びて、日本将棋連盟も笑いが止まらない。かつて坂田三吉をモデルにした村田英雄のヒット曲「王将」の世界から見ると隔世の感がある。棋士が世間的に認められた感が強く、勝負師として世間の裏街道を行くというイメージはもはやない。具体的にいうと、升田幸三のような棋士は今はいなくて、サラリーマン化している印象は否めない。
将棋界でプロになるためには、奨励会に入会後四段に昇段することが条件だが、満26歳の誕生日を迎えるまでに三段リーグ戦を勝ち抜いて上位二位以内に入らなければならない。このリーグ戦は年二回行われ一年間でプロになれるのは4人ということになる。天才が集うこのリーグ戦を勝ち抜くのは容易ではなく、泣く泣く将棋界を去った者は多い。本書の主人公の小磯竜介も夢破れた一人である。逆に、先述の藤井八段は中学生でプロになった天才中の天才である。竜介は故郷の長野県上田市に帰省するが、その時若くして戦死した大叔父(祖父の弟)が駒師だったことを知る。どんな人物だったのか興味を覚え、大叔父の商業学校の同級生だった老人田能村淳造を訪ねて話をきくのだが、、、、、。
話は大叔父の作った幻の駒「無月」を訪ねてシンガポール、マレーシア、ニューヨークと旅する話である。そして26歳で奨励会を退会して48歳で子供に恵まれた家族を築き上げるまでの自分史が描かれる。最後はハリウッド映画のようなハッピーエンドだ。新聞小説の型を踏襲しているという意味ではある種ありきたりと言えるが、これは構造上そうならざるを得ないという宿命を背負っている。この小説と並行して最近映画になった重松清の『とんび』(角川書店)も読んでみたが、これも新聞小説で、主人公の一代記。その中で希望と失意と再生が描かれる。それが市民の目線で描かれているので読者の共感を得やすい。それだから映画にもなるのだろう。
しかし新聞小説は逆に一日一日の積み重ねであるから、毎回山あり谷ありの構成にしないと読者に飽きられる危険がある。それを挿絵がカバーするということもあるが、なかなか難しい。かつてドイツ文学者の高橋義孝氏は、新聞小説を、「あんな細切れの文章を載せて意味あるんでしょうかねえ」とテレビで言っておられたのを思い出す。夏目漱石は朝日新聞社に入社して連載小説を書いたが、その当時の新聞の読者は今とは違ってインテリが多かった。だから読者層が明確なので、書きやすかったこともあるだろう。しかし今は大衆化して、新聞を読まない人も多い中で読者をつなぎとめるのは至難の業である。よって俗な話題で書かざるをえない。ここが辛いところだ。
著者の松浦氏はフランス文学の研究家で元東大教授。詩人・評論家・小説家でもある多才な人で、芥川賞の選考委員もされていが、昨年の芥川賞の選評がおもしろかった。氏曰く、重要なことは「小説で何をやろうとしているか」という問いだと思う。それも実際に何を「やり遂げたか」より何を「やろうとしたか」のほうに意味がある。(中略)少なくとも何ごとかをやろうと試みたという気概と意欲が伝わってくる作品を読みたいと。これは新人作家に対する要望であるが、かなりハードルが高い要望である。新人に要望した手前、自作の小説にも当然その考え方を反映させていると拝察するが、それを頭に入れながら本書を読むと面白さが倍増するかもしれない。
将棋界でプロになるためには、奨励会に入会後四段に昇段することが条件だが、満26歳の誕生日を迎えるまでに三段リーグ戦を勝ち抜いて上位二位以内に入らなければならない。このリーグ戦は年二回行われ一年間でプロになれるのは4人ということになる。天才が集うこのリーグ戦を勝ち抜くのは容易ではなく、泣く泣く将棋界を去った者は多い。本書の主人公の小磯竜介も夢破れた一人である。逆に、先述の藤井八段は中学生でプロになった天才中の天才である。竜介は故郷の長野県上田市に帰省するが、その時若くして戦死した大叔父(祖父の弟)が駒師だったことを知る。どんな人物だったのか興味を覚え、大叔父の商業学校の同級生だった老人田能村淳造を訪ねて話をきくのだが、、、、、。
話は大叔父の作った幻の駒「無月」を訪ねてシンガポール、マレーシア、ニューヨークと旅する話である。そして26歳で奨励会を退会して48歳で子供に恵まれた家族を築き上げるまでの自分史が描かれる。最後はハリウッド映画のようなハッピーエンドだ。新聞小説の型を踏襲しているという意味ではある種ありきたりと言えるが、これは構造上そうならざるを得ないという宿命を背負っている。この小説と並行して最近映画になった重松清の『とんび』(角川書店)も読んでみたが、これも新聞小説で、主人公の一代記。その中で希望と失意と再生が描かれる。それが市民の目線で描かれているので読者の共感を得やすい。それだから映画にもなるのだろう。
しかし新聞小説は逆に一日一日の積み重ねであるから、毎回山あり谷ありの構成にしないと読者に飽きられる危険がある。それを挿絵がカバーするということもあるが、なかなか難しい。かつてドイツ文学者の高橋義孝氏は、新聞小説を、「あんな細切れの文章を載せて意味あるんでしょうかねえ」とテレビで言っておられたのを思い出す。夏目漱石は朝日新聞社に入社して連載小説を書いたが、その当時の新聞の読者は今とは違ってインテリが多かった。だから読者層が明確なので、書きやすかったこともあるだろう。しかし今は大衆化して、新聞を読まない人も多い中で読者をつなぎとめるのは至難の業である。よって俗な話題で書かざるをえない。ここが辛いところだ。
著者の松浦氏はフランス文学の研究家で元東大教授。詩人・評論家・小説家でもある多才な人で、芥川賞の選考委員もされていが、昨年の芥川賞の選評がおもしろかった。氏曰く、重要なことは「小説で何をやろうとしているか」という問いだと思う。それも実際に何を「やり遂げたか」より何を「やろうとしたか」のほうに意味がある。(中略)少なくとも何ごとかをやろうと試みたという気概と意欲が伝わってくる作品を読みたいと。これは新人作家に対する要望であるが、かなりハードルが高い要望である。新人に要望した手前、自作の小説にも当然その考え方を反映させていると拝察するが、それを頭に入れながら本書を読むと面白さが倍増するかもしれない。