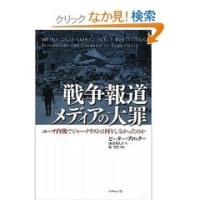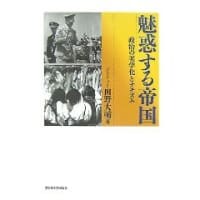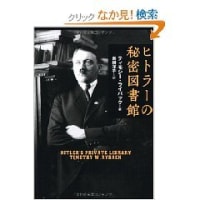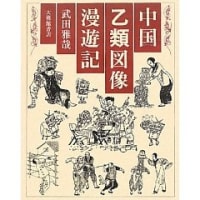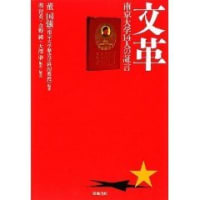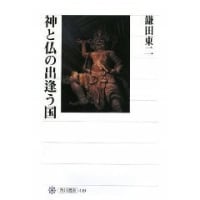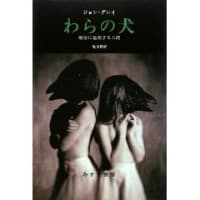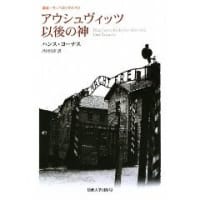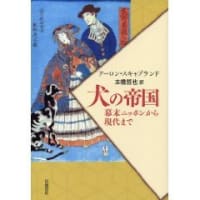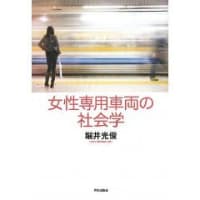本書は1993年10月に発刊されたもので、30年前の作品である。なぜこの本を知ったかというと、先にブログに挙げた車谷長𠮷の『癲狂院日乗』(新書館)で、車谷が本作品を褒めていたので、読んでみた。表題作を含めて10編から成る短編小説集で、どれも大阪が舞台である。大阪が舞台となれば織田作之助の作品がまず挙げられるが、本書は作之助より後の昭和30年以降のもので、舞台も淀川周辺であるところが特徴である。著者は大阪の旭区出身であり、作之助のように大阪市内の中心ではない。でも使われている大阪弁は懐かしさを覚えるのもので、上品な感じを与える。
どの作品も市井の庶民の生活を過不足なく描いており、高評価の理由も納得できる。人と人の距離が近いのが大阪の特徴だが、それが見事に表現されている。表題作もいいが、個人的には「釘を打つ」が独居老人の日常をリアルに描いており、今の世相を予見したような内容になっている。主人公の伴造は元大工だが、22年前に妻が病死して、子供もおらず今は独居老人だ。市役所の老人福祉課の職員がいろいろ相談に来てくれるが、伴造はなかなか心を開かない。近所の若い主婦からはゴミ当番をしっかりしてくださいというクレームを受けたり、彼女の二人の娘との日々のやり取りにも心を開けない。悪意の第三者を相手に日々苦闘している感じがリアルだ。
家に風呂はなく銭湯に行っているが、最近は銭湯もどんどん閉店してこれから先どうなるかわからない。また最近腹の具合がよくない。徐々に悪くなっていく感じだ。一度は医者に行こうかとも考えたが、「だが医者へ行って、この体をどうしようというのだ、とさらに突っ込んで考えたとき、彼は、もうええやないか、もうたくさんや、と自分に呟いたのだった。もうわしは充分生きた。女房に死なれたとき、いやそれとも会社を辞めたときだったか、あとは余生やいつまで生きんならん命でもない、と思わなかっただろうか」となって、自死を考えるようになる。人間、晩年になってどう生きるかはそれぞれに事情によって千差万別だが、最低限自尊心を損なわないような生き方をしたいという思いは個人的にはある。もし自分が伴造のような状況になったら自分はどうするだろうか。自分で考えるのはめんどくさいから、とりあえず施設に入ってみよう、それから考えようとなるが、入ったら最後死ぬまで出られない。この見極めが難しい。そして最後の場面、伴造は台所の三和土の上にロープをかけるための釘を打つ。そしてこう結ばれる、「勝手口から梯子を運び入れ、攀じ登る。これが最後の仕事になるな、、、、、、、、、、そう思ったとたん足がふるえ、梯子がカタカタと音をたてた。五寸釘の先を舌で湿らせ、あらかじめ見当をつけておいた場所にゆっくり確実に打ち込んでいく。金槌の音が、耳に軽快に響いた」。
元大工としての仕事が自分の未来を閉ざすものであるとは、何とも悲しいことである。「金槌の音が、耳に軽快に響いた」は人様の家や自分の家を建てる時の表現に使いたいところだが、ここでは残念ながらそうではない。でもこれによって作者の、伴造の人生に対する顕彰の気持ちが出ていて素晴らしい。岩阪氏ははじめ詩人として出発したらしいが、その感性がよく出ていると思う。今回車谷のおかげで、岩阪恵子という作家を知ることができた。他の作品も読んでみたい。
どの作品も市井の庶民の生活を過不足なく描いており、高評価の理由も納得できる。人と人の距離が近いのが大阪の特徴だが、それが見事に表現されている。表題作もいいが、個人的には「釘を打つ」が独居老人の日常をリアルに描いており、今の世相を予見したような内容になっている。主人公の伴造は元大工だが、22年前に妻が病死して、子供もおらず今は独居老人だ。市役所の老人福祉課の職員がいろいろ相談に来てくれるが、伴造はなかなか心を開かない。近所の若い主婦からはゴミ当番をしっかりしてくださいというクレームを受けたり、彼女の二人の娘との日々のやり取りにも心を開けない。悪意の第三者を相手に日々苦闘している感じがリアルだ。
家に風呂はなく銭湯に行っているが、最近は銭湯もどんどん閉店してこれから先どうなるかわからない。また最近腹の具合がよくない。徐々に悪くなっていく感じだ。一度は医者に行こうかとも考えたが、「だが医者へ行って、この体をどうしようというのだ、とさらに突っ込んで考えたとき、彼は、もうええやないか、もうたくさんや、と自分に呟いたのだった。もうわしは充分生きた。女房に死なれたとき、いやそれとも会社を辞めたときだったか、あとは余生やいつまで生きんならん命でもない、と思わなかっただろうか」となって、自死を考えるようになる。人間、晩年になってどう生きるかはそれぞれに事情によって千差万別だが、最低限自尊心を損なわないような生き方をしたいという思いは個人的にはある。もし自分が伴造のような状況になったら自分はどうするだろうか。自分で考えるのはめんどくさいから、とりあえず施設に入ってみよう、それから考えようとなるが、入ったら最後死ぬまで出られない。この見極めが難しい。そして最後の場面、伴造は台所の三和土の上にロープをかけるための釘を打つ。そしてこう結ばれる、「勝手口から梯子を運び入れ、攀じ登る。これが最後の仕事になるな、、、、、、、、、、そう思ったとたん足がふるえ、梯子がカタカタと音をたてた。五寸釘の先を舌で湿らせ、あらかじめ見当をつけておいた場所にゆっくり確実に打ち込んでいく。金槌の音が、耳に軽快に響いた」。
元大工としての仕事が自分の未来を閉ざすものであるとは、何とも悲しいことである。「金槌の音が、耳に軽快に響いた」は人様の家や自分の家を建てる時の表現に使いたいところだが、ここでは残念ながらそうではない。でもこれによって作者の、伴造の人生に対する顕彰の気持ちが出ていて素晴らしい。岩阪氏ははじめ詩人として出発したらしいが、その感性がよく出ていると思う。今回車谷のおかげで、岩阪恵子という作家を知ることができた。他の作品も読んでみたい。