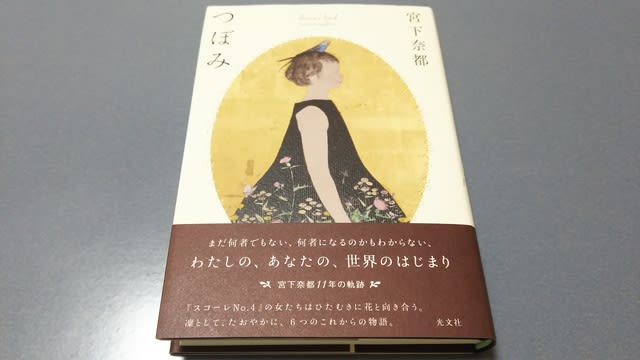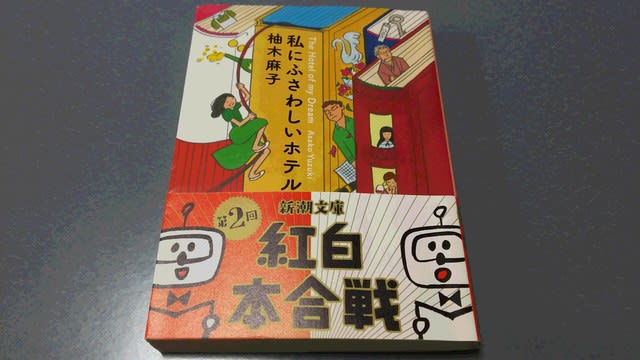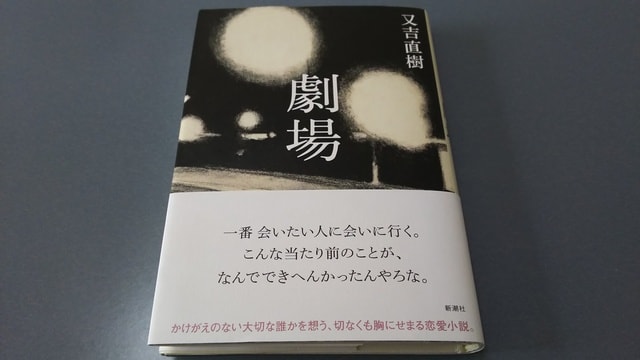今回ご紹介するのは映画「関ヶ原」です。
-----内容-----
関ヶ原の戦い――
それは、戦乱の世に終止符を打ち、後の日本の在りようを決定づけた。
幼くして豊臣秀吉(滝藤賢一)に才を認められ、秀吉の小姓となった石田三成(岡田准一)。
成長し大名にとりたてられた三成は自分の石高の半分をもって、猛将として名を馳せた牢人・島左近(平岳大)を家来に乞う。
秀吉に忠誠を誓いながらも、利害によって天下を治めることに疑問を感じ正義で世の中を変えようとする三成の姿に、左近は「天下悉く利に走るとき、ひとり逆しまに走るのは男として面白い」と配下に入る。
伊賀の忍び・初芽(有村架純)も、“犬”として三成に仕えることになる。
秀吉の体調が思わしくない。
天下取りの野望を抱く徳川家康(役所広司)は、秀吉の不興を買う小早川秀秋(東出昌大)や他の秀吉恩顧の武将たちに、言葉巧みに取り入っていく。
三成は、そんな家康が気にくわない。
1598年8月、秀吉逝去。
翌1599年閏3月、大老・前田利家(西岡德馬)も亡くなると、先の朝鮮出兵時から三成に恨みを持つ福島正則、加藤清正ら秀吉子飼いの七人党が、三成の屋敷を襲撃する。
三成は家康の屋敷に逃げ込み難を逃れるが、このことで佐和山城に蟄居。
家康の影響力が増していく。
1600年6月、家康が上杉討伐に向かう。
上杉家家臣・直江兼続(松山ケンイチ)と家康の挟み撃ちを図っていた三成は、盟友・大谷刑部らを引き込み、毛利輝元を総大将に立て挙兵。
三成の西軍、家康の東軍が、覇権をかけて動き出す。
1600年9月15日。
決戦の地は関ヶ原。
三成は、いかにして家康と世紀の合戦を戦うのか?
そして、命を懸けて三成を守る初芽との、密やかな“愛”の行方は……。
権謀渦巻く中、「愛」と「正義」を貫き通す“純粋すぎる武将”三成と野望に燃える家康の戦いが今、幕を開ける!!
-----感想-----
今日は映画「関ヶ原」を見に行きました。
関ヶ原の戦いは戦国時代最大の戦い、天下分け目の大戦(おおいくさ)として知られています。
太閤豊臣秀吉の死後、天下取りへの野望を露にする徳川家康に対し、秀吉の忠実な部下、石田三成が兵を挙げ戦いを挑みます。
石田三成の西軍8万人は総大将に中国地方120万石(豊臣、徳川に次ぐ領地の広さ)の大名、毛利輝元を据え、徳川家康の東軍10万人は江戸250万石(豊臣に次ぐ第2位の領地の広さ)の大名、家康が総大将を務め、両軍は関ヶ原で激突します。
戦いの結果は徳川家康率いる東軍の勝利で、何日にも及ぶ長い戦いになるという予想に反し6時間で勝負がついたことでも知られています。
どちらが勝つかは大抵の人が知っているのでそれをどう見応えたっぷりに描くかが注目でした。
まず徳川家康の権謀術数に長けた腹黒タヌキぶりがよく描かれていました。
役所広司さんの演技力が抜群に高く、腹黒い上に器の大きさも漂う良い家康になっていました。
家康は序盤で豊臣秀吉が亡くなる前から、小早川秀秋を言葉巧みに自身に好意を持つように仕向けていました。
小早川秀秋といえば名前を聞けばすぐに「関ヶ原で西軍を裏切った人」と思い浮かぶくらい、日本史における明智光秀と並ぶ代表的な裏切り人物という印象があります。
この映画では関ヶ原の戦いが始まると西軍と東軍どちらに味方するか髪をかきむしるくらいの勢いで混乱しながら迷っているのが印象的でした。
最後は裏切るのですが、裏切り方が今までの映像作品で見てきた小早川秀秋とは少し違っていたのが印象的でした。
そして最後のほうで「小早川家は長い年月をかけて徳川家康に飲み込まれてしまった」ということを言っていたのも印象的でした。
小早川秀秋一人だけ石田三成の西軍に味方しようという気があったとしても、家全体が親徳川にまとまってしまってはどうにもならないのだと思います。
私は小早川秀秋の迷いぶりを見ると、もし小早川隆景(たかかげ)が生きていればと思います。
小早川隆景は秀秋の養父で、一代で中国地方120万石の領地を築き上げた名将毛利元就の息子(三男)です。
隆景は関ヶ原の戦いの三年前に亡くなっています。
長男の毛利隆元、次男の吉川元春とともに元就が頼りにした「毛利三兄弟」として有名です。
隆景であれば、秀秋のように物凄く迷って混乱するようなことにはならず、毛利、小早川、吉川にとって一番良い方法を考え出していたと思います。
西軍の総大将、毛利輝元も叔父である隆景が生きていれば西軍の総大将に担がれることもなく、関ヶ原の戦いの後に家康によって領地を120万国から36万石に減らされることもなかったと思います。
しかし隆景は亡くなり、毛利家跡取りの輝元と小早川家跡取りの秀秋はどちらも頼りなく、元春亡き後の吉川家は裏で家康に内通するようになっていて、時代は家康に味方していました。
五大老(徳川家康、前田利家、宇喜多秀家、上杉景勝、毛利輝元)の中で唯一家康に負けない存在感のあった前田利家が秀吉の死の一年後に亡くなってしまったのもまた家康に味方しました。
家康は加藤清正、福島正則ら豊臣恩顧の大名も調略します。
言葉巧みに石田三成を憎み家康の陣営に味方するように仕向けていました。
「自分は豊臣の天下が続くことを願う、ただし三成が私利私欲に走り悪政をし、傍若無人な振る舞いをしている」というような話をし、加藤清正や福島正則が「そうだそうだ!」となり三成をどんどん憎むようにしていました。
ただし三成にも問題があり、愛想やお世辞ができずさらに言葉も相手の感情を無視した物言いをするため、敵を作りやすいです。
三成がもう少し相手の心情に配慮することができていれば、加藤清正や福島正則と決定的に対立することはなかったと思います。
岡田准一さんは三成の不器用さ、愚直さを上手く演じていたと思います。
V6というアイドルグループのメンバーなのですが演技力も高いと思います。
家康は北政所(きたのまんどころ)も調略します。
北政所は秀吉の正室で、子供の頃から北政所に育てられた加藤清正、福島正則ら豊臣恩顧の大名は北政所のことを「おかか様」と呼び、絶大な影響力を持っています。
ナレーションで「北政所が諸大名に”家康を討て”と命じれば、歴史は大きく変わっていた」と言っていたのが印象的でした。
ただし秀吉の死後、家康は北政所に近づき親密に話をするようになり、北政所も三成より家康を信用するようになります。
北政所が三成と家康の対立について「先々のことを考えると三成が負けたほうが良い」と言っていたのは、三成は豊臣のために汚れ仕事も一手に引き受けていたのに報われないなと思います。
これは不器用で愚直に邁進するだけでなく、周りの人の心情にも配慮し、愛想良く接したりお世辞も言えるようにならないと政(まつりごと)を円滑に行うのは難しいということだと思います。
家康はこの点に優れていて、豊臣方の人物を次々と調略していきました。
三成の家来、島左近も凄く存在感があったのが印象的です。
平岳大さんの演技力が際立っていました。
武芸に秀で、不器用な三成を静かでありながら厳かな雰囲気の話し方で支えていた姿がとても良かったです。
有村架純さんが演じた史実には登場しない架空の人物、初芽(はつめ)も良かったです。
初芽は伊賀の忍びで、冒頭で起きた事件がきっかけで三成に仕えるようになります。
そして仕えるうちに次第に三成のことを想うようになっていきました。
有村架純さんも演技力が高く、忍びとしての立ち居振る舞いを上手く演じていました。
映画は関ヶ原の戦いで最高潮を迎えます。
戦いが始まるまで、日本中から戦国武将たちが行軍して集まってくる様子や陣地を築く様子、そして三成と家康のいつ戦いを始めるかの駆け引きが印象的でした。
戦いは天下分け目の大戦と呼ばれるように大規模に描かれていました。
西軍がやや優勢に戦いますが、毛利秀元(大阪城に居た輝元の代わりに毛利を率いた人物)や小早川秀秋は動こうとしません。
三成が馬に乗って戦場を奔走し、秀元や秀秋のところに行って「動いてくれ!」と頼む姿は印象的でした。
やがて戦いの開始から3時間後、ついに小早川秀秋の裏切る時がやってきます。
戦局が大きく変わり、三成は敗戦を悟ることになります。
三成は「義が不義に負けることがあってはならない」と言っていました。
また小早川秀秋は「義が不義に飲み込まれた」と言っていました。
三成(義)と家康(不義)の戦いは忠義を尽くしたほうが勝つとは限らないという結末になっていて、なかなか辛いものがあります。
私は映画を見ていて、石田三成の不器用さと愚直さ、小早川秀秋の迷い、徳川家康の腹黒さ、どれも人間らしいと思いました。
そして義を貫き勝利を収めるには、愚直に突き進むだけではなく味方の数を増やす政治力も重要だということを感じました。