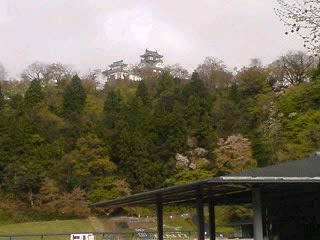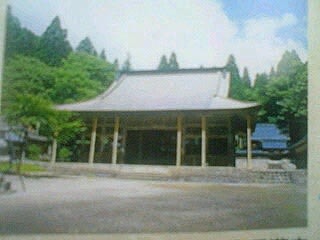〈尾瀬ヶ原からケイズル沢と頂上を望む~左の尾根を登り、右の沢を下った〉
景鶴山(2004m)は、尾瀬ヶ原の北西に位置する山で、以前は登山道があったが、自然保護のために入山禁止となり、廃道となってしまったらしい。したがって、鳩待峠までの道が開通する4月下旬を待って積雪期に登られている。
4:00、HYML創設当時(当時札幌勤務)からの岳友である東京の牧さんと道の駅「白沢」で6年ぶり?の再会。
途中に牧さんの車を置いて、鳩待峠を目指す。ここの駐車料金は暴利と評判の悪い2500円。
素晴らしい天候の下、5:20スタート。まずは、尾瀬ヶ原に出る山の鼻を目指す。-2℃で良く締まった堅い雪面なのがうれしい。さらに、至仏山を背に、燧ヶ岳に向かって、まったく埋まることがない雪面を快調に飛ばす。雪どけがかなり遅れているようで、牛首分岐からヨッピ川橋までも真っ直ぐ進む。ただでさえ怖い吊り橋のヨッピ橋は踏み板が外されていて、ワイヤーしがみつきながら鉄骨の上を怖々渡る。川面までの高度感がなかったのと短かったのが幸いした。
その先から真っ直ぐ続くトレースもあり、それを辿ることにした。なんと、それはケイズル沢右岸の尾根に続いていた。ネットでは目にしなかったルートで、ノーマルルートよりかなり近い。頂上を右手上に見ながらアイゼンも着けないで登る。高度を上げるに連れて、尾瀬ヶ原がどんどん広がってくる。頂上の岩峰は裏側から巻いて狭い頂上に到着。
頂上からの展望は、尾瀬ヶ原を取り巻くこれまでに登った至仏山、燧ヶ岳はもちろん上州や会津や越後の山々などがぐるっと・・・。
下りは、先行グループのトレースを辿り、ケイズル沢へ直接駆け降りる。頂上からヨッピ橋まで45分で到着。しかし、その後の尾瀬ヶ原は雪が溶けて非常に歩きづらく、往きの1.5倍ほども掛かった。
登り3時間20分、下り3時間10分、12:30ゴール。結局ヨッピ橋から先は、予定していたノーマルルートを歩くことはなく、マニアックエコルートで、予定より3時間ほども早くゴールできた。
〈逆光でシルエットになった燧ヶ岳に向かって〉

〈平ヶ岳をバックに、頂上の牧さん〉

〈裏側から巻いて登った頂上岩峰〉

下山後、白根温泉に入り、日光を経由し、明日の男鹿岳に近い道の駅たじまへ向かう。途中で夕食を摂り、車の中で宴会の予定。
景鶴山(2004m)は、尾瀬ヶ原の北西に位置する山で、以前は登山道があったが、自然保護のために入山禁止となり、廃道となってしまったらしい。したがって、鳩待峠までの道が開通する4月下旬を待って積雪期に登られている。
4:00、HYML創設当時(当時札幌勤務)からの岳友である東京の牧さんと道の駅「白沢」で6年ぶり?の再会。
途中に牧さんの車を置いて、鳩待峠を目指す。ここの駐車料金は暴利と評判の悪い2500円。
素晴らしい天候の下、5:20スタート。まずは、尾瀬ヶ原に出る山の鼻を目指す。-2℃で良く締まった堅い雪面なのがうれしい。さらに、至仏山を背に、燧ヶ岳に向かって、まったく埋まることがない雪面を快調に飛ばす。雪どけがかなり遅れているようで、牛首分岐からヨッピ川橋までも真っ直ぐ進む。ただでさえ怖い吊り橋のヨッピ橋は踏み板が外されていて、ワイヤーしがみつきながら鉄骨の上を怖々渡る。川面までの高度感がなかったのと短かったのが幸いした。
その先から真っ直ぐ続くトレースもあり、それを辿ることにした。なんと、それはケイズル沢右岸の尾根に続いていた。ネットでは目にしなかったルートで、ノーマルルートよりかなり近い。頂上を右手上に見ながらアイゼンも着けないで登る。高度を上げるに連れて、尾瀬ヶ原がどんどん広がってくる。頂上の岩峰は裏側から巻いて狭い頂上に到着。
頂上からの展望は、尾瀬ヶ原を取り巻くこれまでに登った至仏山、燧ヶ岳はもちろん上州や会津や越後の山々などがぐるっと・・・。
下りは、先行グループのトレースを辿り、ケイズル沢へ直接駆け降りる。頂上からヨッピ橋まで45分で到着。しかし、その後の尾瀬ヶ原は雪が溶けて非常に歩きづらく、往きの1.5倍ほども掛かった。
登り3時間20分、下り3時間10分、12:30ゴール。結局ヨッピ橋から先は、予定していたノーマルルートを歩くことはなく、マニアックエコルートで、予定より3時間ほども早くゴールできた。
〈逆光でシルエットになった燧ヶ岳に向かって〉

〈平ヶ岳をバックに、頂上の牧さん〉

〈裏側から巻いて登った頂上岩峰〉

下山後、白根温泉に入り、日光を経由し、明日の男鹿岳に近い道の駅たじまへ向かう。途中で夕食を摂り、車の中で宴会の予定。