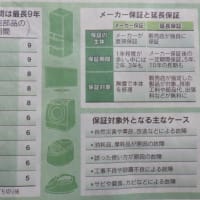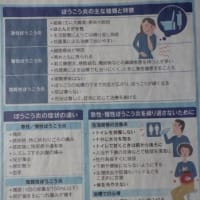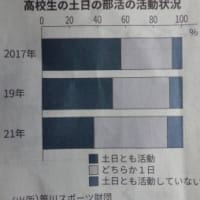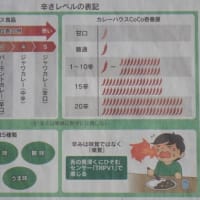日本の近海から魚が減っている。 温暖化による海水温の変化などで生育環境が変わり、
スルメイカの漁獲量は最盛期の5%まで減った。 一部の魚種では乱獲も響き、回復の
兆しは見えない。 展望を開くには、陸上養殖などで漁業を産業化する取り組みが必要
になる。
北海道函館市でスルメイカ漁を20年以上続けた”野呂さん”は5年前に漁船を売った。
かつてほどイカがとれず、売上高は最も多かった時期に比べると半分程度になってい
た。 「イカ漁では利益が確保できない」。 今は魚介の卸売業を営む。
 日本のスルメイカはピークだった1968年
日本のスルメイカはピークだった1968年
に約66.8万㌧もの漁獲高があったそうだ。
2021年は約3.2万㌧にすぎない。魚介類
は広大な海で育つ。年によっては不漁もあり、
原因は一つでない。ただ、長期にわたるスル
メイカの減少は温暖化が影響しているとされ
る。 水産庁の調査によると産卵場となる東
シナ海の水温が上がり、産卵や生育に適さな
くなった。サンマも最盛期の3%ほどしかと
れていない。
代表的な魚介類が長期的な不漁に見舞われ、日本の漁獲量は大きく減った。 農林水産
省の海面漁業生産統計調査によると漁獲高は1984年に約1150万㌧だったが、
2021年は約319万㌧と4分の1程度だ。
とれるようになった魚もある。 代表例のブリは年12万㌧ほどと、00年代に入って
から緩やかな増加基調にある。
漁業関係者が漁や加工のを変えるのは「魚種転換」と言われる。 自然を相手にするた
め知恵だが、ハードルは高い。 漁船や網などの設備を入れ替える必要があるため。
国からの補助金もあるが、利益が確保できる水準で魚がとれるとは限らない。
温暖化だけが不漁の理由ではない。 乱獲も避けなければならないが、漁獲可能量を制
限する法律が施行されたのは20年のことだ。 東京海洋大学の"勝川准教授"は「日
本近海での漁獲量は、50年頃にはほぼゼロになるベースで減っている。 今後の水
産業は持続可能な漁獲量に制限し、その価値を高めることが重要」と話している。
漁獲量が制限される漁業者は収入が減る。 23年度予算では漁業収入安定対策事業と
して漁業者の収入保障に580億円超が計上された。
巨額の予算も魚を増やす効果はない。 政策支援も「とる」から「育てる」に発想を切
り替えなければ、産業としての復活は難しい。
国の方策として第1次産業の政策をもっともっと力を入れてほしいものです。
スルメイカの漁獲量は最盛期の5%まで減った。 一部の魚種では乱獲も響き、回復の
兆しは見えない。 展望を開くには、陸上養殖などで漁業を産業化する取り組みが必要
になる。
北海道函館市でスルメイカ漁を20年以上続けた”野呂さん”は5年前に漁船を売った。
かつてほどイカがとれず、売上高は最も多かった時期に比べると半分程度になってい
た。 「イカ漁では利益が確保できない」。 今は魚介の卸売業を営む。
 日本のスルメイカはピークだった1968年
日本のスルメイカはピークだった1968年に約66.8万㌧もの漁獲高があったそうだ。
2021年は約3.2万㌧にすぎない。魚介類
は広大な海で育つ。年によっては不漁もあり、
原因は一つでない。ただ、長期にわたるスル
メイカの減少は温暖化が影響しているとされ
る。 水産庁の調査によると産卵場となる東
シナ海の水温が上がり、産卵や生育に適さな
くなった。サンマも最盛期の3%ほどしかと
れていない。
代表的な魚介類が長期的な不漁に見舞われ、日本の漁獲量は大きく減った。 農林水産
省の海面漁業生産統計調査によると漁獲高は1984年に約1150万㌧だったが、
2021年は約319万㌧と4分の1程度だ。
とれるようになった魚もある。 代表例のブリは年12万㌧ほどと、00年代に入って
から緩やかな増加基調にある。
漁業関係者が漁や加工のを変えるのは「魚種転換」と言われる。 自然を相手にするた
め知恵だが、ハードルは高い。 漁船や網などの設備を入れ替える必要があるため。
国からの補助金もあるが、利益が確保できる水準で魚がとれるとは限らない。
温暖化だけが不漁の理由ではない。 乱獲も避けなければならないが、漁獲可能量を制
限する法律が施行されたのは20年のことだ。 東京海洋大学の"勝川准教授"は「日
本近海での漁獲量は、50年頃にはほぼゼロになるベースで減っている。 今後の水
産業は持続可能な漁獲量に制限し、その価値を高めることが重要」と話している。
漁獲量が制限される漁業者は収入が減る。 23年度予算では漁業収入安定対策事業と
して漁業者の収入保障に580億円超が計上された。
巨額の予算も魚を増やす効果はない。 政策支援も「とる」から「育てる」に発想を切
り替えなければ、産業としての復活は難しい。
国の方策として第1次産業の政策をもっともっと力を入れてほしいものです。