多くの人には見えているものでも、自分には見えないもの。
自分には見えているのに、他人には見えないもの。
自分が見ている世界(もの)と現実とでは、ズレがあるのかも知れない。
こんな話を、子供たちの夏休みが終わる時期にすれば、
怪談話かオカルトにも思えるけど。
個人の主観が、客観的な事実とは異なることがあるということ。
さて・・・。
人間に限らず、視覚というものは、
目に入ってくる光から、空間や物体を認識する感覚。
“光を感じとる”感覚ということ。
それは、物質、そのものが“光”を発しているのでもなく。
物質に照射されている“光”の反射から、物質を認識している。
光に対する学説は、色々あるけど。
光は、宇宙線、ガンマ線、マイクロ波、電波など、
電磁波の仲間であると(も)言われている。
人間が視覚的に認識できる波長は、380nm~780nmになり。
太陽光は、屈折率の異なる7つの色の光から構成されている。
これは万有引力の発見で知られるアイザック・ニュートンが、
天体望遠鏡のプリズムの光が分かれたことで発見する(1666年)。
(ニュートンと万有引力に関する過去の記事「空の下、地の上」 ⇒)
それから、およそ150年後、ウィリアム・ハーシェルによって、
赤外線が解明される。
さらに、ヨハン・リッターが紫外線の存在を証明していく。

※夕空が赤く見えるのは、赤色の光の波長の長さによるもの。
子供の頃、科学の授業で習った話では…。
水のような液体が入ったコップに、光(光線)が入るとき、
水面との角度に対して、ズレが生じる「屈折」と呼ばれる現象が起きる。
この光の方向変更、屈折する角度(屈折率)は、色ごとに異なる。
ちなみに雨上がりの空にできる虹も、自然界における光の屈折現象の1つ。
もう少し説明をするなら…。
太陽光は波長域の異なる複数の光で構成されているから、
異なる波長ごとに屈折する角度(屈折率)が分解されるような状態となる。
長波長 ⇒赤 波が長いから、長波長。
中波長 ⇒緑~黄
短波長 ⇒紫~青
だから、虹の外側の色は、波長の長い“赤”が、長いカーブを描き、
内側は、波長域の短い色(青)へと形成されていく。
この波長の短い紫の光の外に、存在するのが「紫外線」。
(殺菌、熱を冷ます効果もある。)
「赤外線」は、反対に、波長の長い赤の光の外に、存在するものになる。
※通常、「赤外線」も「紫外線」ともに、人間には視認できない。
蛇足:
“色目で見る”とも言われるせいか?
日本人と欧米人とでは「目の色が違う」ために、
色の見え方が異なると言う“俗説”があるけど。
日本人と欧米人との目の色が異なるのは、
眼球内の遮光膜、「虹彩」の色が異なるため。
虹彩は、色が異なっても、光を通さないので、この俗説は間違っている。
所詮、“俗説”でしかないということ(?)。
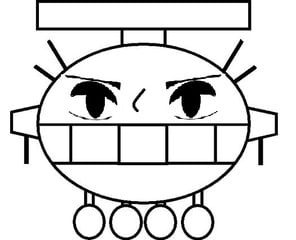
ブックマーク登録しているブログによると・・・。
空気(酸素や窒素)が、目に見えないのは、
可視光線が吸収されないためだからとのこと。
空気が見えるときは、余分なものが含まれている。










