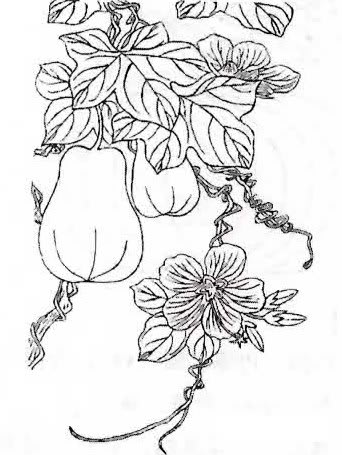【コリアンダー】
南米から旧大陸に渡った野菜を取り上げましたが、野菜大国・南米にはないアジアの野菜が今や、当たり前のようにメキシコの人々の口に入っているものもありました。
その一つがシャンツアイ、タイではパクチー、英語でコリアンダーと呼ばれる野菜。メキシコでは豊富に使われていました。刻まれたものが、食堂で頼んだ料理とともに、ほぼ、毎回、出てきました。
メキシコではシラントロといいました。スペイン語です。チキンスープにうまみのある辛みがのっかり、その上にすきなだけ、載せてよいという、シラントロ。
娘は懐かしい雲南でよく食べた味に似ている、と感激しておりました。
この野菜の原産地は地中海東部といわれていますが、日本やロシアなど一部の地域を除いてはすっかり定着してますね。
【市場の様子】
最後のメキシコの市場で見かけた変わった食品を見ていきましょう。
一つ目は大小さまざまなサソリ。珍しそうに眺めていると、自慢げに見せてくれます。メキシコに何度も通う日本人の女性に聞くと、食べたことはない、とのことですが、揚げ物にして、エビのように食べるのでしょうか? 毒の処理が気になるところではあります。
雲南ではたとえばイナゴや蜂の子などは、籠にざっと無造作に山盛りに置かれていました。ですからメキシコのサソリの芸術的な一匹ずつ置いた並べ方はたっぷりと食べるもの、というより宝飾品のように見えてきます。
ただ、その横には虫を串刺しにして黒茶色のたれがかかったものが売られていたので、やはり食べ物であることは間違いないようでした。



次に調味料売り場には醤油や片栗粉が売られていました。「わさび」もあります。この店はアジア系の方が経営していて、日本人と聞くと、たいへんフレンドリーに接してくれました。
この店に限らず、たいてい日本人と聞くと、態度がやわらかくなります。いままでこの地を訪れた日本人がいかにメキシコの人と誠実に接していたのかがわかって、有り難かったです。積み重ねは、大切ですね。
(この章おわり)
※次回より、しばらく更新をお休みします。
夏になって2ヶ月ほど。夏ばてに追いつかれないようにしたいですね。