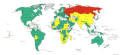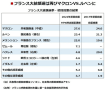黒澤明を見るシリーズ4回目(最後)は、いよいよ最長の「
問題作」、「
七人の侍」(1954)である。見るのは多分4回目だと思う。つい2年前に国立映画アーカイブの
三船敏郎生誕100年特集で見たんだけど、その時はコロナ禍でチケットが事前発売の指定席制になっていた。パソコンなら席を選べることをよく知らず、適当に買ったら前の方の席だった。3時間以上ずっと上を向いて首が疲れた記憶しかなくて、もう一度
4K版で見たかった。「
生きる」と「
七人の侍」は僕の若い頃はなかなか上映されなくて、どっちも名画座ではなくロードショーで見た記憶がある。京橋にあった
テアトル東京という巨大映画館で見たのが最初だと思う。
今は日本で「日本映画ベストテン」投票などをすると、「
七人の侍」が1位になることが多い。しかし、1954年当時のキネ旬1位は木下恵介監督の「
二十四の瞳」だった。2位も木下の「
女の園」で、「
七人の侍」は3位だった。これはまあ、歴史的な意味合いからいって、僕もこの年の1位は「二十四の瞳」なんじゃないかと思う。ところで、自分は歴史専攻だったから、「七人の侍」には最初から
違和感が強かった。この映画は凄いなあと思えるようになったのは割と最近のことで、やっぱり非常に優れていて、面白いのは間違いない。違和感の方は後回しにして、面白さ、凄さの部分から考えたい。

(七人の侍)
野武士たちに襲われる村があって、村人が「サムライ」を雇って野武士を撃退しようと考える。要するにそれだけの物語だが、
襲撃と撃退のシーンが圧倒的である。それは黒澤監督が時間を掛けて撮影したということであり、伝説的なエピソードが多々語り継がれている。まるでどこか実際にある村でロケしたような感じに見えるが、そんな都合の良い村はロケハンで発見出来なかった。全景を見せるシーンもあって、それは伊豆北部の丹那あたりで撮ったというが、後は各地で撮影して一つの村のようにつなげたのである。俳優たちもほとんどが軍隊体験のある世代だけに、
「サムライ」の身体性を身にまとっている。今の若い世代が戦争映画や時代劇に出て来るときの身体的違和感を感じないのである。
「
七人の侍」というんだから、もちろん
7人いるわけである。7人の主要人物を描き分けるのは大変なはずだが、この映画では実に上手に性格や年齢などが設定されている。若い人だと名前は知らないかもしれないが、知らなくても顔で見分けられるだろう。
7人をリクルートする場面が全体の3分の1ぐらいあって、そこが長いという人が時々いる。でも大人になるに連れ、このリクルートしていくところが面白くなってきた。本当はもっともっと見たいぐらいである。最初にリーダーになる
勘兵衛(
志村喬)を口説き落とす。要するに「
義を見てせざるは勇なきなり」ということだろう。参謀役、孤高の剣客、陽気な男、昔の部下と集めて、後は慕ってくる若者と、何だかよく判らない「
菊千代」(
三船敏郎)で7人。この
絶妙な組み合わせは、同種の物語の原型となったと言えるだろう。それにしても前作「
生きる」に続く、
志村喬の存在感の深さ。(
澤地久枝による評伝「
男ありて」がある。)

(志村喬の勘兵衛)
ところで中でも非常に重大なのか、
三船敏郎演じる「
菊千代」である。カギを付けたのは、本名じゃないからで、偽系図を見せて武士だと名乗るが、実は農民出身なのである。それも親を早く戦乱で失った「
戦災孤児」だったことが示唆される。言うまでもなく、製作時点では大空襲による戦災孤児を誰もが思い浮かべただろう。その後自力で生き抜いてきて、村へ行ったら(映画内の表現で言えば)、「
百姓に対しては侍」「
侍に対しては百姓」という「
両義的」存在として振る舞う。谷川雁的に言えば「
工作者」であり、山口昌男的に言えば「
トリックスター」でもある。子どもたちにも懐かれ、村人の物真似をして笑わせる。単に農民と武士の両義性だけでなく、大人と子どもの両義性をも生きている。
三船敏郎は東宝ニューフェースとして俳優となって人気を得た。世界に知られた大スターだったけど、今では知らない人が結構いる。「
酔いどれ天使」「
野良犬」では志村喬の下に立っている。「
七人の侍」でも志村喬がリーダーだから、その下には違いないが、かなり独自性が強くなっている。次の「
生きものの記録」「
蜘蛛巣城」では三船がはっきりとした主演で、志村喬が助演。次の「
どん底」になると、三船は出ているが志村喬は出ていない。三船敏郎を知った時にはすでに大スターで、「
男は黙ってサッポロビール」というコマーシャルをやっていた。寡黙で近づきがたい大スターで、僕も敬遠していた。しかし、後に「
東京の恋人」などのコミカルな演技も素晴らしいと知った。晩年に演じた熊井啓監督の「
千利休」や「
深い河」は素晴らしかった。

(三船敏郎と志村喬)
「
!」(素晴らしい)を書いてると終わらないから、そろそろ「
?」(おかしいな)の方を。今見ると、このような村は中世史の研究の進展により、あり得ないだろう。そもそもこの物語は
1587年に設定されているという。これは
四方田犬彦「
『七人の侍』と現代」(岩波新書、2010)に出ているが、今回再読してみた。三船演じる「菊千代」の偽系図を見て、じゃあ菊千代は今13歳なのかとからかわれるシーンがある。「菊千代」は文字が読めないことが示唆されている。この生年から計算すると、1587年になる。すでに
豊臣秀吉の関白就任は2年前、全国統一目前だった。それを考えると、野武士たち(映画内では「
野伏せ」)も、一方の七人側も、信長・秀吉の統一戦争に敗れた側の武士だったため、志を得ないまま日を送っていたと想定出来る。
四方田犬彦前掲書では、中世史研究として
藤木久志先生の「
刀狩」「
雑兵たちの戦場」の2冊が挙げられている。わずか2冊だったのか。僕は大学時代に藤木先生の講義を聞いているから、「七人の侍」に違和感があったのである。中世史研究の進展によって新たに得られた知見をもとに、「七人の侍」の武士や農民の描き方をあれこれ批判するのは「
ヤボ」だと言われるかもしれない。僕もそう思うが、若い頃はどうしてもそう見えたということである。この映画に出て来る村のあり方は、
惣村の実態から相当にかけ離れている。それはまあ良いのだが、全体に「
近代から見た近世的な意識」を感じてしまうのである。
兵農分離以前なのに、農民と武士の身分差を強調するのはその代表。娘しかいない万蔵という農民が、娘が若い侍と恋仲になると、「傷物にされた」と怒る。そんな処女性に拘る中世農民がいるのか。婿を取らなければ祖先祭祀が出来ないんだから、むしろ良い婿を捕まえたと
勝四郎(
木村功)に土着することを迫るのが本当だろう。それより何より、一番大きな問題は「
宗教の不在」である。いや、ラストに亡くなった侍の墓所が出て来るわけだが、村の葬送はどうなっているのか。村に神社があるはずだが、どこにあるんだろうか。決戦前にはそこに集まって「
一揆を結ぶ」はずだが、そんな様子は全くない。そもそも侍を雇うかどうかも、神に伺いを立てるはずである。何しろ足利6代将軍がくじ引きで選ばれた時代である。
くじは神慮ということである。重大事なんだから、村の神社で長老がくじを引くはずだ。要するに近世以後の「世俗的な村」に近いということに違和感を持つわけだ。
まあ、そんなことは問題にせず、メキシコやブラジルのことだと思って楽しめば良いとも言える。実際黒澤の目論見は「
西部劇を越える時代劇を作る」ことにあった。実際に、リメイクは西部劇になった。ただし、「七人の侍」を初めて見た頃には、ハリウッド製の特撮を駆使したアクション大作がいっぱい作られていた。比べて見るとカラーで作られたSFやホラー大作の方が面白かったのである。「七人の侍」を楽しむためには、今では
映画史的な知識が多少なりとも必要なんじゃないだろうか。七人を演じた俳優たちはどんな人かなどは知っていた方が断然面白い。四方田書で指摘するように、志村喬は死んだと思っていた
加東大介と再会したが、小津「
秋刀魚の味」でも笠智衆の上官と戦後になって再会する。
木村功は大人気スターだったが早く亡くなって、妻が書いた回想記がベストセラーになった。中でも素晴らしいのが寡黙な剣士を演じた
宮口精二である。

(宮口精二)
宮口精二(1913~1985)は戦前から文学座に所属した俳優だが、今では「七人の侍」で一番記憶されるだろう。他にも映画出演は数多く、他の映画では寡黙な剣士ではなくコミカルな役柄も上手である。「
あいつと私」では有名美容家の頼りない夫を演じて笑える。「
張り込み」では東京から佐賀まで張り込みに行くし、「
古都」では京都の呉服問屋の主人で岩下志麻の育て親。「
日本のいちばん長い日」では東郷茂徳外相…、などなど50年代、60年代の古い映画を見るとき、宮口精二の名前を楽しみに見るようになった。「七人の侍」を見るまで全然知らなかったが、こういう「助演」で映画を見る楽しみを教えてくれた人でもある。
 (4月29日段階の地図)
(4月29日段階の地図) (3月27日段階の地図)
(3月27日段階の地図)