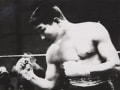冤罪救援に関しては「再審法改正」がいよいよ本格的に議論されぞうだが、次に日本の死刑制度をめぐる動きも見ておきたい。袴田事件で袴田巖さんの心が閉ざされたのは何故か? それは単なる「拘禁反応」ではなく「死刑執行の恐怖」に原因があったことは、袴田事件関連の本や映画に触れていればよく知っているだろう。冤罪事件と死刑制度は本来無関係だと強調する人もいる。「論理」的にはその通りだが、人の世は「論理」だけで成り立っていない。現実に社会には差別が存在し、警察は「見込み捜査」を行うことがある。間違った「見込み」で無実の人が死刑になる可能性。その恐怖を世に知らせたのが袴田事件ではないのか。
日本でも死刑制度に関する大きな動きが相次いでいる。まずは「日本の死刑制度について考える懇話会」が2024年11月13日に報告書をまとめ政府への提言を行った。残念なことにネットニュースやテレビではほとんど報道されていない。新聞に出ていて知ったのだが、僕もそのような懇話会が活動していたことは知らなかった。24人の委員がいて、井田良氏(中央大大学院教授、前法制審会長)が座長、笹倉香奈氏(甲南大法学部教授)が座長代行を務めた。政界からは平沢勝栄(自民)、西村智奈美(立民)、上田勇(公明)3氏。他に肩書きだけ挙げれば、前検事総長、元日弁連会長、元警察庁長官、経済同友会代表理事、前連合会長、被害者と司法を考える会会長に加え、宗教界やマスコミからも入っている。映画監督の坂上香氏も加わっている。
このように現代日本の相当に幅広い層を代表する人々が議論したのは重要なことだろう。そして「現制度は放置が許されない数多くの問題があり、このまま放置してはいけない」としたのである。ただこの会では存廃の結論は出さず「国会や政府のもとに、存廃を含め議論する会議体を設置するべき」としている。その会議体で検討するべき点として、「死刑廃止は国際的潮流で、執行継続が国益を損ねていないか」「誤判の可能性を排除するための制度」「被害者遺族への支援強化」「死刑に代わる最高刑のあり方」「死刑囚の処遇の問題」「情報開示と世論調査のあり方」など問題点が網羅されている。
死刑廃止が世界の潮流であるということは、上の地図を見ればよく判る。また、2024年12月7日付朝日新聞によれば、国連人権委員会に任命された「特別報告者」は「日本の死刑制度が国際法に違反する疑いがある」という報告を日本政府に通報したという。この通報は11月下旬に国連のウェブサイトに公表されたもので、「死刑執行が当日の朝まで本人に告知されず家族も事後まで分からないこと」「再審請求中の執行が相次いでいること」「絞首刑という方法」などが「非人道的な刑罰」を禁じた国際法に触れる恐れがあると指摘したという。これらの論点は日本でも今まで指摘されてきたことで、全くおかしい事態というしかない。
もっとも表面上は日本政府は今までの対応を変える考えはないようである。2020年11月に国連総会で死刑の執行停止(モラトリアム)を求める決議案が採決されたとき、日本政府は反対票を投じた。反対したのは39か国だそうで、アジアでは中国、日本、インドなどが反対している。アジア諸国の人権意識が疑われる状況になっていて、日本と中国は死刑廃止に反対するという「同盟」を結んでいるかのようだ。そのような対応が続いて良いのかどうか、日本政府もよくよく世界を見て欲しいと思う。死刑制度の本格的議論をする余裕がないけれど、今回は現状の報告ということで。