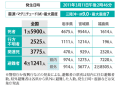中国は一体どうなってしまったのだろうか。最近こう思うことが多い。いや、前からずっと「中国は中国」とも言えるだろう。中国の大自然は変わらず、今日も長江は流れ黄砂は飛んでくる。しかし、ここでは主に「中華人民共和国」の政治体制を問題にしている。それも習近平指導部になってからのあり方だ。現在の中華人民共和国に限らず、大昔の歴代王朝を振り返っても、とんでもない驚くべきエピソードが歴史を彩っている。それは連綿たる「独裁者」の歴史だった。
毛沢東も鄧小平も独裁者だったが、その後はもうそういうタイプの独裁者は出て来ないと思っていた。中国の最高指導者は中国共産党総書記だが、21世紀になってからは「一期5年、二期まで」が慣例になっていた。しかし、その規定は撤廃され習近平総書記が3期目まで続くことは確実だ。その中国をめぐっては、ウィグルや香港の人権状況が問題化している。しかし、中国は「内政不干渉」をタテにして全く批判を受け付けない。それどころか、軍部がクーデタを起こし国民を弾圧するミャンマーの後ろ盾となっている。
王毅外相は最近中東6ヶ国を訪問したが、その中にはサウジアラビアも含まれている。イランを訪問して対アメリカで共闘するのは理解出来る。しかし、中東一番の親米国であり、議会政治さえ存在しない独裁的な王国のサウジアラビアを訪れて、最高実力者のムハンマド皇太子と会談したのである。サウジ側はウイグルや香港で中国の立場を支持し、中国側は「サウジ内政に口を出すいかなる勢力にも反対する」と述べたという。アメリカではトランプ政権が発表しなかったCIA報告書をバイデン大統領が発表した。そこではムハンマド皇太子がトルコで起こったカショギ氏殺害を承認していたとされている。そんなムハンマド皇太子と会談したわけだ。
 (王毅、ムハンマド会談)
(王毅、ムハンマド会談)
今から半世紀以上も前には、世界に独裁国家があったら支持しているのは必ずアメリカだった。その国で独裁反対の反政府運動が起こったら、それを支持するのがソ連や中国だった。いつからか、それが逆になってしまった。世界に独裁国家があれば、それを支持するのが中国やロシアなのである。何でそうなったのだろうか。中国は中国共産党の「一党独裁」国家である。「革命」をするわけだから、普通の意味での「民主」ではない。それは自明の前提だと思うが、それでも「共産党」と名乗る以上は今でも共産主義社会の実現を目指しているのだろうか。
共産主義社会では「国家の廃絶」が実現するはずだ。一体全体、最近のような「国家主義」そのものに変異してしまったことに理論的説明は付くのだろうか。もっとも中国は「社会主義市場経済」という不思議な経済体制を取っている。株式市場が存在し、多くの国民が参入できるようだから、そういう経済体制は「資本主義」と呼ばれるはずだ。しかし、「市場の自由」というよりは最終的には「党がコントロールできる」ようだ。それは「国家主義的資本主義」と言うべきだろう。
 (全人代での習近平国家主席と李克強首相)
(全人代での習近平国家主席と李克強首相)
本質を隠蔽して「社会主義的用語」を駆使してそれらしい理論的粉飾を行う。それが党官僚の役割なんだろうが、いくら何でもこれではおかしいと思っている人はいないのか。きっといるに違いないと思う。それは数少ないかもしれない。最近アメリカ新政権のブリンデン国務長官と中国の楊潔篪(よう・けっち)中央政治局委員がアラスカで会談した。アメリカ側がウィグルや香港情勢などを取り上げたところ、楊は「我々が西洋人から受けた苦しみはまだ足りないというのか。外国から押さえつけられた時間がまだ短いというのか」などと語気鋭く反論した。
ほとんど「言葉の戦争」のようになったが、この楊氏の反論は中国で受けているらしい。その事を聞いて僕が思い出したのは、1933年の国際連盟総会で脱退を表明した松岡洋右の演説だ。これも日本で大喝采を受けたが、結局のところ歴史の中で愚かだったのは松岡の方だった。世界からの批判は謙虚に受け止めないといけないというのは、日本が世界に伝えていくべき歴史的教訓だと思う。「ウィグルで何が起こっているのか」。非難されたら、中国はなぜ「新疆ウィグル自治区を自由に取材して真実を報道して欲しい」と言い出さないのだろうか。
中国に「報道の自由」なんかないし、世界の報道機関に自由な取材を許すなんて発想は全く浮かばないだろう。僕はこういう問題が起きるたびに、自由な取材を認めていない側に何かしら隠すべきことがあるのだと判断することにしている。先の会談では中国側はアメリカの黒人問題などを取り上げていた。アメリカの国際法違反の事例なんか幾らでも思い浮かぶのに、何で中国はそれら(中東政策など)を取り上げず、アメリカに「内政干渉」したのだろうか。もちろん自分たちの反論がトンチンカンなものであることぐらい認識しているだろう。このやり取りの中に、中国共産党の知的退廃を見ることも出来るのかもしれない。この問題はもう少し考えたい。
毛沢東も鄧小平も独裁者だったが、その後はもうそういうタイプの独裁者は出て来ないと思っていた。中国の最高指導者は中国共産党総書記だが、21世紀になってからは「一期5年、二期まで」が慣例になっていた。しかし、その規定は撤廃され習近平総書記が3期目まで続くことは確実だ。その中国をめぐっては、ウィグルや香港の人権状況が問題化している。しかし、中国は「内政不干渉」をタテにして全く批判を受け付けない。それどころか、軍部がクーデタを起こし国民を弾圧するミャンマーの後ろ盾となっている。
王毅外相は最近中東6ヶ国を訪問したが、その中にはサウジアラビアも含まれている。イランを訪問して対アメリカで共闘するのは理解出来る。しかし、中東一番の親米国であり、議会政治さえ存在しない独裁的な王国のサウジアラビアを訪れて、最高実力者のムハンマド皇太子と会談したのである。サウジ側はウイグルや香港で中国の立場を支持し、中国側は「サウジ内政に口を出すいかなる勢力にも反対する」と述べたという。アメリカではトランプ政権が発表しなかったCIA報告書をバイデン大統領が発表した。そこではムハンマド皇太子がトルコで起こったカショギ氏殺害を承認していたとされている。そんなムハンマド皇太子と会談したわけだ。
 (王毅、ムハンマド会談)
(王毅、ムハンマド会談)今から半世紀以上も前には、世界に独裁国家があったら支持しているのは必ずアメリカだった。その国で独裁反対の反政府運動が起こったら、それを支持するのがソ連や中国だった。いつからか、それが逆になってしまった。世界に独裁国家があれば、それを支持するのが中国やロシアなのである。何でそうなったのだろうか。中国は中国共産党の「一党独裁」国家である。「革命」をするわけだから、普通の意味での「民主」ではない。それは自明の前提だと思うが、それでも「共産党」と名乗る以上は今でも共産主義社会の実現を目指しているのだろうか。
共産主義社会では「国家の廃絶」が実現するはずだ。一体全体、最近のような「国家主義」そのものに変異してしまったことに理論的説明は付くのだろうか。もっとも中国は「社会主義市場経済」という不思議な経済体制を取っている。株式市場が存在し、多くの国民が参入できるようだから、そういう経済体制は「資本主義」と呼ばれるはずだ。しかし、「市場の自由」というよりは最終的には「党がコントロールできる」ようだ。それは「国家主義的資本主義」と言うべきだろう。
 (全人代での習近平国家主席と李克強首相)
(全人代での習近平国家主席と李克強首相)本質を隠蔽して「社会主義的用語」を駆使してそれらしい理論的粉飾を行う。それが党官僚の役割なんだろうが、いくら何でもこれではおかしいと思っている人はいないのか。きっといるに違いないと思う。それは数少ないかもしれない。最近アメリカ新政権のブリンデン国務長官と中国の楊潔篪(よう・けっち)中央政治局委員がアラスカで会談した。アメリカ側がウィグルや香港情勢などを取り上げたところ、楊は「我々が西洋人から受けた苦しみはまだ足りないというのか。外国から押さえつけられた時間がまだ短いというのか」などと語気鋭く反論した。
ほとんど「言葉の戦争」のようになったが、この楊氏の反論は中国で受けているらしい。その事を聞いて僕が思い出したのは、1933年の国際連盟総会で脱退を表明した松岡洋右の演説だ。これも日本で大喝采を受けたが、結局のところ歴史の中で愚かだったのは松岡の方だった。世界からの批判は謙虚に受け止めないといけないというのは、日本が世界に伝えていくべき歴史的教訓だと思う。「ウィグルで何が起こっているのか」。非難されたら、中国はなぜ「新疆ウィグル自治区を自由に取材して真実を報道して欲しい」と言い出さないのだろうか。
中国に「報道の自由」なんかないし、世界の報道機関に自由な取材を許すなんて発想は全く浮かばないだろう。僕はこういう問題が起きるたびに、自由な取材を認めていない側に何かしら隠すべきことがあるのだと判断することにしている。先の会談では中国側はアメリカの黒人問題などを取り上げていた。アメリカの国際法違反の事例なんか幾らでも思い浮かぶのに、何で中国はそれら(中東政策など)を取り上げず、アメリカに「内政干渉」したのだろうか。もちろん自分たちの反論がトンチンカンなものであることぐらい認識しているだろう。このやり取りの中に、中国共産党の知的退廃を見ることも出来るのかもしれない。この問題はもう少し考えたい。