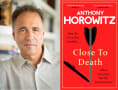文春文庫新刊の若竹七海『まぐさ桶の犬』をさっそく読んだので、その紹介。同窓の誼だからというわけでもないが、昔から若竹七海のミステリーはずいぶん読んできた。中でも「最も不運な探偵」葉村晶シリーズは現代屈指のハードボイルドで、ずいぶん楽しませてもらった。しかし、2019年の『不穏な眠り』以来、新刊が出てなかった。つまり「コロナ禍」以来ということになるが、作中ではコロナ時代には全く探偵の依頼がなかった、皆家に閉じこもっていて、探偵に会いに行き謎を解明するのも「自粛」だったとされる。ようやく2023年5月に「5類移行」という話が出て来た頃、そのちょっと前にやっと依頼を受けたのが今回の話。
葉村晶シリーズは、今まで『「錆びた滑車」』と『若竹七海の「葉村晶シリーズ」』と2回記事を書いている。葉村晶は日本には珍しい「女性探偵」だが、昔はちゃんと大手興信所の調査員だったこともある。その後無職となって、吉祥寺のミステリ専門書店の「アルバイト」をしている。店主の意向もあって、2階にちゃんと免許を受けた「白熊探偵社」の看板を掲げているが、ほとんど客は来ない。コロナ時代は店も閉めてることが多く、ネット注文の本を送るぐらいしかすることがなかった。付き合う相手もほぼご近所の住人しかいなかったが、ようやく実際に顔を合わせる会合が開かれる時期となってきた。
ということで、何故かご近所に頼まれて高齢女性を法事に連れて行くことになってしまう。そこで会う人々は奇妙な人々が多いが、早速その日から「不運」と「事件」に巻き込まれる。しかし、まあそのつながりで数年ぶりの依頼人を獲得出来たのである。ある学園の元理事長で、エッセイストとしても知られる老人。今は高齢者住宅に移ったが、そこを訪ねると昔の知り合いを探して欲しいという。それはかつて勤めていた高校の同僚だった養護教諭だという。電話をもらったままになっているので、連絡先を調べて欲しい、しかし、そのことは周囲には秘密にして欲しい、ミステリーのエッセイを出す仕事を頼んだことにしてくれという。
まあ、最初からちょっと変な依頼だなとは思ったけど、その学園創立者一族の面々は奇人変人勢揃い。さらに困った仕事を押しつけられるし、よりによって不運のオンパレード。そして数年ぶりの探偵稼業は、その間の加齢によって思ったように体が動かない。しかし、だからといって、またまた怪しい事件に当たりすぎ。今はネットで基本情報をかなり集めることが出来るが、ネットで調べきれない部分もあるから、やはり「現場」に行くしかない。そうすると「不運」が待っているわけ。
ま、そういうコンセプトで出来ているシリーズだから、やむを得ないとはいえ、今回は少し葉村をいじめすぎかもしれない。季節はいつでも良いはずが、よりによって花粉症の季節に山へ行くハメになる。おまけに歯も痛くなるし、車に至っては代車の代車が必要になる。そのうえ、冒頭で出てくるけど、何と殺されかかるじゃないか。その時思ったことは、自分をねらう容疑者が多すぎて絞れないという悲しい現実だったのである。警察小説ではないのに、「モジュラー型」、つまり同時並行的に主人公が様々なトラブルに巻き込まれるタイプの小説で、今回もついあちこち動き回る葉村晶だった。
推理を外しまくって悔やむこと多い葉村だが、今回はやむを得ないのではないか。依頼者もおかしいし、周辺人物も怪しすぎる。それにしても学校法人には怪しい人物が巣くうことがある。現実の事件も思い浮かべてしまう。時々出てくるミステリーのうんちくが定番ながら楽しい。例によってラストに解説が付いてるから安心である。
さて「まぐさ桶の犬」の意味だが、冒頭にロス・マクドナルド『さむけ』からの引用が出ている。イソップ物語で「自分に不必要な物は他人にも使わせない」と出ている。ちょっと判りにくいが、小説内でもう少し詳しく出てくる。「秣」(まぐさ)は馬や牛の食べる草である。犬は食べないのに、犬がまぐさ桶近くで吠えていると怖がって馬や牛が近づかない。犬は自分には何の利益もないのに、馬や牛をジャマしているわけである。つまり、自分に何の利益もないのに、他人が得しそうになるとジャマする輩。いるよな、そういうヤツ。世界的に増えているのかもしれない。
なお、中にジョイス・ポーターの『ドーヴァー』シリーズのことがちょっと出てくる。あったなあ。しかし、これは復刊されないだろうな。「青春ミステリ」特集の話も納得。僕は小峰元のファンで、まさに高校時代に読んでいた。