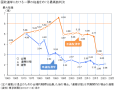2025年の参議院通常選挙の結果について3回書いてきたが、4回でいったん終わりにしたい。最後はやはり参政党の「躍進」に関して。3年前の参院選で国政選挙に初参加して、1議席を獲得した。その3年後に選挙区7、比例区7の合計14議席を獲得したのだから、やはり「躍進」というしかない。改選議席は124なんだから、1割以上になる。党勢を維持すれば、3年後には「予算を伴う法案を一党で提出できる」20議席を上回ることは確実だろう。今後参政党がどうなるのか、多くの人が注目している。
参政党は「日本人ファースト」を掲げて、参院選の争点を変えてしまった。それをマスコミが取り上げたからいけないという人もいるが、現実にウェブ空間では大きな問題になっていたから、当然大手マスコミも触れざるを得ない。僕は『「外国人問題」は存在しないー「外国人犯罪」は増えているのか?』を書いて、「外国人犯罪」がけっして増えているわけではないというデータを示した。しかし、いま思えば僕の論点は不十分なところがあったと思う。今になって、これは選挙中のキャッチコピーであり、「外国人の特権」など日本に存在しないと神谷宗幣代表は言い始めている。もともと選挙目当ての「幻の争点」だったのである。
ちょうど20年前、2005年夏は「郵政解散」の年だった。小泉純一郎首相執念の「郵政民営化法案」をめぐって自民党内は大きくもめて、衆議院は多くの反対がありながら何とか通過したが、参議院では否決されてしまった。その時小泉首相は衆議院を解散し、反対派議員に「刺客」を差し向けたのだった。マスコミはこの騒動に熱中し、人々は「郵政民営化」を支持したのだった。(ちなみに小池百合子氏は「刺客」となって、兵庫県から東京都に選挙区を移した。そのままだったら今は兵庫県知事だったのかも。)御用エコノミストは郵政民営化こそ「景気回復の起爆剤」と強く支持し、打ち出の小槌のように持ち上げたものである。
今になってみると、「郵政民営化」で何が変わったのかと思う。特に良くならなかったどころか、民営化されたはずの日本郵便は不祥事続きである。外国企業に投資して大きな損失を出し、国富を流出させた。あの時多くの国民が「郵政民営化」に熱中したのは何故だろうか? 郵便局を利用していて、この組織を民営化しなくてはなどと感じていた国民はいないだろう。それが日本経済に何をもたらすかなど、普通の人には判らない。しかし、「郵政民営化が必要」と言われると、そうかそういうことだったのか、これで長い不況も終わって景気が良くなるのかと思わせる効果があった。誰も実感してないテーマだから「発見」出来たのである。
同じようなことが「日本人ファースト」「外国人犯罪」にも言えたと思う。今回の報道で見る限り、「自分が外国人犯罪で悩んでいる」と訴える人はほとんどいないようだった。そうじゃなくて、「外国人の犯罪が多くなっているらしいと聞いたことがある」などという人が多かったと思う。本当に「身近な課題」なんだったら、とっくに現実の中央・地方政府が対策を講じている。「幻のテーマ設定」だったからこそ、人々は「そうだったのか」「今まで誰も言ってくれなかった」と「発見」出来たのである。問題は「イメージ」だったのであり、「事実」としてデータを示しても反証にならないのだ。むしろ感情的な反発を呼んだのだろう。
今まで「自民党の右側」に新党を作ろうという動きはあまりなかった。かつて石原慎太郎氏が名付けた「たちあがれ日本」という党があり、一時「日本維新の会」と合同したが再び分れて「次世代の党」を結成した。その後「日本のこころを大切にする党」「日本のこころ」と名を変えて、結局2018年に自民党に合流した。この党の結成は主要メンバーの平沼赳夫氏が「郵政民営化」に反対して離党せざるを得なかったという事情が大きかった。自民党を離れて一定の勢力を維持しても、「自民党より左」の党とは政策的に連立を組めず、自民党以外に連立の対象がない。それなら自民党内で保守的政策を訴えた方が良いわけである。
ところが「参政党」「日本保守党」が登場したのは何故だろうか? それは「自民党の世襲政党化」「財政悪化のため強力な財政出動が望めない」という事情が背景にある。また、自民党は政権政党として国際的動向に無関心ではいられない。従って東京五輪を前にして「LGBT理解促進法」(あれほど実質がない骨抜き法案であるにも関わらず)などを提案するわけである。そんなことは知っちゃいないと独自路線を取れるのは、超大国アメリカのトランプ政権ぐらいである。日本では米民主党のオバマ政権、バイデン政権にも配慮せざるを得ない。しかし、そのことは「今後もどんどん多様性政策が進んでいく」可能性を示すわけである。
「日本の多様化政策」を防ぐためには、もはや自民党以外の党を作るしかないと思う人が登場したのは、そういう理由だろう。自民党内で「保守派」として活動しても、世襲の安倍晋三氏などを別にすれば権力の頂点は望めない。全国300小選挙区の大体は「自民党議員がすでにいる」か、強力な野党議員がいて当選が望めないかである。今回比例3位で当選した安藤裕議員は、京都6区の自民党議員を3期務めた人である。ここは立憲民主党(元民主党)の山井和則議員が強く、2003年以来8回当選している。小選挙区で敗れたのは2017年だけで、その時勝ったのが安藤氏。しかし、3期当選のうち2回は比例当選で、2021年には公認を得られなかった。
そういう人は他党に移る強い動機がある。神谷代表もかつて自民党の地方議員を務めていたし、今回比例で当選した松田学元共同代表は、2012年に「日本維新の会」から衆議院議員に当選していた。分裂後は次世代の党から出馬して落選し、一時自民党に所属した経歴がある。一方で、3年前には「ボードメンバー」として神谷、松田氏などと党の中核を担っていた吉野敏明氏(3年前の参院選比例区は個人票4位で落選)は、2023年11月に離党して、今回の参院選には「日本誠真会」を結成して立候補、33万3千票あまりで0議席に終わった。このように離合集散が激しいのは、まだ利益で結びつく「利害集団」ではなく、「理念集団」だからだろう。
参政党に注目が集まるとともに、多くの右派系人士が参政党に集うようになっただろう。もちろん日本保守党もあるが、中心メンバーのリーダー性はかなりはっきりしている。一方、参政党は「手作り感」があるうえ、地方議員を多く出している。東京で2位当選した「さや」(塩入清香)氏はもともと田母神俊雄氏が都知事選に出馬したときの「田母神ガールズ」だったという。田母神氏は元自衛隊の航空幕僚長だったが、アパグループの論文コンクールに歴史修正主義的論文で応募して受賞した。その論文が政府見解と違うとして問題化し、麻生内閣の浜田靖一防衛相に罷免された。自民党は国家統治上、あまりにも偏向するわけにいかない。
そのようなことを考えると、参政党には「歴史修正主義」の「国防女子」などが集まり始めていると考えられる。神奈川で当選した初鹿野裕樹(はじかの・ひろき)氏は元警察官という経歴で、かなり荒い発言を繰り返している。このように「タカ派防衛族」のような面々の影響力が強くなっているのかもしれない。今後の政治活動として「スパイ防止法」提出を挙げているのも、その事を示しているかもしれない。しかし、そうなると国民の求める経済政策優先を求める人も出て来るだろう。またもっと「純右翼」的な政策を求める人もあるだろう。大所帯になれば、内部に幾つかの考えの違いが生じる。そこでどうなるのか?
今のところ「大躍進」の多幸感が党を覆っているんだろうと思う。それがいつまで続くか。神谷宗幣代表のキャラクターが大きな意味を持っているのは間違いない。それは玉木雄一郎国民民主党代表とも似ている「陽性のカリスマ性」で、石破首相や野田佳彦代表と少し違う。また立花孝志氏や石丸伸二氏などの「陰性さ」とも違っている。参政党の躍進によって、NHK党などの中途半端な右派の存在感が飛ばされてしまった。そして本格的な右翼政党が初めて登場したのである。



































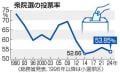
 (ニューヨークタイムスWeb版に掲載された石破首相の写真)
(ニューヨークタイムスWeb版に掲載された石破首相の写真)