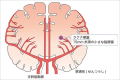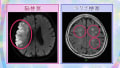9月5日。前日に「しばらく休載します」と書いたんだけど、ブログ引っ越しが滞っているのでメモ的に近況を報告。
◎ブログ引っ越しについて
本日は台風接近ということで、家でパソコンに向き合っている。過去のブログ記事を「引っ越しデータ」にしてダウンロードするところまでは出来た。次に「はてなブログ」を開設した。その上で、そこにある「インポート」機能からデータを移すわけだけど、そこがどうしても上手く行かない。「圧縮データを解凍する」のもやったはずなんだけど、「インポートに失敗しました」になっちゃう。
ビックカメラグループのサポートに入っているので、電話してみたけど、そういうのはサービス内容にないと言われてしまった。パソコン(OS)の問題じゃなくて、個別の問題はわからないのでというような感じだった。ということで、困っている状況。
今までは「引っ越し」に数日かかって、その後は新ブログで書いて行こうと思ってたけど、このまま移転出来なかったら、どうしよう。9月いっぱいはここでも書けるわけだけど。
ちなみに「はてなブログ」では、アイコンの写真を現在のものに変えました。いつまで昔の写真を使っているのもどうかと思うし。5月に岡山に行った時に鬼ノ城で撮った写真から顔だけ拡大したもの。
◎最近見た新作映画
8月に書いた映画記事には旧作が多い。夏休みは新作がエンタメ系映画ばかりになって、見る気も書く気も少なくなる。それでも見てないわけじゃない。『近畿地方のある場所について』は途中まではなかなか面白いホラーだったけど、ラスト付近の展開がムチャ。8月下旬に封切られたイタリア映画、パオロ・ソレンティーノ監督『パルテノペ』は時間があったら書いたかもしれない。流麗な映像美に浸れるし、主人公役の女優が見事。「才色兼備」はつらいよという人生を送るが、どうも今ひとつよく判らないシーンが多い。映画祭などでも無冠に終わってるが、それもやむを得ないかな。
横浜聡子監督の新作『海辺に行く道』も同じような感じかも知れない。小豆島で撮影された、面白エピソード満載の映画。アートと遊び心に満ちている。しかし、全体としてみるとバラバラ感があって、何なんだかよく理解出来ない感じ。
◎安岡章太郎の小説
梅崎春生の戦争文学を読んだので、手元にあった『安岡章太郎戦争小説集成』(中公文庫)も読んでみた。そこから他の読んでない本(岩波文庫の『安岡章太郎短編集』)などへ読み進めている。安岡章太郎という作家は、戦時中に留年、浪人(旧制中学から旧制高校へ)を繰り返し、最後になって徴兵された。長編『遁走』などの他、数多くの短編で軍隊生活を書いている。「満州国」最北部に配備されたが、全然戦闘体験はない。最末期に部隊は南方に送られて全滅するが、移送直前に病気になって入院、送還となった。梅崎春生以上の落伍兵で、過食したり下痢したり、そんな話ばかり。「落第生」の見た軍隊という意味で、興味深い。読みやすいんだけど、違和感を感じる箇所も結構多い。占領下に書かれたデビュー作『ガラスの靴』はとても良いと思う。
◎「政局」と国際情勢
自民党の「総裁選前倒し」問題。要するに石破首相は辞めるべきか、辞めざるべきか。僕はこれにはほとんど関心がない。自民党総裁に関しては自民党員が考えてくださいという感じ。まあ、何か新しい政策を打ち出して、どこかの野党を巻き込んで衆参で法案を成立させるということは、かなり難しいのではないか。どこかの時点で「辞意表明」は避けられず、新内閣で連立枠組拡大を目指すと見るのが起こりうる流れなんじゃないかと思うんだけど。
野党の方こそ考えるべきこといっぱいだが、どうも猛暑で意欲が湧かない。そのうちに。国際情勢では、どうしても「トランプ政権をどう考えるか」になってしまう。アメリカ国内が次第に大変なことになっていく気がする。どうも「単なる保守派」を越えている。「驚くべきこと」(憲法解釈を変えて三選を目指すとか)がないとは言えないと覚悟している。
「ガザ」「ウクライナ」の悲惨は続いている。いずれじっくり考えたいと思ってるけど。ミャンマーを初め、タイ、インドネシアなど東南アジア諸国の動向(政治的混乱)も気になるところ。
◎「戦後80年」について
「戦後80年」という節目の問題点もいずれきちんと考えておきたい。しかし、近年の8月は暑すぎる。「満州事変」が起こり、「日ソ戦争」の最終戦闘が終了した9月こそ「戦争を考える」時期とするべきではないか。それにしても、旧ソ連は(日本への宣戦布告後)ポツダム宣言に加わったのに、大日本帝国が宣言受諾を連絡したのちに戦闘を起こしたのをどう考えているのか。(アメリカはヤルタ宣言で、ソ連に千島を与える代わりに対日参戦を求めた。日本はサンフランシスコ講和条約で千島列島の領有を放棄した。それはそれとして、合法的な日本領だった千島列島を、連合国軍の一員のソ連軍が勝手に切り取って良いのだろうか。)
まあ、そう思っているけれど、「実力で切り取ったものは返さない」のである。だから、イスラエルは1967年に占領した地域を実質的に領有している。ゴラン高原に続いて、ヨルダン川西岸地区も併合しようとしている。ガザ地区も完全に封鎖して、いずれ返還するべき「占領地」とは思ってないだろう。同じようにロシアもウクライナから切り取ったドンバス地方などを返還する意思は全く無いだろうと思う。なお、そういう「ホンネ」を隠したまま、安倍政権時に「二島返還」を匂わせて経済協力だけ取り付けようとした。プーチンには「欺された」というのに、安倍昭恵氏を招いたりして、「分断」を策している。それを何故か「保守派」が批判しない。
ところで、「いつまで戦後なのか」という人がいるけれど、第二次世界大戦は単なる「帝国主義戦争」ではなかった。そこで問われた「核兵器の登場」や「ファシズム」という問題意識が終わってない以上、歴史区分としての「戦後」が続くのだと思う。マスコミは中国で「抗日戦争勝利80年」の軍事パレードと書くけれど、単なる「抗日」ではなく「反ファシズム戦争勝利」とうたっている。ファシズムの定義は難しいが、少なくとも「民主主義」や「自由主義」の反対である。
なぜ「反ファシズム戦争」に勝利した中国で、自由選挙が行われていないのか。言論の自由が存在しないのか。負けた日本の方が少なくとも社会的には「自由」なのは何故なんだろう。その問題こそ問われるべきだと思う。
もっと言えば、人類史を巨視的にみれば、「ヨーロッパ列強」の世界分割の最終段階で、「中国の半植民地化」と「日本の軍国主義化」が進行したが、それはコインの裏表なのである。(中国人が特に民族的に劣っていて、近代国家を形成出来なかったわけではない。同じように日本人が特に民族的に残虐で戦争が好きだったために軍国主義化したわけではない。)
「ヨーロッパ列強」の達成した「科学技術の発展」と「国内的な自由民主主義体制」は、どっちもアジア、アフリカ、ラテンアメリカ世界でも受け入れるべき人類史的達成である。しかし、その「科学技術の発展」が核兵器をもたらし、「国内的な自由民主主義体制」が世界恐慌で破綻して「ファシズム」が生まれた。その問題を「戦後80年」は解決出来なかった。だから、まだ「歴史的段階として」「(第二次世界大戦)後」なんだと思っている。
★猛暑もあるけど、このブログ問題に引っ掛かって、旅行などが出来ないのが困ったことだ。