「終戦のエンペラー」が史実的に「トンデモ映画」だったので、細かいことを思い出すために現代史関係の本を読み直した。その中で豊下楢彦「昭和天皇・マッカーサー会見」(岩波現代文庫)に、全く記憶にない興味深い事実があったので紹介したい。多分知らない人が多いと思う。それは「千島」のソ連領有とアメリカの「ミクロネシアの信託統治」が取引されたという事実である。そのこと自体も重要だけど、この事実は「核兵器の実験場がどこに置かれたか」という問題に関連する。
論点はかなり複雑だが、最初はロバート・D・エルドリッヂ「沖縄問題の起源」(2003)という本に関する議論である。その本は昭和天皇のいわゆる「沖縄メッセージ」に新しい解釈をしているが、豊下氏はその解釈は成り立たないと批判する。まず「昭和天皇の沖縄メッセージ」を解説しておくと、新憲法施行後の1947年9月、昭和天皇が御用掛の寺崎英成を通してシーボルト(連合国最高司令官政治顧問)に対して、「米国が沖縄その他の琉球諸島の軍事占領を続けるよう」「長期租借による、これら諸島の米国軍事占領の継続」を希望するというメッセージを伝えたというものである。
1979年に進藤榮一氏(当時筑波大助教授)が、アメリカの情報公開により入手した文書を公表すると大きな衝撃を与えた。沖縄はアメリカ軍の統治で大きな苦しみを受けてきた。その「原点」は「天皇に棄てられた」という事実にあったという驚きである。また新憲法で天皇は「象徴」になったが、国政に関わるメッセージを天皇が直接伝えるだろうかという疑問もあった。その後の研究の進展により、昭和天皇は時には日本政府(吉田首相)や占領軍(マッカーサー元帥)さえバイパスして、米国政府に直接接触したことがもあったと判ってきた。まさに君主による「二重外交」である。昭和天皇は「天皇制を守る」=「共産主義の攻勢を米軍の力で防ぐ」=「沖縄に米軍が存在することが必要」という、「政治的リアリズム」に徹していたのである。天皇の動きが現実政治に大きな影響を与えたと今では思われている。
このメッセージは「沖縄が本土の都合で切り捨てられた」とみなされることが多い。それに対しエルドリッヂは、「天皇メッセージ」が沖縄を日本領土に残したと評価しているという。米陸軍は沖縄の併合を求めていたが、天皇が米軍に先立って「米国の施政権を認める」という提案をしたため、併合の主張を押さえられたというのである。天皇メッセージがなければ、永久に沖縄は日本領土から切り離されただろうと。しかし、豊下氏は当時の国連における信託統治に関する議論を見れば、到底そのような評価はできないとエルドリッヂを批判するのである。
戦前に「国際連盟の委任統治」という制度があった。旧ドイツ領の「南洋諸島」は日本の「委任統治領」だった。旧ドイツ領のアフリカ諸国やオスマン帝国領のパレスティナ(イギリス委任統治)などもそうだった。日本は事実上、南洋諸島を軍事基地にしたため、サイパン島などで日米の激戦が繰り広げられた。アメリカ軍は「血で獲得した」それらの島々を併合することを求めていた。しかし、それは国連では認められるはずがない主張だというのである。国連はドイツ領南アフリカ(ナミビア)問題で揉めていた。ナミビアは戦前から南アフリカの委任統治領だったが、戦後になって南アフリカが勝手に併合を宣言した。国連はこれを「不法占領」と見なして認めなかった。南アのアパルトヘイト問題もあり、1990年にナミビアの独立が果されるまでこの問題は続いた。
国連安保理で南アの「不法占領」を非難していたアメリカは、沖縄どころか「南洋諸島」の併合さえ主張できる情勢ではなかった。そこで国連信託統治委員会の米代表だったダレス(後に日米安保条約をまとめ、米国務長官になる)は、「戦略的信託統治」という制度を認めさせた。普通の「信託統治」は国連総会の管轄下にあり軍事的利用は認められないが、安保理の管轄下におかれる「戦略区域信託統治」は「戦略地域」に指定されれば「軍事利用」「立ち入り禁止」が出来るという制度である。アメリカは安保理の拒否権を持つから、一度この指定を受ければ、後は事実上自由に統治できる。
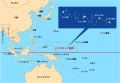 (ミクロネシア連邦)
(ミクロネシア連邦)
「戦略的信託統治」は米軍がミクロネシアで核兵器の実験をできる仕組みだから、当然ソ連は反対すると思われていた。ソ連も拒否権を持つから、ソ連が反対すればこの制度は実現しない。トルーマン米大統領がこの方針を明らかにした1946年11月に、ニューヨークで4か国外相会談が開かれた。その時にアメリカのバーンズ国務長官はソ連のモロトフ外相に対して、「千島列島をソ連に引き渡すという、『ルーズヴェルトの約束』を米国が守るかどうかは、このミクロネシア戦略統治にソ連がどういう態度を示すかにかかっている」と迫ったのである。1947年2月に、この戦略的信託統治案は安保理でソ連を含む全会一致で認められた。米ソは「ミクロネシア」と「千島」を取引したのである。
 (日本政府が主張する千島列島)
(日本政府が主張する千島列島)
千島問題に簡単に。カイロ宣言で、日本が「暴力および領土的野心により獲得した全領土」から追放されると述べ、それがポツダム宣言にも引き継がれた。一方、1945年2月のヤルタ会談の秘密協定で、ソ連はドイツ降伏後3カ月以内に対日参戦する、その代償として千島列島をソ連に引き渡す密約が交わされた。もちろん秘密協定だから、そのままでは日本は拘束されない。日露戦争後に日本領土になった南樺太はともかく、千島列島は本来「千島樺太交換条約」で平和裏に日本領となった地域である。しかし、日本はサンフランシスコ講和条約で、千島の放棄を認めた。
「放棄した千島列島はどこまでか」に関して北方領土問題はあるが、日本が北千島を放棄したことは条約上の事実である。(ただ講和条約にソ連は署名しなかった。)その条約を結ぶ前に、米ソの知られざる取引があったわけである。なお、ソ連はアジアで米国と張り合いすぎると、最重要の東欧支配に影響しかねないと心配したと思われる。東欧地域はソ連が解放した地域が多く、その経過を重視してソ連優位を認めよと米英に迫っていた。だからアメリカが戦闘の結果日本から獲得したミクロネシアに文句を言うと、逆効果になりかねない。
ここで考えるべきことはアメリカの核実験がミクロネシアで行われてきたという事実である。1953年の世界初の水爆実験はビキニ環礁(現マーシャル諸島共和国)で行われた。住民は強制的に移住させられて、今も帰ることができない。ソ連は現カザフスタン領のセミパラチンスク、イギリスはオーストラリア領の島々(クリスマス島など)、フランスはサハラ砂漠やフランス領ポリネシア(ムルロア環礁など)、中国は新疆ウィグル自治区のロプノールで行った。中国では独立運動がある地域だし、フランスも植民地で行っている。しかし、それでも自国領土で行っているとは言えるだろう。
アメリカがミクロネシアで核実験を行うことの「合法性」には、各国の中でも一番疑問があるのではないか。「戦略的信託統治」だから許されると言えばそれまでだが。もちろんどこで行おうが、核実験を大気中で行うことは許されない。今まで「米国がミクロネシアで核実験できる理由」という問題意識がなかったので、ここに書き記す次第である。なお、ミクロネシアの信託統治は、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、パラオが独立し、北マリアナ諸島(サイパン、テニアン等)が米国自治領(コモンウェルス)となって、今は行われていない。
論点はかなり複雑だが、最初はロバート・D・エルドリッヂ「沖縄問題の起源」(2003)という本に関する議論である。その本は昭和天皇のいわゆる「沖縄メッセージ」に新しい解釈をしているが、豊下氏はその解釈は成り立たないと批判する。まず「昭和天皇の沖縄メッセージ」を解説しておくと、新憲法施行後の1947年9月、昭和天皇が御用掛の寺崎英成を通してシーボルト(連合国最高司令官政治顧問)に対して、「米国が沖縄その他の琉球諸島の軍事占領を続けるよう」「長期租借による、これら諸島の米国軍事占領の継続」を希望するというメッセージを伝えたというものである。
1979年に進藤榮一氏(当時筑波大助教授)が、アメリカの情報公開により入手した文書を公表すると大きな衝撃を与えた。沖縄はアメリカ軍の統治で大きな苦しみを受けてきた。その「原点」は「天皇に棄てられた」という事実にあったという驚きである。また新憲法で天皇は「象徴」になったが、国政に関わるメッセージを天皇が直接伝えるだろうかという疑問もあった。その後の研究の進展により、昭和天皇は時には日本政府(吉田首相)や占領軍(マッカーサー元帥)さえバイパスして、米国政府に直接接触したことがもあったと判ってきた。まさに君主による「二重外交」である。昭和天皇は「天皇制を守る」=「共産主義の攻勢を米軍の力で防ぐ」=「沖縄に米軍が存在することが必要」という、「政治的リアリズム」に徹していたのである。天皇の動きが現実政治に大きな影響を与えたと今では思われている。
このメッセージは「沖縄が本土の都合で切り捨てられた」とみなされることが多い。それに対しエルドリッヂは、「天皇メッセージ」が沖縄を日本領土に残したと評価しているという。米陸軍は沖縄の併合を求めていたが、天皇が米軍に先立って「米国の施政権を認める」という提案をしたため、併合の主張を押さえられたというのである。天皇メッセージがなければ、永久に沖縄は日本領土から切り離されただろうと。しかし、豊下氏は当時の国連における信託統治に関する議論を見れば、到底そのような評価はできないとエルドリッヂを批判するのである。
戦前に「国際連盟の委任統治」という制度があった。旧ドイツ領の「南洋諸島」は日本の「委任統治領」だった。旧ドイツ領のアフリカ諸国やオスマン帝国領のパレスティナ(イギリス委任統治)などもそうだった。日本は事実上、南洋諸島を軍事基地にしたため、サイパン島などで日米の激戦が繰り広げられた。アメリカ軍は「血で獲得した」それらの島々を併合することを求めていた。しかし、それは国連では認められるはずがない主張だというのである。国連はドイツ領南アフリカ(ナミビア)問題で揉めていた。ナミビアは戦前から南アフリカの委任統治領だったが、戦後になって南アフリカが勝手に併合を宣言した。国連はこれを「不法占領」と見なして認めなかった。南アのアパルトヘイト問題もあり、1990年にナミビアの独立が果されるまでこの問題は続いた。
国連安保理で南アの「不法占領」を非難していたアメリカは、沖縄どころか「南洋諸島」の併合さえ主張できる情勢ではなかった。そこで国連信託統治委員会の米代表だったダレス(後に日米安保条約をまとめ、米国務長官になる)は、「戦略的信託統治」という制度を認めさせた。普通の「信託統治」は国連総会の管轄下にあり軍事的利用は認められないが、安保理の管轄下におかれる「戦略区域信託統治」は「戦略地域」に指定されれば「軍事利用」「立ち入り禁止」が出来るという制度である。アメリカは安保理の拒否権を持つから、一度この指定を受ければ、後は事実上自由に統治できる。
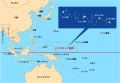 (ミクロネシア連邦)
(ミクロネシア連邦)「戦略的信託統治」は米軍がミクロネシアで核兵器の実験をできる仕組みだから、当然ソ連は反対すると思われていた。ソ連も拒否権を持つから、ソ連が反対すればこの制度は実現しない。トルーマン米大統領がこの方針を明らかにした1946年11月に、ニューヨークで4か国外相会談が開かれた。その時にアメリカのバーンズ国務長官はソ連のモロトフ外相に対して、「千島列島をソ連に引き渡すという、『ルーズヴェルトの約束』を米国が守るかどうかは、このミクロネシア戦略統治にソ連がどういう態度を示すかにかかっている」と迫ったのである。1947年2月に、この戦略的信託統治案は安保理でソ連を含む全会一致で認められた。米ソは「ミクロネシア」と「千島」を取引したのである。
 (日本政府が主張する千島列島)
(日本政府が主張する千島列島)千島問題に簡単に。カイロ宣言で、日本が「暴力および領土的野心により獲得した全領土」から追放されると述べ、それがポツダム宣言にも引き継がれた。一方、1945年2月のヤルタ会談の秘密協定で、ソ連はドイツ降伏後3カ月以内に対日参戦する、その代償として千島列島をソ連に引き渡す密約が交わされた。もちろん秘密協定だから、そのままでは日本は拘束されない。日露戦争後に日本領土になった南樺太はともかく、千島列島は本来「千島樺太交換条約」で平和裏に日本領となった地域である。しかし、日本はサンフランシスコ講和条約で、千島の放棄を認めた。
「放棄した千島列島はどこまでか」に関して北方領土問題はあるが、日本が北千島を放棄したことは条約上の事実である。(ただ講和条約にソ連は署名しなかった。)その条約を結ぶ前に、米ソの知られざる取引があったわけである。なお、ソ連はアジアで米国と張り合いすぎると、最重要の東欧支配に影響しかねないと心配したと思われる。東欧地域はソ連が解放した地域が多く、その経過を重視してソ連優位を認めよと米英に迫っていた。だからアメリカが戦闘の結果日本から獲得したミクロネシアに文句を言うと、逆効果になりかねない。
ここで考えるべきことはアメリカの核実験がミクロネシアで行われてきたという事実である。1953年の世界初の水爆実験はビキニ環礁(現マーシャル諸島共和国)で行われた。住民は強制的に移住させられて、今も帰ることができない。ソ連は現カザフスタン領のセミパラチンスク、イギリスはオーストラリア領の島々(クリスマス島など)、フランスはサハラ砂漠やフランス領ポリネシア(ムルロア環礁など)、中国は新疆ウィグル自治区のロプノールで行った。中国では独立運動がある地域だし、フランスも植民地で行っている。しかし、それでも自国領土で行っているとは言えるだろう。
アメリカがミクロネシアで核実験を行うことの「合法性」には、各国の中でも一番疑問があるのではないか。「戦略的信託統治」だから許されると言えばそれまでだが。もちろんどこで行おうが、核実験を大気中で行うことは許されない。今まで「米国がミクロネシアで核実験できる理由」という問題意識がなかったので、ここに書き記す次第である。なお、ミクロネシアの信託統治は、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、パラオが独立し、北マリアナ諸島(サイパン、テニアン等)が米国自治領(コモンウェルス)となって、今は行われていない。


























































