僕は参院選の争点は「憲法」だと書いた。その通りだと思うけど、だからと言って、改憲や安保法制の「危険性」だけ訴えていても、勝てないと思っている。「政権が隠す争点」を暴くのも大事だが、「政権が掲げる争点」の欺瞞も論じていかないといけない。今も安倍内閣の支持率は高い。「アベノミクス」への期待も残っている。「失敗」だという野党の主張もかなり支持があるようになってきたが、まだまだ期待があるのである。じゃあ、絶対に成功すると確信しているかというと、そうでもないだろう。
でも、「野党に対案がない」と思われている。熊本の地震やイギリスのEU離脱など、いろいろあってなかなか成功が見えてこない。だけど、もうすぐ東京五輪もあるし、そのころにはだいぶ成功が見てきているのではないか。いや、そう信じたい。という風に、「俺はまだ本気を出してないだけ」と呪文のように唱えて、日本経済には本来すごいものがあるんだと信仰告白しているのが、現在の経済政策ではないか。本当に、日本経済の現状と今後はどう考えるべきなんだろうか。
僕には正直言って、よく判らない。判るわけない。世界の経済学者だって、消費税をどうするかで意見が分かれた。バブル経済崩壊以後、日本経済をどう理解すべきかで、多くの経済学者の見解が全然かみ合わなかった。今はデフレ脱却が叫ばれているが、そもそも日本経済がデフレなのかどうかも、長いこと決着がつかなかった。そんな問題を僕が完全に判るわけがない。多くの人もそうだろう。「競馬必勝法」なんていうのと同じで、もしそんなものがあったら公開せずに自分で儲けるはずなのだ。世界経済、日本経済のゆくえも、誰もはっきりと予測することはできない。
ところで、以上のことは非常に大事なことだ。本来断言できないようなことを断定的に語る。そこにはトリックがある。トリックがあるということをわかっておくことが大事だ。まず、「データはどこを基準にするか」という問題。2009年に民主党政権ができた。2008年にリーマンショックが起き、世界経済が大きな混乱に見舞われた。そのような経済大混乱こそが、自民党ではなく民主党に期待を寄せた大きな要因だろう。そして、2011年に東日本大震災が起きた。工場なども被災し大きな損害を受けたし、原発事故で原発が停止し火力発電のための資源輸入が増えた。
安倍首相は「民主党政権時代から、自分の政権になって経済が大きく回復したではないか」といった主張をよく使う。それが本当なのかも検証の必要があるが、本当だとしても「それが何を意味するか」はよく考えないといけない。本来資本主義経済は「景気の波」があるわけで、国家の政策やグローバル化で昔ほど「教科書通り」の動きはしないと思うが、リーマンショックや大震災は一時的なものだから、数年後に回復していくのは自然なことだろう。どのくらいが「安倍政権の政策」によるものであり、どのくらいが自然な景気回復によるものかは、判断が難しい。
ではいくつかのデータを調べてみたい。いっぱい書くと長くなりすぎるから、一回目は「税収」と「株価」を取り上げる。税収に関しては、安倍首相は「アベノミクスによって、税収は21兆円増えた」と大宣伝している。だけど、自分が総理として消費税を3%アップしたんだから、税収が増えるのは当たり前だ。2013年の消費税収は10.8兆円、2015年の消費税収は17.1兆円とあるから、6兆円強は税率アップによるものである。今の数字は、財務省のHPにあるグラフから取ったもので、以下に示しておく。(なお、首相の言う21兆円は中央と地方を合わせた数字だが、以下のグラフは国の税収のみ。)
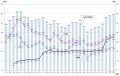
このグラフを見ると、税収が一番多かったのは、1990年。バブル経済さなかに加え、消費税が新たに作られた(税率3%)直後で、税収は約60兆円あった。翌1991年も大体同じ。その後バブル崩壊で税収が減り始め、増減はあるものの98年の消費税率アップを機に失速が始まる。いったん回復するが、実は小泉内閣時代の2002年、03年頃が40兆円台と最低を記録した。少しづつ回復し2007年に51兆円と50兆円台を回復した。第一次安倍政権の時代である。
翌2008年にリーマンショックが起き、税収が極端に落ちる。2008年が44.3兆円、09年はなんと38.7兆円である。その年が民主党政権誕生の年である。民主党政権の時に、財源がなくてマニフェストが実現できないと言われた。それはマニフェストがおかしいと言われ続けているが、とんでもない税収減の年に政権を引き継がなくてはならなかったという「特殊事情」があったのである。そして、以後はずっと毎年税収が増えている。つまり、民主党政権で増え、自民党政権に戻って増えた。年末まで大体は野田政権だった2012年は43.9兆円。以後、安倍政権になり、47、54、56.4と増えている。増えているけど、消費税アップ分を除けば、第一次安倍政権時代と同じである。
これは「アベノミクスで企業の業績がアップし、税収が増えた」という通念に反した事実ではないか。リーマンショックによる税収減が回復してきた軌道にあるところに、消費税をアップしたから、税収が多くなったというだけではないかと思える。ここ10年では一番経済が厳しかった民主党政権時代と比べると、確かに増えた増えたと思うけれど、実はようやく10年前の自分の政権の時代に戻っただけなのである。どこと比べるかが大事ということだ。
次は「株価」。まあやむを得ないから「日経平均」を使う。株価は上がり下がりがあり、これもどこを取るかで変わってくるけど、資料の都合で「年末の終値」で見る。まあ、大体の目安としては使えるのではないか。本日、2016年6月30日の終値は、15,575.92円。今はイギリス問題で下がった局面だから、この数字でいいかも問題だが、とりあえず今日書いてるので。
これは民主党政権の2011年の「8,455.35」円よりずいぶん高い。それは事実だが、この年は震災があった。リーマンショックの2008年の「8,859.56」円から、2010年の菅政権時代の「10,228.92」円まで、民主党政権で1400円アップしている。それは何も民主党政権が成功したというのではなく、一時的な混乱が収束していったということだろう。2013年は「16,291.31」円、2014年は「17,450.77」円、2015年は「19,033.71」で、確かに高くなった。そして、それが今も続いているならば、少なくとも株価は上がっていると言えるわけだが、安倍首相も昨今の株価低迷でさすがに話題にしないようである。
第一次安倍政権時代の2006年はどうだろうか。それは「17,225.83」円だった。前の政権時代より、選挙戦中の今の方が低いのだから、あまり触れたくないだろう。この間の株価上昇のかなりの部分は、外国人投資家に買いが多かったことよるものである。円の為替レートは、80円から120円ぐらいまで、大幅な円安を記録していた。つまり、外国人投資家にとっては、日本株は大幅に安くなっていた。そして、円安により企業業績がアップし、配当も増えたが、その分は国内投資家にももちろん入るが、外国人投資家にも入る。そして、そろそろアベノミクスに見切りをつけて、まだ高値のうちに売り払ってしまう。結局、この間の「株高」というのは、日本企業の利益を外国に流出させただけではないか。
こうして、税収と株価を見ても、リーマンショック後の民主党政権時代と比べるのがおかしいと思う。安倍首相はアベノミクスの成果だと言い張るわけだが、実は第一次安倍政権時代と比べれば、せいぜい同じ程度である。それが事実である。では、他の指標はどうだろうか。
でも、「野党に対案がない」と思われている。熊本の地震やイギリスのEU離脱など、いろいろあってなかなか成功が見えてこない。だけど、もうすぐ東京五輪もあるし、そのころにはだいぶ成功が見てきているのではないか。いや、そう信じたい。という風に、「俺はまだ本気を出してないだけ」と呪文のように唱えて、日本経済には本来すごいものがあるんだと信仰告白しているのが、現在の経済政策ではないか。本当に、日本経済の現状と今後はどう考えるべきなんだろうか。
僕には正直言って、よく判らない。判るわけない。世界の経済学者だって、消費税をどうするかで意見が分かれた。バブル経済崩壊以後、日本経済をどう理解すべきかで、多くの経済学者の見解が全然かみ合わなかった。今はデフレ脱却が叫ばれているが、そもそも日本経済がデフレなのかどうかも、長いこと決着がつかなかった。そんな問題を僕が完全に判るわけがない。多くの人もそうだろう。「競馬必勝法」なんていうのと同じで、もしそんなものがあったら公開せずに自分で儲けるはずなのだ。世界経済、日本経済のゆくえも、誰もはっきりと予測することはできない。
ところで、以上のことは非常に大事なことだ。本来断言できないようなことを断定的に語る。そこにはトリックがある。トリックがあるということをわかっておくことが大事だ。まず、「データはどこを基準にするか」という問題。2009年に民主党政権ができた。2008年にリーマンショックが起き、世界経済が大きな混乱に見舞われた。そのような経済大混乱こそが、自民党ではなく民主党に期待を寄せた大きな要因だろう。そして、2011年に東日本大震災が起きた。工場なども被災し大きな損害を受けたし、原発事故で原発が停止し火力発電のための資源輸入が増えた。
安倍首相は「民主党政権時代から、自分の政権になって経済が大きく回復したではないか」といった主張をよく使う。それが本当なのかも検証の必要があるが、本当だとしても「それが何を意味するか」はよく考えないといけない。本来資本主義経済は「景気の波」があるわけで、国家の政策やグローバル化で昔ほど「教科書通り」の動きはしないと思うが、リーマンショックや大震災は一時的なものだから、数年後に回復していくのは自然なことだろう。どのくらいが「安倍政権の政策」によるものであり、どのくらいが自然な景気回復によるものかは、判断が難しい。
ではいくつかのデータを調べてみたい。いっぱい書くと長くなりすぎるから、一回目は「税収」と「株価」を取り上げる。税収に関しては、安倍首相は「アベノミクスによって、税収は21兆円増えた」と大宣伝している。だけど、自分が総理として消費税を3%アップしたんだから、税収が増えるのは当たり前だ。2013年の消費税収は10.8兆円、2015年の消費税収は17.1兆円とあるから、6兆円強は税率アップによるものである。今の数字は、財務省のHPにあるグラフから取ったもので、以下に示しておく。(なお、首相の言う21兆円は中央と地方を合わせた数字だが、以下のグラフは国の税収のみ。)
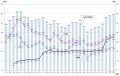
このグラフを見ると、税収が一番多かったのは、1990年。バブル経済さなかに加え、消費税が新たに作られた(税率3%)直後で、税収は約60兆円あった。翌1991年も大体同じ。その後バブル崩壊で税収が減り始め、増減はあるものの98年の消費税率アップを機に失速が始まる。いったん回復するが、実は小泉内閣時代の2002年、03年頃が40兆円台と最低を記録した。少しづつ回復し2007年に51兆円と50兆円台を回復した。第一次安倍政権の時代である。
翌2008年にリーマンショックが起き、税収が極端に落ちる。2008年が44.3兆円、09年はなんと38.7兆円である。その年が民主党政権誕生の年である。民主党政権の時に、財源がなくてマニフェストが実現できないと言われた。それはマニフェストがおかしいと言われ続けているが、とんでもない税収減の年に政権を引き継がなくてはならなかったという「特殊事情」があったのである。そして、以後はずっと毎年税収が増えている。つまり、民主党政権で増え、自民党政権に戻って増えた。年末まで大体は野田政権だった2012年は43.9兆円。以後、安倍政権になり、47、54、56.4と増えている。増えているけど、消費税アップ分を除けば、第一次安倍政権時代と同じである。
これは「アベノミクスで企業の業績がアップし、税収が増えた」という通念に反した事実ではないか。リーマンショックによる税収減が回復してきた軌道にあるところに、消費税をアップしたから、税収が多くなったというだけではないかと思える。ここ10年では一番経済が厳しかった民主党政権時代と比べると、確かに増えた増えたと思うけれど、実はようやく10年前の自分の政権の時代に戻っただけなのである。どこと比べるかが大事ということだ。
次は「株価」。まあやむを得ないから「日経平均」を使う。株価は上がり下がりがあり、これもどこを取るかで変わってくるけど、資料の都合で「年末の終値」で見る。まあ、大体の目安としては使えるのではないか。本日、2016年6月30日の終値は、15,575.92円。今はイギリス問題で下がった局面だから、この数字でいいかも問題だが、とりあえず今日書いてるので。
これは民主党政権の2011年の「8,455.35」円よりずいぶん高い。それは事実だが、この年は震災があった。リーマンショックの2008年の「8,859.56」円から、2010年の菅政権時代の「10,228.92」円まで、民主党政権で1400円アップしている。それは何も民主党政権が成功したというのではなく、一時的な混乱が収束していったということだろう。2013年は「16,291.31」円、2014年は「17,450.77」円、2015年は「19,033.71」で、確かに高くなった。そして、それが今も続いているならば、少なくとも株価は上がっていると言えるわけだが、安倍首相も昨今の株価低迷でさすがに話題にしないようである。
第一次安倍政権時代の2006年はどうだろうか。それは「17,225.83」円だった。前の政権時代より、選挙戦中の今の方が低いのだから、あまり触れたくないだろう。この間の株価上昇のかなりの部分は、外国人投資家に買いが多かったことよるものである。円の為替レートは、80円から120円ぐらいまで、大幅な円安を記録していた。つまり、外国人投資家にとっては、日本株は大幅に安くなっていた。そして、円安により企業業績がアップし、配当も増えたが、その分は国内投資家にももちろん入るが、外国人投資家にも入る。そして、そろそろアベノミクスに見切りをつけて、まだ高値のうちに売り払ってしまう。結局、この間の「株高」というのは、日本企業の利益を外国に流出させただけではないか。
こうして、税収と株価を見ても、リーマンショック後の民主党政権時代と比べるのがおかしいと思う。安倍首相はアベノミクスの成果だと言い張るわけだが、実は第一次安倍政権時代と比べれば、せいぜい同じ程度である。それが事実である。では、他の指標はどうだろうか。























































