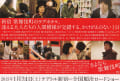イラン映画と言えば、90年代以後ずいぶん日本でも公開された。巨匠アッバス・キアロスタミやモフセン・マフバルドフを中心に、クルド系のバフマン・ゴバディや映画撮影禁止処分を受けながらも今年のベルリン映画祭金熊賞作品を作ったジャファル・パナヒなど何人もの監督が思い浮かぶ。初めは「子ども映画」が多く、イスラム体制の厳しい検閲を逃れるため児童映画の枠組みで作っていると言われていた。キアロスタミ「友だちのうちはどこ?」やマジッド・マジディ「運動靴と赤い金魚」などキネ旬ベストテンに入選している。その後、女性の不自由な境遇や辺境の人々を描く映画も公開された。でも、ファルハディの映画を見ると、今までのイラン映画受容って、ジブリと大島渚だけ見て日本を論じていたような感じがしてくる。
では彼の映画が好きかと言われると、それはちょっと…。「ある過去の行方」はイラン人も関係はしてるけど、外国で撮ってるから、人間関係の大変さを普遍的に描いている。でも「別離」は脚本や演技の卓抜さは認めないわけにはいかないけど、物語を観賞する前にイランの法体系の不条理さにいらだってしまって、どうも心穏やかに見ることができないのである。今回はデビュー作の「砂塵にさまよう」(2003)、第2作「美しい都市(まち)」(2004)、第3作の「火祭り」(2006)が上映されたが、いずれも「別離」と同様に、テヘランで生きる庶民の不条理な生活が描かれている。
「砂塵にさまよう」は、親が結婚に反対したために一目ぼれした結婚相手と別れなければならない男の話。カネもないのに慰謝料を払うと裁判で約束し、砂漠で毒蛇を取る危険な仕事につく。蛇取りの男の車に乗り込んで、教えてもらおうとするが、男は彼を拒否し…と話はどんどんおかしくなり、ついに彼は毒蛇にかまれてしまう。大体なんで別れなければならないかが全く納得できない。(理解はできる。)主人公ナザルは直情径行すぎるし、声が馬鹿でかい。映画内でも妻にバスでは静かに話してと言われてる。とにかく一方的にまくしたて続けるナザルを見てるだけで、こっちもウンザリ。

第2作を後にして、3作目「火祭り」。夫婦のいさかいを描く心理ドラマで、非常に完成度が高い。ポランスキーが映画化した「おとなのけんか」という映画があるが、その原作の舞台劇と同じぐらい迫力がある。若いルーヒは職業案内所で紹介された家政婦の仕事でマンションに行くと、夫婦げんかでめちゃくちゃな家庭の片付け依頼。妻は夫の浮気を疑い、その相手と疑う向かいの部屋の美容サロン(もぐり)に「偵察」に行かされたり、子どもの出迎えに小学校に行かされたり…。もうすぐ結婚を控えた彼女は、夫婦に振り回された一日をどう思っただろう。

演出の冴えが印象的で、その才気は並々ならぬものがある。主演のタラネ・アリデュスティという女優(薬師丸ひろ子っぽい)が魅力的で目を奪われる。題名はイランの新年にならされる爆竹の祭りからで、ロケだと思うが中国の春節を超えるのではないかと思うすごさ。男の方は映像関係の仕事で、正月には家族でドバイに行く予定にしている。しかし大みそかにも仕事で呼び出され、映像に「毛が映ってる」と処理のお仕事。もちろん、「スカーフの下に頭髪が見えてる」という問題である。
さて、中味的に「トンデモ」なのが「美しい都市(まち)」で、脚本、演出、演技はずいぶん洗練されて来ているが、とにかくイスラム法の不可思議な世界に頭クラクラである。まず「美しい都市」というのは少年院の名前で、盗みで入っていたアーラはもうすぐ収容期間が終わる。担当官が期間が延びてるのは懲罰によるものだから、もう出してもいいだろうと判断して釈放される。ここでもう不思議。現場裁量でできるのか。アーラはシャバでやりたいことがあった。それは中で知り合った友人のアフマドが18歳になったので、死刑にされるかもしれない、そのために被害者の許しをもらいたいのである。
アフマドは16歳の時に恋人が出来たが、相手の親が認めず、悩んで心中しようと思い相手の娘を殺して自分は生き残る。相手の親が許してくれずに死刑判決になったらしい。内容的に死刑になる事件ではないが、被害者が求めると死刑なのである。さらに、国連人権規約は18歳未満の死刑を禁止し、日本の刑法も18歳未満の場合は死刑に当たる罪を無期懲役とすると定めている。当たり前のことだが、これは「犯行当時、18歳未満」の事例である。イランでは、犯行当時18歳未満でも、捕まえといて18歳になれば死刑にできるのか。ありえないでしょ、それは。
さらにすごいのは、その後。アーラがアフマドの姉フィルゼー(「火祭り」の家政婦役のタラネ・アリデュスティ)とともに被害者を訪れても、父親は絶対に許さないと言う。ではすぐに死刑執行となるかというと、被害者側が賠償金を払わないと死刑執行ができない。被害者が加害者に払うのである。なぜなら、女の価値は男の半分だから、女が1人死に、男を死刑にすると、1人分男側の家族が損をすることになる。賠償金を女側が男側に払わないといけないのである。通常の日本人は理解できないだろう。というか、絶対にそんなことはあってはいけないと思うだろう。それを父親側が許すと言えば、アフマド少年は釈放されるのだが、今度は加害者側が被害者側に賠償金を払う必要があるのである。両家とも貧乏で、執行も釈放も出来ない状況となり…。父親の妻は死んでいるのだが、後添えを貰っていてもうひとり女の子がいる。その子は足が悪い障害者で、器量も悪いので、このままでは結婚の相手も見つからないと思った後妻は、許しを求めに来るアーラが真面目そうなので、娘と結婚してくれたら父親に許しを出させるという策略をめぐらす。(ちなみに義母が許すだけでは、娘と血のつながりがないので、死刑判決を取り消す効力がない。)
この筋の進み具合のトンデモぶりは実に凄まじい。アーラはアフマドの姉フィルゼーに子どもがいるので結婚していると思っていたが、離婚して独身と知り、思慕の念を募らせる。フィルゼーとしては、子のいる自分が年下の男と結ばれるより、弟の命を救うためにも障害者の娘と結婚して欲しいし。一体どうなっていくんじゃ、というところで映画は終わってしまう。結婚はともかく、死刑というか、刑罰というものは国家の刑罰権の問題である。被害者が許すとか許さないとか、ましてや賠償金を払うとか払えないとか、そういう問題は情状酌量の点では意味があるが、それですべてが決まるという構造自体がおかしい(近代的な法概念では)。でも、イスラム法では刑事と民事に本質的な区別がない。裁くのは神にしかできないことだから、被害者が許せばそれで終わりでいい。モスクでは、許せば神の国に行きやすくなるから、許せと指導される。父親は「神の方がおかしい」と冒涜的な言葉さえ発するが、でも元はと言えばこの父が男女交際を許していれば、すべてはなかったではないか。
特に、男女の差から被害者側が賠償金を求められるという超トンデモがホントにあるのかと疑う人もあるだろうが、それはある。2003年にノーベル平和賞を授与されたイランの女性弁護士、人権活動家、シリン・エバディ「私は逃げない」という著書にくわしく出ている。この本は2007年に出た本だが、今でも入手可能だし、図書館等でも比較的見つかると思う。イランを知るためには必須の本で、とにかく凄まじい状況に驚くが、エバディの不屈の闘士ぶりにも敬意を抱かざるを得ない。
中でも一番すごいのは、以下の事件である。農村地帯で、ある11歳の少女が3人の男に強姦され崖の上から落とされ殺された。3人の男は逮捕されたが主犯は自殺、2人の男に死刑判決が下った。イスラーム法においては(というかイランのイスラーム体制における解釈では)「殺人の被害者は、法的処罰か金銭的補償かを選べる」。そして「女は男の権利の半分の価値がある。」そこで、少女の命を1ポイントとすると、男2人が死刑となるので男側のポイントは2×2の4ポイントとなる。被害者家族は、「レイプ被害者の家族という汚名」を晴らすため、死刑を求めるしかない。(イランの農村部の家父長的価値観の中では。)そのため、死刑となる男の家族の側に、少女の家族に対して「3ポイント分の補償」を求める権利が生じる。裁判所は少女の父親に処刑費用を含む多額の金額を払うように命じる判決を出した。家族は財産を投げ出したが足りないので、腎臓を売ろうとするが、父は薬物乱用の過去があり、兄は小児麻痺のため腎臓摘出ができなかった。なぜ家族で臓器を売るのか不思議に思った医者が事実を知り、司法省のトップに手紙を書き、問題を訴えたというのである。これはイランでも問題化したらしいし、そこからエバディが担当し、犯人が脱走したり、再審になったり複雑な経過をたどったらしい。とにかくこれが「イスラム法」体制であり、そういうのが理想だと思ってる人々が権力を握るとどうなるかの実例である。