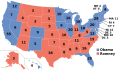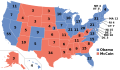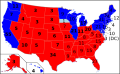数日前に見て書いてない映画「ちはやふる」の話。僕はこういう若い人向け大ヒット映画を見ない方だと思うが、見ないと決めているわけではない。むしろ、「時々見るけど、記事には書いてない」ということが多い。まあ、僕が書く必要もないし、くさす内容をわざわざ書きたくない。「ちはやふる」を何で見たのかというと、「家族はつらいよ」を見た時にちょうど「上の句」をピタリでやってたのが大きい。「部活映画」は展開が予想できるが、「競技かるた」は見たこともないし、イメージがわかない。たまたま新文芸座で(「恋人たち」と一緒に)「海街diary」を見直して広瀬すずの本格主演を見てみたいなとも思ったし。だけど「下の句」はなかなか見るチャンスがなかった。


で、どうだったかというと、「上の句」は面白かったが、「下の句」は期待外れ。まあ、大長編マンガのごく一部を映画化しただけだから、(2作合わせて、高校1年の夏休みまでしか進まない)、「上の句」でちりばめた伏線が回収されるどころか、さらに拡散したまま終わってしまうのも仕方ない。今後どうなっていくかは、ウィキペディアに詳しく載っていたが、なるほど映画というメディアも不自由なものだと思った。マンガで読めば、同じ時間でもっと進めるところを、人物をしぼって単純化しないと映像化できない。それでも実写化で得るものも大きい。
筋書きはここでは書かないが、「競技かるた」の世界を舞台に、「宿命的な人間関係」を幾重にも散りばめたストーリーが誇張的な表現で描かれていく。ヒロインである綾瀬千早(広瀬すず)は、もともと周囲が目に入らない人物設定になっているが、「下の句」になるとエキセントリックぶりがついていけない感じもする。それもこれも「高校生クイーン」である若宮詩暢の登場による。それまで知らなかったというのも不自然だけど、それはともかくどんどん「思い込み」の世界を深めていくのは、見ていて「痛い」感じがしてしまう。同級生で部長の真島太一(野村周平)や、「運命の人」の綿谷新(真剣祐=アメリカ生まれの千葉真一の長男である)との関わりも気になるが、それよりも何か社会生活が大丈夫かなあと思わせる描き方である。
ところで、「千早振る」という落語がある。小遊三なんかがよくやる噺で、僕も何度か聞いたことがある。百人一首の珍解釈で笑わせる展開だが、どうもこの歌はそっちを思い出してしまう。もとは在原業平の歌だけど、「ちはやぶる 神代もきかず 竜田川 からくれなゐに 水くゝるとは」というのは、訳がわからんと言えばその通りである。(現代語訳を探してみると、「(川面に紅葉が流れていますが)神代の時代にさえこんなことは聞いたことがありません。竜田川一面に紅葉が散りしいて、流れる水を鮮やかな紅の色に染めあげるなどということは。」とある。これでもわからん。)
もうちょっと調べると、歌は皇太子妃の藤原高子の宴で屏風を見ながら歌ったものとある。屏風に描かれた竜田川の紅葉(竜田川は生駒、斑鳩=いかるがを流れる川で、古来より紅葉の名所)を「神代にも聞いたことがないほどの、水をくくり染にするほど美しいですね」と新鮮な表現で、おおげさにほめたたえたところに興趣があるということらしい。ちなみに在原業平は桓武天皇のひ孫だが、桓武天皇の子である平城(へいぜい)天皇の子、阿保親王の子となる。祖父の平城天皇は薬子の変で権力を失ってしまったから、王権から遠く生まれて臣籍に降下した。ものすごい「イケメン貴公子」で知られ、何人もと浮名を流し、その一人が皇太子妃、高子である。そういう「政治的背景」のある「危険なラブロマンス」に関わる宮廷遊戯歌なんだろうと思う。
ところで、こういった高校生(役)がいっぱい出ている映画を見る場合、僕には映画と別の問題がある。それは教員生活の中で、多分千人を大きく超える中高生の顔を見てきたから、高校生映画を見ると「誰かと似ている」と思うのである。思い出せる人ばかりではなく、中には多分教えてもいないような生徒の顔もあるんじゃないかと思う。誰だろう、似てるなあとつい考え込んでしまうのである。もちろん本人が出ているはずもないわけだが。人間が認識する「顔のタイプ」というのがあり、それが頭の中に蓄えられているんだろうと思う。で、今度の場合、千早も結構いるタイプの顔なんだけど、新や大江奏(同級生の部員)なんかが誰かに似てそうで、そんなことをつい考えながら見てしまった。
映像で勝負する映画ではないから仕方ないのかもしれないが、僕はもう少し映像に凝ってほしい気がした。高校や神社は栃木県足利市でロケされたというが、非常に魅力的な場所だと思う。誇張表現にも飽きてくるが、「競技かるた」そのものが、最初は興味深いがだんだん見ていて関心がなくなってくる気がした。物語的に「どっちが勝つか」が大体わかっていて、意外性がないからである。それでもスポーツ映画なら見せてしまうし、合唱や吹奏楽、演劇なんかでも、それ自体が見たり聞いたりする価値があるから、見栄えする部活映画にできる。案外「かるた」は映像化が難しいのではないかとも思った次第。まあ、大ヒットを受けて、続編が作られるそうだから、期待しておこう。


で、どうだったかというと、「上の句」は面白かったが、「下の句」は期待外れ。まあ、大長編マンガのごく一部を映画化しただけだから、(2作合わせて、高校1年の夏休みまでしか進まない)、「上の句」でちりばめた伏線が回収されるどころか、さらに拡散したまま終わってしまうのも仕方ない。今後どうなっていくかは、ウィキペディアに詳しく載っていたが、なるほど映画というメディアも不自由なものだと思った。マンガで読めば、同じ時間でもっと進めるところを、人物をしぼって単純化しないと映像化できない。それでも実写化で得るものも大きい。
筋書きはここでは書かないが、「競技かるた」の世界を舞台に、「宿命的な人間関係」を幾重にも散りばめたストーリーが誇張的な表現で描かれていく。ヒロインである綾瀬千早(広瀬すず)は、もともと周囲が目に入らない人物設定になっているが、「下の句」になるとエキセントリックぶりがついていけない感じもする。それもこれも「高校生クイーン」である若宮詩暢の登場による。それまで知らなかったというのも不自然だけど、それはともかくどんどん「思い込み」の世界を深めていくのは、見ていて「痛い」感じがしてしまう。同級生で部長の真島太一(野村周平)や、「運命の人」の綿谷新(真剣祐=アメリカ生まれの千葉真一の長男である)との関わりも気になるが、それよりも何か社会生活が大丈夫かなあと思わせる描き方である。
ところで、「千早振る」という落語がある。小遊三なんかがよくやる噺で、僕も何度か聞いたことがある。百人一首の珍解釈で笑わせる展開だが、どうもこの歌はそっちを思い出してしまう。もとは在原業平の歌だけど、「ちはやぶる 神代もきかず 竜田川 からくれなゐに 水くゝるとは」というのは、訳がわからんと言えばその通りである。(現代語訳を探してみると、「(川面に紅葉が流れていますが)神代の時代にさえこんなことは聞いたことがありません。竜田川一面に紅葉が散りしいて、流れる水を鮮やかな紅の色に染めあげるなどということは。」とある。これでもわからん。)
もうちょっと調べると、歌は皇太子妃の藤原高子の宴で屏風を見ながら歌ったものとある。屏風に描かれた竜田川の紅葉(竜田川は生駒、斑鳩=いかるがを流れる川で、古来より紅葉の名所)を「神代にも聞いたことがないほどの、水をくくり染にするほど美しいですね」と新鮮な表現で、おおげさにほめたたえたところに興趣があるということらしい。ちなみに在原業平は桓武天皇のひ孫だが、桓武天皇の子である平城(へいぜい)天皇の子、阿保親王の子となる。祖父の平城天皇は薬子の変で権力を失ってしまったから、王権から遠く生まれて臣籍に降下した。ものすごい「イケメン貴公子」で知られ、何人もと浮名を流し、その一人が皇太子妃、高子である。そういう「政治的背景」のある「危険なラブロマンス」に関わる宮廷遊戯歌なんだろうと思う。
ところで、こういった高校生(役)がいっぱい出ている映画を見る場合、僕には映画と別の問題がある。それは教員生活の中で、多分千人を大きく超える中高生の顔を見てきたから、高校生映画を見ると「誰かと似ている」と思うのである。思い出せる人ばかりではなく、中には多分教えてもいないような生徒の顔もあるんじゃないかと思う。誰だろう、似てるなあとつい考え込んでしまうのである。もちろん本人が出ているはずもないわけだが。人間が認識する「顔のタイプ」というのがあり、それが頭の中に蓄えられているんだろうと思う。で、今度の場合、千早も結構いるタイプの顔なんだけど、新や大江奏(同級生の部員)なんかが誰かに似てそうで、そんなことをつい考えながら見てしまった。
映像で勝負する映画ではないから仕方ないのかもしれないが、僕はもう少し映像に凝ってほしい気がした。高校や神社は栃木県足利市でロケされたというが、非常に魅力的な場所だと思う。誇張表現にも飽きてくるが、「競技かるた」そのものが、最初は興味深いがだんだん見ていて関心がなくなってくる気がした。物語的に「どっちが勝つか」が大体わかっていて、意外性がないからである。それでもスポーツ映画なら見せてしまうし、合唱や吹奏楽、演劇なんかでも、それ自体が見たり聞いたりする価値があるから、見栄えする部活映画にできる。案外「かるた」は映像化が難しいのではないかとも思った次第。まあ、大ヒットを受けて、続編が作られるそうだから、期待しておこう。