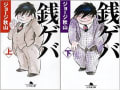東京都知事選挙をやっている。僕は今回の選挙について今まで何も書いていない。今回もちゃんと書く気はしない。そこに自分の意見表明があると思って貰っていい。東京都民は石原慎太郎氏を知事に4回も選んだ有権者である。都民であっても、「都民の判断」に納得できたことがない。それでもちょっと書いておきたいことがある。ついでに「泡沫候補」の世界をガイド。

まず立候補者数である。なんと22人で、史上最多である。前回の21人というのも多かったが、なんでこんなに立候補するんだろう。鹿児島知事選にも過去最多の7人が出ている。同時に行われる都議補選が4つあるが、それも結構出ている。(北区都議補選は、自民党と「都民ファーストの会」が激突し、立憲民主、維新に加えて「ホリエモン新党」まで全員女性候補が出ている。ここは都知事選と違って、票の出方が要注目である。)
何でそんなにたくさん立候補するんだろう。タダじゃないのである。日本の選挙は供託金が異例に高いということは指摘してきたが、都道府県知事選挙は300万円である。有効投票数の10分の1を超えないと没収される。東京都の有権者数は約1144万人で、投票率を50%とすると572万。50%は行かないと思うけれど、とにかく50万票ぐらいないと没収である。それは主要4候補(と言われている人)以外は不可能だろう。ほとんどの人は300万が戻ってこない。それでも出る。全部で5千万円以上になるけど、コロナ対応に使えるんだろうか。
ところで、当初マスコミは「主要5候補」と紹介していた。5人の中で現職以外は国政政党の公認、推薦を得ている。前参議院議員の山本太郎は「れいわ新選組」公認だが、同党は参議院に2議席を持っている。しかし、「ホリエモン新党」から出た立花孝志は、国政政党「NHKから国民を守る党」党首でもあり同党推薦を得ている。同党は(丸山穗高なる議員を抱き込んだので)衆参に一人ずつ議席がある。山本太郎と立花孝志は国政政党党首として同格になる。
世論調査の結果を待つまでもなく、22人の中で数十万票を見込める候補は4人である。だから終盤になって「主要4候補」という記事も多くなってきた。4人の中でも「法定得票」に達しない(=供託金没収)人が出ないとは限らない。それはともかく、今回は22人中、12人が無所属である。残りの10人が「諸派」になる。「会派」に所属すれば「諸派」に入ると考えれば、自民党だって「諸派」だろうが、普通は国会に議席を持たないミニ政党をまとめて「諸派」と呼んでいる。
その中で「ホリエモン新党」が立花氏を含めて、3人を公認している。全員選挙公報が同文である。上の画像にあるポスター掲示板では、2段目にまとめて3人が貼ってある。抽選すればバラバラになるはずで、それを避けるために主要候補が立候補を済ませた後に3人一緒に手続きをしたという。そして立花氏以外の二人はポスターに候補の名前がない。党首(?)の堀江貴文氏の顔が載っている。立候補者以外の顔を掲載するのは違法ではないかと都選管に多数の問い合わせがあるという。それは違法ではないが、これでいいのか。
しかも、一人しか当選しない知事選挙に3人を公認するとは、いくら何でも有権者をバカにし過ぎではないだろうか。どうせ当選しないんだし、お金持ちの道楽なんだから、どうでもいいのか。自民党系で複数が出てしまうような時もあるけど、その場合も公認は一人、あるいはどちらも公認しないだろう。国政選挙に向けた宣伝なんだろうけど、知事を選ぶのが都知事選の目的なんだから、最低限のルールには則って欲しいと思う。
さて「れいわ新選組」「ホリエモン新党」の他に、諸派としては「幸福実現党」、「日本第一党」(元「在特会」創設者桜井誠が前回10万票獲得)が割合有名。それ以外に「スーパークレイジー君」(という党名らしい。「現職か、俺か。」と主張し、「風営法の緩和」を掲げる)、「トランスヒューマニスト党」(一夫多妻、一妻多夫、多夫多妻合法化)、「庶民と動物の会」(庶民と動物に優しい東京に)、「国民主権党」(コロナはただの風邪)など多彩な主張をする党が存在する。
無所属候補では、主要候補以外でも割合穏当な主張をしている人が多い。(例外もいるが。)中では「新型コロナウイルスの治療薬と予防薬を発明しました」という候補がいる。ホントなら、都知事になるより他にすることがあるだろ。「未来の薬局を目指します」という薬剤師の候補もいる。都知事になっても仕方ないと思うが。ちなみに「やくざいし」の「ざ」にアクセントを付けないで、平板に発音するニュースがあって「ヤクザ医師」に聞こえてしまう。
まあ誰でも立候補する自由はあるわけだが、「消費税ゼロ」とか都知事になっても実現できない公約をなんで掲げる人がいるのか。しかし、国政選挙で比例区に出るには供託金が高すぎる。小選挙区に出ても、選挙区が小さいからポスターや広報、政見放送などの機会が限られる。ある意味、300万ムダにする気になれば、都知事選は「日本一注目される選挙」なんだろう。
都知事選と言えば、昔は赤尾敏、東郷健、秋山祐徳太子、近年もドクター中松、マック赤坂らの「有名泡沫候補」がいたものだ。マック赤坂は2019年に港区議選に当選してしまい、もう都知事選は卒業である。今回は候補者名を書いてないが、全員ホームページやツイッター等を持っているようだから、関心がある人は自分で調べて欲しい。

まず立候補者数である。なんと22人で、史上最多である。前回の21人というのも多かったが、なんでこんなに立候補するんだろう。鹿児島知事選にも過去最多の7人が出ている。同時に行われる都議補選が4つあるが、それも結構出ている。(北区都議補選は、自民党と「都民ファーストの会」が激突し、立憲民主、維新に加えて「ホリエモン新党」まで全員女性候補が出ている。ここは都知事選と違って、票の出方が要注目である。)
何でそんなにたくさん立候補するんだろう。タダじゃないのである。日本の選挙は供託金が異例に高いということは指摘してきたが、都道府県知事選挙は300万円である。有効投票数の10分の1を超えないと没収される。東京都の有権者数は約1144万人で、投票率を50%とすると572万。50%は行かないと思うけれど、とにかく50万票ぐらいないと没収である。それは主要4候補(と言われている人)以外は不可能だろう。ほとんどの人は300万が戻ってこない。それでも出る。全部で5千万円以上になるけど、コロナ対応に使えるんだろうか。
ところで、当初マスコミは「主要5候補」と紹介していた。5人の中で現職以外は国政政党の公認、推薦を得ている。前参議院議員の山本太郎は「れいわ新選組」公認だが、同党は参議院に2議席を持っている。しかし、「ホリエモン新党」から出た立花孝志は、国政政党「NHKから国民を守る党」党首でもあり同党推薦を得ている。同党は(丸山穗高なる議員を抱き込んだので)衆参に一人ずつ議席がある。山本太郎と立花孝志は国政政党党首として同格になる。
世論調査の結果を待つまでもなく、22人の中で数十万票を見込める候補は4人である。だから終盤になって「主要4候補」という記事も多くなってきた。4人の中でも「法定得票」に達しない(=供託金没収)人が出ないとは限らない。それはともかく、今回は22人中、12人が無所属である。残りの10人が「諸派」になる。「会派」に所属すれば「諸派」に入ると考えれば、自民党だって「諸派」だろうが、普通は国会に議席を持たないミニ政党をまとめて「諸派」と呼んでいる。
その中で「ホリエモン新党」が立花氏を含めて、3人を公認している。全員選挙公報が同文である。上の画像にあるポスター掲示板では、2段目にまとめて3人が貼ってある。抽選すればバラバラになるはずで、それを避けるために主要候補が立候補を済ませた後に3人一緒に手続きをしたという。そして立花氏以外の二人はポスターに候補の名前がない。党首(?)の堀江貴文氏の顔が載っている。立候補者以外の顔を掲載するのは違法ではないかと都選管に多数の問い合わせがあるという。それは違法ではないが、これでいいのか。
しかも、一人しか当選しない知事選挙に3人を公認するとは、いくら何でも有権者をバカにし過ぎではないだろうか。どうせ当選しないんだし、お金持ちの道楽なんだから、どうでもいいのか。自民党系で複数が出てしまうような時もあるけど、その場合も公認は一人、あるいはどちらも公認しないだろう。国政選挙に向けた宣伝なんだろうけど、知事を選ぶのが都知事選の目的なんだから、最低限のルールには則って欲しいと思う。
さて「れいわ新選組」「ホリエモン新党」の他に、諸派としては「幸福実現党」、「日本第一党」(元「在特会」創設者桜井誠が前回10万票獲得)が割合有名。それ以外に「スーパークレイジー君」(という党名らしい。「現職か、俺か。」と主張し、「風営法の緩和」を掲げる)、「トランスヒューマニスト党」(一夫多妻、一妻多夫、多夫多妻合法化)、「庶民と動物の会」(庶民と動物に優しい東京に)、「国民主権党」(コロナはただの風邪)など多彩な主張をする党が存在する。
無所属候補では、主要候補以外でも割合穏当な主張をしている人が多い。(例外もいるが。)中では「新型コロナウイルスの治療薬と予防薬を発明しました」という候補がいる。ホントなら、都知事になるより他にすることがあるだろ。「未来の薬局を目指します」という薬剤師の候補もいる。都知事になっても仕方ないと思うが。ちなみに「やくざいし」の「ざ」にアクセントを付けないで、平板に発音するニュースがあって「ヤクザ医師」に聞こえてしまう。
まあ誰でも立候補する自由はあるわけだが、「消費税ゼロ」とか都知事になっても実現できない公約をなんで掲げる人がいるのか。しかし、国政選挙で比例区に出るには供託金が高すぎる。小選挙区に出ても、選挙区が小さいからポスターや広報、政見放送などの機会が限られる。ある意味、300万ムダにする気になれば、都知事選は「日本一注目される選挙」なんだろう。
都知事選と言えば、昔は赤尾敏、東郷健、秋山祐徳太子、近年もドクター中松、マック赤坂らの「有名泡沫候補」がいたものだ。マック赤坂は2019年に港区議選に当選してしまい、もう都知事選は卒業である。今回は候補者名を書いてないが、全員ホームページやツイッター等を持っているようだから、関心がある人は自分で調べて欲しい。