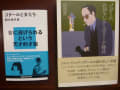マイケル・フレイン「コペンハーゲン」という有名な戯曲を読んだ。ハヤカワ演劇文庫で、去年11月に刊行。日本の現実を見てみると、大震災、原発事故という巨大なエネルギー放出が我々の生活を一変させ、未だにどのように対処すべきか、傷ついている。そういう中で、今まさに「コペンハーゲン」を読む時が来たなと思ったわけ。

「コペンハーゲン」という劇は、有名な物理学者ニールス・ボーアとその妻マルグレーテ(二人はデンマーク人)、同じく有名な物理学者で「不確定性原理」のハイゼンベルク(ドイツ人)、この3人しか出てこない。恐ろしく緊迫した劇空間が展開される。「読む戯曲」として、こんなにスリリングな話も珍しい。1941年、コペンハーゲン。かつての弟子ハイゼンベルクは、ドイツ占領下のコペンハーゲンにかつての師を訪ねる。そこでどのような会話が交わされたか。今では死者になった3人が、その一点で切り結ぶ。これはドイツの原爆開発に関わる話で、ハイゼンベルクの訪問は歴史的事実。しかし、一体何が話されたかは謎。ボーアは半分ユダヤ人の血を引き、その後亡命している。ハイゼンベルクは何をしにデンマークの旧師を再訪したか。占領下、今では敵どうしである。
 (ヴェルナー・ハイゼンベルク)
(ヴェルナー・ハイゼンベルク)
ハイゼンベルクは、ヒトラーのために原爆開発を進めていたのか。いや、すべて判ってサボタージュしていたのか。それとも、ハイゼンベルクの計算違いで原爆開発ができなかったのか。師ボーアを訪ねて、原爆開発の知恵を借りようとしたのか。はたまたドイツの原爆開発は成功しないと暗にボーアを通じてアメリカに伝えて欲しいと考えたのか?
ハイゼンベルクは「ドイツ人愛国者」として、「物理学者」として、何をしようとし、何をすべきであり、かつ何をしようとしながら失敗し、あるいは成功したのか? 歴史の闇に埋もれたこのドラマを、作者はたった3人の劇として、恐るべき緊迫感をもってドラマ化している。が、これを読む我々はもっと深刻な気持ちでこれを読まざるをえない。井上光晴の小説「明日」(黒木和雄監督が映画化したことでも有名)のように、我々は知っている。ドイツが開発するのを防ぐために、アメリカは亡命ユダヤ人学者の協力を得て核開発を急いだが、それはドイツ降伏には間に合わず、日本の上に投下されたのだった。そこに結びつく、歴史のドラマ。
60頁にも及ぶ、歴史解説のような長い長い作者の後書きが付いていて、歴史的事実はかなりよくわかる。実際、史実を確定させることは難しい問題であるようだ。「コペンハーゲン」というのは、有名なボーアの研究所がデンマークの首都にあり多くの若き物理学徒が集ったというエピソードが背景にある。量子力学に関して、有名な「コペンハーゲン解釈」というのがあるけれど、調べても僕には理解不能。ボーアは親分肌で多くの若者を集めたらしい。アインシュタイン受賞の翌年、1922年にノーベル賞受賞。10年後、ハイゼンベルク受賞。名前くらいは知ってた有名な物理学者の、戦争中の格闘。
 (ニールス・ボーア)
(ニールス・ボーア)
ノーベル物理学賞の受賞者を見ると、初期には放射線研究が多い。第1回はレントゲン。第3回はキュリー夫妻と、今や毎日単位の名前で聞いてるベクレル。放射性元素というのは、放射線を出しながら別の元素に変わっていく。ウラン238はいろいろ変化を重ね、14回後に鉛で安定するという。これは、発見した学者にとって、まさに錬金術を見つけたような驚くべき事実で、放射線の危険性は長く気づかれなかった。キュリー夫人も放射線障害で再生不良性貧血が死因だった。
村山斉さんのベストセラー「宇宙は何でできているのか」(幻冬舎新書)を読むと、宇宙の話と素粒子の話はつながっていると分る。そして、そういう物理学の理解が、現実の世界に関係してくる。放射線の話は、結局現代世界で最大の「暴力」である核兵器をどう考えるかに帰着する、と思う。「原発」という技術を考えると、人間はこのエネルギーを手にして良かったのだろうかという根本的疑問が起こる。しかし、「ヒトラー」が原爆先にを開発したらどうすればいいのか?
それでも人類は核開発をすべきではなかったという論理と倫理があるとすれば、世界に発信すべき立場にいるのが日本国民であると僕は思うけど、それは難しい命題だなとも思う。
いろんな角度から「核」を考えることが大切だと改めて確認する意味での紹介。すごい劇だと思うから、機会があったら読んでみて。日本でも上演があったのを知ってるけど、行ってない。見ておけば良かった。なお、日本にはマキノ・ノゾミ「東京原子核クラブ」という名作戯曲がある。朝永振一郎と理研をモデルにした劇で、比べて論じる必要がある。(2022.3.10一部改稿)

「コペンハーゲン」という劇は、有名な物理学者ニールス・ボーアとその妻マルグレーテ(二人はデンマーク人)、同じく有名な物理学者で「不確定性原理」のハイゼンベルク(ドイツ人)、この3人しか出てこない。恐ろしく緊迫した劇空間が展開される。「読む戯曲」として、こんなにスリリングな話も珍しい。1941年、コペンハーゲン。かつての弟子ハイゼンベルクは、ドイツ占領下のコペンハーゲンにかつての師を訪ねる。そこでどのような会話が交わされたか。今では死者になった3人が、その一点で切り結ぶ。これはドイツの原爆開発に関わる話で、ハイゼンベルクの訪問は歴史的事実。しかし、一体何が話されたかは謎。ボーアは半分ユダヤ人の血を引き、その後亡命している。ハイゼンベルクは何をしにデンマークの旧師を再訪したか。占領下、今では敵どうしである。
 (ヴェルナー・ハイゼンベルク)
(ヴェルナー・ハイゼンベルク)ハイゼンベルクは、ヒトラーのために原爆開発を進めていたのか。いや、すべて判ってサボタージュしていたのか。それとも、ハイゼンベルクの計算違いで原爆開発ができなかったのか。師ボーアを訪ねて、原爆開発の知恵を借りようとしたのか。はたまたドイツの原爆開発は成功しないと暗にボーアを通じてアメリカに伝えて欲しいと考えたのか?
ハイゼンベルクは「ドイツ人愛国者」として、「物理学者」として、何をしようとし、何をすべきであり、かつ何をしようとしながら失敗し、あるいは成功したのか? 歴史の闇に埋もれたこのドラマを、作者はたった3人の劇として、恐るべき緊迫感をもってドラマ化している。が、これを読む我々はもっと深刻な気持ちでこれを読まざるをえない。井上光晴の小説「明日」(黒木和雄監督が映画化したことでも有名)のように、我々は知っている。ドイツが開発するのを防ぐために、アメリカは亡命ユダヤ人学者の協力を得て核開発を急いだが、それはドイツ降伏には間に合わず、日本の上に投下されたのだった。そこに結びつく、歴史のドラマ。
60頁にも及ぶ、歴史解説のような長い長い作者の後書きが付いていて、歴史的事実はかなりよくわかる。実際、史実を確定させることは難しい問題であるようだ。「コペンハーゲン」というのは、有名なボーアの研究所がデンマークの首都にあり多くの若き物理学徒が集ったというエピソードが背景にある。量子力学に関して、有名な「コペンハーゲン解釈」というのがあるけれど、調べても僕には理解不能。ボーアは親分肌で多くの若者を集めたらしい。アインシュタイン受賞の翌年、1922年にノーベル賞受賞。10年後、ハイゼンベルク受賞。名前くらいは知ってた有名な物理学者の、戦争中の格闘。
 (ニールス・ボーア)
(ニールス・ボーア)ノーベル物理学賞の受賞者を見ると、初期には放射線研究が多い。第1回はレントゲン。第3回はキュリー夫妻と、今や毎日単位の名前で聞いてるベクレル。放射性元素というのは、放射線を出しながら別の元素に変わっていく。ウラン238はいろいろ変化を重ね、14回後に鉛で安定するという。これは、発見した学者にとって、まさに錬金術を見つけたような驚くべき事実で、放射線の危険性は長く気づかれなかった。キュリー夫人も放射線障害で再生不良性貧血が死因だった。
村山斉さんのベストセラー「宇宙は何でできているのか」(幻冬舎新書)を読むと、宇宙の話と素粒子の話はつながっていると分る。そして、そういう物理学の理解が、現実の世界に関係してくる。放射線の話は、結局現代世界で最大の「暴力」である核兵器をどう考えるかに帰着する、と思う。「原発」という技術を考えると、人間はこのエネルギーを手にして良かったのだろうかという根本的疑問が起こる。しかし、「ヒトラー」が原爆先にを開発したらどうすればいいのか?
それでも人類は核開発をすべきではなかったという論理と倫理があるとすれば、世界に発信すべき立場にいるのが日本国民であると僕は思うけど、それは難しい命題だなとも思う。
いろんな角度から「核」を考えることが大切だと改めて確認する意味での紹介。すごい劇だと思うから、機会があったら読んでみて。日本でも上演があったのを知ってるけど、行ってない。見ておけば良かった。なお、日本にはマキノ・ノゾミ「東京原子核クラブ」という名作戯曲がある。朝永振一郎と理研をモデルにした劇で、比べて論じる必要がある。(2022.3.10一部改稿)