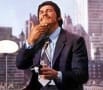映画監督の篠田正浩が3月25日に亡くなった。94歳。もうすぐ定例の「毎月の訃報」をまとめる時期だが、その前に特に篠田監督について書いておきたい。最近書きたいことがたまって、なかなか休めないのが困るが、まあ頑張って毎日書くことにしたい。篠田正浩は1960年に『恋の片道切符』で監督に昇進し、「松竹ヌーヴェルヴァーグ」の一人と呼ばれた。本家フランスのゴダール、トリュフォーら若い監督登場の波と同じく、1960年頃に松竹で監督に昇進した大島渚、吉田喜重らをそう呼んだのである。
他にも後の直木賞作家高橋治、脚本家として知られた石堂淑郎、田村孟らもいるが、映画史的には大島、吉田、篠田が代表格である。その中で大島渚は政治的に敏感なテーマに果敢に挑み、革命や差別などを考察した。吉田喜重は観念的なセリフ、露出過多の映像で「前衛芸術」風の作品が多い。この二人の映画は一見して難解なので、「あれはどういう意味か」といつも論評されてきた。それに対し、篠田作品は映画文法的には理解しやすく、興行的にヒットした映画も多い。そのため逆に篠田論が少なく、大島、吉田に比べて海外の評価が高まっていない。名画座などで篠田特集が組まれることも少なく、ちょっと忘れられた存在なのである。
僕は篠田正浩監督の映画がとても好きで、もっと評価されて欲しいとずっと思ってきた。僕が思うに、篠田作品を貫くテーマは「日本文化とは何か」である。特に「日本の歴史」に日本文化の特性を探り、日本の共同体から外れた人間を多く描いた。日本史を遡ると邪馬台国時代になるから、妻の岩下志麻をタイトルロールに配した『卑弥呼』という映画まで作ったぐらいである。(成功していないと思ったが。)ただ大島、吉田は監督自身が脚本を書いた作品が多く、映像を見れば大島印、吉田印と判る映画が多い。それに対して、篠田映画は原作を他の人が脚色したものが多い。そのため作風が多彩で独自色がないように見えてしまうのである。
だがお仕着せの脚本で撮影した商業映画ではなく、独特の感性を持った人に脚本を書いてもらい、監督は演出に専念するやり方も当然ある。それでも共同脚本に名を連ねた映画も多く、内容的なこだわりから自分が脚本に参加する場合も当然多かった。例えば『沈黙』は原作者の遠藤周作と篠田が脚本にクレジットされていて、原作とラストが違っている。初期作品は寺山修司の脚本が多く、中期には富岡多恵子が多い。『処刑の島』(1966)は武田泰淳原作を石原慎太郎が脚色している。まだ政治家になる前で、「共同体」から外れた少年たちを離島を舞台に描く意欲的な問題作である。再評価が必要な映画だと思う。
代表作は間違いなく『心中天網島』(1969)で、近松門左衛門の原作を富岡多恵子、武満徹、篠田が脚本にした。どう分担したか知らないが、武満が脚本にクレジットされている映画は他にないと思う。なお、主要な篠田映画は武満が音楽を担当していて、最後の作品となった『スパイ・ゾルゲ』(2003)は1996年に亡くなった武満徹に捧げられている。『心中天網島』はATG(日本アートシアターギルド)製作映画として初のベストワンになった。紙屋治兵衛は故中村吉右衛門、妻おさんと遊女お春は岩下志麻の二役。映画なんだから必要ないはずの「黒子」があえて画面を動き回る。二人の女性を岩下志麻がともに演じたことは素晴らしい工夫で、画面にものすごい緊迫感をもたらした。「身分」と「金」と「意地」がぶつかり、深い感動をもたらす映画だった。
岩下志麻主演という意味では、水上勉原作、長谷部慶次、篠田脚本の『はなれ瞽女(ごぜ)おりん』(1977)も素晴らしい。瞽女だから主人公は盲目である。岩下志麻の最高傑作だと思う。雪深い越後路で「はなれ瞽女」(男と関係して集団から外された瞽女)が脱走兵(原田芳雄)と結ばれる。美しい風景ながら厳しいリアリズムで、共同体から外れた人間を見つめるのである。同じ水上原作の『あかね雲』(1967)でも脱走兵が登場する。パルチザン運動などなかった日本でも、徴兵逃れは少しあった。2作も脱走兵を取り上げた監督は他にいない。「抵抗」ではなく「逃亡」だが、戦時下に自由を求めるとどんな苦難が待つか。
ごく初期の寺山脚本の『夕陽に赤い俺の顔』(1961)、『涙を、獅子のたて髪に』(1962)のポップな感覚も面白いが、最初に大きく認められたのは、1964年の2本の映画だと思う。『乾いた花』と『暗殺』である。前者は石原慎太郎の短編をもとに、賭場に現れた謎の少女(加賀まりこ)をヒリヒリした感触で描く。後者は司馬遼太郎の短編『奇妙なり八郎』の映画化で、丹波哲郎が幕末の風雲児、出羽脱藩浪人清河八郎を演じた。両作ともやはり「外れた」人間を描くが、どちらも相当に映画化が難しい原作だと思う。ベストテン15位、16位で、同じ年で損をした。謎めいた人物の孤独感が伝わってきて深い余韻を残す映画だ。
こうして書いていると終わらないが、『心中天網島』『沈黙』の両傑作の後、頼まれた『札幌オリンピック』をそつなくこなした後、『卑弥呼』『桜の森の満開の下』を経て『はなれ瞽女おりん』(1977)までが独自色、アート色が強い時代。その後は坂東玉三郎を主演にした『夜叉が池』、角川映画『悪霊島』を経て、阿久悠原作『瀬戸内少年野球団』(1984)とエンタメ色が強い作品が多くなる。しかし、そんな中でも近松原作『鑓の権左』(1986、ベルリン映画祭銀熊賞)、森鴎外原作『舞姫』(1989)を郷ひろみ主演で映画化した。郷ひろみ主演の『舞姫』なんて知らない人が多いのでは? 見るべき価値があったと思う。
1990年に『少年時代』、1995年に『写楽』を映画化した。その後も3作品あるが、傑作と言えるのはここまで。前者は井上陽水の主題歌で知られる「学童疎開」映画。都会の子が富山に疎開して味わう疎外感、いじめが壮絶。『写楽』は真田広之が東洲斎写楽、フランキー堺が蔦屋重三郎を演じた映画で、何で今再上映されないか不思議。どちらも面白いが、やはり共同体から外れた人間を描いている。そういう時に篠田映画は心に刺さるのである。同時代に日本社会、共同体を描いた監督に今村昌平がいるが、今村作品は土俗的な関心が強い。今村は東京生まれ、篠田は岐阜市生まれで、篠田には「共同体」への思い入れがないのだと思う。
映画監督引退を表明した後も日本文化研究を進め、2009年の『河原者ノススメ 死穢と修羅の記憶』という本では泉鏡花文学賞を受賞したぐらいである。戦国時代から幕末までを描く映画が8作品、戦争にふれる映画が6本あって、「江戸時代」と「戦争」が日本を考える際のカギになると考えていたのだろう。作品が多彩であっても、日本の歴史の中で、特に日本的共同体からはみ出た人々を見つめるというのが共通点であることが多い。僕には共感できる映画が多かった理由である。
なお、岩下志麻は再婚で、最初の妻は早稲田大学同期の詩人白石かずこだった。篠田はもともと陸上選手で、1年生で箱根駅伝に出場したことは有名。(2年でケガして引退。)前衛書家の篠田桃紅はいとこ。大島渚は小山明子、吉田喜重は岡田茉莉子、篠田正浩は岩下志麻とそれぞれ松竹を代表する女優と結婚して添い遂げたのが、本家ヌーヴェルヴァーグと一番違うところか。大島渚は2013年に亡くなり『追悼・大島渚』を書き、吉田喜重は2022年に亡くなり『吉田喜重監督の逝去を悼む-『エロス+虐殺』『秋津温泉』の思い出』を書いた。年齢を考えるとやむを得ないだろうが、今後の再評価が待たれる映画群が遺されている。