第一講 行政法とは何か
*行政法とは
行政法という法律は存在しない。
国家行政組織法、行政手続法、行政代執行法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(いわゆる情報公開法)など
+
国家公務員法、地方自治法、警察法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法)、土地収用法、都市計画法、建築基準法、所得税法、法人税法など
などがあつまって「行政法」という法分野を作っている
*行政法理論
ドイツ法:「法律による行政の原理」
英米法:「法の支配rule of law」ないし「適正な法手続きdeu process of law」
日本は、明治維新以後、ドイツ法の強い影響を受け、第二次世界大戦後、アメリカ法の影響を受けた。
*行政とは
故田中二郎氏(藤田氏の恩師)の定義
「近代国家における行政とは、法のもとに、法の規制を受けながら現実具体的に国家目的の積極的実現をめざしておこなわれる、全体として統一性を持った継続的な形式的国家活動である。」
*「行政主体」と「私的法主体」「私人」
「行政主体」:ある者がそれをおこなえば「行政活動」とみなされるばあい、この者のこと
「私的法主体」「私人」:通常の会社(私企業)とか個人のように「行政主体」としての性質を認められない者
*行政法上の法関係
行政の外部関係:「行政主体」と「私人」との間の相互関係、これを規律する行政法 「行政作用法」
行政の内部関係:「行政主体」の内部の人々相互間の関係、これを規律する行政法 「行政組織法」
*「活動様式」=「行為形式」
行為が、「私人」の「権利」に対してどんなかたちでかかわりあっているか
=行為は、私たち市民の自由や財産に対してどんなかたちで影響をおよぼしているか
に注目して見る
第二講 行政法上の法関係
*行政主体と私人との相互関係における「公報」と「私法」
「(行政に関する)公法」:行政活動に固有な法
「(行政に関する)私法」:私人間でもまた適用される法」
なにが公法と私法の区別および判別基準 かつては、問題であった
*「行政機関」:法的地位のこと
*「独任性の行政機関」と「合議制の行政機関」
*「行政庁」と「補助機関」
「行政庁」:みずからの名で、しかし行政主体のために意思決定をし、対外的に(つまり私人に対して)これを表示する権限を、法令上与えられている行政機関
*上級機関の指揮監督権
報告の聴取、訓令・通達、同意(承認)など、さまざなな形で指揮監督をする
調整
*指揮監督権の限界
1)権限行使の独立性を保証された行政機関
2)代替執行は原則的に許されない
第三講 法律による行政の原理
*法律による行政の原理
行政の諸活動は、法律の定めるところにより、法律にしたがっておこなわれなければならない
*意義
1)「法による行政」の原理ではなく「法律による行政」の原理
国民の法的安全(法的安定)
国民からの民主的なコントロール
2)行政の担い手の恣意をコントロールすることにより、私たち国民(私人)の権利・自由を保護する
*法律の優位の原則
行政活動は、現に存在している法律の定めに違反しておこなわれてはならない
*法律の留保の原則
行政活動は、それがおこなわれるためには、必ず法律の根拠(すなわち法律の授権=法律の根拠)を必要とする
*法律の留保の適用範囲
「侵害留保理論」オットー・マイヤー(ドイツ近代行政法学の父)
法律の留保の原則が適用されるのは、行政の相手方である私人に対して不利益な効果を持つ行政活動、つまり私人の「自由と財産」を侵害するような行政活動だけ
「全部留保理論」
およそ行政機関がおこなうあらゆる行動には、明文の法律の根拠(授権)が必要である。
「権力留保説」
「本質性理論=重要事項留保説」
*法律の専権的法規制創造力の原則
新たに法規を創造するのは法律すなわち立法権の専権に属することであって、行政権は、法律による授権がないかぎり法規を創造することはできない
第四講 法律による行政の原理の例外と限界
*例外:自由裁量論
行政活動の法律適合性はどのようにして確保されるか
法律による行政の原理の例外 「侵害留保理論」
包括的なかたちで授権→自由裁量行為
便宜裁量=目的裁量
法規裁量=覊束(きそく)裁量
覊束(きそく)行為
*自由裁量の限界:裁量権の限界を超えた行為
裁量権の踰超(ゆえつ)
裁量権の濫用(らんよう)
*覊束(きそく)行為と自由裁量行為の判別の基準
美濃部三原則
*限界
1)行政が法律にしたがってさえいればすべて万々歳とはいかない
2)私人権利救済という見地からしても不十分なものが残る
以上
*行政法とは
行政法という法律は存在しない。
国家行政組織法、行政手続法、行政代執行法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(いわゆる情報公開法)など
+
国家公務員法、地方自治法、警察法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法)、土地収用法、都市計画法、建築基準法、所得税法、法人税法など
などがあつまって「行政法」という法分野を作っている
*行政法理論
ドイツ法:「法律による行政の原理」
英米法:「法の支配rule of law」ないし「適正な法手続きdeu process of law」
日本は、明治維新以後、ドイツ法の強い影響を受け、第二次世界大戦後、アメリカ法の影響を受けた。
*行政とは
故田中二郎氏(藤田氏の恩師)の定義
「近代国家における行政とは、法のもとに、法の規制を受けながら現実具体的に国家目的の積極的実現をめざしておこなわれる、全体として統一性を持った継続的な形式的国家活動である。」
*「行政主体」と「私的法主体」「私人」
「行政主体」:ある者がそれをおこなえば「行政活動」とみなされるばあい、この者のこと
「私的法主体」「私人」:通常の会社(私企業)とか個人のように「行政主体」としての性質を認められない者
*行政法上の法関係
行政の外部関係:「行政主体」と「私人」との間の相互関係、これを規律する行政法 「行政作用法」
行政の内部関係:「行政主体」の内部の人々相互間の関係、これを規律する行政法 「行政組織法」
*「活動様式」=「行為形式」
行為が、「私人」の「権利」に対してどんなかたちでかかわりあっているか
=行為は、私たち市民の自由や財産に対してどんなかたちで影響をおよぼしているか
に注目して見る
第二講 行政法上の法関係
*行政主体と私人との相互関係における「公報」と「私法」
「(行政に関する)公法」:行政活動に固有な法
「(行政に関する)私法」:私人間でもまた適用される法」
なにが公法と私法の区別および判別基準 かつては、問題であった
*「行政機関」:法的地位のこと
*「独任性の行政機関」と「合議制の行政機関」
*「行政庁」と「補助機関」
「行政庁」:みずからの名で、しかし行政主体のために意思決定をし、対外的に(つまり私人に対して)これを表示する権限を、法令上与えられている行政機関
*上級機関の指揮監督権
報告の聴取、訓令・通達、同意(承認)など、さまざなな形で指揮監督をする
調整
*指揮監督権の限界
1)権限行使の独立性を保証された行政機関
2)代替執行は原則的に許されない
第三講 法律による行政の原理
*法律による行政の原理
行政の諸活動は、法律の定めるところにより、法律にしたがっておこなわれなければならない
*意義
1)「法による行政」の原理ではなく「法律による行政」の原理
国民の法的安全(法的安定)
国民からの民主的なコントロール
2)行政の担い手の恣意をコントロールすることにより、私たち国民(私人)の権利・自由を保護する
*法律の優位の原則
行政活動は、現に存在している法律の定めに違反しておこなわれてはならない
*法律の留保の原則
行政活動は、それがおこなわれるためには、必ず法律の根拠(すなわち法律の授権=法律の根拠)を必要とする
*法律の留保の適用範囲
「侵害留保理論」オットー・マイヤー(ドイツ近代行政法学の父)
法律の留保の原則が適用されるのは、行政の相手方である私人に対して不利益な効果を持つ行政活動、つまり私人の「自由と財産」を侵害するような行政活動だけ
「全部留保理論」
およそ行政機関がおこなうあらゆる行動には、明文の法律の根拠(授権)が必要である。
「権力留保説」
「本質性理論=重要事項留保説」
*法律の専権的法規制創造力の原則
新たに法規を創造するのは法律すなわち立法権の専権に属することであって、行政権は、法律による授権がないかぎり法規を創造することはできない
第四講 法律による行政の原理の例外と限界
*例外:自由裁量論
行政活動の法律適合性はどのようにして確保されるか
法律による行政の原理の例外 「侵害留保理論」
包括的なかたちで授権→自由裁量行為
便宜裁量=目的裁量
法規裁量=覊束(きそく)裁量
覊束(きそく)行為
*自由裁量の限界:裁量権の限界を超えた行為
裁量権の踰超(ゆえつ)
裁量権の濫用(らんよう)
*覊束(きそく)行為と自由裁量行為の判別の基準
美濃部三原則
*限界
1)行政が法律にしたがってさえいればすべて万々歳とはいかない
2)私人権利救済という見地からしても不十分なものが残る
以上



















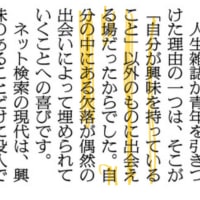








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます