婚姻の成立(夫婦の間)で生じる法的効果は、大きく分けて4つに整理できます。
人格的効果、財産上の効果、相続、その他。
まずは、そのうちの人格的効果の内容を見てみます。
1)同居義務
ただし、裁判に訴えることはできる(自然債務)が、強制執行を求められない義務です。
民法752条:夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
2)協力義務
協力し合うこと。
民法752条:夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
3)扶助義務
相手方に事故と同一程度の生活を保障する義務(生活保持義務)があります。 なお、一定の親族間に認められる扶養義務(生活扶助義務)よりも水準の高い義務です。
民法752条:夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 原則を規定しています。
なお、
760条:夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
という条文もあり、こちらは、「婚姻費用分担」義務を規定しています。
4)貞操義務
直接に定めた明文の規定はありませんが、不貞行為が離婚原因になると770条1項1条が間接的に定めています。
貞操義務違反は、離婚原因になるほか、不貞行為の相手に配偶者から慰謝料を請求できます。
- 第770条
- 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
- 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
以上、

















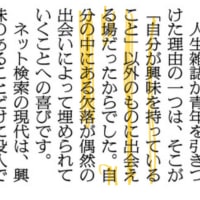









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます