弁護士の方が、扶養義務について、述べられていました。
ひとつの考え方の参考になると思います。
もちろん、法律論だけで片付けず、立法政策、倫理道徳的な面もあわせ、総合的に考えていく必要がありますが、まずは、法律でどのように規定されているかは、物事を考える上での基本となります。
関係法令は、民法の以下の規定。
*****民法******
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
*************
******引用*****
ystk@lawkus
ここ数日,「三親等内の親族については扶養義務がある」という趣旨の(あるいはそのことを前提とした)twが散見されるんだが,これ間違いですからね。配偶者並びに直系血族及び兄弟姉妹以外については扶養義務はないのが原則。三親等以内については,家裁の審判により義務が発生する場合があるだけ。
【再掲・1/8】何だかTL上で話題になっているようなので,民法上の扶養義務について,まともな法学部生なら知ってるであろうレベルの基礎知識をちょっと述べておきましょう。民法上,まず,夫婦並びに直系血族及び兄弟姉妹は,相互に扶養義務を負います。(民752条,民877条1項)(続く)
【再掲・2/8】逆に言うと,その他の親族については原則的に扶養義務はなく,家裁の審判があった場合に例外的に扶養義務が生じます(民877条2項)。つまり姻族(配偶者の血族。嫁姑等)や,兄弟姉妹以外の傍系血族(従兄弟,叔父叔母甥姪等)については,扶養義務はないのが原則です。(続く)
【再掲・3/8】このように,一般的に「親族には扶養義務がある」とは言えないことが,まず大前提ですね。更に,先に原則的に扶養義務が認められると述べた配偶者並びに直系血族及び兄弟姉妹についても,解釈論上,扶養義務の内容は,一律ではないものとされています。(続く)
【再掲・4/8】まず,配偶者及び未成熟子に対する扶養義務は,講学上「生活保持義務」と呼ばれる高度な義務とされています。自らと同程度の生活をさせる義務とか,最後の肉の一片まで分けて食うべき義務とか言われています。(続く)
【再掲・5/8】他方,その他の親族(成年した子,子以外の直系卑属(孫等),直系尊属(親等),兄弟姉妹)に対する扶養義務は,講学上「生活扶助義務」といって,簡単にいうと,自らの生活を犠牲にしない範囲で扶助すればよい義務ということです。(続く)
【再掲・6/8】つまり,話題の河本さんがお母様に対して負う扶養義務は,法的には「生活扶助義務」,換言すれば,孫とか兄弟姉妹とかに対して負う扶養義務と同等のものに過ぎないということですね。そこは押さえておく必要があるでしょう。法律論としては以上です。(続く)
【再掲・7/8】後は政策論の問題で,扶養義務を負う資力ある親族がいるというだけで親族優先を貫き現に困窮している人を見放すべきなのか,人的関係等から事実上扶養を期待し難い場合には親族扶養は諦めて公的な扶助を与えるべきなのか,という問題に帰着するでしょう。(続く)
【再掲・8/8】前記政策論のうち,私は後者が望ましいと思いますが,今回の件が示すのは,前者を支持する人が結構いるというだけのことですね。親を扶養しないとはけしからんという話を「法律だからドヤッ」と言い換えても,説得力は低いかと。曾孫でも兄弟姉妹でも常に扶養すべしというなら別...
ひとつの考え方の参考になると思います。
もちろん、法律論だけで片付けず、立法政策、倫理道徳的な面もあわせ、総合的に考えていく必要がありますが、まずは、法律でどのように規定されているかは、物事を考える上での基本となります。
関係法令は、民法の以下の規定。
*****民法******
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
*************
******引用*****
ystk@lawkus
ここ数日,「三親等内の親族については扶養義務がある」という趣旨の(あるいはそのことを前提とした)twが散見されるんだが,これ間違いですからね。配偶者並びに直系血族及び兄弟姉妹以外については扶養義務はないのが原則。三親等以内については,家裁の審判により義務が発生する場合があるだけ。
【再掲・1/8】何だかTL上で話題になっているようなので,民法上の扶養義務について,まともな法学部生なら知ってるであろうレベルの基礎知識をちょっと述べておきましょう。民法上,まず,夫婦並びに直系血族及び兄弟姉妹は,相互に扶養義務を負います。(民752条,民877条1項)(続く)
【再掲・2/8】逆に言うと,その他の親族については原則的に扶養義務はなく,家裁の審判があった場合に例外的に扶養義務が生じます(民877条2項)。つまり姻族(配偶者の血族。嫁姑等)や,兄弟姉妹以外の傍系血族(従兄弟,叔父叔母甥姪等)については,扶養義務はないのが原則です。(続く)
【再掲・3/8】このように,一般的に「親族には扶養義務がある」とは言えないことが,まず大前提ですね。更に,先に原則的に扶養義務が認められると述べた配偶者並びに直系血族及び兄弟姉妹についても,解釈論上,扶養義務の内容は,一律ではないものとされています。(続く)
【再掲・4/8】まず,配偶者及び未成熟子に対する扶養義務は,講学上「生活保持義務」と呼ばれる高度な義務とされています。自らと同程度の生活をさせる義務とか,最後の肉の一片まで分けて食うべき義務とか言われています。(続く)
【再掲・5/8】他方,その他の親族(成年した子,子以外の直系卑属(孫等),直系尊属(親等),兄弟姉妹)に対する扶養義務は,講学上「生活扶助義務」といって,簡単にいうと,自らの生活を犠牲にしない範囲で扶助すればよい義務ということです。(続く)
【再掲・6/8】つまり,話題の河本さんがお母様に対して負う扶養義務は,法的には「生活扶助義務」,換言すれば,孫とか兄弟姉妹とかに対して負う扶養義務と同等のものに過ぎないということですね。そこは押さえておく必要があるでしょう。法律論としては以上です。(続く)
【再掲・7/8】後は政策論の問題で,扶養義務を負う資力ある親族がいるというだけで親族優先を貫き現に困窮している人を見放すべきなのか,人的関係等から事実上扶養を期待し難い場合には親族扶養は諦めて公的な扶助を与えるべきなのか,という問題に帰着するでしょう。(続く)
【再掲・8/8】前記政策論のうち,私は後者が望ましいと思いますが,今回の件が示すのは,前者を支持する人が結構いるというだけのことですね。親を扶養しないとはけしからんという話を「法律だからドヤッ」と言い換えても,説得力は低いかと。曾孫でも兄弟姉妹でも常に扶養すべしというなら別...

















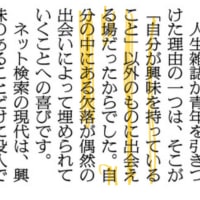









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます