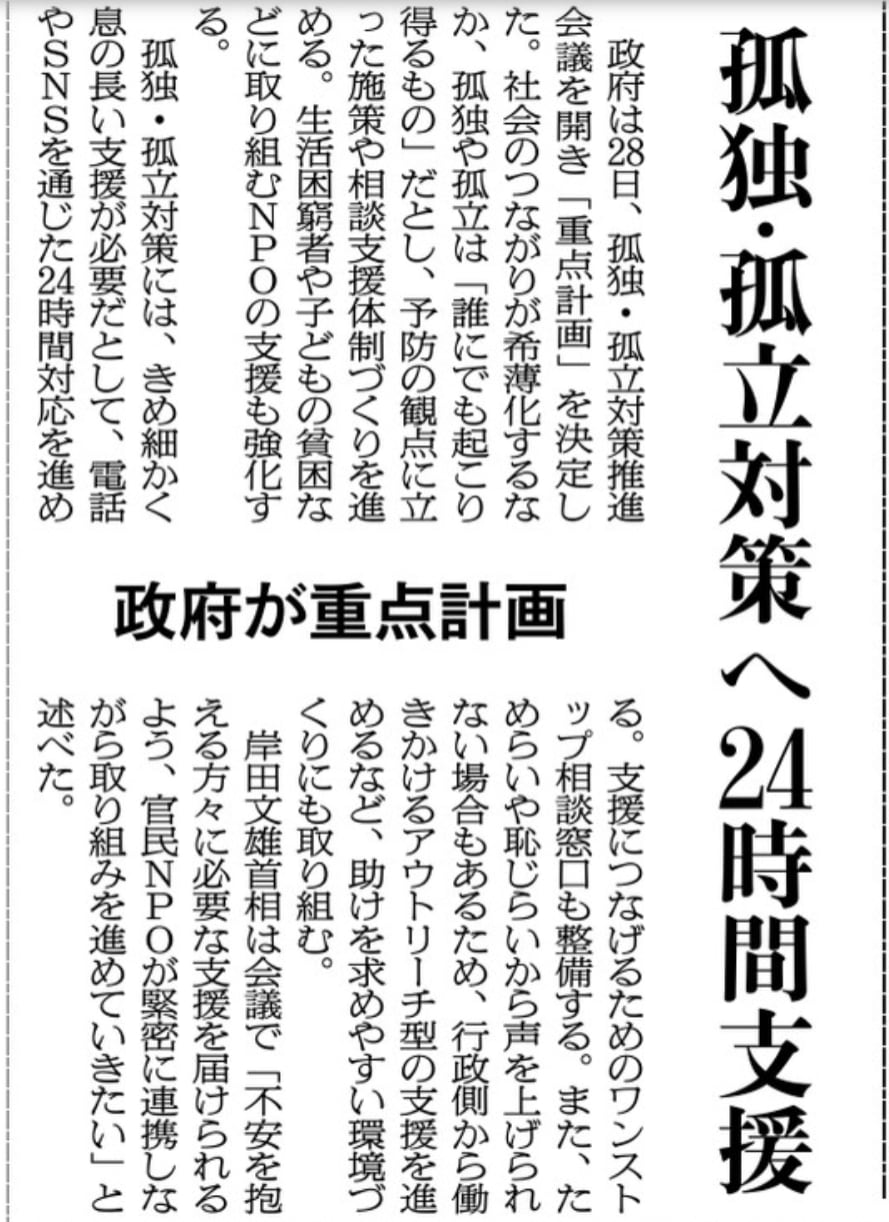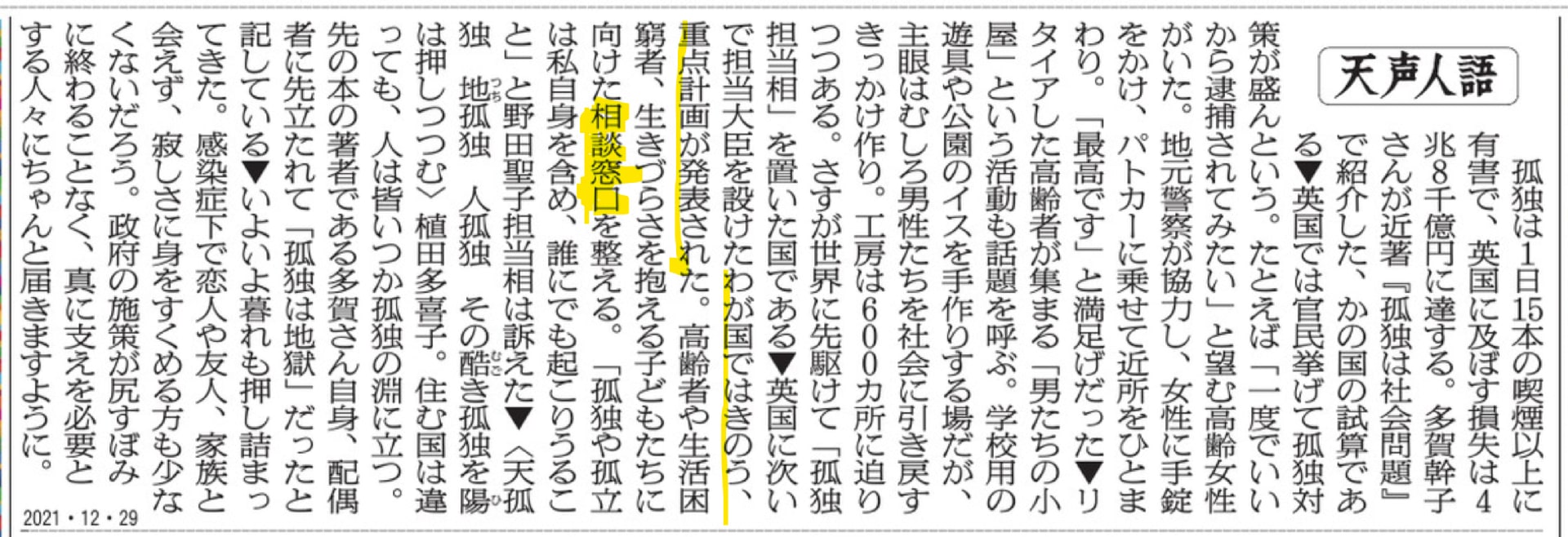「想いをつなぐノート」とは
「自分たちのなきあとも、障がいのある子が笑顔で暮らしていってほしい」
そのために保護者として、家族として、できることを今から考えてみませんか。
障がいのある人の家族にとって、「親なきあと」の暮らしをいかに支えていくか、家族支援のあるうちから将来的な支援の見通しについて検討を進めておくことは、とても大切です。
本市では、保護者等が「親なきあと」の支援を考え、準備を進める契機となるよう、「想いをつなぐノート」を作成しました。
作成にあたっては、自身も障がいのある子の保護者である、(一社)親なきあと相談室 関西ネットワーク代表理事の藤井奈緒氏による監修のもと、市が企画し、趣旨に賛同した八尾菊花ライオンズクラブ様が作成、本市に寄贈していただきました。
「想いをつなぐノート」の記入のしかた
- このノートは、障がいのある人が自分らしく暮らしていくことを願い、保護者や家族の想いを支援者につなぐためのノートです。
- 書けるところから、気軽に書き始めてみてください。気づいたこと、思いついたことなども書き加えてみましょう。
- いつでも書き直しができるよう、鉛筆か消せるボールペンで記入するようにしましょう。
- バインダーに綴じるようにすると、書き足りないページを後から追加したり、状況が変わったときにページの差し替えをするのも楽にできます。
- 必要な書類(かかりつけの病院の診察券や障がい福祉サービスの受給者証などのコピー)を一緒に綴っておくのもよいでしょう。
- 『私について』では、記入者自身の情報を記入する欄を設けました。“親なきあと”がくる前に必要な情報です。いざという時のために、自分自身のことも記入しておくようにしましょう。
- 書かれている内容がいつの情報なのかは、とても重要です。各ページ右上の『記入日』は必ず記すようにしましょう。また、書き直しをした際には、日付も更新しましょう。
ノートの活用のしかた
- 本人の様子をご家族と事業所で共有するツールとして活用してください。
- 例えば、新たに利用する事業所に、このノートで本人の状況を共有できると、スムーズに支援に入ることができると思います。
- 療育手帳や障がい福祉サービスの更新時に、本人の様子を伝えるツールとして活用してください。