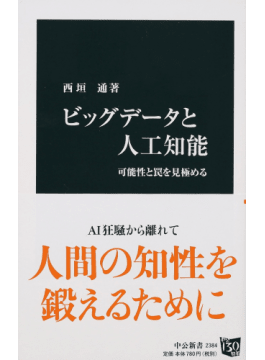
書名:ビッグデータと人工知能~可能性と罠を見極める~
著者:西垣 通
発行:中央公論新社(中公新書)
目次:第一章 ビッグデータとは何か
1・1 データが主役の時代
1・2 富とセキュリティ
1・3 超えるべき壁
第二章 機械学習のブレイクスルー
2・1 人工知能ブームの再来
2・2 深層学習の登場
第三章 人工知能が人間を超える!?
3・1 シンギュラリティ狂騒曲
3・2 生物と機械の違い
3・3 ロボットとのコミュニケーション
第四章 自由/責任/プライバシーはどうなるか
4・1 一神教の呪縛
4・2 社会メガマシン
第五章 集合知の新展開
5・1 ビッグデータと集合知
5・2 人間と機械の協働
2017年という年は、人工知能(AI)の歴史に残る年になるだろう。それは、2017年5月にAIソフトを搭載した碁と将棋のソフトがそれぞれの名人クラスを打ち破ったからだ。碁と将棋は、複雑なルールを持っているため、ここ当分はAIソフトが人間を打ち破ることは難しいと見られていた。そんな大方の見方を根底からひっくり返して、AIソフトが人間を破り去ってしまったのである。これは、最近急速に高まったコンピューティング処理能力に加え、機械学習の一つである深層学習機能を駆使することによって実現できたと言われている。そんな背景の中、クローズアップされてきたのが、米国の発明家であり実業家、さらには未来学者でもあるレイ・カーツワイルの予言「2045年には人工知能が人間の知能を上回る技術的特異点に到達する」、すなわち「2045年にはシンギュラリティが到来する」という予言が、ここにきて人々の口に上り始めてきた。果たして本当に「シンギュラリティが到来する」のであろうか?この説に真正面から反論するのがこの書「ビッグデータと人工知能~可能性と罠を見極める~」(西垣 通著/中央公論新社)である。この書の優れている点は、ただ感情的に「シンギュラリティ説」を否定するのではなく、人工知能の歴史を詳しく紹介し、人類がどのようなアプローチで人工知能を開発して来たかを順々と解き明かす。そして、生物と機械の違い、ロボットとのコミュニケーション、シャノンの情報理論への誤解、さらには欧米人の一神教の呪縛にまでに話が及ぶ。この書を最初から丁寧に読み進むと、最後には、「なるほどシンギュラリティはそう簡単に来るものではない」という筆者の結論に、多くの読者は同感するに違いない。それでは「シンギュラリティ到来派」とそれを否定する派を分けるポイントとは何か。
その答えの一つは、「弱いAI」と呼ばれる専用人工知能と、「強いAI」と呼ばれる汎用人工知能(AGI)やそれを上回る超人工知能(ASI)とを混同して考えることにあろう。将棋や囲碁のAIソフトは「弱いAI」であり、現在は完成域に到達したようだ。素人考えでも、碁や将棋のルールをコンピューターに覚え込ませれば何とかなりそうなのだ。だからといって、「弱いAI」の延長上に「強いAI」が来るかというと、そう単純なことではない。「弱いAI」と「強いAI」の間の壁は、限りなく高く、人類が乗り越えるのは容易なことではない。ここで問題となるのが、「フレーム(枠組み)問題」である。人工知能は、問題の論理的なフレームが明確にならないと、演繹推論ができない。フレームを臨機応変に設定し、刻々と変動する状況に応じて問題解決をするという、人間には何でもなくできることが、人工知能には困難なのである。言い換えると、この問題は「文脈(コンテキスト)を読むことが人工知能には困難だ」ということに行き着く。ところがである、米グーグルのAIソフト「アルファ碁」の生みの親である同社グループのAIベンチャー英ディープマインド社の最高経営責任者(CEO)であるデミス・ハサビス氏は「脳の働きは非常に複雑だが、コンピューターで再現できないものはない、というのが我々の現時点の見方だ」と語っているのだ。つまり彼は「弱いAI」の延長上に「強いAI」が来る」と主張する。
これに対し筆者は「シンギュラリティ仮説の信奉者は、徹底的な『人間機械論者』である。人間という生物は、頭のてっぺんからつま先まで、すべて機械と思い込んでいるのだ。1回性のある生命と再現性のある機械とを峻別する議論など、いくら聴いても馬の耳に念仏なのである」と反論する。そしてシンギュラリティ仮説の信奉者の多くがシャノンの情報理論を誤解していることを指摘する。今でもシャノンの情報理論こそが、“情報の基礎理論”と信じている人は、IT専門家の中に多いという。「シャノンの業績は通信工学的には確かに立派なものだし、今でも画像圧縮などに利用されている。だが、意味を扱えない情報概念を、いったい情報学の基礎に位置づけても良いものか?ここには、単なる誤解として片づけられない、巨大な問題が含まれている」と筆者は警鐘を鳴らす。現在、端的に言うと、たとえ意味を扱えなくても、記号の伝達だけで情報社会を築ける、という漠然とした思い込みが一般的風潮となり、だんだんそれが広がってしまったのが“シンギュラリティ仮説”の正体だと筆者は言う。「われわれはゾウリムシのような原始的生物さえ、製造することはできないだはないか。それなのに、いったいなぜ、複雑なホモサピエンスの脳を『コピーする』ことができるのか」というわけだ。要するにビッグデータ分析に人工知能が活用され、それがもしかしたら人間以上の知力を持つというのは、21世紀の巨大な文明論的テーマなのである。ITによるビジネス振興や経済効果といった次元の話ではないことを筆者は強調する。
人工知能が人間の知能を上回る特異点が来るとするシンギュラリティ仮説の危ういことは、国立情報学研究所が中心となり進めてきた、2021年度までに人工知能「東ロボくん」を東大入試に合格させるプロジェクトが頓挫したことからも窺える。東大合格には偏差値80前後が目安となるが、「東ロボくん」は偏差値57.1まで来たが、それ以上は現状では難しいという。その原因は「一文問題はほぼ完全に解けるが、複数文問題は難しい」からだ。一文問題とは、一つの文で完結する問題。一方、複数文問題とは、文と文のつながりの理解が必要となる。要するに、人工知能は、文脈の理解が苦手であり、読解力が著しく低いのである。このことは、この書が指摘する「人工知能は、問題の論理的なフレーム(枠組み)が明確にならないと演繹推論ができない」という指摘を裏書するものだ。最後に筆者は「シンギュラリティの愚劣さは、人間社会が生命的な価値によって支えられているにもかかわらず、ビッグデータや人工知能によって人間社会を機械的に統御できると勘違いしている点にある」と切って捨てる。また筆者は「人工知能すなわち『AI(Artificial Intelligence)』という名称には、どこか矛盾した響きがある。なぜなら『知能』とは本来、自然な生命活動と不可分であって、『人工物』にはなりえないからだ。ところが、人間の知能を大きく補強することは幾らでも可能である。だからAIのかわりに『IA(Intelligence Amplifier)』とよぶべきなのだ。これは、端的には、汎用目的でなく、特定目的に向けた現行のいわゆる『専用人工知能』である。そして人工知能によって『仕事の質』が変わるだけで、仕事を奪われるわけではない」と結論付ける。同書には人工知能の未来を考えるための材料がたくさん詰まっている。(勝 未来)
















