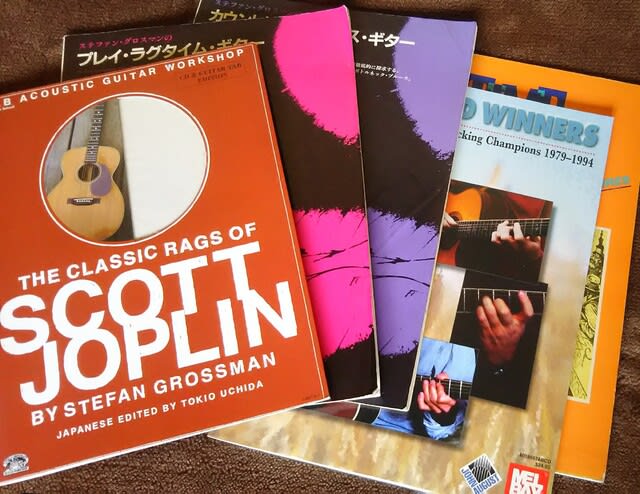弁天百暇堂 別館 no.1 六重奏憧憬 2020年8月2日(日) ティアラこうとう 小ホール
-ブラームス : 弦楽六重奏曲 第1番 変ロ長調 op.18
-ブラームス : 弦楽六重奏曲 第2番 ト長調 op.36
こいづは行ぐしかねぇ!って宵に紛れて疫病をかい潜り、参上して来た。何といっても主催者との付き合いが満20年になる今年に此のプログラムと来ては!である。定員140名のホールに散開した30名強の観客はそれぞれに「此処へ来た」理由を携えてるらしく、聴かねば死ねん!なのか、聞いたら笑顔でバイバイなのか、兎に角年配が多かったw
二人ずつのヴァイオリン、ヴィオラ、チェロからなるダブル・トリオ編成なので、二曲で各パートの1stと2ndをとっかえる事が可能になる。二曲通して各自、表パートと裏パートを両方楽しめると云う寸法。
さて六人の奏者だけど、上から下まで年齢はどういう配分なの?が、演奏始まって直ぐ抱いたギモンだった。何故と言って、若いと思しきプレーヤーの楽器の奏で方が、自分が弾いてた頃ともう全然違うのだ。今のアマチュアはきっと今のプロ、と云うか現代の奏法(音楽や楽器に対する認識も含めた)を下敷きにしてる訳で、さすが第一線のアマチュア達は凄いと素直に感心したのであるが、いっぽう主催者(ヴィオラ弾き)あたりは自分とひと回りちょい位の年の差に付き、およそ自分と地続きな範囲内なので、ステージを見てるとそんな新旧勢力が己の地点からそれぞれの感性を繰り出してアンサンブルしている様に、かなりエキサイトしてしまった。
ところで変ロ長調の1番を聞くといつも、オレ、この曲、知らねーなーという感じがして、事実、後半の楽章はぜんぜんいつ聴いてもよく判らない。ちょっと思ったのは、一楽章でフォルテがみっつ位くっついてるのではないか?と思う箇所で、そこをストレートな音量でやるのはちとどうか?と云うこと。あれは響きが欲しいってことじゃないのか?
翻って二番、このト長調くらい自分と切った張ったやった室内楽も珍しく、過去2回本番を踏んだが、まあ自分的な結果は推して知るべしである。という訳で曲についてはぜんぶ知り尽くしている自負を持って聞き始めたのであるが、一楽章の展開部に入ったあたりでそういうのがもう面倒くさくなり、止めてしまった。あとはもうただただ聴いていた。
ちらと頭を掠めたのは四楽章、6連の十六分音符がパート間を行き来する箇所だが、ありゃあ日本でいうならヒグラシのかそけき啼き声なんだな。あちらこちらと彷徨いながら聞こえて来る、そうか二番は夏の六重奏なのだと変に納得した次第。
ま、全体を評するなら、六人の奏者がしっかりと自分の楽器を鳴らし(ホントにひとりひとり、よく聞こえていた)、ホールを響かせていた其れだけで、この晩はじゅうぶんに成り立っていた様に思う。若い奏者を機会を捉えては育んでいこうと云う意思が主催者に感じられたのは、これまでもそうだったけど、その想いはいっそう強くなってるようだった。その辺がこの20年なのかな?
晩飯は地下鉄住吉駅前のレッドウッドピザで食した、これが滅法旨い、熱いオリーブオイルはブラームスとも相性がいい。