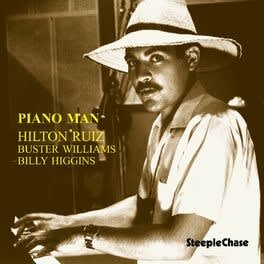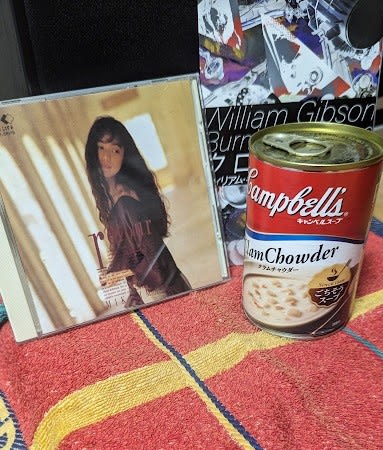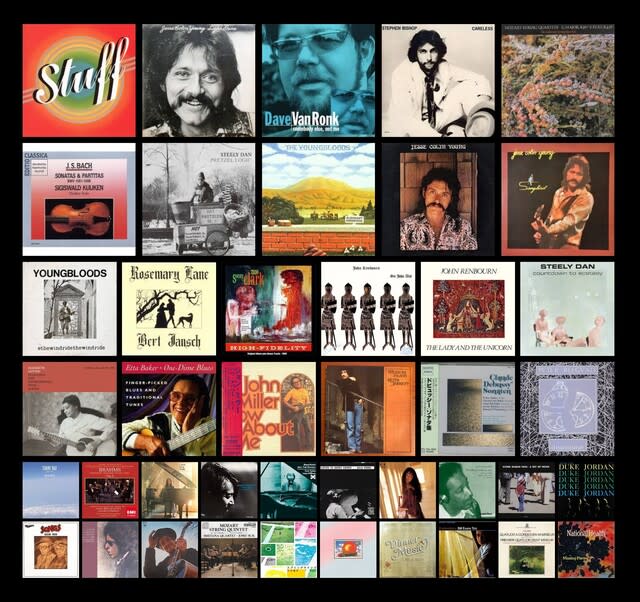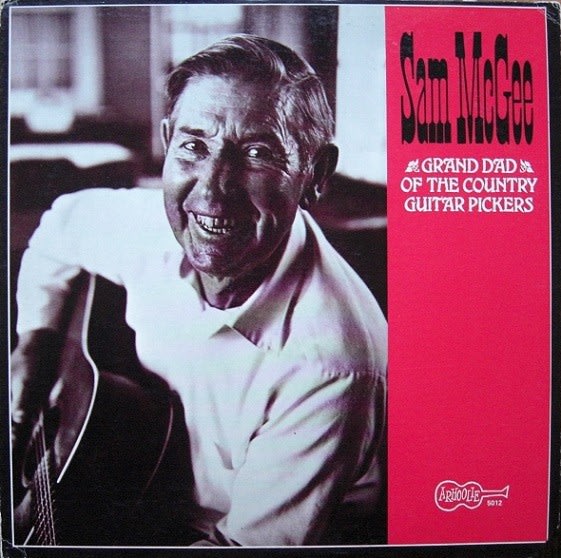1.
没後100年を迎えるフォーレの作品115でひーひー云ってるtweet(by相方)が流れて来て、115ってブラームスにもあったな、池袋で聞かせて呉れたの何時だっけ?と返したら、ちょうど20年前!ってリプがあり、それで思い出した、その年、つまり2004年は998と呼ばれる、相方がイロイロ充実してたと遠い目で仰るよな、そんな年だったのだ。
2.
バッハの無伴奏ヴァイオリン曲を弾こう、デュオなら何とか行けるのでわ?が当初のコンセプトだ。3曲あるフーガを材に取り、入り組んだ各声部を2パートに割り振ってみたが然したる成果は得られず、思い余ってプロの作曲家に相談するもやんわり断られ、プロジェクトは暗礁に乗り上げる。その時ふと耳をよぎったのが、他ならぬ998だった。
3.
998とはバッハが1940年頃に作ったリュート曲「プレリュード、フーガとアレグロ 変ホ長調」のこと。或る日、石丸電気(水戸に石丸があった時代があるのさ)で何気なく手にしたCDが決定打を放つ。テルデックからリリースされたバッハ全集のリュート編でharpsichordを弾いていたのはMichele Barchi、イタリアの新進と解説にはあった。

4.
実は家には既に同曲の盤があった、Gustav Leonhardtのハルモニア・ムンディ盤。フーガの技法とパルティータ ロ短調メインの2枚組の片隅にちんまりと収まっていた、然しこれにはいまひとつ興をそそられなかったのに対し、前述のバルキの緩急とダイナミクスに富んだ若さ溢れる演奏は
5.
そうと決まれば次は譜面の入手。ピアノ教師をしてる妹が、それなら図書館にあったぜと云うんで、貰ったらギター譜だった。それでアカデミアから取り寄せもした、こちらはドロップDチューニングのアレンジで、何より手書き譜のファクシミリ版がオマケ。余談だが原譜は国内の某大学が所有していた、飽くまで当時の話だけど。

6.
次は此れを二丁のヴィオラにアレンジする段。何故「二丁のヴィオラ」かと云えば、私と相方が二人ともヴィオラ弾きだったから。この頃muse scoreは未だ手許になく全部手書き、初稿は14段見開きの五線譜にボールペンテルで書いた。所謂スコアで、2パートにどう分けるか検討した結果なのだ。‘03.11.28脱稿の書付けがある。

7.
編曲のアイディアはシンプルだ、プレリュードはウォーキング・バスに乗って二声が対話を交わし、アレグロではバスとソプラノが明確に分かれる。だから前者はバスを交互に弾き乍らメロを弾き、後者はリピートで上下が入れ替わる協奏曲仕様となった。困ったのは真ん中のフーガ、これはちょっとずつ相手に手を差し伸べながら渡り行く形を取った。

8.
編曲に2003年をまるまる費やし、わたしたちは翌年これをステージに掛けることにした。そっちが先決事項だったんだっけ?もう覚えてない。隣県栃木市で16回目の開催となる栃木[蔵の街]音楽祭にエントリーした。後はもう練習しかなく、水戸で3回のリハが行われた。3階まで吹抜けと云うおよそオフィスとは云い難い社屋が、この時は役に立った。

9.
2004.9.18(Sat) 第16回 栃木[蔵の街]音楽祭メインステージ at 栃木市文化会館
・J.S.バッハ:パルティータBWV.1006よりルール
・J.S.バッハ:音楽の捧げものBWV.1080よりオクターヴのカノン
・J.S.バッハ:プレリュード、フーガとアレグロBWV.998
10.
Pitch=430は相方には辛かった様だが、ロシア音楽好きの同業(≒ヴィオラ奏者)編集者や10巻に及ぶコミックスをリリースし現在も週刊誌連載中の売れっ子漫画家のヴァイオリン弾きを巻き込みライヴは無事終了、そして2024年10月の今ここに私は居る。ま、いるだけだけど...