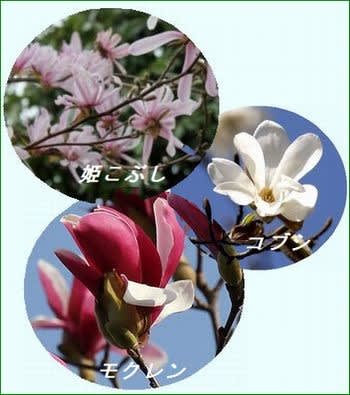月に一度の、四人組「若草物語」の会でした。
「若草物語」とはラインのためにつけたグループ名ですが、
学生時代からの50年以上の付き合いです。
何年かぶりに、ランチ会を我が家ですることになりました。
せっかく我が家でするのですから、目的はお茶を頂くこと。
というわけで、ささやかな茶会を計画しました。
まずはリビングで、お懐石代わりの食事会。
お弁当を予約して持参してくださいました。
食事中の話題は、5月に計画している旅行について。
最近、私の勧めもあって、みな「大人の休日」に入会して、
準備万端ととのっています。
残るはホテルを決めるだけになりました。
全員が足腰が丈夫なうちに、
春と秋の年に二度の旅をもくろんでいます。
二部は私の点前で、濃茶と薄茶を楽しんでいただきました。
お茶を本格的に習った方ばかりではないので、
和気あいあいと教え合いながらです。
濃茶は、茶入れは丹波の肩衝を使い、お茶碗は萩にしてみました。
黒楽が他の道具と並べると、皆真っ黒になってしまったので、
花見の気分に合わせて、桜色の萩にしました。
お菓子や茶碗に桜を咲かせて、やはりこの時期は春らしい席になりますね。
締めくくりはコーヒータイム。
話は尽きないので、次回の日程を決めたときには、
「あらあらこんな時間」でした。
すっかり日が伸びて、まだまだ明るいことに、
時が過ぎたことに気が付きませんでした。
お茶を知っている人知らない人、
そんな同士が、ああだこうだと楽しむ茶会も、とてもいいものですね。
人生これだけ生きていたら、
何事も自分流で楽しめばよいのだと思いますね。
夜になって感想のLINEが。
「今日はリラックスした雰囲気で、お茶の真髄を体験させてもらえました。
接待疲れしませんように。私たちは、楽しむばかりでしたが。」
ですって。
ちゃんとお茶事のお礼状の三要素を押さえていて、
お茶人顔負けのお礼の言葉ですね。