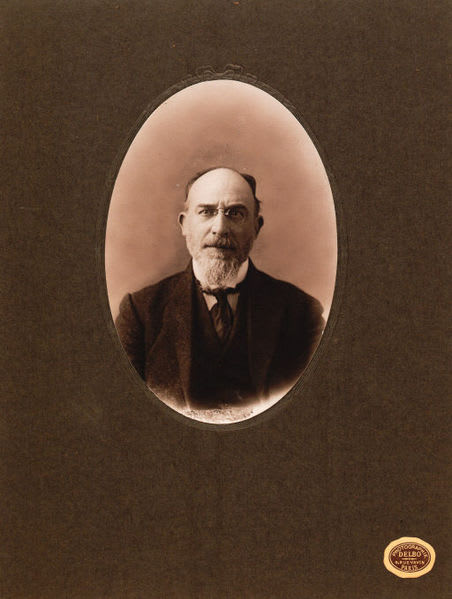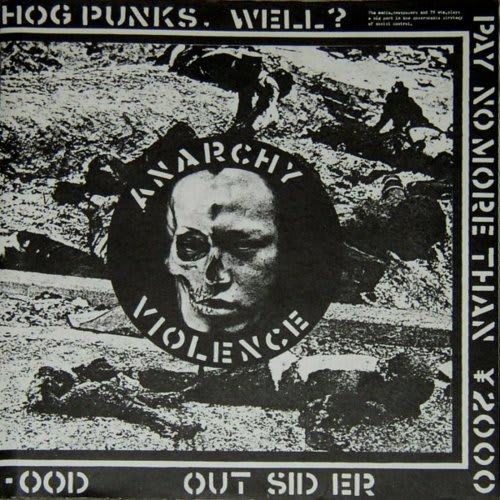
だんだんノッてきたぞ、この後ろ向き特集。第3弾は個人的に愛憎入り混じるハードコアを中心にパンク系のバンドを紹介しよう。
1979年高校2年の時にヨーロッパ旅行に行くことになった。どういう経緯か忘れたが親がユネスコ主催の中高生向け研修旅行に行かないかと言ってきたのである。外国、特にヨーロッパに憧れていた私は二つ返事で行く!と決意。ローマ~パリ~ロンドンというお決まりの3大都市を全国から参加した20名位の中高生の団体で巡る旅行だった。仲良くなった静岡の高校生がロック・ファンで、観光や研修(パリのユネスコ本部訪問など)以外の時間は一緒にレコード店巡りに費やした。ローマでカッコいいポスターの貼ってあった歌手のレコードを買ったのはいいが、パリへ行く列車の中に置き忘れて悔しい思いをしたが、ロンドンではパンク・ブームは終わりニューウェイヴの時代で街中にパンクスの姿は無かったが、日本では買えないシングル盤や出たばかりのニューウェイヴ系LPを買い込んだ。帰国してから伸ばしていた髪の毛を自分でハサミで散切りにし、石鹸の泡で逆立てた。作業着を安く買ってきて母にチャックをたくさん縫いつけてもらい、そこに"TERRORIST"とか"100% IS SHIT"などとペンキでプリントした。科学の実験用の白衣を破いて赤いペンキを塗りたくった。そんな格好でスポーツ自転車で通学してたのだから笑える。放課後友人と学校近くの駄菓子屋でアイスを食べながら転がっている木の破片やゴミ袋を意味なく蹴っ飛ばしいきがっていたのも可愛い。
その頃から吉祥寺マイナーや荻窪ロフトなどにミラーズ、フリクション、SYZE、BOYS BOYS、マリア023、東京2チャンネル(このバンドの情報求む!)など東京ロッカーズ系のライヴに通い始めた。愛読誌は「DOLL」の前進「ZOO」だった。編集長の森脇美貴夫氏の「カッコだけまねてもダメ。行動してこそ真のパンクスだ」という檄文に心酔し、SYZEのギターの川田良氏が自ら書いた文章にも影響を受けた。またナイロン100%の店長中村直也氏の連載でポップ・グループやスロッビング・グリッスル、キャバレー・ヴォルテールなどのオルタナティヴ・ミュージックを知った。
ZOOかどうか忘れたが雑誌に「フォーク歌手の遠藤みちろうが”自閉体”というバンドを作るので各パートのメンバー募集中」という広告が載っていたのを覚えている。その自閉体がザ・スターリンになったのかどうか確証はないが、1980年秋に吉祥寺のレコード舎でザ・スターリンのデビュー・ソノシート「電動こけし/肉」を買った。初めての自主制作ソノシートだった。"電動こけし"の意味すら知らないウブな高校生にも叩きつけるようなギター・サウンドと吐き捨てるヴォーカルは衝撃的だった。
[7/5追記:「自閉体」でググってみたらザ・スターリンの前進バンドとの記載がありました]
The STALIN スターリン " 電動こけし" 1st Flexi POLITICAL レコード
▼手持ちのZOOを探しても自閉体の広告は見つからなかったが、代わりにコレを見つけた。

下北沢に五番街というインディーズ専門のレコード店があり、そこでよく自主盤ソノシートやレコードを買った。特にパンクやハードコアが好きだったわけではないが、その手の自主制作盤はいろいろ買った。中でもチフスのソノシートには大きな影響を受け、音作りまで完コピして自作のパンク・ナンバーを宅録したりした。このバンドは後にザ・スターリンに参加するギタリストのタム氏が在籍したバンドで、90年代のインディーズ・ブームの時、貴重盤として万単位で売れた。
Typhus - flexi 7" EP
今年3月16日の記事で書いたが女性ハードコアのザ・カムズやナース、キャ→も愛聴盤だった。
80年代前半にジャパニーズ・パンク最大のヒットとなったのがラフィン・ノーズの「ゲット・ザ・グローリー」だった。渋谷の公園通りを歩いていると有線でこの曲が流れてきたものである。ヴォーカルのチャーミーは「宝島」の表紙を何度も飾り、その頃のインディー・ロック界のオピニオン・リーダー的存在だった。有頂天、ザ・ウィラードと並んで「インディーズ御三家」と呼ばれた彼らを渋谷公会堂へ高校時代のバンド仲間と観に行った。ザ・ウィラードも何処かの学祭で観た覚えがあるが、ヴォーカルのJUN氏のアダム・アントみたいな海賊ファッションが嘘っぽくてあまり好きになれなかった。
Laughing Nose - Get The Glory
The Willard
この件は以前ブログで書いたが、私にぎゃていのバイトを紹介してくれた榎本リュウイチという先輩が1982年5月22日学祭で「東大赤門オールナイトGIG」というハードコア・イベントを企画した。私はギター・アンプを貸しただけでライヴは観なかったのだが、翌日に会場の学生ホールの窓ガラスが全部割られ消火器がぶち撒かれて機材が泡だらけになっており絶句した。出演バンドの名前は記憶してないがたぶんこの辺のバンドが総出演したと思われる。アレルギーも出演したとHPに載っている。
G.I.S.M. - Fire
THE EXECUTE - The Voice
LSD - Kill You
Ghoul - Street Gangs
大学時代の音楽サークルの日高さんという先輩がベースをやっていたマネキン・ノイローゼはハードコアではなくオリジナル・パンクを継承したタイトなロックで好きだった。そのサークルにはG-シュミットのメンバーもいたし、才能のある人たちが集まっていた。昨年サークルの創設者であり詩人として著名な林浩平さんが「ロック天狗連:東京大学ブリティッシュロック研究会と七〇年代ロックの展開について知っている二、三の事柄」という本を出版し70年代のロックを巡る状況を明らかにしたが、80年代のサークルの躍進についても誰かが著してくれないかと思う。
Mannequin Neurose 外人墓地
80年代半ばになるとインディーズ御三家はこぞってメジャー・デビューし、他のハードコア・バンドもメジャー・レーベルでコンピLPが出たりしてシーン全体が変わっていき、唯一ガーゼ主催のイベント「消毒GIG」だけが現在まで続き、初期ハードコア精神を継承している。ドラムのHIKO氏は灰野さんとたびたび共演しており、パワフルなドラムは健在である。
gauze
ザ・カムズのメンバーを中心に1984年に結成されたハードコア・バンド、リップ・クリームのドラマーだったPILL氏が2002年に休業中だったフリクションのレック氏、灰野さんとロック・トリオHEAD RUSHを結成して数回ライヴを行っていたのはもう7年前になる。その後レック氏が中村達也氏と共にフリクションとして活動開始したのは周知の事実。
Lip Cream
ガーゼと並び80年代初期ハードコア時代から続くベテラン・バンド、あぶらだこは現在でも超個性的でアグレッシヴなサウンドを展開しているカルトな人気を誇る。ヴォーカルの長谷川裕倫氏の特異なパフォーマンスと捩じれた歌詞、変拍子を多用したサウンドはハードコアを超えた唯一無二の存在である。
あぶらだこ 1983 高画質版 ノーカット 屋根裏
ハードコア
錆びたアンプを
弁償しろよ!
灰野さんは当時からイギリスのハードコア・バンドCHAOS UKが好きで、最近も無名のハードコアのLPを大量に買い込んでいた。曰く「モヒカンや鋲付革ジャンなど過激なルックスをしたバンドよりも普通の格好の人がやるハードコアの方が本物だ」とのこと。