※ネタバレ注:ラストに触れています。
----これは、フォーンも一緒に観た映画。
えいが、とても観たがっていたし、
じゃあ、付き合ってみようかと…。
でも、ニャんだか複雑な顔してたね。
「うん。
これって、原作が川本三郎氏。
彼の実体験に基づいた話だよね。
観ていて、ああ、なるほど、
これはどうしても彼が書いておきたかった話だなと言うのは
よく分かったんだけど、
それをなぜ、映画化したのかがよく見えてこなかった。
でも、やはり監督がいま注目の山下敦弘だけあって、
さすがに巧い。
決して飽きさせることがない」
----じゃあ、その巧いと思ったところを突き詰めてみたら?
それって、監督が力を入れているという証拠でしょ。
「おっ。
いいこと言うね。
この映画が他のこの時代を扱った映画と決定的に違うのは、
東大安田講堂落城の“画”を入れていないところ。
タイトルバック前からその<音>だけを流す。
まるでハリウッドの大作みたいに…。
それで、分かるのは、
この映画の主軸が“学生運動”ではないということ。
冒頭で語られるのは、
『週刊東都』記者・沢田(妻夫木聡)の潜入取材の様子。
そこにいるタモツやキリストといったヒッピーたちは、
学生運動や政治活動からは遠く離れている。
日々を食っていくことで精いっぱい。
そんな彼らを騙して一緒にいる自分に、
この沢田は罪悪感にも似たものを感じている」
----その取材を終えてしばらくしてから
革命を目指す梅山(松山ケンイチ)なる男が近づいてくるんだよね。?
「うん。
時代に深くかかわった取材をしたがっていた沢田にとっては、
願ってもないはずなんだけど、
でも、この梅山が実に胡散臭い。
映画では、彼は“運動”に遅れてきた男で、
それでも自分がヒーローになろうとしているという描き方をされている。
話は飛ぶけど、『祭りの準備』 でも
“左翼運動”のリーダーが
それにかこつけてヒロインをモノにする様子が描かれたけど、
これも似たようなものがある。
実際に起こす事件は“自衛隊員殺人”という非道なものだけど、
あまりにも彼ら赤邦隊なる組織が子どもじみている。
一方の沢田の方は、
社会のダイナミックな動きに関わりたくとも自分は社会人。
しかも、そちらの方面を中心に扱う『東都ジャーナル』には属していない。
だからこそ、あせりもあってか、
いともたやすく、ニセモノに騙されてしまう。
つまり、ふたりともその時代の中にいながら、
核となる部分ではなく、
“周縁”のところで出逢っている。
それぞれの思惑を秘めながら…」
---でも、
原作者の川本三郎氏は、梅山の実際の姿を知らないわけだよね。
ということは、この部分は映画ならではの創作ってことなのかニャ。
「かもしれないね。
ともあれ、この描き方だと
忽那汐里演じるヒロイン・倉田眞子の。
『嫌な感じがする』というセリフが出てくるのもうなずける。
ぼくもそう思ったもの。
思惑が独り歩きしていて
どうにも、すっきりしない。
ただ、先ほどフォーンが言った
“映画の巧さ”からいくと、
この倉田の立ち位置は大きい。
映画『ファイブ・イージー・ピーセス』 を沢田と一緒に観た後、
『真夜中のカーボーイ』をも引き合いに出し、
彼に言う言葉『私はきちんと泣ける男が好き』。
これがラストのある人物との再会のシーンで生きてくる。
この構成が、ほんとうに巧い」
---フォーンは、あのシーンは胸にぐっときたニャあ。
最初の方から、彼は自分の取材に後ろめたさを感じていたわけで、
で、あのセリフ“生きていればそれでいい”でしょ。
「ここの受け止めかたは人それぞれだろうね。
ぼくは沢田が梅田を思想犯と見て、
殺人というか“命”の重さに思いいたらないのが
どうにも納得がいかなかったためか、
あそこは、フォーンとは違う見方をしたんだよね」
---その“命”の重さに気づいての涙と言うのは違うと思うよ。
あれは、日々を一生懸命、
営んでいる人の嘘いつわりのないセリフが
彼の心をほどいたんだよ。
それまで重い荷物をひとりで抱えて
ずっと心を閉ざしていたわけでしょ。
ほら、その前のシーンでも、
飲み会に誘われて断っていたじゃニャい。
「確かに。
ただ、あそこはもっと複雑。
潜入取材のときに自分が言った嘘を
そのまま相手は信じていて、
それを目の前であのように喋られると…。
心を慰撫されたのじゃなく、
逆にもっとつらくなったのかもしれないよ」
(byえいwithフォーン)
フォーンの一言「いろんな観方ができるのが、いい映画の条件のひとつなのニャ」
※『初恋・地獄篇』のポスター、ぼくも部屋に貼っていた度


 こちらのお花屋さんもよろしく。
こちらのお花屋さんもよろしく。
こちらは噂のtwitter。

「ラムの大通り」のツイッター

 人気blogランキングもよろしく
人気blogランキングもよろしく
☆「CINEMA INDEX」☆「ラムの大通り」タイトル索引
(他のタイトルはこちらをクリック→)

----これは、フォーンも一緒に観た映画。
えいが、とても観たがっていたし、
じゃあ、付き合ってみようかと…。
でも、ニャんだか複雑な顔してたね。
「うん。
これって、原作が川本三郎氏。
彼の実体験に基づいた話だよね。
観ていて、ああ、なるほど、
これはどうしても彼が書いておきたかった話だなと言うのは
よく分かったんだけど、
それをなぜ、映画化したのかがよく見えてこなかった。
でも、やはり監督がいま注目の山下敦弘だけあって、
さすがに巧い。
決して飽きさせることがない」
----じゃあ、その巧いと思ったところを突き詰めてみたら?
それって、監督が力を入れているという証拠でしょ。
「おっ。
いいこと言うね。
この映画が他のこの時代を扱った映画と決定的に違うのは、
東大安田講堂落城の“画”を入れていないところ。
タイトルバック前からその<音>だけを流す。
まるでハリウッドの大作みたいに…。
それで、分かるのは、
この映画の主軸が“学生運動”ではないということ。
冒頭で語られるのは、
『週刊東都』記者・沢田(妻夫木聡)の潜入取材の様子。
そこにいるタモツやキリストといったヒッピーたちは、
学生運動や政治活動からは遠く離れている。
日々を食っていくことで精いっぱい。
そんな彼らを騙して一緒にいる自分に、
この沢田は罪悪感にも似たものを感じている」
----その取材を終えてしばらくしてから
革命を目指す梅山(松山ケンイチ)なる男が近づいてくるんだよね。?
「うん。
時代に深くかかわった取材をしたがっていた沢田にとっては、
願ってもないはずなんだけど、
でも、この梅山が実に胡散臭い。
映画では、彼は“運動”に遅れてきた男で、
それでも自分がヒーローになろうとしているという描き方をされている。
話は飛ぶけど、『祭りの準備』 でも
“左翼運動”のリーダーが
それにかこつけてヒロインをモノにする様子が描かれたけど、
これも似たようなものがある。
実際に起こす事件は“自衛隊員殺人”という非道なものだけど、
あまりにも彼ら赤邦隊なる組織が子どもじみている。
一方の沢田の方は、
社会のダイナミックな動きに関わりたくとも自分は社会人。
しかも、そちらの方面を中心に扱う『東都ジャーナル』には属していない。
だからこそ、あせりもあってか、
いともたやすく、ニセモノに騙されてしまう。
つまり、ふたりともその時代の中にいながら、
核となる部分ではなく、
“周縁”のところで出逢っている。
それぞれの思惑を秘めながら…」
---でも、
原作者の川本三郎氏は、梅山の実際の姿を知らないわけだよね。
ということは、この部分は映画ならではの創作ってことなのかニャ。
「かもしれないね。
ともあれ、この描き方だと
忽那汐里演じるヒロイン・倉田眞子の。
『嫌な感じがする』というセリフが出てくるのもうなずける。
ぼくもそう思ったもの。
思惑が独り歩きしていて
どうにも、すっきりしない。
ただ、先ほどフォーンが言った
“映画の巧さ”からいくと、
この倉田の立ち位置は大きい。
映画『ファイブ・イージー・ピーセス』 を沢田と一緒に観た後、
『真夜中のカーボーイ』をも引き合いに出し、
彼に言う言葉『私はきちんと泣ける男が好き』。
これがラストのある人物との再会のシーンで生きてくる。
この構成が、ほんとうに巧い」
---フォーンは、あのシーンは胸にぐっときたニャあ。
最初の方から、彼は自分の取材に後ろめたさを感じていたわけで、
で、あのセリフ“生きていればそれでいい”でしょ。
「ここの受け止めかたは人それぞれだろうね。
ぼくは沢田が梅田を思想犯と見て、
殺人というか“命”の重さに思いいたらないのが
どうにも納得がいかなかったためか、
あそこは、フォーンとは違う見方をしたんだよね」
---その“命”の重さに気づいての涙と言うのは違うと思うよ。
あれは、日々を一生懸命、
営んでいる人の嘘いつわりのないセリフが
彼の心をほどいたんだよ。
それまで重い荷物をひとりで抱えて
ずっと心を閉ざしていたわけでしょ。
ほら、その前のシーンでも、
飲み会に誘われて断っていたじゃニャい。
「確かに。
ただ、あそこはもっと複雑。
潜入取材のときに自分が言った嘘を
そのまま相手は信じていて、
それを目の前であのように喋られると…。
心を慰撫されたのじゃなく、
逆にもっとつらくなったのかもしれないよ」
(byえいwithフォーン)
フォーンの一言「いろんな観方ができるのが、いい映画の条件のひとつなのニャ」

※『初恋・地獄篇』のポスター、ぼくも部屋に貼っていた度



 こちらのお花屋さんもよろしく。
こちらのお花屋さんもよろしく。こちらは噂のtwitter。
「ラムの大通り」のツイッター

☆「CINEMA INDEX」☆「ラムの大通り」タイトル索引
(他のタイトルはこちらをクリック→)










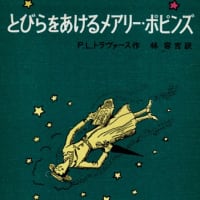

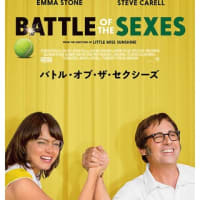



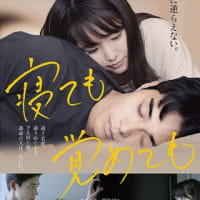



あの時代を知らなくても、あの時代を生きた人の気持ちを知るいい手段だったのかも。
シナリオにもかなり時間をかけたのでしょうか、隅々まで練られていますね。
仰る様にラストの解釈がカギだと思います。
おそらくこれは観客の人生観や生きてきた時代などによっても大きく異なると思います。
えいさんと私も解釈が少し違うようですし。
76年生まれの監督は、なるほどこう時代を捉えたかと思いました。
アメリカン・ニュー・シネマは、
映画としてのあの時代を象徴していました。
その中の主人公と、
この映画の沢田を重ね合わせたのも
巧いなあと思いました。
ぼくも、それを書こうとしていました。
これは
「生きていた時代、生き方に対する姿勢」によって、
あの涙の意味が変わってくると…。
観たときは、この映画がつくられた意味が
あまり分からなかったのですが、
ノラネコさんのレビューを読んだり、
他の方のサイトを拝見しているうちに、
この映画への
自分の理解度がかなり変わってきた気がします。
私は、フォーンの見方に近いです。
沢田を泣かせたあの台詞ですが、
命の重さより思想が先に立ってた自分を
後で少しづつ後悔できるようになったからこそ、
感情が先に立つ行動、「泣く」という行為が出来たのかなあ、と思いました。
また、彼が沢田を本当に自分の仲間であるか否かすら疑っていなかった、
つまり彼が本物であるか偽者であるかを、判断基準に置かなかった、
そこに感動を感じたこともあったのかもしれない、と思います。
あのセリフは、それだけでぼくも泣けました。
ということは、そのとき、
ぼくも沢田と同じ気持ちになっていたのかなと…。
でも、あの後、いろんな方が
いろんな回答を導き出されていて、
その解釈の多様性が
この映画の魅力でもあると…。
理想を貫くことが正しいとは限らないと知る青春の終焉、
自分が現実に営まれている人々の幸福からは遠いところにいる…。
う~ん。まだまだ出てきそうです。