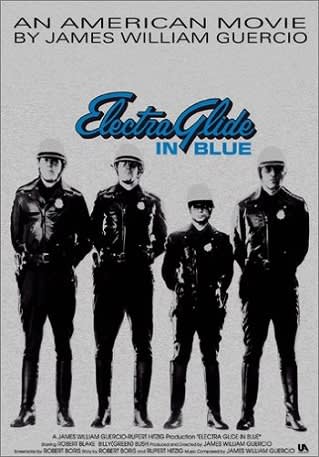■Keep On Moving / The Butterfield Blues Band (Elektra)

ブルースロックと言えば、本日ご紹介のアルバムも、サイケおやじが衝撃を受けた1枚です。
結論から言えば、今となってはバジー・フェイトン(g) とデイヴィッド・サンボーン(as) という、後のフュージョンスタアが駆け出し時代の音源という興味が優先される証拠物件ではありますが、しかし中味の真価は制作発売された1969年当時最先端のファンキーロック!
全くその発祥と発展が見事に記録され、もちろん聴けば歓喜悶絶の名盤だと思います。
A-1 Love March
A-2 No Amount Of Loving
A-3 Morning Sunries
A-4 Losing Hand
A-5 Walking By Myself
A-6 Except You
B-1 Love Disease
B-2 Where Did My Baby Go
B-3 All In A Day
B-4 So Far So Good
B-5 Buddy's Advice
B-6 Keep On Moving
ところで、バターフィールド・ブルース・バンドと言えば、やはりマイク・ブルームフィールドやエルビン・ビショップという、偉大なギタリストが在籍していた時代が最高!
と、相場は決まっていますし、実際、サイケおやじも、それについては異存などありはしません。
しかしバターフィールド・ブルース・バンドはリーダーのポール・バターフィールドが率いてこその存在意義が確かにあって、それは「黒人音楽のブルース」と「白人音楽のロック」を結びつけただけではなく、そこから生まれた新しい音楽様式の「ブルースロック」をさらに発展させようと奮戦した、その現場がバターフィールド・ブルース・バンドだったように思うわけです。
それは前述の二大ギタリストを擁して作り上げたブルースロック極みの名盤「イースト・ウェスト」から、相次いで彼等人気者が去って行く過程においての諸作でホーンセクションを導入し、ジャズ風味を強めながら、これはひとつのブラスロックの方向性をも見据えた展開でありました。
で、この「キープ・オン・ムーヴィン」はバンドとしては通算5作目のアルバムにして、今や歴史的イベントになってしまった「ウッドストック」の映画サントラ盤扱いだった3枚組アルバムにライプ音源として収められていた「Love March」のオリジナルスタジオバージョンが聴ける事でも気を惹かれるわけですが、これがなんとも、サイケおやじにとっては面白くありません。
それは、やはり先入観念としてのバターフィールド・ブルース・バンドにしては完全に肩すかしというか、前述した3枚組LP「ウッドストック」で聴けた、そのマーチングバンドみたいな演奏とソウルっぽい歌のミスマッチには、ど~しても馴染めないのです。
なんでギンギンのブル~スギターが出ないんだぁ~~~~~!?
ほとんど憤りに近いものさえ覚えていたのが、当時のサイケおやじの本音でありました。
ところが、このアルバムでの「Love March」は既にして立ち位置が異なるようで、全体に重くて歯切れの良いピートが蠢くエレキベースを核として最後まで貫かれますから、ホーン隊がキメまくるリフもビシッとファンキー♪♪~♪
まあ、今となってはドC調の歌詞とボーカル&コーラスの兼ね合いが失笑を誘いかねませんが、リアルタイムではマジだった事が時の流れを痛感させますねぇ。
ちなみに既に述べたとおり、このアルバム制作時のバンドメンバーはポール・バターフィールド(vo,hmc,etc)以下、バジー・フェイトン(vo,g,key,etc)、ロッド・ヒックス(b)、フィリップ・ウィルソン(ds,vo)、スティーヴ・マダイオ(tp)、キース・ジョンソン(tp)、デイヴィッド・サンボーン(as)、トレバー・ローレンス(ts)、ジーン・ディンウィディ(ts,fl,vo)、フレッド・ベックマイヤー(b)、テッド・ハリス(p) 等々のクレジットを確認出来ますが、無記名の助っ人が参加している可能性も、聴けば納得されると思います。
で、全体の音作りはブルースロックから一歩進んだファンキー感覚のブルーアイドソウルを狙ったのでしょう。リズム隊が挑むノーザンビートやラテンリズムを含む、まさにポリリズムなロックビートが結果的にフィリーソウルやニューソウルのような、これがアブナイほどにイカスんですよ♪♪~♪
もろちんそれは白人っぽい、ちょいダサ感覚である事は言うまでもないんですが、レコードを聴き進んでいくうちに中毒させられるような「何か」があるんじゃ~ないかっ!?
錯覚であったとしても、このアルバムの魅力は、まさにそれだっ! と、サイケおやじは思っています。
例えばファンキー&ブラスロックの「No Amount Of Loving」ではギターのリズムカッティングがサザンソウルしていながら、アドリブソロはニューロック! また、アップテンポでリズムアレンジやベースがカッコE~「So Far So Good」は、ホーンセクションの使い方を含めて、明らかにジェームス・ブラウンに敬意を表したファンク路線!
う~ん、死ぬほどギターが、カッコE~~~~~♪
さらにゴスペル味濃厚な「Where Did My Baby Go」はバジー・フェイトンのギターも狂おしく、ポール・バターフィールドが本領発揮の粘っこいボーカルがたまらない「Morning Sunries」は、これまたファンキーなブラスロックという趣向ですから、聴いているうちに、思わずグッと力が漲ってきますよ。
一方、従来路線の正統派ブルースロックとしては、「Walking By Myself」におけるハーモニカとギターのアドリブのしなやかさ♪♪~♪
実は告白すると、サイケおやじがこのアルバムを初めて聴いたのは1973年晩秋でしたから、ここまで書いてきた当時のバターフィールド・ブルース・バンドの音楽性と共通点が聴かれるニューロックやブラスロックの名作やヒット曲にはそれなりに馴染んでいた所為で、例えばリアルタイムのシカゴがやっていたファンキーロック&ソウルフルなスタイルの根源を発見した事は、実に衝撃でした。
なにしろ、これが世に出ていたのは、1969年!
つまりシカゴやBS&T等々に代表されるブラスロックがブレイクしていた時期と一緒であり、しかもファンキー&ソウルな味わいは、こっちが格段に上なんですから、たまりません♪♪~♪
しかもバジー・フェイトンという、初めて意識したギタリストのスタイルはロックでもあり、ジャズでもあり、ど真ん中のソウルフィーリングさえ弾いてしまう汎用性が、全く当時は意味不明の凄さと感じられましたですねぇ~~♪
おまけにそれが果たして本人の意図するところか、否か?
後で知り得たところによれば、このセッション当時のバジー・フェイトンは弱冠二十歳前後だったそうですから、狙っていたのなら、完全に天才だと思いますが、本人の語るところによれば、何かバンド全体の雰囲気に引っ張られたという部分は否めないとの事で、それをちょいと安心と書けば不遜でしょう。
ただ、その真相云々は別にして、とにかくこのアルバムの魅力の大部分はバジー・フェイトンの当時としては新鮮なギターワークであり、またリズム隊の自由奔放にして緻密なグルーヴである事はまちがいありません。
そしてもうひとつ、随所にモロ出しとなるジャズっほさも侮れません!
中でもスロ~ブル~スにしてゴスペルロックな「Losing Hand」におけるテナーサックスのアドリブやホーンリフの使い方は、ポール・バターフィールド十八番のハーモニカやバジー・フェイトンのギターワークさえも、ジャズへと導いていきますし、これまたじっくりとジャズ歌謡調の「Except You」が、一転して中間部で力強い盛り上がりを聞かせるあたりの仕掛の妙、さらには死ぬほどカッコ良すぎるファンキーブラスロック「Love Disease」が中盤で4ビートに突入してしまう構成の熱さ!!
もう、このあたりの展開は、全くサイケおやじの好むところがテンコ盛りなんですねぇ~~♪
そこで気になるデイヴィッド・サンボーンの活躍は、ほとんどがホーンセクションの構成員という存在ではありますが、それでもアップテンポのゴスペルロック「Buddy's Advice」では既に後年お馴染みとなる、例の「泣きのアルト」の片鱗を聞かせるアドリブソロの熱演が嬉しいところ♪♪~♪
ちなみに曲調はサム&デイヴやデラニー&ポニー風という、これがバジー・フェイトンの自作自演でリードボーカルもやらかしてしまった憎らしいトラックでありながら、個人的には大好きですし、もうひとつ、バジー・フェイトンが書いて歌った「All In A Day」がファンキーロックになっているのも興味深いと思います。
もちろん本人のリズムギターや蠢くベースにビシバシのドラムス、些か暑苦しいコーラスがゴスペル狙いなのは言わずもがな、このあたりが当時のバジー・フェイトンの趣味(?)であったとしたら、それはそれで興味深いところでしょう。
ということで、これは冒頭で「名盤」と書いてしまいましたが、その扱いも実質的には局地的なものでしょう。もちろんやっている歌と演奏も、従来型「ブルースロック」ではありませんから、そこに期待しては納得出来ないのも確かです。
しかし基礎的因子としての黒人音楽、あるいは黒人音楽から誕生したロックという白人音楽が好きであれば、何時かは必ずファンクやファンキーロック、ソウルジャズやブラコンなぁ~んていうシンコペイトしたリズムとピートの魔法に夢中になれるはずで、何か断定的な言い方かもしれませんが、その時にこそ、このアルバムがさらに愛おしくなるんじゃ~ないでしょうか?
アヴェレイジ・ホワイト・バンドあたりがお好きな皆様にも、オススメですよ。
それとやっぱりバジー・フェイトン!
ご存じのとおり、この才人ギタリストが本格的に注目されたのはステーヴィー・ワンダーの傑作アルバム「心の詩」や「トーキング・ブック」のレコーディングセッションに参加し、引き続いて巡業用バンドのメンバーに抜擢された1970年代初頭だと言われていますが、告白すればサイケおやじは、そうと知っての後追いでの感動が強く、殊更意識することはありませんでした。
それが既に述べたとおり、結局は1973年晩秋、このアルバムに出会って以降は、バジー・フェイトン熱に浮かされていた時期が確かにありましたですねぇ~♪
そしてキャリアを辿ってみると、そこにはサイケおやじの大好きなラスカルズとの関わり、さらにはグレッグ・オールマンのソロ名義アルバムへの参加から、盟友とも言えるニール・ラーセンとのコラポレーション、また途中には因縁深い様々なメンバーとのバンド活動等々が連綿と続いている事実には驚かされるばかりです。
ただし本人は1970年代中頃から悪いクスリ(?)でリタイアしていた時期もあった事から、決して意欲的に前へ出るタイプじゃ~ないようですし、今日まで残されているレコード諸作はマニアックな領域にある事も確かでしょう。
そこでぜひとも、キャリアの出発点とも言える、このアルバムから聴いていただきたいのです。
本気で好きになったら、ずぅ~~~っと飽きないで聴ける1枚だと思います。
最後になりましたが、ここまでやってしまったリーダーのポール・バターフィールドは直後、何故か自らのグループを活動休止状態にし、伝統的な黒人ブルースへの回帰やメンバーを入れ替えた新バンドの結成と解散を繰り返し、ついには……。
その意味でも、このアルバムは大切に聴かれるべきと思うのでした。