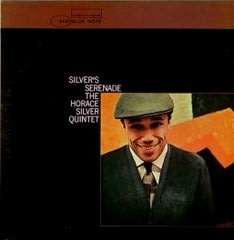職場で急に体調を崩した者が出て、救急車騒ぎになりました。なんと心臓が悪くなっていて緊急入院! 一応、命に別状がなくてホッとしたんですが、手術が必要だそうです。う~ん、まだ40歳になっていないからなぁ……。
全く健康そうに見えても、病は突如、襲ってきますね。健康は本当にありがたいことです。
ということで、本日は――
■Minor Move / Tina Brooks (Blue Note)
これはジャズに限った話では無いんですが、何時でも買えると思っていたレコードが、あっという間に廃盤になり、その後は中古も出てこないという惨劇が、確かにあります。
私にとっては、このアルバムもそのひとつでした。
内容はブルーノートならではのハードバップ作品でありながら、何故か長年オクラ入りしていたという因縁があり、1980年頃に我国優先で発売された未発表シリーズの中では、特に気になる1枚でした。
なにしろリーダーのティナ・ブルックスは、如何にも黒人というアーシーな感覚を持ったテナーサックス奏者ですし、これまで公式発表されていたブルーノートでの録音は少ないながらも、その全てがハードバップ愛好者の琴線に触れる演奏ばかりです。
加えてこのアルバムは、後述しますが、共演者が魅力的なんですねぇ~♪ 発売された当時はジャズ喫茶でも頻繁に鳴っていたと記憶しています。
ところが私は、何故かすぐに買わなかったんですねぇ……。
で、ハッと気がついた時には廃盤状態でした。もちろん、そうなってみるとジャズ者の哀しいサガとでも申しましょうか、急激に入手意欲が刺激されてしまいます。そこで中古盤屋巡りでは、まず最初に発見すべく、必死になっていた時期がありました。
そして数年後、ようやく見つけたブツは、なんとジャケットの一部分に青インクの染みがあり、おまけに印刷までもが薄れたような……。どうやら店員が仕入れた時に、ジャケットに付着していたベタベタの汚れを拭き取ろうとしてアルコールを使ったのが致命的だったようです。う~ん……。
しかし値段が900円でしたし、盤質には問題が無かったんでゲットしたという、愛着の1枚になりました。
さて、お待たせしました。録音は1958年3月16日、メンバーはティナ・ブルックス(ts)、リー・モーガン(tp)、ソニー・クラーク(p)、ダグ・ワトキンス(b)、アート・ブレイキー(ds) という、震えがくるほどハードバップな面々です――
A-1 Nutville
ティナ・ブルックスが書いた正統派ハードバップのブルースで、初っ端からのグルーヴィな雰囲気がたまりません♪ しかもアドリブ先発のソニー・クラークが、もうファンキーそのものの快調さ! この人のスタイルはシンプルで、ちょっと聞きには地味かと思いますが、その「間」の取り方とか、音の選び方のちょっとハズシ気味のところが、たまらなくファンキーなんですねぇ~♪ この感覚は虜になったら、もう最後まで抜け出せません!
そしてリー・モーガンも最初からメチャ、ファンキーなフレーズを連発してくれます。全体としては、若干の不安定さもあるんですが、それが逆に素晴らしいという、まさに全盛期の良さが堪能出来ます。倍テンポ吹きも潔いカッコ良さですねっ♪
肝心のティナ・ブルックスはR&Bに根ざしながらも、スマートな感覚も身につけた隠れ名手の実力を存分に発揮しています。それはハンク・モブレーにも近い感覚なんですが、そこまでのタメやモタレは無く、寧ろ素直なところに好感が持てるのです。
それとダグ・ワトキンス&アート・ブレイキーのリズムコンビが、実に強力です。この野太いピートが醸し出す真っ黒な感覚こそ、ハードバップの醍醐味!
A-2 The Way You Look Tonight
モダンジャズでは急速スピードで演じられることが多いスタンダード曲ですから、ここでもそれは裏切れないという熱演が展開されています。まずティナ・ブルックスがテーマ吹奏をリードして、途中のリー・モーガンの登場までが、いきなりの快感です。しかもティナ・ブルックスが、そこでも絶妙の絡みを聞かせるんですねぇ♪
その快調さはアドリブパートでも大いに発揮され、流れるようなフレーズ展開は、全く見事だと思います。ただし、それ故の引っ掛かりの無さというか、黒っぽさが希薄な事が??? バックのリズム隊が物凄いだけに、やや勿体無い感じです……。
しかし、そこへいくとリー・モーガンは流石というか、十八番のフレーズを吹きまくって、痛快なハードバップ天国を現出させていくのです。あぁ、これが当時、日常的に行われていたセッションの一場面なんですから、モダンジャズ黄金期の熱気には本当に感動させられます!
そして絶好調のソニー・クラーク! 全く「ソニクラ節」しか出ないという恐ろしさは、これまた当たり前なんですが、今更ながらにハードバップの魅力に打ちのめされます。
クライマックスでのアート・ブレイキー対2管の対決も、良いですねぇ~♪ ラストテーマの吹奏も纏まりすぎているほどです。
B-1 Star Eyes
有名なスタンダード曲ですが、リー・モーガンのミュートトランペットによるイントロが珍しく、全体的には軽やかに演奏されていますが、ハードバップの魅力は失われていません。
それはリズム隊が最高に強力だからでしょう。グイノリのダグ・ワトキンスや大技・小技を駆使するアート・ブレイキー、絶妙の伴奏というか、合の手がニクイほどのソニー・クラーク♪ こんな贅沢なサポートは、ブルーノートの保守本流を示すものでしょう。
ですからティナ・ブルックスもリラックスした好演を聞かせていますし、ソニー・クラークはファンキーな歌心が全開♪ リー・モーガンもタメとモタレ、ボケとツッコミを出し惜しみせずに見事な展開です。ただし若干の不安定さが……。まあ、この纏まりの悪さもリー・モーガンの魅力ではあるんですが……。
B-2 Minor Move
ラテンリズムも取り入れたティナ・ブルックスのオリジナル曲で、なかなか凝ったテーマ構成がカッコ良さに繋がっています。
ただし何故か、作者自身のアドリブにその面白さが活かせていない感じです。全く当たり前の冴えないフレーズが多くて残念なんですねぇ……。
それはリー・モーガンにも伝染した雰囲気でしょうか、やや精彩を欠いたマンネリが……。う~ん、このあたりがオクラ入りしていた要因なんでしょうか? けっして悪い演奏では無いんですが、ちょっとダレてしまったように感じます。
ただしソニー・クラークは、地味に素敵ですよ♪
B-3 Everything Happens To Me
さてオーラスは、このアルバム唯一のスローバラード演奏で、これが素晴らしい! 素材はマット・デニスが書いた有名な「泣き」のメロディということもありますが、それを存分に自分だけの「節」に変換していくメンバー全員の素晴らしさに乾杯です。
まずソニー・クラークのイントロが絶品ですねぇ♪
テーマ・メロディを素直に吹いてくれるティナ・ブルックスは、控えめなサブトーンも交えてながら、ソフトで黒い雰囲気描写が、もう最高です♪
またリー・モーガンが思慮深い思わせぶりを発揮して、これも素晴らしいかぎり! こういうアドリブが出来るのは、当に天才の証明だと思います。
さらにソニー・クラークが、これまた気分はロンリーなアドリブを聞かせてくれますから、私のような者にとっては、夢見心地の演奏です。そしてアドリブからラストテーマに場を締めていくティナ・ブルックスが、畢生の名演!
個人的には、このアルバムの中で一番好きな演奏になっています。
ということで、実はデータ的にはティナ・ブルックスの初リーダーセッションらしいのですが、それにしても、この豪華なメンバーは会社側の期待の表れとしか言えません。またそれを惜しげなくオクラ入りさせる潔さにも驚愕です。
そのあたりは、このセッションを聞き込むと理解出来るところでしょう。確かに纏まり過ぎている部分やマンネリしている部分が無きにしも非ずです。
これが初登場した1980年頃のジャズ界は、フュージョンブームが一段落して4ビートに原点回帰しつつあった時期でしたから、必然的に大歓迎というムードがありましたけれど、モダンジャズの黄金期では当たり前過ぎる演奏だったのか? と私は不遜にも思ってしまいます。
まあ、それだけ当たり前の凄さ・良さが味わえる作品だと、ご理解願えれば幸いですが……。やはり今となっては豪華なメンバーが揃った、かけがえの無い演奏ということで楽しめると思います。