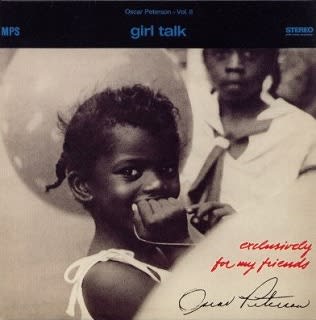■The Cooker / Lee Morgan (Blue Note)
モダンジャズのイメージ的花形スタアは、やっぱりトランペッターでしょう。実際、マイルス・デイビスやチェット・ベイカーあたりはジャズを超えて広く大衆に知られた存在でしょうし、例え演奏を聞いたことがなくても、イメージとしてのモダンジャズをカッコイイ音楽にしているのも、そういう花形スタアだと思います。
そしてリー・モーガンもまた、その中のひとりでしょう。
とにかくビシッとキメたファッションセンスの良さ、十代にしてジャズシーンのトップで活躍した実力、奔放にして繊細なフィーリングを秘めた音楽的才能! リアルタイムでは、まさに怖いもの知らずだったと思いますが、その天才が決して暴走しなかったのは周囲に良き理解者が居たからでしょう。
例えばそれは看板として在団していたジャズメッセンジャーズのボス=アート・ブレイキー、その参謀だったペニー・ゴルソン、そして専属契約を結んでいたブルーノートの主催者=アルフレッド・ライオンです。
特にキャリア初期のリーダーセッションにはペニー・ゴルソンのアレンジが大きなシバリとして存在し、リー・モーガンの弾ける若さを絶妙な纏まりに収斂させていたのが、成功のポイントだったろうと思います。
しかし流石はアルフレッド・ライオン! リー・モーガンの奔放な魅力を飼殺しにする事はせず、ついにブルーノートでは5枚目のリーダー盤となるセッションで、若き天才の自由意思を解き放ったようです。
録音は1957年9月29日、メンバーはリー・モーガン(tp)、ペッパー・アダムス(bs)、ボビー・ティモンズ(p)、ポール・チェンバース(b)、フィリー・ジョー・ジョーンズ(ds) という魅力溢れるクインテットです――
A-1 A Night In Tunisia
説明不要というモダンジャズの名曲として、リー・モーガンもディジー・ガレスピーの楽団やジャズメッセンジャーズで幾多の名演を残しているにもかかわらず、ここでまたまた録音を残した意義は聴いて吃驚です。
まず執拗なラテンビートを敲き出すフィリー・ジョー、さらにその隙間を埋めようと奮闘するポール・チェンバースの存在感が異様に強く、またボビー・ティモンズの意地悪な伴奏はこれ如何に!
そしてそんな空間を一気呵成に駆け抜けていくリー・モーガン! もはや混濁の中のひとり相撲という感じが圧巻です。誰一人妥協する者がいないんですねぇ~。いや、実際の現場では緻密な打ち合わせがあったのかもしれませんが、この全く和みの無い雰囲気は心底、怖いです。
当然ながらペッパー・アダムスも修羅の道を歩みますが、驚いたことに、こんな演奏がリアルタイムではAB面に分割されたシングル盤として発売されていたんですねぇ~。う~ん、売れていたのか……!?
まあ、そんな余計な御世話は別にしても、これだけ混濁したハードバップは前衛としか思えないのが私です。つまり聴くのには根性が必要かと……。
どうにか正当的な4ビートに展開されるボビー・ティモンズのアドリブパートが救いといえば、それまでかもしれません。
A-2 Heavy Dipper
一転して痛快無比なフィリー・ジョーのドラミングが楽しいイントロとなる、如何にも「らしい」ハードバップです。もちろんリー・モーガンはトリッキーなフレーズを使いまくって楽しく疾走する名演を披露♪
ペッパー・アダムスも歌心があるんだか否か、言語明瞭なれど意味不明という得意技で力演ですし、ボビー・ティモンズの硬派な魅力もいっぱいですが、やはりここはどうしてもフィリー・ジョーのドラムスに耳にいってしまいますねぇ~♪ ハイハットやシンバルワークの冴えまくりが気持ち良すぎます。
B-1 Just One Of Those Things
このアルバムのもうひとつのウリが、この演奏だと思います。
曲は有名スタンダードというお馴染みのメロディがアクの強いイントロのアレンジとスピード感満点のテーマ吹奏、そして痛快なアドリブパートで再構成されていく展開は最高です。
ほとんど決定的なリー・モーガンは畢生の名演ですし、ペッパー・アダムスも生涯の熱演アドリブじゃないでしょうか。とにかく強烈無比! 颯爽として潔いメンバー全員のジャズ魂が燃え上がっています。
B-2 Lover Man
これまた興味深々の演目ですねぇ、ジャズの歴史では説明不要の経緯がありますから。まあ、そういう因縁で語られるのが、この曲の不幸と幸せな結末ではありますが……。
しかしここでのリー・モーガンは真摯な演奏姿勢というか、殊更にそうした部分を意識させない見事な吹奏を聞かせてくれます。まあ、そんなところに拘って構える自分が恥ずかしくなります。名曲には名演が必要という見本かもしれません。
虚心坦懐でボビー・ティモンズのピアノにもシビレますし、意外に過激なポール・チェンバースも強い印象を残します。またハードエッジなバリトンの魅力に白人らしい歌心のペッパー・アダムスも立派!
しかしやっぱり、ここではリー・モーガンでしょうねっ♪ 特に中盤からのグルーヴィなノリと絶妙のメロディ展開には驚嘆して感涙するしかない、まさにジャズを聴く喜びがいっぱいです。
B-3 New-Ma
オーラスは、これぞハードパップというダークでグルーヴィな演奏です。ただし、その魅力的なテーマ部分では、フィリー・ジョーが些かミスマッチなドラミングで賛否両論……? 正直言えば、こういう曲調にはアート・ブレイキーだよなぁ~。
と、そんな不遜な事も浮かんでまいりますが、アドリブパートでは先発のポビー・ティモンズが十八番のゴスペルファンキーな感覚を全開させ、続くポール・チェンバースがエグイばかりのペースソロ! そして地底怪獣の蠢きというペッパー・アダムスの重厚なバリトンサックスが咆哮すれば、そんなモヤモヤはブッ飛びです!
さらに満を持して登場するりー・モーガンがハードボイルドな「節」を聞かせてくれます。
う~ん、しかしやっぱりフィリー・ジョーが、なぁ……。
ちなみにこの曲はリー・モーガンのオリジナルですが、A面2曲目の「Heavy Dipper」も併せて、もしかしたら公式レコーディングでは初めての自作曲演奏になっているのかもしれません。
ということで、これはリー・モーガンの本格的な独立宣言! というよりも成人式でしょうか。ブロデューサーのアルフレッド・ライオンにも、あえてリー・モーガンを好き放題にやらせてみる思惑があったんじゃないでしょうか?
そして結果は奔放にして混濁と颯爽が同居した傑作盤になっています。
もちろん好き嫌いは十人十色でしょう。実際、私は最初、A面ド頭の「A Night In Tunisia」にどうしても馴染めず、B面ばかり聴いていましたし、これは今でも変わりません。しかしその「A Night In Tunisia」には、やっぱり凄いものが蠢いて噴出していく怖さを否定出来ません。ジャズメッセンジャーズでの演奏とは全然、別種のカリスマがあるというか、う~ん、上手く言えません。
これはぜひとも皆様に聴いて、感じていただきたいというアルバムです。