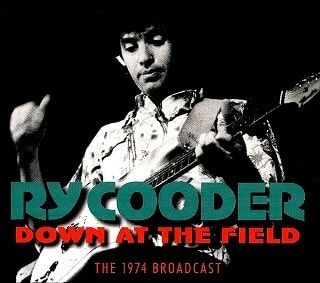■Paris, Texas / Ry Cooder (Warner Bros.)
サントラと言うよりも、映画の劇伴音楽としては、ライ・クーダーが担当した「パリ・テキサス」も最高に好きです。
ご存じのとおり、ヴィム・ヴェンダース監督による1984年の映画本篇は傑作として決定的な評価を得ていますが、もしもここにライ・クーダーの音楽が入っていなかったら……!?
なぁ~んていう想いは愚問です!
何故?
と問われれば、それは実際に映画本篇を鑑賞していただくのが最良の答えなんですが、美しい映像も、出演者の的確な演技も、そして監督以下撮影スタッフの意図をも暗黙の了解の如く纏め上げているのは、ライ・クーダーの音楽としか思えないんですよねぇ~♪
例えば劇中の映像演出で多用されるインサートシーンや曖昧な場面転換におけるライ・クーダーのギターの存在感は、もしもそれが無かったら、非常にギクシャクした映画になっていたようにも感じられるほどです。
物語は恣意的な行動として、互いに理解しあえない夫婦とその間のひとり子供が、最良の方策は何時までも結論を出さない事だと言わんばかりの存在を見せつけるのでしょうか、とにかく行き倒れの浮浪者=ハリー・ディーン・スタントンがなんとか弟に預けられていた息子=ハンター・カーソンと再会し、ふたりでハンター・カーソンの母親=ナスターシャ・キンスキーを探しに旅をするという展開です。
そして風俗店で働いている彼女を発見したハリー・ディーン・スタントンは……、というところから、なんともせつない物語のクライマックスが演出されますので、後はぜひともご覧いただきたい名作なんですが、ほとんど効果音的な使われ方をされるライ・クーダーのギター、あるいは付随するピアノやマンドリン等々が、ジワジワと心の中に染み込んでくる情動も、なかなか強い印象になると思います。
そこでサイケおやじは、基本的にライ・クーダーが好きではありますが、掲載したサントラアルバムをゲットする時でさえ、映画の中の様々な場面を回想する目的が一番でありました。
A-1 Paris, Texas
A-2 Borthers
A-3 Nothing Out There
A-4 Cancion Mixteca
A-5 No Safety Zone
A-6 Houston In Two Seconds
B-1 She's Leaving The Bank
B-2 On The Couch
B-3 I Knew These People
B-4 Dark Was The Night
さて、ライ・クーダーと言えば映画音楽の仕事も相当にやっていますが、この「パリ、テキサス」は基本的にライ・クーダー(g)、デイヴィッド・リンドレー(etc.)、ジム・ディッキンソン(key) の3人で演奏されているようです。
しかし、もちろんライ・クーダーのギターはフィンガービッキングもスライドも流麗にしてエグ味の効いた特有の音を聞かせてくれますし、例によってデイヴィッド・リンドレーはマンドリンやバイオリンみたいな不思議な音を出す楽器を操っているようでもあり、またジム・ディッキンソンはピアノをメインにしながら、おそらくはシンセ系の楽器も使っているのでしょうか、おそらくは多重録音も使いつつ、なかなか深みがあって、厚みのある演奏が出来上がっていると思います。
ところが同時に、それが非常にシンプルな響きに聞こえるところが、美麗な映画本篇の映像や刹那の物語演出を見事に彩っている秘密かもしれません。
実はこのLP裏ジャケットには上記メンバーの演奏風景を撮った写真が掲載されているのですが、ライ・クーダーは妙にボロッちいギターを使っていますし、デイヴィッド・リンドレーは見た事もないバンジョーと胡弓のハーフみたいな楽器を弾いていることに加えて、ジム・ディッキンソンはピアノの鍵盤にガムテープを張り付けている作業中!?
う~ん、だから、この劇伴トラックは奥行きの深~い音作りになっているんでしょうかねぇ~~~。
そこで肝心の演奏そのものなんですが、まず注目されるのはオーラスの「Dark Was The Night」で、これはサイケおやじが大好きなライ・クーダーの初リーダーアルバムのオーラスにも置かれていた古典ブルースのインスト演奏であり、他のトラックの大部分は、この曲の変奏というのが真相だと言われています。
しかし、それにしても、流石のバリエーションの多彩さはライ・クーダーならではの感性であって、例えばタイトルバックに流れたA面ド頭の「Paris, Texas」の不気味な予感、続く「Borthers」でのフィンガービッキングとスライドの巧みな交錯によるシミジミ感、そして「Nothing Out There」での、これまた悪い予感の満たされ方!?
何れもライ・クーダーの名人芸とも言うべきスライドギターの魔法が冴えまくりなんですが、さりげなくバックに入っている妙な鐘の音や意味不明のオドロなサウンドは、おそらくは他の2人によるものでしょうか、それが意外にも大きな存在感を示しているようです。
また「Houston In Two Seconds」や「She's Leaving The Bank」は、不安と希望が絶妙にミックスされた演奏とでも申しましょうか、この緩いテンポでの力強さや不思議な躍動感はクセになりそうな上手さですよねぇ~♪
それは父親と息子が互いに相手をどう思っていいのか、そんな深層心理に踏み込んでいるようでもあり、また客観的に登場人物を眺めて欲しいという監督の意図の代弁なのか……?
このあたりは映画本篇を観ていると、それこそリスナーが十人十色の感性で聴けるんじゃ~ないでしょうか。
その意味で極めて効果音に近い演奏の「No Safety Zone」、あるいはライ・クーダーが独り舞台でスライドギターを響かせる「On The Couch」は両テイク共に短いながらも相当に印象的ですよ。
そしてもうひとつ、この音源集で素敵なのが、こよなく美しいワルツの「Cancion Mixteca」で、これはライ・クーダーが十八番とするメキシコの伝承歌を自己流にアレンジしたものらしいのですが、映画本篇の中では随所にチラチラと流れてきたりもして、これまた心に染み入りますよ♪♪~♪
おまけにこのトラックでは、途中から主演男優のハリー・ディーン・スタントンが泣き節のボーカルで歌ってくれるんですからねぇ~~♪ 思わず、うるっとしてしまうですよ♪♪~♪
実は些かネタバレになりますが、このアルバムのクライマックスは映画本篇と同じく、所謂「覗き部屋」で働いる妻のナスターシャ・キンスキーにハリー・ディーン・スタントンが鏡越しに、これまでの経緯を第三者的に物語る台詞がそのまんま入っていて、その途中から、この「Cancion Mixteca」の演奏パートがジンワリと流れてくるんですねぇ~~♪
いゃ~、この場面ではサイケおやじも映画館で本当に泣いてしまいそうになったんですが、レコードを買って、聴いているだけもそのシーンに浸りこんだ感じで、完全うるうる状態……。
全くお恥ずかしいかぎりではありますが、こうして迎えるラストシーンは「お約束」である母親と息子の再会であって、いよいよそこに流れる「Dark Was The Night」の潔さは絶品!
しかもそれに続く終わり方が最高の余韻なんですよっ!
とにかく全ての皆様にご覧いただきたいとお願いするに相応しい、これぞっ! 永遠不滅の名作映画にして、傑作劇伴音楽集なのは、そのラストの余韻の見事さがあればこそです。
ちなみにリアルタイムでは家庭用ビデオも普及し始めていましたし、今は懐かしのレザーディスクも登場した頃とあって、この「パリ、テキサス」の映像ソフトも人気がありました。
それは普通に鑑賞するのも良いんですが、所謂環境ビデオとして、お洒落なカフェバーとかブティック等々で雰囲気作りに使われていたんですよねぇ~♪ 結局、そこまで用いられてしまうほど、映像と音楽の融合完成度が高かったという証だと思われます。
ということで、本日の文章内容は映画「パリ、テキサス」をメインに書いてしまったので、「Movie」のジャンルが真っ当かもしれませんが、あえて「Ry Cooder」に入れてあるのは既に述べたとおり、ライ・クーダーの演奏が映画本篇を絶対的な存在に導いているからに他なりません。
まあ、それは例によってサイケおやじの独断と偏見ですから、このアルバムだけを聴けば、つまらないと感じられる皆様が圧倒的に大勢だと推察しております。
しかし、一度でも映画本篇を鑑賞すれば、この音源集がライ・クーダーの最高傑作と断言されるファンさえも存在する理由がご理解願えるかもしれませんよ。
それほど、「パリ、テキサス」は全てに秀逸な作品だと思うばかりです。
ちなみにサイケおやじは車の中でこれを流すことも度々で、もちろん孤独な運転時に限っているんですが、それで劇中のハリー・ディーン・スタントンのようにストイックな気分に浸るというジコマンは悪くありません。
まあ、そんなところがサイケおやじの本性であります。