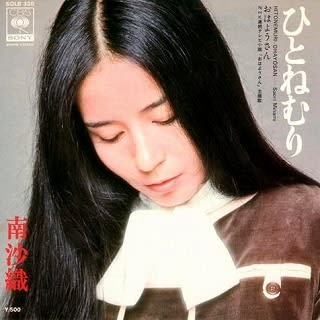■The Kinks At The BBC (Universal)

長年活動を続けたミュージシャンの復刻&発掘アイテムには喜びを隠せないサイケおやじも、それがあまりにも長大なブツになると、これは所謂嬉しい悲鳴です。
例えば本日ご紹介するキンクスのBBC音源集大成セットは、なんとっ!? CD5枚にDVD1枚の計6枚という、とても一気に鑑賞出来るものではなく、特にDVDは、ど~やって収めたものか、50以上のパートに曲とインタビュー等々が入った3時間40分以上の長尺なんですから、たまりませんねぇ~~♪
しかも、ちょいと流して見た限りでも、そりゃ~、中にはヨレているパートも少しはありますが、相対的に画質はこれまで出回っていたブート映像等々とは比較にならないほど、率直に言えば、なかなか良好だと思っています。
ちなみに収録ソースはCDが1964~1994年の間に録られたラジオ番組からの音源がメイン、DVDはリージョンフリーで、1964~1993年までの有名なところはほとんど見られますよ♪♪~♪ しかも曲の途中でフェードアウトなぁ~んてところは、ほとんど無いという感じなんですから、これは絶対!!
気になる収録詳細については、あまりにも膨大なんで、今回はご容赦願いたいところではありますが、それでも特にお楽しみいただきたいパートだけ、簡単に――
まずDVDでは、何んと言っても、1972年の「レインボーシアター」でしょう。
これは1972年1月31日に収録されたライプ映像で、キンクスのレギュラーメンバーに加えて、マイク・コットン・サウンドと名乗っていたホーンセクションが参加していた、つまりは例の傑作アルバム「マスウェル・ヒルビリーズ」発表後の全盛期(?)がばっちり!
Till The End Of The Day
Waterloo Sunset
The Money-Go-Round
Sunny Afternoon
She Bought A Hat Like Princess Marina
Alcohol
Acute Schizophrenia Paranoia Blues
You Really Got Me
途中に短いインタビューやイメージ映像、リハーサル風景等々も挟み込まれていますが、約40分間、上記のようなヒットパレードが堪能出来るのは、キンクスファンのみならず、普通の洋楽好きにとっても歓喜感涙だと思います。
特にその頃の特徴であった、フニャフニャした歌と古いジャズ様式を活かした曲構成は、実演ステージの場であればこその尚更に「ひねくれた」楽しさがあり、これぞっ! キンクスのひとつの真骨頂が楽しめるんじゃ~ないでしょうか。
その意味でクロージングの「You Really Got Me」がハードロックのルーツを解き明かす、絶妙の大団円として演じられるのは流石! 何度でも見たくなる中毒性には要注意かもしれませんよ♪♪~♪
そして同時期の演奏は、もうひとつ、1973年1月24日に録られたとされる「イン・コンサート」でも、似たような演奏が楽しめますが、こちらはさらに演目が下記のように増えているのも嬉しいところでしょう。
Victoria
Acute Schizophrenia Paranoia Blues
Dedicated Follower Of Fashion
Lola
Holiday
Good Golly Miss Molly
You Really Got Me
All Day And All Of The Night
Waterloo Sunset
The Village Green Preservation Society
やはり、何んと言っても「Victoria」と「Lola」の二大ヒット曲が嬉しいですよねぇ~♪ もちろん、それを含めての全体的なノスタルジックサウンドの提供は、まさに当時のキンクスではありますが、オールドR&Rの「Good Golly Miss Molly」から「You Really Got Me」、そして「All Day And All Of The Night」と続く構成も、これまたキンクスの本性を堪能出来るものです。
ちなみに、そのパートあたりから、チャプター番号の実際とプックレットの記載が異なってくるのは微細な減点対象かもしれませんが、約30分の良好な画質に免じて……。
さて、このDVDのもうひとつのお目当てが、1977年の「キンクス・クリスマス・ショウ」というのは、衆目の一致するところだと思います。
場所はお馴染み、レインボー・シアターに満員のお客を入れてのライプステージから約1時間の構成で、下記演目が楽しめますよ♪♪~♪
Juke Box Music
Sleepwalker
Life On the Road
A Well Respected Man
Death Of A Clown
Sunny Afternoon
Waterloo Sunset
All Day And All Of The Night
Slum Kids
Celluloid Heroes
Get Back In The Line
Schoolboys In Disgrace
Lola
Alcohol
Skin And Bones / Dry Bones
Father Christmas
You Really Got Me
この時期のキンクスはセールスが伸び悩んでいたRCAからアリスタに移籍しての心機一転! アメリカでの本格的な活動に目標を定めた事から、つまりは十八番にしていたLP単位でミュージカル仕立のコンセプト作品を打ち切った頃でした。そして同時にライプバンドとしての持ち味を再認識させるべく、積極的に巡業ステージをやっていたのでしょう。
ですから、このパートのテンションが予想以上に高いのもムペなるかな、キンクスにとってもファンにとっても、まさに温故知新のソリッドなロックと懐古趣味的な人気曲が巧みに並べられた歌と演奏には、最良の瞬間がたっぷり楽しめるはずです。
おまけにクリスマスという祝祭ムードの中、笑ってしまいそうな衣装を身につけたメンバー、パイ投げで頭にクリームをつけたまま熱演熱唱のレイ・デイビスは、ついにサンタクロースの扮装までやってしまうんですよっ!?
いゃ~、このステージライプをブートとは比較にならないほどの良好画質で楽しめるんですから、長生きはするもんですねぇ~♪
実は同年のライプセッションとしては、もうひとつ、このパートの前に収録された春の「オールド・グレイ・ホイッスル・テスト」からの映像ソースが約47分間楽しめるんですが、こちらもまた、なかなかパワフルな熱演が良い感じ♪♪~♪
All Day And All Of The Night
Sleepwalker
Life Goes On
Stormy Sky
Celluloid Heroes
Muswell Hillbilles
Full Moon
Life On The Road
Juke Box Music
という、上記の演目は既に述べたとおり、アリスタに移籍しての新譜LP「スリープウォーカー」からの曲が中心であり、しかもジョン・ドルトン(b) に代わってアンディ・パイル(b) が新参加した時期というのも興味津々でしょう。
そしてあらためて思うのは、件のアルバム「スリープウォーカー」がアメリカでも売れまくった好盤であるという事実!
う~ん、この時期のキンクスも、本当に良いですねぇ~~~♪
そして、それゆえに残念というか、実はこのブツには契約の関係なんでしょうか、以降のアリスタ時代が全く入っていないんですねぇ……。
まあ、もしかしたら、次なる企画発売の予定に組み込まれているのかもしれませんが、出し惜しみだけはしてほしくありません。それは全てのファン、共通の思いでしょう。
ということで、他にも見どころがたっぷりの映像パート、さらにはCD5枚に収められた「お宝」ライプ音源は、とても本日は紹介しきれるものではありませんが、「Disc-1」に収録の1964~1967年の歌と演奏には、ピートバンドとしてのキンクスが独自の懐古趣味路線を確立していく様がはっきりと楽しめますよ。
そして「Disc-2」が1967~1972年という、これまたキンクスの個性が確立された時期が、意外なほどパワフルに演じられているという事実に驚愕! これまでのレコードで聞けた曲が、如何に狙ったものだとしても、そのフニャフニャした印象とは逆の「太さ」は、やっぱりキンクスだけのロックの本質だと痛感させられました♪♪~♪
ちなみに音源がラジオ放送のソースということで、随所に英語のアナウンスや曲紹介が歌と演奏に被っているんですが、それもまた実にカッコE~~♪ まあ、話の内容は案外ど~しようもないズレもあったりするんですが、流石に本場の雰囲気は充分に楽しめると思います。
さらに「Disc-3」は曲と演奏の雰囲気がますますスワンプ化していった1973~1974年の音源で、特にこれまでブートネタの定番にもなっていた1974年の「イン・コンサート」のパートには素直に夢中にさせられるんじゃ~ないでしょうか。ホーンセクションと女性コーラスを加えたサウンドそのものが、本当にイカシているんですよっ!
前述した映像パートからの流れで楽しむのもOK♪♪~♪
そして「Disc-4」には、前述の映像パートにも入っていた1977年の「キンクス・クリスマス・ショウ」と基本的に同じものが、実は「ラジオ放送バージョン」で再収録!? しかし、これがきっちりFM用(?)ステレオミックスですし、おまけに部分的な音源の差し替え疑惑もありますので、これはこれで意味があると思います。
また後半には1994年のラジオショウ音源が、オマケ的(?)に入っているのも得した気分です。
ただし、これはど~しても書いておきたいんですが、相対的に良好な音質の中、「Disc-5」の大部分が、とんでもなく音が悪いんですよっ!? 全く意図が分からないというか、一応「Off Air Bootleg Recording」なぁ~ていう、注意書きはあるんですが、いやはやなんともです。
しかし、そうであったとしても、これだけのブツが輸入盤のネット購入ならば4~5千円で買えるのは嬉しいかぎりで、特にDVDのパートは満足出来るはずですよ!
ちなみに予定されている日本盤は、1万5千円ほどらしいですから、例えインタビューのパートに字幕があったとしても、それは個人的に納得出来ません。
ということで、これは素晴らしい♪♪~♪
その一言が全てです!
特に初期~中期のキンクスが生演奏で出していた本当に「太いロックのピート」が、ここまで堪能出来る音源集は初めてかもしれません。中でもミック・エイヴォリーのパワフルなドラミング、ピート・クウェイフの図太いベースの存在にはド肝をぬかれましたですねぇ~♪
またデイヴ・デイビスのワイルドなギターワークは、かまやつひろしが真似(?)たと思われるほどロックの本質を体現していますし、途中参加のジョン・ゴスリング(key) やジョン・ダルトン(b) の音楽センスも、キンクスがキンクスとして成立するには必要不可欠な人材だと再認識でした。
そして主役のレイ・デイビスは、ボケとツッコミをひとりでやれる、まさに天才ロッカーにして、偉大な音楽家であり、演出家としても超一流!
大袈裟で無く、そう思うわざるをえないのが、この長大なセットが出た意味合いかもしれません。
願わくば、続篇企画がありますようにっ!