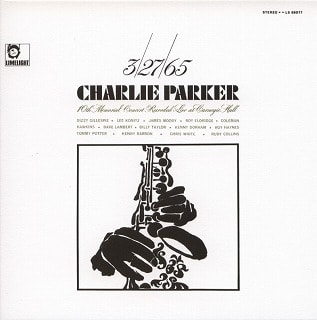■The Phil Woods Six Live From The Showboat (RCA)
1970年代に吹き荒れたフュージョンの嵐の中では、ベテラン実力派さえもその色合いが強いレコーディング作品を残していますが、流石に正統派ジャズメンの矜持を持ち続けたひとりがフィル・ウッズでした。
白人ながらチャーリー・パーカー直系の真正ビバップスタイルに独特のウネリを加えたスタイルは、1950年代中頃からのハードバップ期に一躍人気を集め、さらにモダンジャズが混迷した1960年代中期以降は欧州に活路を求め、同時に1970年代前半まではスタジオの仕事もやりながら持ち続けたジャズ魂は人間国宝でしょう。
そしてもちろん各時代には物凄い人気傑作盤を残しているのは言わずもがな、これは1970年代後半の決定的な名演集になっています。
録音は1976年秋、メリーランド州にある「ショウボートラウンジ」という店におけるライブで、メンバーはフィル・ウッズ(as,ss)、マイク・メロリ(p,key)、ハリー・リーヘイ(g)、スティーヴ・ギルモア(b)、ビル・グッドウィン(ds)、アリリオ・リマ(per) という当時のレギュラーバンドです――
A-1 A Sleepin' Bee
ビル・エバンスの名演も記憶されている素敵なメロディのスタンダード曲で、ギターとのデュオで思わせぶりを演じた後は快適なテンポで自在にアルトサックスを歌わせるウィル・ウッズは流石の名人です。とにかくこのウネリと歌心、見事な緊張と緩和♪ これがハードバップというか、永遠のジャズグルーヴでしょうねぇ~~♪
録音の雰囲気から言えば、電気増幅アタッチメントが付いたウッドペースの音が如何にも1970年代ですし、バランスが良すぎて軽く聞こえるドラムスが物足りなくもありますが、このあたりは音量を上げることで解消出来ると思います。ちょっと安っぽいピアノの響きも同様でしょう。
それゆえにこのアルバムは、入荷したとたんにジャズ喫茶の人気盤! ド頭の些か勿体ぶったフィル・ウッズのアルトサックスが鳴り出せば、店内は忽ちジャズ色に染まりましたですね。
A-2 Rain Dansc
ギタリストのレイ・リーヘイのオリジナルで、ちょっとプログレなイントロから16ビートも使ったテンションの高いテーマアンサンブルへと続く流れは、明らかに当時のフュージョン色が強くなっています。
しかしギターの音色はロック系のエフェクターを使っていない正統派ジャズそのものですから安心感がありますし、ツッコミするどいリズム隊とソプラノサックスで対決するフィル・ウッズの過激な姿勢は潔いかぎり!
このあたりの折衷性というか、実は時代の要求にもきちんと応える物分かりの良さが、フィル・ウッズのプロ意識なんでしょうか。良くも悪くも凄い人だと思います。
A-3 Bye Bye Baby
これも楽しいスタンダード曲の名演で、展開としては「A Sleepin' Bee」と同じですが、ここではマイク・メリロのピアノが大活躍♪ 私はこのアルバムで、この人の大ファンになったほどです。
もちろんフィル・ウッズもアップテンポの4ビートで飛ばしまくり! 「Amapola」を煮詰めたようなテーマメロディの解釈も憎らしく、アドリブは素晴らしい歌心を徹底的にハードドライヴさせる物凄さです。アルトサックスの鳴りも強烈至極で、このあたりがフィル・ウッズの全盛期だったのかもしれません。
A-4 Django's Castle
タイトルどおり、ジプシー系ギタリストのジャンゴ・ラインハルトが書いた名曲ですから、ここではギタリストのハリー・リーヘイが大フィーチュア♪ 疑似ボサノバにアレンジされたリズムも心地良く、ジンワリした歌心がその場の空気を和ませてくれます。
ちなみに私は、この人もこのアルバムで知ったのですが、その経歴も演奏も、ここでの快演しか知らないという気になるギタリストです。
肝心のフィル・ウッズはテーマメロディの変奏が流石の味わい、そして最後のお礼の挨拶では、人の良いオヤジって感じにも和みます♪
B-1 Cheek To Cheek
これも有名スタンダードで、このアルバムでは「お決まり」という演奏展開ですが、それがまた気分最高! 思わせぶりなテーマ演奏からスピード感満点のアドリブパートへの傾れ込みが、わかっちゃいるけど、やめらない♪
フィル・ウッズの流麗にして豪快なノリは余人のツケ入る隙も無く、唯我独尊の響きがイヤミ寸前ではありますが、それこそがジャズの醍醐味を満喫させてくれると思います。
また終盤で展開されるアルトサックスとペースの二人三脚から激しいラストテーマへの突入も良い感じ♪ このあたりのバンドアンサンブルはレギュラーならではの強みでしょうね。
しかし我儘を言えば、ダンポールみたいなバスドラの響きは、なんとかならんのかっ!? ビル・グッドウィンが名演なだけに勿体無いというか……。これはCDリマスターではどうなっているか? 大いに気になるところでもあります。買ってみようなぁ……。
B-2 Lady J
フィル・ウッズのオリジナル曲で、ほとんど大野雄二っぽい疑似ボサノバに気分は最高♪ 適度に力んだアルトサックスの響きにシビレまくりです。
纏まりの良いリズム隊ゆえに、アルバムをここまで聴きとおしてくると、些かマンネリも感じられるのですが、それはそれとして……。
B-3 Little Niles
アフリカの民族意識を強く打ち出していた黒人ピアニストのランディ・ウェストンが書いた代表曲で、この人は小型のセロニアス・モンクみたいなスタイルでしたが、作曲能力はなかなかです。
この曲もミステリアスな魅力がいっぱいの人気メロディでしょうね。フィル・ウッズもそのあたりを活かした吹きっぷりですし、バンドメンバーも思わせぶりとグイノリを巧み使い分けた好サポートを聞かせてくれます。特にベースのスティーヴ・ギルモアが実に良いですねぇ~♪
しかし、やっぱりフィル・ウッズは圧倒的! 緩急自在なノリ、千変万化の音色、ウネリとヒネリのフレーズが洪水のように押し寄せてくるのでした。
C-1 A Litte Peace
マイク・メリロが書いた思わせぶりがたっぶりのスロー曲ですが、フィル・ウッズにとっては、こういう雰囲気が十八番ですからねぇ~。ここでも粘っこく激情を発散させて、正直言えば、疲れる演奏を聞かせてくれます……。ハッとするほど良いアドリブメロディも飛び出すのですが……。
バンドメンバーも自分達が楽しんでいるような感じでしょうか。中盤からのグイノリのパートは痛快ですが、やっぱり聴いていて疲れます……。
C-2 Brazilian Affair
タイトルどおり、ブラジル系ラテンフュージョンのハードバップ的展開に終始したフィル・ウッズのオリジナル曲で、全体が4パートで組み立てられています。なんと22分近い熱演!
スタートはキャノンボール・アダレイの「Jive Samba」みたいなリズムパターンを使い、渡辺貞夫みたいなテーマメロディが楽しい雰囲気ですが、流石にフィル・ウッズのアルトサックスは痛快に歌いまくり♪ 適度な力みも良い感じで、熱くさせられます。アリリオ・リマのパーカッションも楽しいですね。ここが「Prelude」というパートになるんでしょうか。
すると続く「Love Song」のパートはスローな疑似ボサノバで、レイ・リーヘイのギターがイマイチ……。フィル・ウッズのAORっぽいアルトサックスも激情的ですが、それなりかもしれません。
しかし次の「Wedding Dance」に入ると躍動的なラテンビートでバンドが強烈にグルーヴし、フィル・ウッズもソプラノサックスで大熱演ですし、「お約束」を多用したマイク・メリロのピアノも憎めません。このあたりは渡辺貞夫がこの時期にやっていた同種の演奏よりは、ずぅ~っとハードバップ寄りというのが、ジャズ喫茶ウケしていたポイントでしょうか。
その秘密は最終パートの「Joy」で展開される全力疾走で明らかにされ、快楽的なテーマの新主流派的な解釈は痛快そのもので、なんとアレンジのキメには、マイルス・デイビスでお馴染みの「天国への七つの階段」のリフが用いられているという稚気が最高です。あぁ、これがフィル・ウッズです! もちろんその場の観客も大熱狂!
D-1 I'm Late
フィル・ウッズのソプラノサックスを中心にリズム隊も共謀したエキセントリックな演奏ですが、全てが終わった後に「不思議の国のアリスからの曲でした」なんていうリーダーのMCに吃驚です。
う~ん、それにしても、この疾走感は痛快至極で、明らかに1970年代ジャズ正統派の響きに満ちています。バンド全員がヤケッパチに力んでいますが、同時に見事なほどの統一感、纏まりがありますから観客も大喜びで、歓喜の拍手喝采がライブ盤ならではの醍醐味になっています。
D-2 Superwoman
一転して、これはメロウでソフトなソウルフィーリングがいっぱい♪ もちろんスティーヴィー・ワンダーの、あの曲ですからねぇ~♪ フィル・ウッズのアルトサックスも本領発揮の甘くて情熱的な歌心です。そしてバンド全体のノリが、決して凡百の軟弱フュージョンになっていないんですねぇ。
ちなみに当時のフィル・ウッズは、例えばビリー・ジョエルの「素顔のままで」とか、所謂AORの歌物セッションでも名演を残していましたから、こうした雰囲気は十八番だったんでしょう。と言うよりも、それがフィル・ウッズがデビュー当時から変わらずに持ち続けた天性の歌心の本質かもしれません。
あぁ、それにしても心地良いジャズのムード♪ まさにフュージョンブームに真っ向から立ち向かったモダンジャズの面目躍如でしょうね。
D-3 High Clouds
これまたアップテンポでブッ飛ばしたラテンジャズの快演で、もちろん時期的にフュージョンっぽいノリやバンドアンサンブルが逆に楽しさを倍加させています。
しかしフィル・ウッズはモダンジャズの正統を継ぐパーカーフレーズの連発で、決して妥協していない姿勢が潔く、そんなリーダーを盛りたてるバンドの面々からも必死さと演奏する楽しみが伝わってきます。特にアリリオ・リマのパーカッションが実に爽快ですねぇ~。
D-4 How's Your Mama (Phil's Theme)
オーラスは当時のライブではラストテーマに使われていた演奏で、如何にもゴキゲンなブルースとメンバー紹介が楽しいところ♪ まさにフィル・ウッズの真摯なサービス精神が良く出た締め括りとして、最高です。
ということで、実はこの2枚組のライブ盤はLP片面が各々30分近くある長丁場ですから、通して聴くと正直、満腹感で疲れます。しかしそれにしても痛快な傑作であることに違いはなく、当時リアルタイムのジャズ喫茶では鳴りまくっていましたですね。
そして正統派4ビートを古臭いと感じていたフュージョンのファン、あるいはそこから本格的にジャズへ入ってきたファンも、これには歓喜悶絶したのが真相だったと思います。
もちろんそれは現在でも充分に通用する感覚でしょう。時代はこの2年後ぐらいから新伝承派と称される4ビートリバイバルになりますが、そんな事象を全く問題にしていなかったのが、フィル・ウッズの矜持だったかもしれません。フュージョンだろうがAORだろうが、何時も一番ヒップなのはモダンジャズという証明が、このアルバムなのでしょうか。