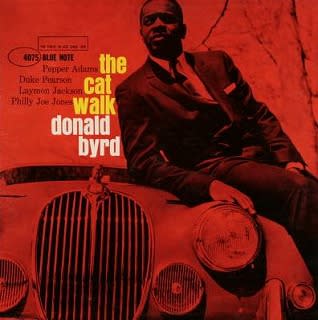■The Last Waltz Complete With Naked Sound / The Band
(Johanna = Bootleg DVD)
先週末は何かに惹きつけられるように入ったブート屋で、いろいろと驚愕のブツを発見しましたが、本日ご紹介も、あぁ、これが大当たり♪♪~♪
内容は1976年11月25日に行われたザ・バンドの最後のライブステージ、通称「ラストワルツ」の夜を可能な限り忠実に追体験出来る映像作品です。
皆様がご存じのように、この「ラストワルツ」はマーティン・スコセッシ監督により映画化され、1978年春に公開されました。そしてサントラ扱いというアナログ盤3枚組の同名アルバムも発売され、ザ・バンドと豪華ゲストメンバーの歌と演奏が存分に楽しめた、まさに1970年代ロックの素晴らしい記録だったわけですが、当然ながらフィルムは商業映画的な面白さを優先するために編集され、当夜のプログラムはバラバラにされていました。またアルバム収録の音源も同様に編集され、歌や演奏には手直しやオーバーダビングが施されていたのです。
それはリアルタイムで出回っていた海賊盤や音楽マスコミによるレポート等々でも明らかでしたし、もちろん裏側にはドロドロした人間関係のトラブルやマネージメントについての、本当に知りたくもない諸事情が渦巻いていたのです。
そんなこんなは、2002年になって世に出たCD4枚組のボックセット「ラストワルツ完全版」とリマスター版DVDによって、ますます顕著になりましたが、実はそれでも、この大イベントの全てを明らかにしていたわけではありません。
そして、ついに出たのが、本日ご紹介の3枚組映像集です。
結論から言えば、当夜のプログラムを進行順に整理し、全ての演奏を収録していますが、その音源は手直しが入っていないリアルライブが基本! しかもサウンドボード直結の高音質ですから、たまりません♪♪~♪ もちろん演奏や歌のミス、そして手違いが随所にあり、それが逆にストレートなロック魂の発露として、実に最高!
ですから映像部分にしてもマーティン・スコセッシ監督の公式映画パージョンとは異なり、そこでカットされていたフィルムパートが、モノクロショットで繋がれているという芸の細かさが泣かせます。つまりマーティン・スコセッシ監督がリアルな演奏をどこでカットし、編集していったかが一目瞭然に楽しめるのです。
ちなみに、ここで繋ぎに使われているフィルムは公式映画クルーが撮影したものではなく、当日の興業を仕切った現場プロデューサーのビル・グレアムのスタッフが記録していたプロショット映像がメインになっていますので、音源との同期も細かい部分まできちんとしています。しかもそこに公式映画のアウトテイクとも思えるフィルムも巧みにミックスしてあるようですから、それが劣化していようとも、極めて自然に「ラストワルツ」の真の姿に接することが出来ました。
おまけに各パートの真相が日本語字幕で画面に出るのも、最高に親切です。
★Disc-1
01 Opening Document with Japanese Tickers
まず冒頭、この企画がスタートした経緯が短く字幕テロップで解説されますが、結局はザ・バンド側とレコード会社の対立、と同時にメンバー間の人間関係が大きな要因だとされています。
しかも当初は、この「ラストワルツ」が決して「解散」では無かったという……。
02 Up On Cripple Creek
03 The Shape I'm In
04 It Makes No Difference
05 Life Is A Carnival
06 This Wheel's On Fire
07 W.S. Walcott Medicine Show
08 Georgia On My Mind
09 Ophelia
10 King Harvest
11 The Night They Drove Old Dixie Down
12 Stage Fright
13 Rag Mama Rag
このパートは所謂「ザ・バンドのヒットパレード」です。
ロビー・ロバートソン(g,vo)、リック・ダンコ(b,vo)、リチャード・マニュエル(p,vo,ds)、ガース・ハドソン(key)、レヴン・ヘルム(ds,vo) というザ・バンドのメンバーは、これが最後のライブということで、実に気合いの入った演奏と書きたいところですが、ここでの手直しが入っていない音源や部分的にカットされたパートの映像を合せて追体験すると、荒っぽくてミスが目立ったり、あるいはそれが逆に熱気を生み出していたりして、なかなか興味深々♪♪~♪ 特に冒頭からの3連発が強烈です。
そして大きな目玉がリチャード・マニュエルがソロで歌う感涙の「Georgia On My Mind」でしょう。これは前述した4枚組ボックスセットからも外された幻の名演! このイベントの後に発売された、リアルなザ・バンドとしての最後のスタジオアルバム「アイランド」に収録のバージョンよりも、確実に素晴らしいのは保証付きです。
また同じく公式には幻化している「King Harvest」にしても、途中でリチャード・マニュエルのボーカルがヘロヘロになりますから、理由はわかるんですが、これが非常に味わい深いですねぇ~♪
個人的には「Rag Mama Rag」で圧巻のローリングピアノを披露するガース・ハドソンの熱演にも、シビレがとまりませんでした。
14 Who Do You Love / Ronnie Hawkins
15 Such A Night / Dr.John
16 Down South In New Orleans / Bobby Charles & Dr. John
17 Mystery Train / Paul Butterfield
18 Caldonia / Muddy Waters
19 Mannish Boy / Muddy Waters
20 All Our Past Times / Eric Clapton
21 Further On Up The Road / Eric Clapton
22 Helpless / Neil Young
23 Four Strong Winds / Neil Young
このパートは「ザ・バンド&ゲスト」というコーナーで、何れも大スタアという所縁の面々が登場し、ザ・バンドをバックした熱演を披露しています。
しかし、この裏側では短期間でゲストと共演する演目を覚えなければならなかったザ・バンドの戸惑いがあり、流石の凄腕メンバー達も些かポロを出しているのが、このリアルな音源と映像にはしっかりと記録されていますが、それでもやっぱり1970年代ロックの魅力が薄れているなんてことはありません。次々に登場してくるゲスト達、それぞれの熱演とリアルな個人的事情も興味を誘います。
特にブルースの巨匠たるマディ・ウォーターズに関しては、主催者側からキャンセルを申し入れる寸前の非礼があったという、実に驚くべき裏話がっ! しかしこれにはレヴォン・ヘルムが大激怒! この企画そのものにも反対していた経緯もあり、結局はマディ・ウォーターズとの共演を条件に「ラストワルツ」が進行したという真実も語られています。しかしそんな気合いが空回りしたのでしょうか、「Mannish Boy」の最初のキメのリフで、リック・ダンコは音を出しそこねていますから、公式フィルム&音源のペースパートは、完全にスタジオでのオーバーダビングだと知られて……。
またニール・ヤングは、ほとんど悪いクスリにどっぷりですねぇ……。詳しくは書きませんが、明らかに公式フィルムでは映せない部分、さらに「Four Strong Winds」でのヘロヘロな歌詞の間違いとか、流石にカットされた実状を痛感させられますよ。
しかし確かに名演もあって、エリック・クラプトンの未発表映像となった「All Our Past Times」の和んだ雰囲気は秀逸ですし、イントロのギターソロでストラップが突然外れてのハプニングが名演となった「Further On Up The Road」では、中間のギターソロがやっぱり少しカットされていたことが詳らかにされています。
あと、ボビー・チャールズやドクター・ジョンの雰囲気の良さは絶品♪♪~♪ 特に前者の「Down South In New Orleans」は、公式映画では全てカットされたのが不思議なほどの名演だと思います。
★Disc-2
01 Coyote / Joni Mitchell
02 Shadows and Light / Joni Mitchell
03 Furry Sings the Blues / Joni Mitchell
04 Dry Your Eyes / Neil Diamond
05 Tura Lura Lural (That's An Irish Lullaby) / Van Morrison
06 Caravan / Van Morrison
07 Acadian Driftwood / The Band, Neil Young & Joni Mitchell
このパートもザ・バンドがバックアップするゲストコーナーの続きです。
まずジョニ・ミッチェルが本当に素晴らしく、正規映像版でも魅力的だった「Coyote」のジャズフュージョンしまくった歌と演奏には、やっぱりシビレますねぇ~♪ 独特の変則コードワークでギターを弾き、真摯に歌う彼女の姿は凛としていますから、浮遊感に満ちた曲調が尚更に輝くのでしょう。ただし、ここでのリック・ダンコのペースワークは、ほとんどがルートの音を出しているだけというか、正規音源とは大きく異なっています。それはもちろん、後のスタジオ作業でダビングされ直したものなんですが、ジョニ・ミッチェルのオリジナルバージョンでは、ジャコ・バストリアスが驚異のベースプレイを披露していましたからねぇ。いくら名手のリック・ダンコにしても、ライブの現場では些か分が悪いということでしょう。ただし完成された正規音源におけるリック・ダンコのフュージョンベースも、独特の味わいがありますから、私は好きです。
そして正規映像版ではカットされた以下の演目では、ほとんどメドレーとなって続く「Shadows and Ligh」が、これまた最高! 幻想的な味わいを見事に演出するロビー・ロバートソンのギターやガース・ハドソンのキーボードも流石の一言です。
しかし二―ル・ダイアモンドの場面は、正規映像版でも些か精彩がありませんでしたが、ここで明らかにされたノーカットの映像でも、やはり同じ……。その真相はグループ内の人間関係にもあるらしいことが、テロップで紹介されています。
で、そんなモヤモヤをブッ飛ばすのが、続くヴァン・モリソンの登場です!
ただし、ここでも様々なゴタゴタがあって、当日に予定されていた「Tura Lura Lural / アイルランドの子守唄」が始まっても、本人が出てきません。どうやら衣装が気に入らなかったと解説されていますが、それをフォローしたのがリチャード・マニュエルの泣き節ソウル♪♪~♪ 本当にシミジミと魂を込めて歌い始めるその瞬間から、ステージと会場にはジワジワと感動が広がっていきます。
すると、それに触発されたかのようにヴァン・モリソンが、ついに登場! 途中からそれを引き継ぎ、熱血とソウルが溢れ出た圧巻の名唱を披露するのです。
あぁ、これは凄いですねぇ~~♪
何度観ても震えが止まらないほどに感動します。
これを正規映像版からカットしてしまったのは、マーティン・スコセッシ監督の大ミステイクだと不遜にも言い切りたいほど!
ちなみに、この2人の熱唱と言えば、ザ・バンドの名盤「カフーツ」に収められている「4% Pantomime」があまりにも有名ですが、それもやって欲しかったですねぇ。もしライブで聴けるのなら、全てを投げ打つ覚悟をしているサイケおやじですが、今はそれも幻になったのは残念至極です。
プログラムはこの後、映画でも名場面となった「Caravan」の大熱演へと続きますが、そこでさえ、このネイキッド版を観ると、かなりのカットがあることに、ちょっとショックを受けるかもしれません。しかし、ここでのヴァン・モリソンのパートは、1970年代ロックの決定的な歴史の一幕として残された世界遺産になると確信しています。
08 Intermission
09 Poetry Reading
このパートは前半から後半に引き継がれる休憩時間で、当時の貴重な資料や写真がスライドショウのように楽しめますし、噂になっていた如何にもサンフランシスコらしい「詩の朗読」が、動く映像で追体験出来るという、なかなかマニアックなものです。
10 Method
11 Chest Fever
12 Theme From The Last waltz - Evangeline (concert version)
13 The Weight (concert version)
続いて実質的な後半のスタートはザ・バンドの演奏で、まず「Method」はガース・ハドンソが様々な音のコラージュやキーボードを駆使して聞かせるプログレっぽい一人舞台ですが、「Chest Fever」へと続く流れは当時のステージでは定番だったようです。もちろん、これまで全く謎に包まれていた完全ロングバージョンですよ。
そして、さらに貴重なのが今回のテーマソング「Theme From The Last waltz」の当夜のライブバージョンでしょう。正直言えば、一期一会の演奏ゆえに、ザ・バンドにしては、些かのポロも露呈していますから、後に出された改訂版4枚組ボックスからも外されたのは当然という結果です。それゆえ、ここにはリアルタイムの面白さが味わえる海賊盤の楽しみがあるのですが、まあ、十人十色の感想かもしれません。
ただし、これも正規映像版からは外された「The Weight」のコンサートバージョンは、汚名返上ともいうべき名演ですから、流石だと思います。
★DISC-3
01 Baby Let Me Follow You Down / Bob Dylan
02 Hazel / Bob Dylan
03 I Don't Believe You / Bob Dylan
04 Forever Young / Bob Dylan
05 Baby Let Me Follow You Down (reprise) / Bob Dylan
こうして迎えるクライマックスが、ザ・バンドを従えたボブ・ディランという、これまたロックの歴史を検証するには相応しい共演が楽しめます。ただし舞台裏では映画撮影におけるボブ・ディランの出演場面や演目についてのゴタゴタが、ここに至っても解消されず……。現場ではスタッフと主催者側の混乱が相当にあった経緯がテロップで流れます。
しかしステージ上では、そんなの、かんけー、ねぇ~!
まずはボブ・ディランが1962年のデビューアルバムでも歌っていた黒人フォークブルースの「Baby Let Me Follow You Down」を、ザ・バンドの熱演とともに、ド迫力のハードロックに改変して披露します。もちろんこれも正規映像版では観ることが叶わなかった名場面ですから、歓喜悶絶♪♪~♪ ボブ・ディランの激した歌いっぷりも最高ですよ。
それはザ・バンドとの共演アルバム「ブラネット・ウェイヴス(Asylum)」に収録されていた中でも、特に地味だった「Hazel」が、情熱的な名唱・名演になっていることでも、当夜の盛り上がりが眩しいほどに追体験されるのですから、たまりません。
もちろん続く「I Don't Believe You」や「Forever Young」も熱気と威厳とロックの魂が溢れる名場面といって過言ではないのです。
さらにボブ・ディランとザ・バンドは、その場のノリで再び「Baby Let Me Follow You Down」を歌い、演奏し始めるのですが、これは完全に予定外だったらしく、現場も混乱! ついにボブ・ディラン側のスタッフが映画の撮影を中止させようとしたとか、これも当時の裏話が興味深いところでしょう。
う~ん、それにしても、ディラン&ザ・バンドって、本当に魅力がありますねぇ。間近いなく、ロック最高の瞬間を作り出せる組み合わせだと思います。
06 I Shall Be Released / Bob Dylan
そしてついに大団円!
当日の出演者のほとんどに加え、リンゴ・スターやロン・ウッドまでもが登場したフィナレーは、もうこれしか無いの名曲・名演です。
いゃ~、なんともせつなくなってきますねぇ。これは私のような中年者だけではないと思いたいところではありますが。
07 Jam #1
08 Jam #2
これは予定外に行われたジャムセッションの場面で、そのきっかけはリンゴ・スターとレボン・ヘルムのドラム合戦というのが、「Jam #1」です。これは音源だけは公式発売されていますが、正直、それだけでは面白くありませんでした。なにしろ演奏そのものがシンプルというか、遠慮気味でしたからねぇ。
それが映像となると俄然、興味深々!
ワンコードのジャムセッションらしく、登場したギタリストはそれなりに相手を立てる事に終始しているのは勿体無いかぎりですが、少しずつ熱くなっていくところは、如何にも当時の雰囲気です。
ただし映像フィルムが途中で終わり、音声だけになっているのは残念……。
それは「Jam #2」でも同様で、このパートは近年にリマスターされたDVDのボーナス映像でもご覧になれますが、むしろ演奏に纏まりが出てきた分だけ、なおさらに……。しかしレゲエなムードからブル~スに展開されていくあたりには、ゾクゾクさせられますよね。
ちなみに参加メンバーは字幕でしっかりと出ますから、ご安心下さい。個人的にはニール・ヤングとスティーヴン・スティルスが並び立つ場面に感涙♪♪~♪
09 Don't Do It
この演奏は劇場版映画では最初にありましたが、実は最後の最後にアンコールで登場したザ・バンドの勇姿です。
これを巧みな編集で纏めたマーティン・スコセッシのミエミエな手法は、本当に憎めませんねっ。やはり流石だと思います。
ちなみにそこで楽しめたは、後にホーンがダビングされ、2分半ほどに編集されたバージョンですが、リアルタイムではザ・バンドだけの演奏でした。
そのあたりを今回のブツでは、ホーンがダビングされた後のコンプリートバージョンを使い、映像パートの欠落は上手く他の部分を入れこんで仕上げた労作になっています。
★ボーナストラック
01 The Weight Studio Performance'76 / The Staple Singers
02 Evangeline Studio Performance'76 / Emmylou Harros
03 Forever Young / Bob Dylan
04 Baby Let Me Follow You Down (reprise) / Bob Dylan
05 I Shall Be Released / Bob Dylan
このパートはザ・バンドとボブ・ディランの名曲名演の中から、歌詞が特に難解と言われているものを選び、丁寧に日本語訳をつけた字幕で楽しめる企画です。
まず「The Weight Studio Performance'76」は、劇場公開版を仕上げるために行われたスタジオセッションで、彼等が尊敬するステイプル・シンガーズとの共演でしたから、殊更にゴスペルムードが高まり、その宗教的な歌詞の味わいも強くなっているようです。
まあ、正直言えば、キリスト教徒でもユダヤ教徒でもない私には???なんですが、それでも人生の重荷を下ろすという、究極の安らぎを歌ったらしいということは、なんとなく理解出来ます。
そしてステイプル・シンガーズのディープな素晴らしさ、ザ・バンドが共演で目指したものが痛感されるのでした。実に名演!!
それは続くトラックでも、確実に楽しめますから、ここは観てのお楽しみと致しますが、それにしてもエミール・ハリスの清涼な佇まいと天使の歌声には、いろんな思惑やゴタゴタが虚しくなる魅力がありますねぇ♪♪~♪
また「I Shall Be Released」は幾つもの解釈があるとされてきましたが、ここでの翻訳は一期一会と人生の最期を歌ったような、ある種の諦観には、ちょいと驚きました。
ということで、「ラストワルツ」を追体験出来るブツとしては、過去最高じゃないでしょうか? なによりも名作映画とされていた、その制作過程の内幕やマーティン・スコセッシ監督の手腕の一端が、それなりに堪能出来るのは、私にとっては大きな喜びでした。
既に述べたように、それを補完しているのがモノクロパートの映像なんですが、惜しむらくは、その鮮明度がイマイチ……。これはカラーをモノクロに落として焼き付ける場合には当たり前のことなんですが、やはり海賊盤ゆえに、その補正が上手くなかったのです。
ただし、逆に言えば、公式版から流用した映像との対比が、より明確になっているのも、また事実ですし、何よりもダビングも手直しもされていないリアルな音声との同期も厳密に調整されていますから、これ以上言うのは贅沢ってものだと思います。
1970年代ロックの素晴らしき瞬間を、ぜひともお楽しみ下さいませ。