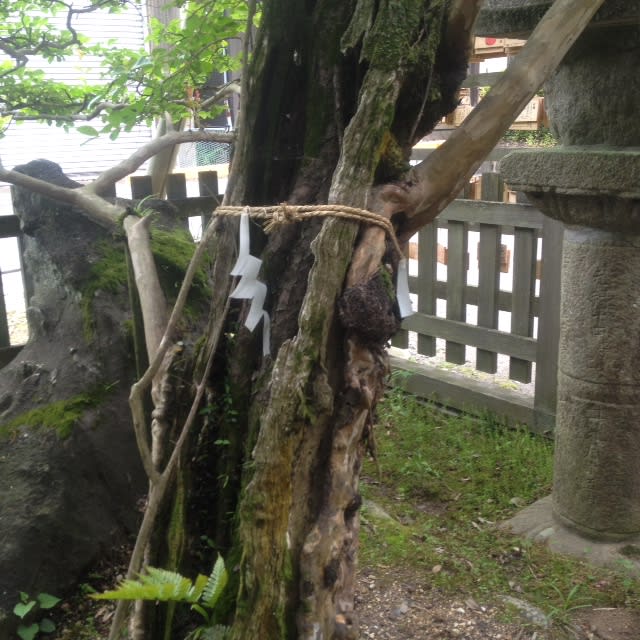東山道を探していて、おそらくこのあたりを通っていたのだろうと思う付近にある
小さな山のようなものが、何なのかずっと疑問でした。
画像です

通り過ぎて東から

さらに南から

こちらのHPに載っていました
各務ヶ原市のHPでしょうか。
結果、古墳でした。正式名は、「鵜沼西町4号墳」とのこと。
4号墳の位置は、こちら
古墳の上に登ると

前回、歩いた愛宕山、そして双子山が見えます
この辺りは、古墳だらけのようです。しかし、現存している古墳は、ごくわずかです。
地図に位置を書き込んでみます。

7号墳まであったようです。
鵜沼西町1号墳(衣装塚古墳)は、前方後円墳が、削られたかもしれないとのことですけど、残っています
横から見ると
4世紀末~5世紀前半に築造されたと考えられるそうです。
3号墳(一輪山古墳)は、三角縁神獣鏡が、出土した古墳ですけど、現在はありません。
そのあたりの画像です
ウィキペディアより引用です
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一輪山古墳から出土した銅鏡は、三角縁波文帯四神二獣鏡と呼ばれ
3世紀後半に、中国において製作されたといわれる三角縁神獣鏡と呼ばれる鏡。
この鏡と同じ鋳型から製作された鏡が島根県松江市新庄町八日山1号墳から1面出土している
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ひょっとすると、一輪山古墳は、3世紀後半若しくは,4世紀前半のものかもしれませんね。
4号墳は、どうなんだろう?
このあたりの地形は、西、北、東を山に囲まれて南が木曽川、そして、平野。
これって、風水じゃない?
3世紀に風水があったかどうかは知りませんけど、暮らすにはいい地形かもしれませんね
木材が豊富で、魚も取れる、水も豊富で、稲もできる。
各務ヶ原という地名は、どこからきたのでしょう?
各務=鏡と思うのですけど
この一輪山古墳にあった「三角縁波文帯四神二獣鏡」からなのでしょうか?
謎です。
小さな山のようなものが、何なのかずっと疑問でした。
画像です

通り過ぎて東から

さらに南から

こちらのHPに載っていました
各務ヶ原市のHPでしょうか。
結果、古墳でした。正式名は、「鵜沼西町4号墳」とのこと。
4号墳の位置は、こちら
古墳の上に登ると


前回、歩いた愛宕山、そして双子山が見えます
この辺りは、古墳だらけのようです。しかし、現存している古墳は、ごくわずかです。
地図に位置を書き込んでみます。

7号墳まであったようです。
鵜沼西町1号墳(衣装塚古墳)は、前方後円墳が、削られたかもしれないとのことですけど、残っています

横から見ると

4世紀末~5世紀前半に築造されたと考えられるそうです。
3号墳(一輪山古墳)は、三角縁神獣鏡が、出土した古墳ですけど、現在はありません。
そのあたりの画像です

ウィキペディアより引用です
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一輪山古墳から出土した銅鏡は、三角縁波文帯四神二獣鏡と呼ばれ
3世紀後半に、中国において製作されたといわれる三角縁神獣鏡と呼ばれる鏡。
この鏡と同じ鋳型から製作された鏡が島根県松江市新庄町八日山1号墳から1面出土している
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ひょっとすると、一輪山古墳は、3世紀後半若しくは,4世紀前半のものかもしれませんね。
4号墳は、どうなんだろう?
このあたりの地形は、西、北、東を山に囲まれて南が木曽川、そして、平野。
これって、風水じゃない?
3世紀に風水があったかどうかは知りませんけど、暮らすにはいい地形かもしれませんね
木材が豊富で、魚も取れる、水も豊富で、稲もできる。
各務ヶ原という地名は、どこからきたのでしょう?
各務=鏡と思うのですけど
この一輪山古墳にあった「三角縁波文帯四神二獣鏡」からなのでしょうか?
謎です。