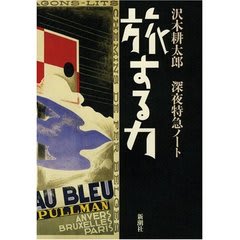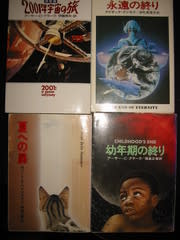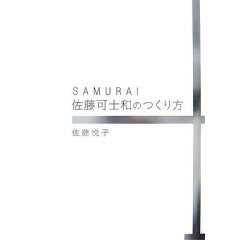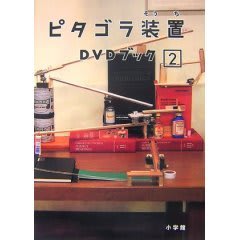観光バスに乗って観光地をめぐる旅行なら、ガイドブックには、観光地に関する解説が載っていさえすれば事足りる。ところが、「地球の歩き方」シリーズ(ダイヤモンド社)は、その名のとおり、どうやって現地を「歩く」か、つまり、移動手段とか宿泊施設に重きを置いて作られたガイドブックでした。しかも、実際に現地を旅した経験者によるナマの情報が掲載されていることも、それまでのお仕着せのガイドブックにはない魅力でした。 . . . 本文を読む
藤原新也のロングセラー『メメント・モリ』の初版は昭和58年(1983)2月12日。それから25年を経た今、「21世紀エディション」として刷新されました。
ニンゲンは犬に食われるほど自由だ。
あのショッキングな写真を見た時の衝撃は、今でも忘れられません。えっ、そういうのって「自由」って言うの…? それが「自由」だとしても、死んでから犬に食われるのだけはいやだなあ…と思ったものでした。あれから . . . 本文を読む
田宮俊作『田宮模型の仕事』(1997年、ネスコ/文藝春秋)。加筆された文庫バージョンも出ていますが、この本は、単行本の表紙がいい。タミヤのプラモデルの白い箱、「ホワイトパッケージ」を思わせる白地に、TAMIYAの二つ星マーク、そして真ん中に描かれているのは、小さな接着剤のチューブ。そう、タミヤのプラモデルに付属品としてついてきた、キャップのない小さな接着剤です。なぜキャップがついていないのかは未だ . . . 本文を読む
ロバート・A・ハインライン、アイザック・アシモフと並んで、「三大SF作家」と言われるアーサー・C・クラークが亡くなりました。これで、SFの一つの時代が終わったと言ってもいいでしょう。
アシモフは、「ロボット工学3原則」の提唱者。彼の説いたロボットや人工知能と人間との関係は、のちのSF界に大きな影響を及ぼしたことは言うまでもありません。もちろん手塚治虫の「鉄腕アトム」を含めて。アシモフ作品では、私 . . . 本文を読む
「アートディレクター」なんだそうである。そういう仕事をする人はこれまでいなかったので、「佐藤可士和」が「アートディレクター」という仕事を世に広めていくようにしたい、と佐藤悦子は語る。佐藤悦子は佐藤可士和のマネージャーであり、妻である。この本は、その佐藤悦子が振り返るこれまでの佐藤可士和と、彼とともに築き上げてきた「SAMURAI」のこれからの展望を記したものです。
佐藤可士和という人は、正直あま . . . 本文を読む
今日は「猫の日」だそうです。222で、にゃんにゃんにゃん。たわいもないというか、単純というか。制定したのは、その名も「猫の日制定委員会」だそうで、背後(?)にはペットフード工業会という団体が。ってことは…と思って調べてみると、案の定、「犬の日」ってのもあって、こちらはわんわんわんで11月1日。…やっぱりたわいもないワン!
なんか調べている中で、イタリアの猫の日というのを見つけました。なんとイタリ . . . 本文を読む
平田オリザは、私とほぼ同年代の劇作家・演出家。最近はテレビのコメンテーターとしても時折登場していますね。
彼は16歳の時、高校を休学して自転車で世界一周の旅を経験しています。その旅を綴ったのが『十六歳のオリザの未だかつてためしのない勇気が到達した最後の点と、到達しえた極限とを明らかにして、上々の首尾にいたった世界一周自転車旅行の冒険をしるす本』。冒険の旅に憧れていた20数年前の私は、彼が世界各地 . . . 本文を読む
「かぐや」の記事で触れたNASA(アメリカ航空宇宙局)で思い出したのが、ダン・ブラウンの『デセプション・ポイント』(角川文庫、越前敏弥訳、2006年)です。
ダン・ブラウンといえば、『天使と悪魔』(2000年)、『ダヴィンチ・コード』(2003年)のいわゆる“ラングドン・シリーズ”。この作品は、日本では、『ダヴィンチ・コード』のヒットを追う形で刊行されましたが、執筆そのものは2001年なのだそう . . . 本文を読む
ベルギー発の漫画「タンタン」シリーズの1作が、「植民地主義的」で「人種差別的な表現」があるとの理由で、英国や米国で抗議の運動が起こっているというニュース。
やれやれ、ですね。
『ちびくろサンボ』をはじめとして、この種の話は引きも切らない。
「タンタン冒険旅行シリーズ」は、少年記者タンタンが愛犬スノーウィとともに、世界中(月までも!)を冒険する物語です。作者はベルギー・ブリュッセルで新聞記者を . . . 本文を読む
現在公開中の「ハンニバル・ライジング」(未見ですが)は、トマス・ハリス原作による「羊たちの沈黙」、「ハンニバル」、「レッドドラゴン」の主役であるハンニバル・レクターの「誕生」を描く映画。この手のスタイルは、ジョージ・ルーカス原作、 スティーブン・スピルバーグ監督による「インディ・ジョーンズ」シリーズでも、テレビ映画として「ヤング・インディ・ジョーンズ」が作られたように、けっこうよく見られるスタイル . . . 本文を読む
何をかくそう、私はカエルが好きである。
ただ、どんなカエルも好きかと言うと、決してそんなことはなくて、イボガエルとかウシガエルとかツチガエルのように巨大なカエルはあんまり得意ではない。というより、はっきり言って図体がデカすぎて気持ち悪い! しかしだからといって小さければいいというわけでもなくて、アマゾンとか東南アジアのジャングルに住むけったいな色をしたカエルなんてぇのも受け付けない。
私が好き . . . 本文を読む
米国漫画「トムとジェリー」なんかによく出てきますが、押したり引いたり、斜面を滑り落ちたりといった単純な動きの連鎖で、最終的に思いがけない結果を見せてくれるという「仕掛け」があります。こうした仕掛けを描いた漫画を多く残した米国の漫画家、ルーブ・ゴールドバーグRube Goldberg (1883-1970) に因んで、「ルーブ・ゴールドバーグ・マシン」と呼ばれます。
ルーブ・ゴールドバーグ・マ . . . 本文を読む
「4 「優しさ」という名の暴力」、「5 「察する美学」から「語る」美学へ」で、中嶋氏は、騒音に対する自身の闘争と同じくらい、「ぶっ飛んだ」主張を展開しています。彼に「攻撃」を受けた人はもちろん、多くの日本人は彼の主張に納得することはできないのではないかと思います。
まずは「「優しさ」という名の暴力」。吉野弘氏の有名な詩「夕焼け」を取り上げつつ、日本では、「他人に対して優しいのみならず、他人が自分 . . . 本文を読む
一見、厳しいおっさんがとんでもないことを言っている、ように見えて、実はよく読むと、いたって正論である。こういう類の本は、林道義氏の『父性の復権』、『母性の復権』(いずれも中公新書)以来のような気がします。
この本は、いたるところ騒音だらけの日本社会に果敢に挑む一人の大学教授の物語です。単行本での初版は1996年と相当前ですが、このたびようやく読むことができました。
彼、中島氏の「闘争」にはホン . . . 本文を読む
佐藤雅彦さんってのは、ホントに日常を「考えながら」生きている人なんだなと思います。
『プチ哲学』(中公文庫)というのがあります。お得意の絵(漫画)と文章でつづる日常の一コマから糸をたぐり寄せるように「哲学」にアプローチしていく。「モノ」が意識を持っていろんな行動をするのが最高に楽しい。
たとえば、テレビ売り場のリモコンが、1台だけスイッチの入っていないテレビを「あいつだけさぼって寝ている」なん . . . 本文を読む