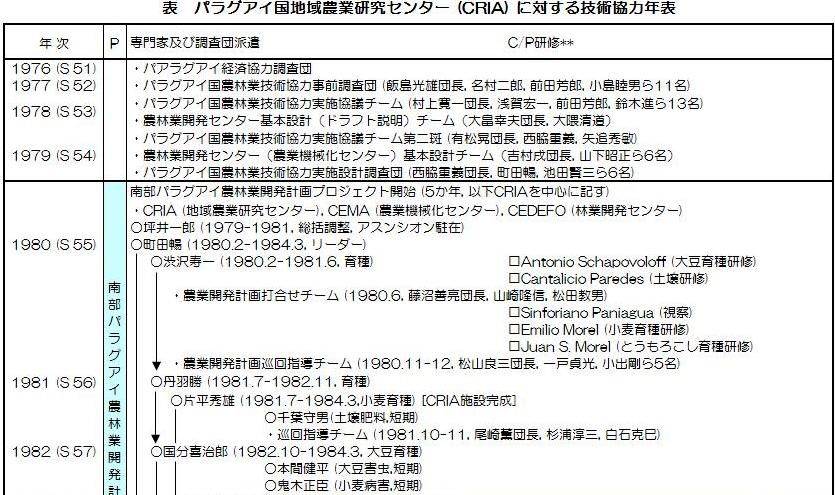南米の樹-1
パラグアイを離れるとき,一人のアミーゴから記念にと「レリーフ」を頂戴した(写真)。パラグアイの形を象った木製のレリーフで,ガラニー語とスペイン語で家族のメッセージが添えられている。中央のパラグアイ地図は,異なる種類の木材を各県の形を象ったブロックに切り取り,それらを組み合わせてある。
パラグアイ共和国は,南米大陸のほぼ中央に位置し,ブラジル・アルゼンチン・ボリビアに囲まれた内陸国である。パラグアイ河が国土の中央を北から南に貫流し,その東部(国土の4割を占める,降水量1,600-1,800mm)は肥沃な農耕地で99%の人口が集中している。この地域は今でこそ,大豆,小麦,牛肉など輸出産品の生産地となり国家経済を支えているが,昔は広大な原生林(乾燥熱帯林)が広がっていた。因みに西部地域は塩分の多い湿地とサバンナで,降水量1,100mm,森林植生としては乾性熱帯低木林地帯である。
1950年以前は,パラグアイ国土の70%が天然林で占められ,木材輸出が外貨を稼いでいた時代であった。1950年以降,森林が切り開かれ農牧地への転換が進み,さらに1960年代には大型農業機械の導入が無秩序な森林伐採を促し,森林は20%まで減少した。その後政府は伐採規制を強めたが(1967年「丸太輸出禁止令」,1973年「森林法」制定,1992年「天然林の商業的伐採規則例」),効果は顕著でなく,1990年代には10%にまで減少した。当国の森林率推移を示す言葉として,「過去70%,今10%・・・」としばしば表現される(参照:植松龍太郎,パラグアイで生かされた日本の林業普及)。
JICAは1995~2001年「林業普及指導事業」を展開し,さらに21世紀に入っては日本のNPO団体なども植林活動に協力している。また,パラグアイ政府は,河川両岸の一定幅の伐採を禁じ,所有地の一定率面積に植林を義務づけるなどの法律を定め,森林保護に努めている。栄華を誇った文明が消え去った過去の歴史のように,「森が枯れて,農業が廃れ,やがて人類が滅亡した」とならないことを願うばかりだ。
FAOSTAT によれば,2010年パラグアイの林業生産量は4,800 million m3と推定され(他の数字もある),その内訳は丸太材70%,製材8%,パネル材6%,再生紙を含むパルプ材8%,紙8%となっている。丸太材の中身は燃料用(薪炭)が38%で,この比率が最も高い。パラグアイに滞在していた頃,トラックに山積みされた木炭が,北部のカニンデジュ県から国境を越えてブラジルに渡るのをよくみかけた。アサード(焼肉)には木炭を使うが,その需要だけでも馬鹿にならない。
レリーフには,トレボル,ラパチョ,インシエンソ,セドロ,ケブラッチョ,パロサント・・・の名前が読み取れる。それぞれ,パラグアイ,アルゼンチン北部,ブラジル・パンタナールなどの地域に植生がみられる固有樹木で形成されている。パラグアイには小さな製材所が各地にあり,これらの稀少材を日本が輸入している事例も見られる。
中には乱伐が進み貴重樹種となっている樹木もあるが,材質,色,香りに特長ある材が多い。これら材の特性を生かした家具,民芸品の人気が高まっている(写真)。