万葉雑記 番外雑話 万葉時代の遣唐使の航路
今回もまた備忘録のようなものとなっており、万葉集の歌の鑑賞には直接には関係しません。ただし、万葉時代は唐の文化や制度を取り入れ、社会を大改革する時代です。その時代の基盤を支えた遣唐使やその遣唐使を運んだ船舶を知ることは、多少、意義はあると考えます。
さて、万葉時代、遣唐使は国家の一大事業です。当時にあって、旧態とした社会を近代国家へと変身させる大事業の遂行中にあって、必要な知識や技術を導入するためには唐への遣唐使派遣は必要不可欠です。一方、大陸の唐は伝統的に管理貿易を実施しており、海上交通路を使い、不定期に朝貢する遠夷国に区分される日本は、朝貢・下賜の形を取る朝貢交易以外、表立った貿易を行うことは唐の商業管理制度からすると出来ません。密貿易や蕃夷国区分で毎年朝貢の中で交易が許された渤海や新羅を経由する形で書籍や物品の調達は可能ですが、日本からの遠隔的な要望書通りに調達し、日本に運ぶことは非常に困難性があります。国家レベルの法制度や学問の整備では一そろいの資料・書籍が必要です。
この大陸側の管理貿易体制を反映するかのように遣唐使の帰国に合わせて、飛鳥・奈良時代の漢文文化水準は階段状に進化・発展します。万葉集でも山上憶良の帰国頃から『遊仙窟』を引用したもの、李善の『文選注』を引用したものが見られるようになります。特に大伴旅人と藤原房前との相聞となる「謌詞両首」の作品などのように李善の『文選注』を知らないと解釈が困難なものがありますから、遣唐使が持ち帰った漢籍は非常に重大です。それを示すように、養老元年の多治比県守を代表とする遣唐使は長安の市中の書籍、すべてを購入・持ち帰ったと唐側は驚きを持って記録します。
ここで、その遣唐使に話題を振りますと、現在、遣唐使の航路の解説では「北航路」と「南航路」の二航路を示し、日本と新羅との外交関係が良好な時は、その航路として朝鮮海峡を横断し、さらに朝鮮半島西岸を北上、その後、甕津半島(現在の北朝鮮黄海南道)から渤海海峡を横断して冊封国を受け入れる山東半島 登州港(現在の山東省煙台市)や莱州港(山東省東栄市)に向かう「北航路」を採用したとします。
他方、一旦、日本と新羅との外交関係が悪化すると、朝鮮海峡を横断した直後に半島への寄港や西岸北上を行わずに真西に転進し、東シナ海(現在の東海)を横断して大陸の揚子江(現在の長河)河口に位置する越州会稽県須岸山(現在の浙江省舟山市 舟山諸島)を目標とする「南航路」を使用したとします。(注意;越州は隋朝大業元年(605)以降の名称で、それまでは呉州)
ただし、唐が定めた冊封制度では山東半島の登州港や莱州港は毎年に朝貢貿易を行う蕃夷国区分の新羅や渤海に許された港であり、不定期に朝貢する遠夷国に区分された日本にはその山東半島の港への入港が許可されていなかった可能性があります。なお、後漢から梁時代、日本は呉州会稽太守が管理する夷洲(台湾)及び亶洲(日本)に区分されていますから、これを唐が踏襲しますと日本は越州(旧呉州)会稽太守の管轄となり、唐の冊封制度では杭州湾の紹興(現在の浙江省紹興市)が入港地となります。ちなみに新羅は朝貢貿易を維持する為に、唐・新羅戦争中も冊封国の立場を放棄していませんから、密貿易などの抜け道がないほどに唐側の貿易管理は厳しく行われています。
ここで、遣唐使について言葉を確認したいと思います。私のような凡なる人間は、根がそそっかしいので、遣唐使とは日本の京(飛鳥の宮/平城京/平安京)から唐の京(長安)への勅使による外交団派遣と思い込みます。一方、歴史の専門家は遣唐使を唐国へ派遣された使者と文字通りに理解します。このため、遣唐使の最初の渡航先が取次と伝送の義務を負う冊封国の新羅や朝鮮半島の唐国の出先機関である熊津都督府でも唐国への使者の経路となります。この場合、従来の滅亡前の百済への渡航経路との違いが出て来ません。
そこで、弊ブログでは「遣唐使」とは冊封国の新羅に取次・伝送を求めない日本の京から唐の京への勅使による外交派遣団と定義します。つまり、斉明天皇三年(657)から四年にあった沙門智通、智達たちの奉勅を下に新羅船に便乗した唐入国や、舒明天皇四年(632)の新羅送使に頼って帰国した舒明天皇二年(630)の遣唐使 犬上君三田耜は弊ブログの定義する「遣唐使」に含めません。『日本書紀』からすると遣唐使 犬上君三田耜は往路でも自前の船団を持っていませんから、唐から招聘/招待を受けた遠夷国である日本が取次と伝送の義務を負う冊封国 新羅の新羅船を使い、唐の窓口 莱州港へと伝送されたと考えます。一般的なイメージの「遣唐使」とは違うのです。彼は、ある種の業務連絡としての唐への使いです。
ここで、従来の認識と異なる話をもう少し紹介します。
壬申の乱の時に大海人皇子が吉野を脱出し陸路、桑名郡家に到着した時に、紀伊国を支配する紀臣阿閉麻呂が既に桑名郡家で待機していました。その紀臣は欽明天皇の時代、朝鮮半島の安羅日本府で韓婦を娶って子を生し、その子、紀臣奈率弥麻沙が百済の武人になるなど、古代にあって紀伊国から朝鮮半島との海上交通能力を持つ一族です。その紀臣阿閉麻呂が戦争を前提に紀伊国から伊勢国桑名郡家に陸路以外を使って到着していますから、当然、軍船を率いて紀伊半島を廻っての出兵です。壬申の乱の時、その紀伊水軍の威力により、二万の軍勢を持つ尾張国司守の小子部連鋤鉤は熱田から桑名への伊勢湾渡海作戦と桑名郡家への攻撃が出来ずに無戦闘のままに降伏した訳です。
次に応神天皇の枯野の伝承が示すように、古代から伊豆国は朝廷の重要な造船拠点であります。加えて奈良時代の軍船建造とその回航の記録、また、国司や防人などの公人の行動記録、延喜式に載る交易雜物の分量などから、難波大津から紀伊半島、伊勢湾と巡り、遠江国国府(大之浦)、伊豆国御嶋への大船の直航路があったと推定されます。この航路の中で難波からの最初の太平洋の風待ち港である紀伊国加太湊から伊豆国御嶋までは海上航路で約470kmです。不思議ですが、飛鳥時代、遣唐使航路で「呉唐之路」と称された、朝鮮半島の沖合、百済南畔之嶋(現在の済州島北岸)から越州(隋朝大業元年に「呉州」から変更)会稽県須岸山(現在の浙江省 舟山市舟山諸島)までの海上航路は約500kmです。外洋航海の距離からすると奈良時代の太平洋航路と遣唐使航路とは大差がありませんから、当時の日本が保有する船舶の性能や造船技術からすると遣唐使渡海への制約は無かったと考えられます。
また、養老六年(722)に「唐人王元仲始造飛舟進之。天皇嘉歎、授従五位下。」と云う記事があり、機会があれば朝廷は積極的に最新の造船技術を取り入れています。さらに「延喜式 大藏省 諸使給法」に定める入諸蕃使の規定では遣唐使の一行には船匠、鍛生、鑄生、細工生が含まれ、航海では造船技師たちを同行させることになっています。何かがあれば、船匠たちは水夫たちを使って対応するわけです。
木造船の時代ですから外洋航海に出る場合、その船に乗り込む船大工たちは、当然、十分に点検・メンテナンスをしますし、渡航先では現地の船大工たちの応援を頼むでしょう。外交使節団などの相互交流があれば、それを支える船舶の造船技術やメンテナンス技術は先進側から伝わるのです。このような背景がありますから、遣唐使時代、日本の造船技術が大陸や半島に対して落ちるかというと、制度で制限をしない限り、その可能性は低いと思います。
もう少し、上古時代の海運に触れますと、律令時代の庸調物(後には交易雜物)の割り当て分量に対し生産地から奈良の都への輸送とその貨物重量を考える時、船舶での運搬を考慮しないと人力運搬では運び切れないのです。駅馬の制度がありますが、庸調物や交易雜物の納入期間は全国一斉です。近国遠国で差がありますが、運搬距離を踏まえると陸路では主要街道に運脚キャラバン隊が集中することになります。貨物重量と運送の実務からすると、海上輸送ルートが確保されていたと考える必要があります。それを反映するように対新羅戦争の号令がかかると、全国の沿岸諸国は朝鮮海峡を越える能力を持つ軍船を建造し、それを難波大津や大宰府那珂湊に廻船します。造船技術や操船技術は即席には生まれませんから、飛鳥から奈良時代、社会は長距離の航海に耐える造船技術や操船技術を保有し、それを日常的に使っていたと考えるのが自然です。これらについては断片資料しか発見されていませんから、文献学上では長距離太平洋航路は無かった、造船技術は未熟だったと結論つけます。
気を取り直して、先に紹介した遣唐使航路の「呉唐之路」に関して、推古天皇十七年(609)に大陸の呉州(越州会稽)を出航した百済船が肥後国葦北津(現在の熊本県芦北市)に入港した事件があります。船長の申告では、事件の経緯として百済帰国を目指し呉州を出航後に暴風に遭遇し、場所が不明のままに肥後国葦北津に入港したとします。また、雄略天皇五年(461)に「呉国遣使貢献」の記事、雄略天皇十二年(468)に呉国への使いの記事「身狭村主青与檜隈民使博徳出使于呉」があり、その身狭村主青の帰国を記す同十四年の「身狭村主青等共呉国使、将呉所献手末才伎、漢織、呉織及衣縫兄媛、弟媛等。泊於住吉津」の記事があります。どうも、上古代 既に大陸の越州(旧呉州)会稽付近と朝鮮半島南端とを結ぶ航路があり、これを奈良時代には「呉唐之路」と呼び、大和の人々は大陸 揚子江方面との連絡では朝鮮海峡を渡った後に、この「呉唐之路」を使ったと思われます。つまり、南宋の趙汝适の《諸蕃志》に載る「在会稽之正東」、唐の姚思廉の《梁書・諸夷伝》に記す「去帶方萬二千餘里,大抵在会稽之東,相去絕遠。」の通りです。越州の会稽県須岸山(現在の浙江省 舟山市舟山諸島)の真東は鹿児島県薩摩半島付近ですから、概略なら会稽から見て大宰府付近はほぼ東です。大陸南部の人たちは朝鮮半島への航路「呉唐之路」を知っていますから、百済が会稽の東北東で、日本は百済の南だから日本は会稽の東にあると判断したわけです。
参考として、唐時代中期にあっても大陸側の認識では安禄山の動乱余波の中、長安から大陸を横断して山東半島を経由して渤海から日本に向かうよりも、越州の会稽から船で帰国するルート「南路」の方が安全と考えています。唐に向かうのに渤海を経由した天平宝字五年(761)の迎藤原清河使の高元度たちは帰国時には唐側の推薦に従い陸上では「南路」、海上では「呉唐之路」となるルートを採用し、大宰府に帰朝しています。その帰国のために唐朝廷は長八丈(約24m:新羅船相当の大きさ)の船一隻を造船し下賜しています。
ただ、「呉唐之路」は季節風の風向に左右されますので、陸路の治安が守られ、また、季節風の時期待ちをしない場合は、山東半島、渤海海峡横断、甕津半島、朝鮮半島西岸を南下し、朝鮮海峡横断するのが一番の確実なルートとなります。大和の歴史ではこれを「新羅道」と称したようです。
遣唐使の歴史を見ると、白雉四年(653)の高田首根麻呂を大使とする遣唐使船は「呉唐之路」を採用します。この時は二船団構成で、大使 高田首根麻呂の第一船は薩摩半島と竹島の間で難破しています。翌年の白雉五年(654)の高向史玄理を大使とする遣唐使船は「新羅道」を採用し、山東半島の北側の莱州で上陸し、陸路、長安へ向かっています。
改めて『日本書紀』と『続日本紀』を確認しますと、飛鳥から奈良時代の「遣唐使」の歴史の中で「新羅道」航路を使用したのは高向史玄理の時だけで、それ以外の「遣唐使」はすべて「呉唐之路」の航路を使用しています。ただ、もう一つの例外では玄宗皇帝時代の安禄山の動乱時代に藤原清河の救出を目的に派遣された迎藤原清河使の時で、その時は動乱の中での漂流時の現地民による殺害強奪を恐れて渤海経由を選択しています。これらの記録を参考としますと、「遣唐使」の標準海上航路は歴史的に一つで「呉唐之路」であり、現在の解説で云う「南航路」です。解説の「北航路」と称す「新羅道」は事例一回の特殊ケースのルートですから、これを「遣唐使」の正規ルートとするには無理があります。
どうも、大陸側と日本側で律令体制の制度整備が進み、唐朝の冊封体制の確立とその朝貢ルート及び担当する地方所轄の整備が終わると、日本の所轄は杭州湾の会稽が、渤海や新羅は山東半島の登州/莱州が執った可能性があります。また、冊封体制では日本が朝貢に新羅経由を望む場合、都度、冊封国新羅の斡旋と了承を受け入れる必要があります。冊封国新羅の斡旋を嫌えば、冊封体制の建前で遠夷国の日本は自力で杭州湾の会稽に行く必要があります。加えて、白雉四年の遣唐使の時、まだ、大和の友好国である百済は勢力を保っていますから、朝鮮半島の動静よりも唐側の冊封体制による都合の方が大きな比重があったと想像します。
おまけで、『隋書 俀国伝』に「俀国在百済新羅東南、水陸三千里於大海之中、依山島而居。魏時譯通中國三十餘國、皆自稱王、夷人不知里數、但計以日、其國境東西五月行南北三月行各至於海。地勢東高西下、都於邪靡堆。則魏志所謂邪馬臺者也。古云去樂浪郡境及帶方郡並一萬二千里、在會稽之東。與儋耳相近」の一文があります。
この末句の「與」を范曄の『後漢書 倭伝』の「與朱崖・儋耳相近、故其法俗多同」と同じく「又類也」の意味と理解しますと、末句の意味は民族を示すものとなり、ここでは儋耳(海南島)の人と似ているとなります。ちょうど、「梁職貢図」に描かれた倭人の姿と同じ理解です。つまり、『隋書』の「古云去樂浪郡境及帶方郡並一萬二千里、在會稽之東。與儋耳相近」の理解は、「昔、倭国の場所は後漢の樂浪郡を起点に道程を計れば一萬二千里の距離にあり、大陸を基準に考えると方角は越州会稽の東にあり、その民族は海南島の人に似ていると伝えた」となります。この地理報告書はおおむね正しいものです。
この紹介する『隋書』の文章は、隋使の報告文、魏時代の記述、それよりも古い時代の伝承の三つに構成されています。およそ、最後の文は『後漢書 倭伝』の「倭在韓東南大海中、依山㠀為居、凡百餘國。自武帝滅朝鮮使驛通於漢者三十許國、國皆稱王世世傳統、其大倭王居邪馬臺國(案今名邪摩惟音之訛也)。楽浪郡徼去其國萬二千里、去其西北界狗邪韓國七千餘里。其地大較在會稽・東冶之東。與朱崖・儋耳相近、故其法俗多同」からの引用と考えるのが相当です。ただ、隋時代の解釈では地域名の會稽が越州、東冶が福州を指し會稽・東冶では地域としては広域であること、また、朱崖が雷州半島、儋耳が海南島を指しこれまた広域であることに加え、民族に関しては雷州半島には山岳民族ミャオ族もおり、海南島海岸部の海洋民族の閩越族と風俗・風習が大きく違います。このため、『隋書』では新たな知見の下、読み手の理解での正確性を付加する為に地域では越州の會稽、民族では海南島閩越族を意味する儋耳に対象を絞ったと思われます。
このように紹介しますと、なんとも、つまらない話ですが、『日本書紀』、『続日本紀』、『隋書』、冊封の規定などを丁寧に確認すると、『後漢書 倭伝』や『隋書 俀国伝』の記述に地理学上での理解困難な記述は何もありません。万葉時代、人々はこのような理解と地理知識で遣唐使となり、大陸と交流をしていたと思います。
終わりに、弊ブログの立場は、柿本人麻呂は人生の最終盤に長門国守を務め、その任期が終わった後に長門国油谷湾から大宰府那珂港経由での帰京の途中に玄界灘で海難事故に遭い、水死したと推定しています。江戸時代にあっても大阪・江戸間の菱垣廻船航路でも年間20隻程度が海難事故に遭っているとの記録が有るそうですから、奈良時代でも遣唐使だけでなく、国内航路でも一定程度の海難事故に遭遇していたと考えます。万葉集を眺めますと沈没はしていませんが、遭難一歩手前の状況を示す柿本人麻呂の詠う讃岐狭峯嶋の歌や遣新羅使の歌群に佐婆海中の歌があり、さらに山上憶良の詠う筑前國志賀白水郎謌十首は白水郎荒雄の九州・対馬航路での海難死を悼む歌です。現代人では想像が難しいと思いますが、万葉人は旅行では一定程度の確率で人は死ぬと覚悟していたようです。
今回もまた備忘録のようなものとなっており、万葉集の歌の鑑賞には直接には関係しません。ただし、万葉時代は唐の文化や制度を取り入れ、社会を大改革する時代です。その時代の基盤を支えた遣唐使やその遣唐使を運んだ船舶を知ることは、多少、意義はあると考えます。
さて、万葉時代、遣唐使は国家の一大事業です。当時にあって、旧態とした社会を近代国家へと変身させる大事業の遂行中にあって、必要な知識や技術を導入するためには唐への遣唐使派遣は必要不可欠です。一方、大陸の唐は伝統的に管理貿易を実施しており、海上交通路を使い、不定期に朝貢する遠夷国に区分される日本は、朝貢・下賜の形を取る朝貢交易以外、表立った貿易を行うことは唐の商業管理制度からすると出来ません。密貿易や蕃夷国区分で毎年朝貢の中で交易が許された渤海や新羅を経由する形で書籍や物品の調達は可能ですが、日本からの遠隔的な要望書通りに調達し、日本に運ぶことは非常に困難性があります。国家レベルの法制度や学問の整備では一そろいの資料・書籍が必要です。
この大陸側の管理貿易体制を反映するかのように遣唐使の帰国に合わせて、飛鳥・奈良時代の漢文文化水準は階段状に進化・発展します。万葉集でも山上憶良の帰国頃から『遊仙窟』を引用したもの、李善の『文選注』を引用したものが見られるようになります。特に大伴旅人と藤原房前との相聞となる「謌詞両首」の作品などのように李善の『文選注』を知らないと解釈が困難なものがありますから、遣唐使が持ち帰った漢籍は非常に重大です。それを示すように、養老元年の多治比県守を代表とする遣唐使は長安の市中の書籍、すべてを購入・持ち帰ったと唐側は驚きを持って記録します。
ここで、その遣唐使に話題を振りますと、現在、遣唐使の航路の解説では「北航路」と「南航路」の二航路を示し、日本と新羅との外交関係が良好な時は、その航路として朝鮮海峡を横断し、さらに朝鮮半島西岸を北上、その後、甕津半島(現在の北朝鮮黄海南道)から渤海海峡を横断して冊封国を受け入れる山東半島 登州港(現在の山東省煙台市)や莱州港(山東省東栄市)に向かう「北航路」を採用したとします。
他方、一旦、日本と新羅との外交関係が悪化すると、朝鮮海峡を横断した直後に半島への寄港や西岸北上を行わずに真西に転進し、東シナ海(現在の東海)を横断して大陸の揚子江(現在の長河)河口に位置する越州会稽県須岸山(現在の浙江省舟山市 舟山諸島)を目標とする「南航路」を使用したとします。(注意;越州は隋朝大業元年(605)以降の名称で、それまでは呉州)
ただし、唐が定めた冊封制度では山東半島の登州港や莱州港は毎年に朝貢貿易を行う蕃夷国区分の新羅や渤海に許された港であり、不定期に朝貢する遠夷国に区分された日本にはその山東半島の港への入港が許可されていなかった可能性があります。なお、後漢から梁時代、日本は呉州会稽太守が管理する夷洲(台湾)及び亶洲(日本)に区分されていますから、これを唐が踏襲しますと日本は越州(旧呉州)会稽太守の管轄となり、唐の冊封制度では杭州湾の紹興(現在の浙江省紹興市)が入港地となります。ちなみに新羅は朝貢貿易を維持する為に、唐・新羅戦争中も冊封国の立場を放棄していませんから、密貿易などの抜け道がないほどに唐側の貿易管理は厳しく行われています。
ここで、遣唐使について言葉を確認したいと思います。私のような凡なる人間は、根がそそっかしいので、遣唐使とは日本の京(飛鳥の宮/平城京/平安京)から唐の京(長安)への勅使による外交団派遣と思い込みます。一方、歴史の専門家は遣唐使を唐国へ派遣された使者と文字通りに理解します。このため、遣唐使の最初の渡航先が取次と伝送の義務を負う冊封国の新羅や朝鮮半島の唐国の出先機関である熊津都督府でも唐国への使者の経路となります。この場合、従来の滅亡前の百済への渡航経路との違いが出て来ません。
そこで、弊ブログでは「遣唐使」とは冊封国の新羅に取次・伝送を求めない日本の京から唐の京への勅使による外交派遣団と定義します。つまり、斉明天皇三年(657)から四年にあった沙門智通、智達たちの奉勅を下に新羅船に便乗した唐入国や、舒明天皇四年(632)の新羅送使に頼って帰国した舒明天皇二年(630)の遣唐使 犬上君三田耜は弊ブログの定義する「遣唐使」に含めません。『日本書紀』からすると遣唐使 犬上君三田耜は往路でも自前の船団を持っていませんから、唐から招聘/招待を受けた遠夷国である日本が取次と伝送の義務を負う冊封国 新羅の新羅船を使い、唐の窓口 莱州港へと伝送されたと考えます。一般的なイメージの「遣唐使」とは違うのです。彼は、ある種の業務連絡としての唐への使いです。
ここで、従来の認識と異なる話をもう少し紹介します。
壬申の乱の時に大海人皇子が吉野を脱出し陸路、桑名郡家に到着した時に、紀伊国を支配する紀臣阿閉麻呂が既に桑名郡家で待機していました。その紀臣は欽明天皇の時代、朝鮮半島の安羅日本府で韓婦を娶って子を生し、その子、紀臣奈率弥麻沙が百済の武人になるなど、古代にあって紀伊国から朝鮮半島との海上交通能力を持つ一族です。その紀臣阿閉麻呂が戦争を前提に紀伊国から伊勢国桑名郡家に陸路以外を使って到着していますから、当然、軍船を率いて紀伊半島を廻っての出兵です。壬申の乱の時、その紀伊水軍の威力により、二万の軍勢を持つ尾張国司守の小子部連鋤鉤は熱田から桑名への伊勢湾渡海作戦と桑名郡家への攻撃が出来ずに無戦闘のままに降伏した訳です。
次に応神天皇の枯野の伝承が示すように、古代から伊豆国は朝廷の重要な造船拠点であります。加えて奈良時代の軍船建造とその回航の記録、また、国司や防人などの公人の行動記録、延喜式に載る交易雜物の分量などから、難波大津から紀伊半島、伊勢湾と巡り、遠江国国府(大之浦)、伊豆国御嶋への大船の直航路があったと推定されます。この航路の中で難波からの最初の太平洋の風待ち港である紀伊国加太湊から伊豆国御嶋までは海上航路で約470kmです。不思議ですが、飛鳥時代、遣唐使航路で「呉唐之路」と称された、朝鮮半島の沖合、百済南畔之嶋(現在の済州島北岸)から越州(隋朝大業元年に「呉州」から変更)会稽県須岸山(現在の浙江省 舟山市舟山諸島)までの海上航路は約500kmです。外洋航海の距離からすると奈良時代の太平洋航路と遣唐使航路とは大差がありませんから、当時の日本が保有する船舶の性能や造船技術からすると遣唐使渡海への制約は無かったと考えられます。
また、養老六年(722)に「唐人王元仲始造飛舟進之。天皇嘉歎、授従五位下。」と云う記事があり、機会があれば朝廷は積極的に最新の造船技術を取り入れています。さらに「延喜式 大藏省 諸使給法」に定める入諸蕃使の規定では遣唐使の一行には船匠、鍛生、鑄生、細工生が含まれ、航海では造船技師たちを同行させることになっています。何かがあれば、船匠たちは水夫たちを使って対応するわけです。
木造船の時代ですから外洋航海に出る場合、その船に乗り込む船大工たちは、当然、十分に点検・メンテナンスをしますし、渡航先では現地の船大工たちの応援を頼むでしょう。外交使節団などの相互交流があれば、それを支える船舶の造船技術やメンテナンス技術は先進側から伝わるのです。このような背景がありますから、遣唐使時代、日本の造船技術が大陸や半島に対して落ちるかというと、制度で制限をしない限り、その可能性は低いと思います。
もう少し、上古時代の海運に触れますと、律令時代の庸調物(後には交易雜物)の割り当て分量に対し生産地から奈良の都への輸送とその貨物重量を考える時、船舶での運搬を考慮しないと人力運搬では運び切れないのです。駅馬の制度がありますが、庸調物や交易雜物の納入期間は全国一斉です。近国遠国で差がありますが、運搬距離を踏まえると陸路では主要街道に運脚キャラバン隊が集中することになります。貨物重量と運送の実務からすると、海上輸送ルートが確保されていたと考える必要があります。それを反映するように対新羅戦争の号令がかかると、全国の沿岸諸国は朝鮮海峡を越える能力を持つ軍船を建造し、それを難波大津や大宰府那珂湊に廻船します。造船技術や操船技術は即席には生まれませんから、飛鳥から奈良時代、社会は長距離の航海に耐える造船技術や操船技術を保有し、それを日常的に使っていたと考えるのが自然です。これらについては断片資料しか発見されていませんから、文献学上では長距離太平洋航路は無かった、造船技術は未熟だったと結論つけます。
気を取り直して、先に紹介した遣唐使航路の「呉唐之路」に関して、推古天皇十七年(609)に大陸の呉州(越州会稽)を出航した百済船が肥後国葦北津(現在の熊本県芦北市)に入港した事件があります。船長の申告では、事件の経緯として百済帰国を目指し呉州を出航後に暴風に遭遇し、場所が不明のままに肥後国葦北津に入港したとします。また、雄略天皇五年(461)に「呉国遣使貢献」の記事、雄略天皇十二年(468)に呉国への使いの記事「身狭村主青与檜隈民使博徳出使于呉」があり、その身狭村主青の帰国を記す同十四年の「身狭村主青等共呉国使、将呉所献手末才伎、漢織、呉織及衣縫兄媛、弟媛等。泊於住吉津」の記事があります。どうも、上古代 既に大陸の越州(旧呉州)会稽付近と朝鮮半島南端とを結ぶ航路があり、これを奈良時代には「呉唐之路」と呼び、大和の人々は大陸 揚子江方面との連絡では朝鮮海峡を渡った後に、この「呉唐之路」を使ったと思われます。つまり、南宋の趙汝适の《諸蕃志》に載る「在会稽之正東」、唐の姚思廉の《梁書・諸夷伝》に記す「去帶方萬二千餘里,大抵在会稽之東,相去絕遠。」の通りです。越州の会稽県須岸山(現在の浙江省 舟山市舟山諸島)の真東は鹿児島県薩摩半島付近ですから、概略なら会稽から見て大宰府付近はほぼ東です。大陸南部の人たちは朝鮮半島への航路「呉唐之路」を知っていますから、百済が会稽の東北東で、日本は百済の南だから日本は会稽の東にあると判断したわけです。
参考として、唐時代中期にあっても大陸側の認識では安禄山の動乱余波の中、長安から大陸を横断して山東半島を経由して渤海から日本に向かうよりも、越州の会稽から船で帰国するルート「南路」の方が安全と考えています。唐に向かうのに渤海を経由した天平宝字五年(761)の迎藤原清河使の高元度たちは帰国時には唐側の推薦に従い陸上では「南路」、海上では「呉唐之路」となるルートを採用し、大宰府に帰朝しています。その帰国のために唐朝廷は長八丈(約24m:新羅船相当の大きさ)の船一隻を造船し下賜しています。
ただ、「呉唐之路」は季節風の風向に左右されますので、陸路の治安が守られ、また、季節風の時期待ちをしない場合は、山東半島、渤海海峡横断、甕津半島、朝鮮半島西岸を南下し、朝鮮海峡横断するのが一番の確実なルートとなります。大和の歴史ではこれを「新羅道」と称したようです。
遣唐使の歴史を見ると、白雉四年(653)の高田首根麻呂を大使とする遣唐使船は「呉唐之路」を採用します。この時は二船団構成で、大使 高田首根麻呂の第一船は薩摩半島と竹島の間で難破しています。翌年の白雉五年(654)の高向史玄理を大使とする遣唐使船は「新羅道」を採用し、山東半島の北側の莱州で上陸し、陸路、長安へ向かっています。
改めて『日本書紀』と『続日本紀』を確認しますと、飛鳥から奈良時代の「遣唐使」の歴史の中で「新羅道」航路を使用したのは高向史玄理の時だけで、それ以外の「遣唐使」はすべて「呉唐之路」の航路を使用しています。ただ、もう一つの例外では玄宗皇帝時代の安禄山の動乱時代に藤原清河の救出を目的に派遣された迎藤原清河使の時で、その時は動乱の中での漂流時の現地民による殺害強奪を恐れて渤海経由を選択しています。これらの記録を参考としますと、「遣唐使」の標準海上航路は歴史的に一つで「呉唐之路」であり、現在の解説で云う「南航路」です。解説の「北航路」と称す「新羅道」は事例一回の特殊ケースのルートですから、これを「遣唐使」の正規ルートとするには無理があります。
どうも、大陸側と日本側で律令体制の制度整備が進み、唐朝の冊封体制の確立とその朝貢ルート及び担当する地方所轄の整備が終わると、日本の所轄は杭州湾の会稽が、渤海や新羅は山東半島の登州/莱州が執った可能性があります。また、冊封体制では日本が朝貢に新羅経由を望む場合、都度、冊封国新羅の斡旋と了承を受け入れる必要があります。冊封国新羅の斡旋を嫌えば、冊封体制の建前で遠夷国の日本は自力で杭州湾の会稽に行く必要があります。加えて、白雉四年の遣唐使の時、まだ、大和の友好国である百済は勢力を保っていますから、朝鮮半島の動静よりも唐側の冊封体制による都合の方が大きな比重があったと想像します。
おまけで、『隋書 俀国伝』に「俀国在百済新羅東南、水陸三千里於大海之中、依山島而居。魏時譯通中國三十餘國、皆自稱王、夷人不知里數、但計以日、其國境東西五月行南北三月行各至於海。地勢東高西下、都於邪靡堆。則魏志所謂邪馬臺者也。古云去樂浪郡境及帶方郡並一萬二千里、在會稽之東。與儋耳相近」の一文があります。
この末句の「與」を范曄の『後漢書 倭伝』の「與朱崖・儋耳相近、故其法俗多同」と同じく「又類也」の意味と理解しますと、末句の意味は民族を示すものとなり、ここでは儋耳(海南島)の人と似ているとなります。ちょうど、「梁職貢図」に描かれた倭人の姿と同じ理解です。つまり、『隋書』の「古云去樂浪郡境及帶方郡並一萬二千里、在會稽之東。與儋耳相近」の理解は、「昔、倭国の場所は後漢の樂浪郡を起点に道程を計れば一萬二千里の距離にあり、大陸を基準に考えると方角は越州会稽の東にあり、その民族は海南島の人に似ていると伝えた」となります。この地理報告書はおおむね正しいものです。
この紹介する『隋書』の文章は、隋使の報告文、魏時代の記述、それよりも古い時代の伝承の三つに構成されています。およそ、最後の文は『後漢書 倭伝』の「倭在韓東南大海中、依山㠀為居、凡百餘國。自武帝滅朝鮮使驛通於漢者三十許國、國皆稱王世世傳統、其大倭王居邪馬臺國(案今名邪摩惟音之訛也)。楽浪郡徼去其國萬二千里、去其西北界狗邪韓國七千餘里。其地大較在會稽・東冶之東。與朱崖・儋耳相近、故其法俗多同」からの引用と考えるのが相当です。ただ、隋時代の解釈では地域名の會稽が越州、東冶が福州を指し會稽・東冶では地域としては広域であること、また、朱崖が雷州半島、儋耳が海南島を指しこれまた広域であることに加え、民族に関しては雷州半島には山岳民族ミャオ族もおり、海南島海岸部の海洋民族の閩越族と風俗・風習が大きく違います。このため、『隋書』では新たな知見の下、読み手の理解での正確性を付加する為に地域では越州の會稽、民族では海南島閩越族を意味する儋耳に対象を絞ったと思われます。
このように紹介しますと、なんとも、つまらない話ですが、『日本書紀』、『続日本紀』、『隋書』、冊封の規定などを丁寧に確認すると、『後漢書 倭伝』や『隋書 俀国伝』の記述に地理学上での理解困難な記述は何もありません。万葉時代、人々はこのような理解と地理知識で遣唐使となり、大陸と交流をしていたと思います。
終わりに、弊ブログの立場は、柿本人麻呂は人生の最終盤に長門国守を務め、その任期が終わった後に長門国油谷湾から大宰府那珂港経由での帰京の途中に玄界灘で海難事故に遭い、水死したと推定しています。江戸時代にあっても大阪・江戸間の菱垣廻船航路でも年間20隻程度が海難事故に遭っているとの記録が有るそうですから、奈良時代でも遣唐使だけでなく、国内航路でも一定程度の海難事故に遭遇していたと考えます。万葉集を眺めますと沈没はしていませんが、遭難一歩手前の状況を示す柿本人麻呂の詠う讃岐狭峯嶋の歌や遣新羅使の歌群に佐婆海中の歌があり、さらに山上憶良の詠う筑前國志賀白水郎謌十首は白水郎荒雄の九州・対馬航路での海難死を悼む歌です。現代人では想像が難しいと思いますが、万葉人は旅行では一定程度の確率で人は死ぬと覚悟していたようです。













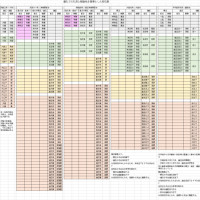





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます