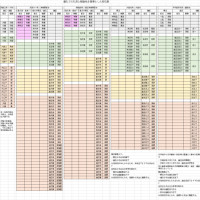万葉雑記 番外雑話 万葉時代の海上交通、フェイクニュースに挑む
今回もまた備忘録のようなものとなっています。前回に「万葉時代の遣唐使の航路」と云うテーマで与太話、酔論を展開しました。今回は、その航路からの発展で海上交通について遊びたいと思いますが、万葉集の歌の鑑賞には直接には関係しません。ただし、万葉時代は唐の文化や制度を取り入れ、社会を大改革する時代です。その時代の社会基盤を支えた海上交通や船舶を知ることは、多少、意義はあると考えます。
なお、今回は主に遣唐使船を中心とする国際交通に焦点を絞り、次回は地域から京へ調庸物などを運んだ国内交通、それも東海道・太平洋航路を扱いたいと思います。
さて、万葉集には大船を信頼性の比喩とする歌があります。他方、現代人は昭和時代の専門家のフェイクな刷り込みにより遣唐使船はすぐに難破するから、遣唐使の人々は任命されるのを恐れていたと信じます。このため、同じ「大船」の言葉ですが万葉人と現代人とでは、その言葉への信頼感が大きく違います。
集歌550
原文 大船之 念憑師 君之去者 吾者将戀名 直相左右二
訓読 大船(おほぶね)し思ひ頼みし君し去(い)なば我(あれ)は恋ひなむ直(ただ)に逢(あ)ふさへに
私訳 大海を往く大船のように頼りに思っていた貴方が奈良の京へと去って行かれたら、私は貴方のことを懐かしく思い出すでしょう。再び直接にお逢い出来ますようにと。
そこで、万葉時代の船の大きさについて調べてみますと、中国大陸の越州会稽と百済又は大和を繋ぐ「呉唐之道」と云う航路を航海する商用船や官船の大きさは乗客90~100人ほどの大きさを持っています。『日本書紀』や『続日本紀』から調べますと、推古天皇十七年(609)の百済船が乗客86人、白雉四年(653)の遣唐使船が総員120人、天平十一年(739)の遣唐使船が総員115人、天平勝宝六年(754)の遣唐使船の総員平均が111人、宝亀九年(778)の遣唐使船が総員97人の数字を見ることが出来ます。
参考に新羅と大和とを繋ぐ朝鮮海峡航路では天平勝宝四年(752)の新羅使船の乗客平均100人、天平宝字八年(764)の新羅使船の乗客91人の数字を見ることが可能です。日本の朝廷が遣唐使船の運航要員である水手までに褒美を下したと考えますと、おおよそですが、万葉時代では東アジア諸国(大和、百済、新羅)の外洋航路で使用する商用船の定員は約120人程度だったと推定できます。従来は遣唐使一行の帰国時の褒美の対象に運航要員である水手たちは含まれていないと考え、『日本書紀』や『続日本紀』に載る記事から得られた人員に、別途、運航要員約40人を加えて奈良時代後期から平安時代には遣唐使船の定員を最大140~150人(4隻船団総員500~600人)を想定します。そのため、弊ブログとの想定と差がありますが、以下、弊ブログでは遣唐使船の定員を120人と想定します。
一方、万葉時代の軍用船の大きさを調べますと、『日本書紀』の欽明天皇十五年(554)の大和船では平均で人が25人/隻+馬が2.5匹/隻の数字、天智天皇元年(662)の百済王とその大和からの護衛部隊の渡海作戦では30人/隻(除く水手)の数字、天智天皇十年(671)の郭務悰が率いる中国軍船では総員からの平均で43人/隻の数字を見ることが出来ます。他方、『続日本紀』の天平宝字五年(761)の対新羅戦争での動員計画では一隻当たり兵士103人+水手41人の数字があります。欽明天皇十五年、天智天皇元年、天智天皇十年のものは戦闘艦、天平宝字五年のものは遠洋航海の商用船/遣唐使船を下にした輸送艦と考え、天平宝字五年のものが特殊例とすると、東アジア諸国の戦闘艦は水手も戦闘要員とすると定員約40人程度の大きさと考えられます。
もう少し調べますと、天平宝字五年(761)に、迎藤原清河使たち11人が安禄山の変により唐から帰国が出来なくなった藤原清河の救援に向かった時、唐が示した藤原清河の帰国許可条件を日本の朝廷に報告する為の緊急帰国の際、唐側が用意した船は越州所属の差押水手官が指揮する船です。沿岸警備所属の船ですからこれを軍船に準じたものと考えると、船長八丈(24m)の船を指揮官・下士官9人、射手を含めた水夫30人の計39人が操船します。これは百済の役の中国軍船や郭務悰の中国軍船と似た大きさです。
ちなみに天智天皇二年(663)の百済の役での白村江の海戦で、旧唐書と三国史記とを総合すると孫仁師が率いる唐水軍は齊兵七千人、船百七十艘の数字があり、平均42人/隻となります。これは天智天皇十年(671)の郭務悰が率いる中国船の平均43人/隻とほぼ同等です。参考として白村江の海戦で対抗した百済・大和連合軍は秦造田来津を攻撃隊長とする大和兵五千人、舟八百艘の数字があり、これは平均6.3人/隻となります。白村江の海戦では中国海軍と大和軍が戦ったようで、それぞれの同盟軍となる新羅軍や百済軍は互いに陸軍として岸で戦況を見ていたとします。また、旧唐書では「船」と「舟」の書分けがあり、「小曰舟、大曰船」と解説しますから、中国海軍は外洋渡海の軍船を使い、対する自前の軍船を持たない秦造田来津を率いる大和軍は地元の百済の漁民から徴発した漁船を使ったと考えられます。
ここで脇道に逸れますが、大和の正規の軍船を調べる過程の中で、百済の役の直前となる、斉明天皇六年(660)に阿倍比邏夫は軍船二百艘を率いて粛慎国を攻撃します。その阿倍比邏夫はすぐの天智天皇元年(662)に軍船百七十艘を率いて、百済王豊璋と主将狭井連檳榔、副将秦造田来津が率いる大和軍で構成する護衛隊五千の百済への輸送作戦を行っています。この『日本書紀』の記事からすると、百済への渡航時に百済王の護衛部隊として長期駐留する予定の秦造田来津は自前の軍船を持っていないことが判りますし、朝鮮渡海で使用した大和軍の軍船は操船水手を除いて30人/隻の規模です。先の白村江の海戦時の平均6.3人/隻の舟と規模が全くに違います。
追加参考で、白村江の海戦時の大和軍兵力五千人の根拠として、護衛部隊輸送の翌年に勃発した百済の役では、天智天皇二年(663)に三軍団・正副六将軍による大和軍中核部隊となる二万七千人の渡海作戦を行っており、それぞれの将軍は自前の軍船百五十艘ほどを率いて、各々の国内支配地域を出発し、博多付近に集結したと推定されます。つまり、総勢八百~九百艘の軍船集団による渡海作戦だったと推定されます。この正副六将軍による中核部隊は新羅本国への攻撃部隊であって、白村江の海戦に参戦するために事前に新羅戦線を離脱し、朝鮮半島南東部から海路転進して朝鮮半島南西部にある白村江に向かったとの記述はどこの国の歴史書に有りません。また、海戦敗退直後に実施した百済敗残の人々と大和軍の撤収・集結地から推測しても新羅攻撃中核部隊の朝鮮半島南西部戦線への転進は確認できません。『日本書紀』では増強して来た中国軍に対応する為に、別途、廬原君が約1万の軍を率いて、百済(白村江)方面に派遣される予定となっていますが、白村江の海戦までに到着したとの記載がありません。ここからも、白村江の海戦勃発が廬原君の着任以前の出来事なら秦造田来津は大きな軍船を保有していません。
ちなみに新羅攻撃中核部隊の上毛野君稚子は関東地区、間人連大蓋は丹後半島地区、巨勢神前臣訳語は近江・若狭地区、宗像一族と同族の三輪君根麻呂は大和地区と玄海地区、阿倍引田臣比邏夫は越前・越中地区、和邇一族と同族の大宅臣鎌柄は大和・河内地区に支配を持つ一族で、それぞれの将軍の支配地域は全国に分散していますから、その支配地域から博多湾への集結手段=軍船を保有する必要があります。つまり、それぞれが大規模な軍船動員能力を持つ豪族です。加えて、百済の役に先立つ、推古天皇十年(602)には来目皇子を総大将として兵二万五千人による新羅戦争を計画した前例がありますから、斉明天皇四年(658)の唐・新羅の盟約成立の報告を受けて開戦準備をしていますと、天智天皇二年(663)までには十分な軍船は整ったと考えます。
振り返って、遣唐使船の構造について調べると『続日本紀』に重要な記事があります。それが宝亀九年(778)の記事の「又第一船海中中断、舳艫各分。主神津守宿禰国麻呂、并唐判官等五十六人、乗其艫而着甑嶋郡。判官大伴宿禰継人、并前入唐大使藤原朝臣河清之女喜娘等四十一人、乗其舳而着肥後国天草郡。」です。この記事が示すように船が船尾部と船首部とに二つに折れても56人と41人との大人数を保持できる浮力を保っていることから、遣唐使船は水密隔壁を持つ構造船だったことが確認できます。漂流時、人々はばらばらに船板などにつかまって流されていたのではありません。
この記事と1973年に中国江蘇省で発掘された唐代初期の民間貨物船とを比較することで、遣唐使船の概要が推測できます。江蘇省の船は唐初となる7世紀頃の長江(揚子江)中流域で使用されていたもので、全長6丈(17.3m)、最大船幅9尺(2.6m)、最大船底幅5尺(1.5m)で、水密隔壁を8か所持ち全9区画に区画されています。その区画では後部に居住区3区画、前部に貨物積載区6区画に区画し、貨物区画と居住区画とは3壁構造の水密隔壁で厳重に区画されています。この場合、海難事故に遭遇した場合、船体構造上、居住区画と貨物積載区画とで二つに折れる可能性が高くなります。ちょうど、宝亀九年の遣唐使船の事故状況と同じです。加えて、江蘇省の船は居住区に上甲板を持っていたと報告しますから、主に遣唐使一行と云う使者=人を輸送する遣唐使船では可積載重量は減りますが全面に上甲板を持ち、船体の強度補強と荒波からの浸水防止を図ったと考えられます。
この江蘇省での唐代船の発掘情報は1975年の『文物』に載り、また、2016年編纂の「中国古代重要科技発明創造」に中国船の隔壁技術の確認上限としてこの江蘇省の民間貨物船の事例を載せますから、昭和後期から平成前期までには日本の上古代船舶研究者は中国大陸では唐代以前に既に隔壁を持つ構造船が標準的な造船技術だったことを承知しています。時代性と船舶技術の発展の妥当性からすると、本来なら特別重要な遣唐使船は江蘇省の船の構造を基準に、水密隔壁を持つ構造船を想定する必要があります。
さらに中国では宋代のものとなりますが、福建省から船長30m級の遠洋航海用の民間貨物運搬船が発掘されています。この船は船内に12の水密隔壁を持ち13区画に分けられており、船型は浙江省の船と同じ楕円形に近い姿であり、船底は竜骨構造からの細い形状で平底ではありません。唐代初めの浙江省の船、宋代の福建省の船も復元図が示されていますから、船長30m級と推定される遣唐使船はこれらを参考に復元が可能となります。その時、現在に示される遣唐使船とは相当に異なる姿となります。ただ、中国大陸では元から明代に船舶建造用の良質な木材の枯渇からメコン・チャオプラヤ流域から大量の良質材が得られるシャム国で多数の水密隔壁とそれを繋ぐ梁の構造によって大木を要する竜骨構造を省略し、かつ、喫水の浅く平底の内航船向きの量産型船舶である竜骨無しジャンク船を大量に建造・輸入します。日本も室町以降の朱印船貿易や南蛮貿易ではこの量産型シャム産ジャンク船を輸入し安価な遠洋航海船として使用します。この歴史があり、室町以降では中国船とは主にこの量産型シャム産ジャンク船をイメージすることになります。参考に日本でも安土桃山時代には仙台藩が示したようにポルトガル船と同様な太い竜骨を持つガレオン船タイプの船を建造する能力はあり、このタイプの船はメキシコやフィリピン方面への通商に使用されています。ただ、その後の江戸幕府の大型船禁止令に加えジャンク船タイプを応用した、穏やかな気象状況の瀬戸内海航行に向いた水密隔壁間隔を大きく省略した安価な弁才船との建造コスト競争で負け、江戸初期にはガレオン船タイプの船の建造技術は失われています。
水密隔壁を大幅に省いた弁才船がそうであるように、建前とは別に政治経済では人の命を大きなコストとは考えません。元から明代に中国の長江内航船と遠洋航海貨物船との船体コストと、「呉唐之道」航路での遭難確率(遣唐使船で22%)とを勘案し、商業採算性があれば、日本向けの遠洋航海であっても長江用の内航船を投入する可能性は有ります。また、浙江省の杭州から江蘇省の海州までは沿岸部は非常な遠浅で長江用の内航船タイプの平底船に有利性があります。杭州から海州の先にある山東州の青島までの航海距離と杭州から薩摩までの航海距離が同じなら、危険ですが冒険商業者なら船体コストが安い平底船で日本への航海を試みる可能性があります。このため、宋代にはすでに二本マストで竜骨を持つ底が細く、複数の水密隔壁をもつ遠洋航海船が運用されていますが、それとは違うタイプの元から明代の長江用の内航船となる竜骨無しジャンク船が東海(東シナ海)では主流となって運行しています。
このような事情がありますから竜骨無しジャンク船と古墳時代の埴輪船とを折衷し、改めて描いた遣唐使船の想像図が飛鳥・奈良時代の遣唐使船を示しているかは保証されません。弊ブログの考えでは、造船時に採算コストを無視できる遣唐使船は当時の最新鋭の遠洋航海船を参考にする必要があります。日本船舶海洋工学会講演会論文集などを参照すると、推定の定員、宋代の発掘船、加藤清正の船の記録、東京国立博物館所蔵の進貢船の記録などから、遣唐使船は水密隔壁と総上甲板を持つ船長30m、船幅8mほどの船だったと推定します。ちなみに唐時代の軍船は長距離移動には帆を使い、戦闘状態では櫂を使い、長距離移動時の帆柱は戦闘前に倒して収納できるように構造になっています。このため、軍船の海戦想像図や内湾接岸時から想像したものと実際の遣唐使船の構造は大きく違う可能性があります。
困るのは中国側の古代船発掘資料を無視した上で日本に残る鎌倉時代以降の「吉備大臣入唐絵巻」などの想像の唐船絵から遣唐使船を想像し、加えて造船工学から計算できる船長30m級の船が受ける外洋航行時の造波抵抗を無視して魯や櫂による操船を想像することです。現実、遣唐使船のような遠洋航海大型船は舷側の位置が高い為に櫂の固定位置が高くなり、腕が非常に長くなります。櫂用の窓を開け、固定位置を下げることも可能ですが、荒天波浪時には浸水沈船の可能性が非常に高くなります。つまり、安全性を勘案し、櫂の腕の長さと固定位置に船幅を踏まえると人力では櫂を漕げない可能性もあるのです。精神論だけでは物理、数学、人間の筋力からの結論を乗り越えるのは困難です。それで根性論や精神論をベースにした実験遣唐使船はすべて失敗したのです。
さらに福建省で発掘された宋代船は二本マストの帆船ですが、遠洋航海の二本マストの帆船がいきなりには誕生はしません。試行錯誤と航海経験から進化すると考えると、二本マストの前に一本マストの遠洋船があったと推定するのが自然です。ちなみに唐代直後の北宋時代に描かれた「清明上河図」に示す大型船も一本マストの船です。
現在、新しい遣唐使船の模型などを作成する場合、国際的な古代船研究成果から福建省の唐初時代の船などを参考にするようになってきました。そのため、平成中期までに提案された遣唐使船とは相当に違う姿があります。また、技術の伝承が途絶えると、時に古代の方が技術で優れていても、技術の劣る中世の姿で古代を想像する可能性があります。近世以前では染色・紡織技術のピークは奈良時代にあり、その時代の古代染色法が復元されるのは平成になってからです。染色法や染料製造などは正倉院御物などの実物があるため、江戸時代の技術から奈良時代を想像して技術が劣っていたとは云わず、高度な技術の伝統が途切れたとします。同じように大型船の造船技術も平安時代中期までには対新羅戦争のような遠洋航海の軍船需要や調庸物を運ぶ長距離貨物輸送などの需要が失われたことから途絶えたと考えられます。近世の例として安土桃山時代には国産のポルトガル・ガレオン船タイプの建造能力は有りますが、需要が無くなると瞬時に技術は失われます。
視線を変えますと、戦国時代に瀬戸内海に塩飽船大工集団がおり、豊臣秀吉の朝鮮の役には朝鮮出兵の軍船建造や補修に従事し、同時に城郭建築にも従事したと伝わります。その塩飽船大工集団は江戸期には需要が増えた北前船などの商船の船大工としての職と同時に神社仏閣や豪商などの建築の職も行い、それが明治期まで技術伝統をつないでいます。また、大工さんで奈良時代の大工道具を研究している人のブログなどを眺めますと、大工道具では船大工と宮大工とで共通点が多いそうです。その例として和釘や舟釘を打つための鐔(つば)ノミにそれが見られるようです。このように、現代とは違い、船大工と宮大工との区分は無かったようです。奈良時代、聖武天皇は全国に国分寺と国分尼寺の建立を号令しますが、その時、全国沿岸部には船大工がいたから、即応出来たのでしょう。上古ですから中央と地方では技術水準は大きな格差があったと思いますが、全国各地の豪族が軍船建造などを通じて船大工を保有していたから、その技術が国府や国分寺の大規模建築にも適用できたのだろうと考えます。ただ、そのような大船建造技術も大寺建造技術も需要が無くなると消えてなくなります。しかしながら、桃山期の仙台藩のガレオン船タイプ建造に見られるように、基礎技術を保有していた結果、少数の外国人の指導があれば、太平洋横断の木造船は瞬時に建造できたのです。万葉時代も同様と考えます。対新羅戦争の軍船五百隻建造計画が、ほぼほぼ、達成できたのはこのような背景ですし、それ以前から技術を保有していたのです。
取り止めがありませんが、現在では遣唐使についてはあらかじめの先入観を持った感覚的な解説から、適切な資料を基にした数値で研究・解説するようになり、例として奈良時代の遣唐使の帰還率は船を使い捨てと考えますと18隻中14隻の数字から78%という値を使います。これに対してご存じのように平成中期頃までは無事の帰還は半分以下だったと感覚的に解説します。この感覚的な数字が、皆さんが思う遣唐使の成功率と考えます。
また、遣唐使の航海時期について、従来は空想的に唐の朝儀の時期に合わせたために日本側の任命から出発までの手続き・儀礼の期間を踏まえると、実際の海上航行期間と陸上移動期間から来る時間的な制約から北航路でなく南航路を選択したなどと解説しています。ところが、現代では季節風や黒潮・対馬海流などの自然条件を勘案した上で、航海ルートと時期を合理的かつ科学的に研究するようになりました。冊封制度の要請で越州会稽(杭州湾)が入港地であり、必然、海上ルート「呉唐之路」を使うことを前提にしますと、日本から杭州湾へは朝鮮海峡を北上して対馬海流を横断し、その後、北東の風に乗れば海流としては弱いのですが東シナ海(東海)反流と合わせて揚子江(長江)沖合に辿り着きます。この北東の風の最適時が旧暦の六月です。逆に杭州湾から日本に渡るには、いかに黒潮・対馬海流に乗るかがカギとなります。石垣島海域より北で世界最強の黒潮に乗ると自然に屋久島から大隅半島の海域に、上手く黒潮支流の対馬海流に乗ると朝鮮海峡へ辿り着きます。このため、杭州湾から北西の風が吹く旧暦11月から2月が最適時となります。これを反映するように円仁の入唐求法巡礼行記に示すように杭州湾には「呉唐之路」になれた杭州湾と朝鮮半島南部とを交易する新羅船・新羅船員や航海経験を持つ中国人たちが多数います。気象、海流などを勘案し、丁寧に『日本書紀』や『続日本紀』を眺めれば、遣唐使たちが冷静に自然状況を優先して航海をしていることが判ります。
既に多くの資料がネット上で閲覧できますから、旧来のように一般人は資料を見ることは無いとして、仲間内の思い付きや結論を先に置いて論説をするのはやめた方が良いと思います。
今回、与太話を垂れ流しましたが、最新の推定遣唐使船は2021年に公開を開始した九州国立博物館が示すものが、一番、それと思います。ただ、九州国立博物館のものは二本マストを持ち、従来の想像図に従いつつ宋代の遠洋航海船や吉備大臣入唐絵巻を写しています。弊ブログでは唐代直後の北宋時代の「清明上河図」に描かれた船を参考にすると、飛鳥・奈良時代の遣唐使船はまだ一本マストだったと考えています。
参考に、九州国立博物館のものは中国や日本の発掘成果を取り入れるなどの方法論であり、奈良県の平城宮跡歴史公園の昭和時代からの引継ぎである絵画を中心に想定したものとでは研究方法論が違うため得られた結論は船体構造などで大きく違います。馬鹿々々しいのですが、九州国立博物館のものは帰還率78%を考慮して東シナ海を船として航海できることを前提とした船体船型ですが、平城宮跡歴史公園のものは難破を前提としたような装飾の船体船型です。どうも、先人研究者の伝統の厚みを反映して遣唐使航海への根本思想が違うようです。まずはともあれ、両船はネットで確認できますので、ネットサーフィンで検索してみてください。
今回もまた備忘録のようなものとなっています。前回に「万葉時代の遣唐使の航路」と云うテーマで与太話、酔論を展開しました。今回は、その航路からの発展で海上交通について遊びたいと思いますが、万葉集の歌の鑑賞には直接には関係しません。ただし、万葉時代は唐の文化や制度を取り入れ、社会を大改革する時代です。その時代の社会基盤を支えた海上交通や船舶を知ることは、多少、意義はあると考えます。
なお、今回は主に遣唐使船を中心とする国際交通に焦点を絞り、次回は地域から京へ調庸物などを運んだ国内交通、それも東海道・太平洋航路を扱いたいと思います。
さて、万葉集には大船を信頼性の比喩とする歌があります。他方、現代人は昭和時代の専門家のフェイクな刷り込みにより遣唐使船はすぐに難破するから、遣唐使の人々は任命されるのを恐れていたと信じます。このため、同じ「大船」の言葉ですが万葉人と現代人とでは、その言葉への信頼感が大きく違います。
集歌550
原文 大船之 念憑師 君之去者 吾者将戀名 直相左右二
訓読 大船(おほぶね)し思ひ頼みし君し去(い)なば我(あれ)は恋ひなむ直(ただ)に逢(あ)ふさへに
私訳 大海を往く大船のように頼りに思っていた貴方が奈良の京へと去って行かれたら、私は貴方のことを懐かしく思い出すでしょう。再び直接にお逢い出来ますようにと。
そこで、万葉時代の船の大きさについて調べてみますと、中国大陸の越州会稽と百済又は大和を繋ぐ「呉唐之道」と云う航路を航海する商用船や官船の大きさは乗客90~100人ほどの大きさを持っています。『日本書紀』や『続日本紀』から調べますと、推古天皇十七年(609)の百済船が乗客86人、白雉四年(653)の遣唐使船が総員120人、天平十一年(739)の遣唐使船が総員115人、天平勝宝六年(754)の遣唐使船の総員平均が111人、宝亀九年(778)の遣唐使船が総員97人の数字を見ることが出来ます。
参考に新羅と大和とを繋ぐ朝鮮海峡航路では天平勝宝四年(752)の新羅使船の乗客平均100人、天平宝字八年(764)の新羅使船の乗客91人の数字を見ることが可能です。日本の朝廷が遣唐使船の運航要員である水手までに褒美を下したと考えますと、おおよそですが、万葉時代では東アジア諸国(大和、百済、新羅)の外洋航路で使用する商用船の定員は約120人程度だったと推定できます。従来は遣唐使一行の帰国時の褒美の対象に運航要員である水手たちは含まれていないと考え、『日本書紀』や『続日本紀』に載る記事から得られた人員に、別途、運航要員約40人を加えて奈良時代後期から平安時代には遣唐使船の定員を最大140~150人(4隻船団総員500~600人)を想定します。そのため、弊ブログとの想定と差がありますが、以下、弊ブログでは遣唐使船の定員を120人と想定します。
一方、万葉時代の軍用船の大きさを調べますと、『日本書紀』の欽明天皇十五年(554)の大和船では平均で人が25人/隻+馬が2.5匹/隻の数字、天智天皇元年(662)の百済王とその大和からの護衛部隊の渡海作戦では30人/隻(除く水手)の数字、天智天皇十年(671)の郭務悰が率いる中国軍船では総員からの平均で43人/隻の数字を見ることが出来ます。他方、『続日本紀』の天平宝字五年(761)の対新羅戦争での動員計画では一隻当たり兵士103人+水手41人の数字があります。欽明天皇十五年、天智天皇元年、天智天皇十年のものは戦闘艦、天平宝字五年のものは遠洋航海の商用船/遣唐使船を下にした輸送艦と考え、天平宝字五年のものが特殊例とすると、東アジア諸国の戦闘艦は水手も戦闘要員とすると定員約40人程度の大きさと考えられます。
もう少し調べますと、天平宝字五年(761)に、迎藤原清河使たち11人が安禄山の変により唐から帰国が出来なくなった藤原清河の救援に向かった時、唐が示した藤原清河の帰国許可条件を日本の朝廷に報告する為の緊急帰国の際、唐側が用意した船は越州所属の差押水手官が指揮する船です。沿岸警備所属の船ですからこれを軍船に準じたものと考えると、船長八丈(24m)の船を指揮官・下士官9人、射手を含めた水夫30人の計39人が操船します。これは百済の役の中国軍船や郭務悰の中国軍船と似た大きさです。
ちなみに天智天皇二年(663)の百済の役での白村江の海戦で、旧唐書と三国史記とを総合すると孫仁師が率いる唐水軍は齊兵七千人、船百七十艘の数字があり、平均42人/隻となります。これは天智天皇十年(671)の郭務悰が率いる中国船の平均43人/隻とほぼ同等です。参考として白村江の海戦で対抗した百済・大和連合軍は秦造田来津を攻撃隊長とする大和兵五千人、舟八百艘の数字があり、これは平均6.3人/隻となります。白村江の海戦では中国海軍と大和軍が戦ったようで、それぞれの同盟軍となる新羅軍や百済軍は互いに陸軍として岸で戦況を見ていたとします。また、旧唐書では「船」と「舟」の書分けがあり、「小曰舟、大曰船」と解説しますから、中国海軍は外洋渡海の軍船を使い、対する自前の軍船を持たない秦造田来津を率いる大和軍は地元の百済の漁民から徴発した漁船を使ったと考えられます。
ここで脇道に逸れますが、大和の正規の軍船を調べる過程の中で、百済の役の直前となる、斉明天皇六年(660)に阿倍比邏夫は軍船二百艘を率いて粛慎国を攻撃します。その阿倍比邏夫はすぐの天智天皇元年(662)に軍船百七十艘を率いて、百済王豊璋と主将狭井連檳榔、副将秦造田来津が率いる大和軍で構成する護衛隊五千の百済への輸送作戦を行っています。この『日本書紀』の記事からすると、百済への渡航時に百済王の護衛部隊として長期駐留する予定の秦造田来津は自前の軍船を持っていないことが判りますし、朝鮮渡海で使用した大和軍の軍船は操船水手を除いて30人/隻の規模です。先の白村江の海戦時の平均6.3人/隻の舟と規模が全くに違います。
追加参考で、白村江の海戦時の大和軍兵力五千人の根拠として、護衛部隊輸送の翌年に勃発した百済の役では、天智天皇二年(663)に三軍団・正副六将軍による大和軍中核部隊となる二万七千人の渡海作戦を行っており、それぞれの将軍は自前の軍船百五十艘ほどを率いて、各々の国内支配地域を出発し、博多付近に集結したと推定されます。つまり、総勢八百~九百艘の軍船集団による渡海作戦だったと推定されます。この正副六将軍による中核部隊は新羅本国への攻撃部隊であって、白村江の海戦に参戦するために事前に新羅戦線を離脱し、朝鮮半島南東部から海路転進して朝鮮半島南西部にある白村江に向かったとの記述はどこの国の歴史書に有りません。また、海戦敗退直後に実施した百済敗残の人々と大和軍の撤収・集結地から推測しても新羅攻撃中核部隊の朝鮮半島南西部戦線への転進は確認できません。『日本書紀』では増強して来た中国軍に対応する為に、別途、廬原君が約1万の軍を率いて、百済(白村江)方面に派遣される予定となっていますが、白村江の海戦までに到着したとの記載がありません。ここからも、白村江の海戦勃発が廬原君の着任以前の出来事なら秦造田来津は大きな軍船を保有していません。
ちなみに新羅攻撃中核部隊の上毛野君稚子は関東地区、間人連大蓋は丹後半島地区、巨勢神前臣訳語は近江・若狭地区、宗像一族と同族の三輪君根麻呂は大和地区と玄海地区、阿倍引田臣比邏夫は越前・越中地区、和邇一族と同族の大宅臣鎌柄は大和・河内地区に支配を持つ一族で、それぞれの将軍の支配地域は全国に分散していますから、その支配地域から博多湾への集結手段=軍船を保有する必要があります。つまり、それぞれが大規模な軍船動員能力を持つ豪族です。加えて、百済の役に先立つ、推古天皇十年(602)には来目皇子を総大将として兵二万五千人による新羅戦争を計画した前例がありますから、斉明天皇四年(658)の唐・新羅の盟約成立の報告を受けて開戦準備をしていますと、天智天皇二年(663)までには十分な軍船は整ったと考えます。
振り返って、遣唐使船の構造について調べると『続日本紀』に重要な記事があります。それが宝亀九年(778)の記事の「又第一船海中中断、舳艫各分。主神津守宿禰国麻呂、并唐判官等五十六人、乗其艫而着甑嶋郡。判官大伴宿禰継人、并前入唐大使藤原朝臣河清之女喜娘等四十一人、乗其舳而着肥後国天草郡。」です。この記事が示すように船が船尾部と船首部とに二つに折れても56人と41人との大人数を保持できる浮力を保っていることから、遣唐使船は水密隔壁を持つ構造船だったことが確認できます。漂流時、人々はばらばらに船板などにつかまって流されていたのではありません。
この記事と1973年に中国江蘇省で発掘された唐代初期の民間貨物船とを比較することで、遣唐使船の概要が推測できます。江蘇省の船は唐初となる7世紀頃の長江(揚子江)中流域で使用されていたもので、全長6丈(17.3m)、最大船幅9尺(2.6m)、最大船底幅5尺(1.5m)で、水密隔壁を8か所持ち全9区画に区画されています。その区画では後部に居住区3区画、前部に貨物積載区6区画に区画し、貨物区画と居住区画とは3壁構造の水密隔壁で厳重に区画されています。この場合、海難事故に遭遇した場合、船体構造上、居住区画と貨物積載区画とで二つに折れる可能性が高くなります。ちょうど、宝亀九年の遣唐使船の事故状況と同じです。加えて、江蘇省の船は居住区に上甲板を持っていたと報告しますから、主に遣唐使一行と云う使者=人を輸送する遣唐使船では可積載重量は減りますが全面に上甲板を持ち、船体の強度補強と荒波からの浸水防止を図ったと考えられます。
この江蘇省での唐代船の発掘情報は1975年の『文物』に載り、また、2016年編纂の「中国古代重要科技発明創造」に中国船の隔壁技術の確認上限としてこの江蘇省の民間貨物船の事例を載せますから、昭和後期から平成前期までには日本の上古代船舶研究者は中国大陸では唐代以前に既に隔壁を持つ構造船が標準的な造船技術だったことを承知しています。時代性と船舶技術の発展の妥当性からすると、本来なら特別重要な遣唐使船は江蘇省の船の構造を基準に、水密隔壁を持つ構造船を想定する必要があります。
さらに中国では宋代のものとなりますが、福建省から船長30m級の遠洋航海用の民間貨物運搬船が発掘されています。この船は船内に12の水密隔壁を持ち13区画に分けられており、船型は浙江省の船と同じ楕円形に近い姿であり、船底は竜骨構造からの細い形状で平底ではありません。唐代初めの浙江省の船、宋代の福建省の船も復元図が示されていますから、船長30m級と推定される遣唐使船はこれらを参考に復元が可能となります。その時、現在に示される遣唐使船とは相当に異なる姿となります。ただ、中国大陸では元から明代に船舶建造用の良質な木材の枯渇からメコン・チャオプラヤ流域から大量の良質材が得られるシャム国で多数の水密隔壁とそれを繋ぐ梁の構造によって大木を要する竜骨構造を省略し、かつ、喫水の浅く平底の内航船向きの量産型船舶である竜骨無しジャンク船を大量に建造・輸入します。日本も室町以降の朱印船貿易や南蛮貿易ではこの量産型シャム産ジャンク船を輸入し安価な遠洋航海船として使用します。この歴史があり、室町以降では中国船とは主にこの量産型シャム産ジャンク船をイメージすることになります。参考に日本でも安土桃山時代には仙台藩が示したようにポルトガル船と同様な太い竜骨を持つガレオン船タイプの船を建造する能力はあり、このタイプの船はメキシコやフィリピン方面への通商に使用されています。ただ、その後の江戸幕府の大型船禁止令に加えジャンク船タイプを応用した、穏やかな気象状況の瀬戸内海航行に向いた水密隔壁間隔を大きく省略した安価な弁才船との建造コスト競争で負け、江戸初期にはガレオン船タイプの船の建造技術は失われています。
水密隔壁を大幅に省いた弁才船がそうであるように、建前とは別に政治経済では人の命を大きなコストとは考えません。元から明代に中国の長江内航船と遠洋航海貨物船との船体コストと、「呉唐之道」航路での遭難確率(遣唐使船で22%)とを勘案し、商業採算性があれば、日本向けの遠洋航海であっても長江用の内航船を投入する可能性は有ります。また、浙江省の杭州から江蘇省の海州までは沿岸部は非常な遠浅で長江用の内航船タイプの平底船に有利性があります。杭州から海州の先にある山東州の青島までの航海距離と杭州から薩摩までの航海距離が同じなら、危険ですが冒険商業者なら船体コストが安い平底船で日本への航海を試みる可能性があります。このため、宋代にはすでに二本マストで竜骨を持つ底が細く、複数の水密隔壁をもつ遠洋航海船が運用されていますが、それとは違うタイプの元から明代の長江用の内航船となる竜骨無しジャンク船が東海(東シナ海)では主流となって運行しています。
このような事情がありますから竜骨無しジャンク船と古墳時代の埴輪船とを折衷し、改めて描いた遣唐使船の想像図が飛鳥・奈良時代の遣唐使船を示しているかは保証されません。弊ブログの考えでは、造船時に採算コストを無視できる遣唐使船は当時の最新鋭の遠洋航海船を参考にする必要があります。日本船舶海洋工学会講演会論文集などを参照すると、推定の定員、宋代の発掘船、加藤清正の船の記録、東京国立博物館所蔵の進貢船の記録などから、遣唐使船は水密隔壁と総上甲板を持つ船長30m、船幅8mほどの船だったと推定します。ちなみに唐時代の軍船は長距離移動には帆を使い、戦闘状態では櫂を使い、長距離移動時の帆柱は戦闘前に倒して収納できるように構造になっています。このため、軍船の海戦想像図や内湾接岸時から想像したものと実際の遣唐使船の構造は大きく違う可能性があります。
困るのは中国側の古代船発掘資料を無視した上で日本に残る鎌倉時代以降の「吉備大臣入唐絵巻」などの想像の唐船絵から遣唐使船を想像し、加えて造船工学から計算できる船長30m級の船が受ける外洋航行時の造波抵抗を無視して魯や櫂による操船を想像することです。現実、遣唐使船のような遠洋航海大型船は舷側の位置が高い為に櫂の固定位置が高くなり、腕が非常に長くなります。櫂用の窓を開け、固定位置を下げることも可能ですが、荒天波浪時には浸水沈船の可能性が非常に高くなります。つまり、安全性を勘案し、櫂の腕の長さと固定位置に船幅を踏まえると人力では櫂を漕げない可能性もあるのです。精神論だけでは物理、数学、人間の筋力からの結論を乗り越えるのは困難です。それで根性論や精神論をベースにした実験遣唐使船はすべて失敗したのです。
さらに福建省で発掘された宋代船は二本マストの帆船ですが、遠洋航海の二本マストの帆船がいきなりには誕生はしません。試行錯誤と航海経験から進化すると考えると、二本マストの前に一本マストの遠洋船があったと推定するのが自然です。ちなみに唐代直後の北宋時代に描かれた「清明上河図」に示す大型船も一本マストの船です。
現在、新しい遣唐使船の模型などを作成する場合、国際的な古代船研究成果から福建省の唐初時代の船などを参考にするようになってきました。そのため、平成中期までに提案された遣唐使船とは相当に違う姿があります。また、技術の伝承が途絶えると、時に古代の方が技術で優れていても、技術の劣る中世の姿で古代を想像する可能性があります。近世以前では染色・紡織技術のピークは奈良時代にあり、その時代の古代染色法が復元されるのは平成になってからです。染色法や染料製造などは正倉院御物などの実物があるため、江戸時代の技術から奈良時代を想像して技術が劣っていたとは云わず、高度な技術の伝統が途切れたとします。同じように大型船の造船技術も平安時代中期までには対新羅戦争のような遠洋航海の軍船需要や調庸物を運ぶ長距離貨物輸送などの需要が失われたことから途絶えたと考えられます。近世の例として安土桃山時代には国産のポルトガル・ガレオン船タイプの建造能力は有りますが、需要が無くなると瞬時に技術は失われます。
視線を変えますと、戦国時代に瀬戸内海に塩飽船大工集団がおり、豊臣秀吉の朝鮮の役には朝鮮出兵の軍船建造や補修に従事し、同時に城郭建築にも従事したと伝わります。その塩飽船大工集団は江戸期には需要が増えた北前船などの商船の船大工としての職と同時に神社仏閣や豪商などの建築の職も行い、それが明治期まで技術伝統をつないでいます。また、大工さんで奈良時代の大工道具を研究している人のブログなどを眺めますと、大工道具では船大工と宮大工とで共通点が多いそうです。その例として和釘や舟釘を打つための鐔(つば)ノミにそれが見られるようです。このように、現代とは違い、船大工と宮大工との区分は無かったようです。奈良時代、聖武天皇は全国に国分寺と国分尼寺の建立を号令しますが、その時、全国沿岸部には船大工がいたから、即応出来たのでしょう。上古ですから中央と地方では技術水準は大きな格差があったと思いますが、全国各地の豪族が軍船建造などを通じて船大工を保有していたから、その技術が国府や国分寺の大規模建築にも適用できたのだろうと考えます。ただ、そのような大船建造技術も大寺建造技術も需要が無くなると消えてなくなります。しかしながら、桃山期の仙台藩のガレオン船タイプ建造に見られるように、基礎技術を保有していた結果、少数の外国人の指導があれば、太平洋横断の木造船は瞬時に建造できたのです。万葉時代も同様と考えます。対新羅戦争の軍船五百隻建造計画が、ほぼほぼ、達成できたのはこのような背景ですし、それ以前から技術を保有していたのです。
取り止めがありませんが、現在では遣唐使についてはあらかじめの先入観を持った感覚的な解説から、適切な資料を基にした数値で研究・解説するようになり、例として奈良時代の遣唐使の帰還率は船を使い捨てと考えますと18隻中14隻の数字から78%という値を使います。これに対してご存じのように平成中期頃までは無事の帰還は半分以下だったと感覚的に解説します。この感覚的な数字が、皆さんが思う遣唐使の成功率と考えます。
また、遣唐使の航海時期について、従来は空想的に唐の朝儀の時期に合わせたために日本側の任命から出発までの手続き・儀礼の期間を踏まえると、実際の海上航行期間と陸上移動期間から来る時間的な制約から北航路でなく南航路を選択したなどと解説しています。ところが、現代では季節風や黒潮・対馬海流などの自然条件を勘案した上で、航海ルートと時期を合理的かつ科学的に研究するようになりました。冊封制度の要請で越州会稽(杭州湾)が入港地であり、必然、海上ルート「呉唐之路」を使うことを前提にしますと、日本から杭州湾へは朝鮮海峡を北上して対馬海流を横断し、その後、北東の風に乗れば海流としては弱いのですが東シナ海(東海)反流と合わせて揚子江(長江)沖合に辿り着きます。この北東の風の最適時が旧暦の六月です。逆に杭州湾から日本に渡るには、いかに黒潮・対馬海流に乗るかがカギとなります。石垣島海域より北で世界最強の黒潮に乗ると自然に屋久島から大隅半島の海域に、上手く黒潮支流の対馬海流に乗ると朝鮮海峡へ辿り着きます。このため、杭州湾から北西の風が吹く旧暦11月から2月が最適時となります。これを反映するように円仁の入唐求法巡礼行記に示すように杭州湾には「呉唐之路」になれた杭州湾と朝鮮半島南部とを交易する新羅船・新羅船員や航海経験を持つ中国人たちが多数います。気象、海流などを勘案し、丁寧に『日本書紀』や『続日本紀』を眺めれば、遣唐使たちが冷静に自然状況を優先して航海をしていることが判ります。
既に多くの資料がネット上で閲覧できますから、旧来のように一般人は資料を見ることは無いとして、仲間内の思い付きや結論を先に置いて論説をするのはやめた方が良いと思います。
今回、与太話を垂れ流しましたが、最新の推定遣唐使船は2021年に公開を開始した九州国立博物館が示すものが、一番、それと思います。ただ、九州国立博物館のものは二本マストを持ち、従来の想像図に従いつつ宋代の遠洋航海船や吉備大臣入唐絵巻を写しています。弊ブログでは唐代直後の北宋時代の「清明上河図」に描かれた船を参考にすると、飛鳥・奈良時代の遣唐使船はまだ一本マストだったと考えています。
参考に、九州国立博物館のものは中国や日本の発掘成果を取り入れるなどの方法論であり、奈良県の平城宮跡歴史公園の昭和時代からの引継ぎである絵画を中心に想定したものとでは研究方法論が違うため得られた結論は船体構造などで大きく違います。馬鹿々々しいのですが、九州国立博物館のものは帰還率78%を考慮して東シナ海を船として航海できることを前提とした船体船型ですが、平城宮跡歴史公園のものは難破を前提としたような装飾の船体船型です。どうも、先人研究者の伝統の厚みを反映して遣唐使航海への根本思想が違うようです。まずはともあれ、両船はネットで確認できますので、ネットサーフィンで検索してみてください。